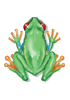ニューフェイス・イン・ヘル
ジェフ・ヴァンダーミア
テリー・ティドウェルのことを私はどれだけ知っているだろう。彼が約三年間、われわれの監視下にあったことは事実だ。具体的な容疑に基づいたものではなく、ごく一般的な監視だった。いわゆる、〈世間を欺くタイプの秘密と醜聞の割合〉というやつだ。しかし特に発覚したことはなく、監視は打ち切りになった。打ち切りに関する諸般の事由はいずれ明らかになるだろうが、他にもうひとつの理由があった。それは、彼を熱心に追うあまり、私が彼と同じような考え方をするようになり、しまいには彼になりきってしまった、ということだ。職業病というやつかもしれない。上司たちはいい顔をしなかった。
ティドウェルに話を戻そう。建設労働者、本の虫、ビール好き。バー通いが日課。妻とは数年前に離婚。ファイルにはその他もろもろの月並みな情報が記載されている。この男の存在を貫くのは平凡さそのものだ――といっても、それはある時点までのことだった。
彼が仲間たちと出かけたある晩のことだった(私はいかにもそのうちのひとりの知り合いのような顔をして紛れこんだ)。ティドウェルがホームレスの男にぶつかった(男はわれわれの工作員ではなかった。まったく予想外の出来事であり、この事実だけで私は背筋が凍りついた)。むっとする体臭や黴の臭いに襲われながら、ティドウェルは男を両手で受け止めた。どこにでもあるような光景だった。第三者から見れば、再会をよろこぶ旧友同士にも見えたかもしれない。
男は白髪まじりの頬ひげに覆われた顔をあからさまにしかめ、じたばたもがいてティドウェルの手をふりほどこうした。一方、ティドウェルはへたに手をほどいて男が転落してはいけないと思って、しばらく男を抱きかかえていた。
ティドウェルから解放されると男はよろめき、あやうく縁石を踏みはずしそうになった。すぐ後ろを次々に車が走り抜けていった。男はティドウェルをにらみつけた。
「気をつけろ」男はうなるように言った。
ティドウェルは一歩下がった。そのとき、彼も私も男の左目の異様さに気がついた。全体が真っ黒で、白い部分がまったくない。まばたきすると、そのまぶたに何本か筋が隆起しているのが、ティドウェルにはたしかに見えた。眼窩のなかに収まっているのは眼球ではなく、何かむしろ機械のようなものだった。
「すまない」ティドウェルは言い、もう一歩下がった。仲間たちはすこし先に行ったところで彼を待っていた。
彼は男に背を向けて歩きはじめた。背筋に走る恐怖が彼を急き立てた。しかし男が背後に追いついて腕をつかんだ。その手は力強く、ロボットアームのように容赦なくティドウェルの腕に食いこんだ。
「ヴォーカンソンはアヒルを持っていた」男が耳にささやいた。「たしかに持っていた。壊れちまったがな。俺のせいじゃない。もうやつらにも感づかれた。ヴォーカンソンだ。ヴォーカンソンを調べるんだ」
男は手を離した。
ティドウェルはふり向いて男を見た。何か言おうとして口を開けたが、言うべき言葉が見つからなかった。ただ一刻も早く男のもとを離れたいと思った。
私は助け舟を出そうとひき返してきていたので、横から声をかけた。「警察を呼ぼうか?」
ティドウェルは異様な目の男を見つめ、男は異様な目で見つめ返した。
「いや」ティドウェルが答えた。「でも、早いところここを離れよう」
「ヴォーカンソンのアヒルだ。そいつを見つけるんだ」男が言った。「そうすればすべてがわかる。俺にはもう時間がない。なす術もない」男の顔に思いがけず哀れみの色が浮かんだ。「幸運を祈る」男は小さくつぶやいた。そして呆然と見送るだけのティドウェルと仲間たちを尻目に、信じられないようなスピードで舗道を走り去り、やがて夜の闇に消えていった。
家に帰ってもまだ、ティドウェルは腕に男の握力を感じていた。つかまれた部分には二本のみみず腫れが残り、治るのには二週間かかった。
案の定、このホームレスとの遭遇はティドウェルの頭を去ることはなかった。彼はこの事件をなんども胸の内で反芻した。たとえば、ティドウェルは友人のひとりにこう話している。考えれば考えるほど、やつが見知らぬ他人とは思えなくなってくる。まるでむかしからの知り合いだったような気がする。だが、この謎にかかる霧のむこうにどんなに目を凝らしてみても、謎は依然として謎のままなんだ。
ティドウェルは、それなら暇をみつけてアヒルとヴォーカンソンについて調べてみようじゃないかと思い立った。はたして実在する人物なのだろうか。出来ることならアヒルもヴォーカンソンも忘れてしまいたかったが、くる日もくる日も不思議なアヒルと、胸にⅤと描かれたシャツを着た正体不明の男が夢に出てくるとあれば無理な話だった。
「今晩一緒にどうだい?」と友人たちに誘われても、ティドウェルはこう答えるようになった。「今夜はあんまり調子がよくないんだ。おとなしくしてるさ」そして彼は町の図書館に行き、〈ヴォーカンソン〉についての調べものをした。
ほどなくしてアヒルとその男が、十八世紀のフランスに実在したということがわかった。湿気で傷み、コーヒーのしみができた黴臭い文献のなかに、彼は次のような記述を見つけた。

最も有名な自動人形(オートマトン)のひとつは、ジャック・ド・ヴォーカンソンという名のフランス人技師が一七三〇年代に作ったものである。彼の作った精巧な機械仕掛けのアヒルは、生きたアヒルのように動き、生きたアヒルのように餌を食べ、生きたアヒルのように魚を消化した。内部には錘(おもり)が据えられ、一千個あまりの可動部品に接続されていた。試行錯誤の末にヴォーカンソンはこれらの部品を連動させ、アヒルをまるで生きているように動かすことに成功した。アヒルにはゴム製のチューブの消化管まであった。このアヒルをはじめ複数のオートマトンを作ったことによってヴォーカンソンは一躍有名になり、何年間もヨーロッパ各地に機械を展示してまわった。この業績によって名声が高まっていく一方で、アヒルは悪魔的な手段を用いて作られたにちがいないと考える人々は彼を白眼視した。やがて世間の関心が薄れると、彼は地方の製糸工場の監督の職に就いた。ヴォーカンソンの作品のほとんどは彼が死去した翌年に起きた火災で焼失したが、一八〇五年、かの大詩人ゲーテが、とあるオーストリア人の骨董品蒐集家のコレクションのなかに奇跡のアヒルを発見した。ほどなくして件のオーストリア人は他界し、そのコレクションが負債返済のために競売にかけられた。ここでアヒルの消息が途絶える。一八〇五年の時点でゲーテが記した言葉によれば、アヒルは見るも無残なありさまで、〈消化器系に異常〉をきたしていたという。オートマトンの内部からは異音がしたということで、一八〇六年に匿名の購入者の手に渡ってまもなく動かなくなってしまった可能性も高い。ヴォーカンソンの血縁の者は、アヒルはヴォーカンソンがもっとも大切にしていた財産であり、彼はそれが科学の謎の鍵を握っていると信じていた、との主張を繰り返している。
ここでティドウェルがアヒルを手に入れるまでのいきさつを――必死に金を貯め、ヨーロッパ各地を旅してまわり、袖の下を使って博物館員に数世紀前にさかのぼる記録を調べさせ、若い頃にアヒルを見たことがあると言い張る老婦人に話を聞かせてもらったことなどを――くどくど語っても意味がない。あるいは、ティドウェルがどんなに痛切な欲求をつのらせて旅を続けていたかを詳らかにしても仕方あるまい。
私があらゆる変装をしながら彼のあとを追い、道のりを共にしたことは言うまでもない。当時の光景は今も鮮やかによみがえる。フィレンツェのホテルのバルコニーから見た、夜明けの空に溶け合う紫色と黄色のほのかな色合い。マルセイユにほど近いワイナリーに漂っていた、輝くような緑色のぶどうの蔓(つる)の香り。ベルリン郊外の小さな村に響く、荷車をひくロバの足音。ティドウェルが聞きこみのために村のある家を訪れているあいだ、私は物陰に身を隠して彼を待っていた。あの頃のことはよく覚えている。私はひたむきでがむしゃらなティドウェルにいつしか好感を抱くようになっていた(上司たちがいつティドウェルとわれわれの求めるものに関連性がないと気づくだろうかと、ずっと気にしていたものだ)。
ともかく、ティドウェルは紆余曲折を経てついにアヒルを手に入れた。そのために罪をひとつも犯さなかったわけではない。ただ私には、アヒルを彼のものにできさえすれば、他のことはすべて許されるように思えたのだ。
ある春の雨の夜、ティドウェルはその手にひとつの箱をたずさえ、最後の旅から戻った。彼は疲れはてた様子でドアを開け、箱をソファに放り投げると、飲み物の準備にとりかかった。アヒル探しの旅をはじめてから、はや五年以上の月日が流れていた。次々と立ちはだかる難関に、この旅は失敗に終わるのだと思い知らされたこともあった。しかしついにマルセイユ近くのワイン産地にあるカフェで、ベレー帽をかぶったしわくちゃの老人が手がかりを与えてくれた。さらに手がかりをたどって、とうとうヴォーカンソンのアヒルが入ったこの箱にたどり着くことができた。
ティドウェルはぼんやりと考えた。家族や友人たちはアヒルに取りつかれてきた自分を許してくれるだろうか。たぶん、許してはくれないだろう。だが今さらどうにもならない。やってしまったことは取り消しようがない。それに――彼はウィスキーをあおりながら思った――取り消したいとも思わない。彼はもう以前の彼ではなかった。旅を続けるうちにさまざまな技術を身につけ、気がつけば危険な局面もひるむことなく切り抜けていた。次にどんなことが待っていようとも、世界はもはやそれまでの世界とは違った姿で彼の前に立ち現れた(すくなくとも、身を隠して見守っていた私にはそう見えた)。
彼はまだアヒルをほんの一瞬しか見ていなかった。あらためて目の当たりにしたその無残なありさまは、彼を動揺させるに足るものだった。片方の翼は動かなくなっていた。くちばしは欠け、片足は途中で切断されていた。かつて金属の胴体を覆っていた羽毛は抜け落ち、あるいはぼろぼろになっていて、ヴォーカンソンのアヒルはまるで解体されかけているように見えた。妙な臭いもした。古い部品から漂う、腐食したオイルの臭いだ。
修復できるのだろうか? ティドウェルには測りかねた。しかし彼はアヒルをいとしげに箱から出し、キッチンのテーブルの上に置いた。そのむかし歴代の所有者たちがアヒルにかつての輝きを取り戻そうとしたのだろう、あちこちにさまざまな修繕の跡があった。片方の目に嵌めこまれているのは模造エメラルドのようだ。首の部分にはよくレースペーパーにある模様が浮かんでいた。残っている方の足にも同じような柄が見える。アヒルはもともと自動巻きのはずだが、予備の手巻きねじさえも壊れ、起動させることは不可能だった。ヴォーカンソンの傑作は数世紀の時を越えてきた。だが、もはやただのがらくたにすぎなかった。
ティドウェルの、そして私の胸に、やるせない想いがこみあげた。彼はウィスキーのグラスを持って、機械仕掛けの鳥が載ったテーブルを前にじっと座っていた。悲しみにも似た気持ちだった。
彼は男の言葉を思い出した。破滅への、あるいは奇跡の大発見への道のりに彼をいざなったあのホームレスだ。どうしてあの男の言葉をあんなにも深刻に受け止めたのだろう。どうして、それが聞き流してはいけない命令や懇願のように思えたのだろう。
だが後悔には遅すぎた――彼にとっても、私にとっても。彼は溜息をついて立ち上がり、ねじ回しやもろもろの道具を取りにいった。旅をはじめたときから、もしアヒルを手にすることがあったら解剖してみようと思っていた。あのホームレスにはじまり、旅の途中で出会った人々――なかにはヴォーカンソンの子孫もいた――にいたるまで、さまざまな人からいろいろな話を聞くにつれ、アヒルの内部にはオートマトンとしての価値以上のものが隠されているにちがいないという確信を深めてきたのだ。
胴体を真二つにこじ開けるのはなかなか骨の折れる作業で、やり終える頃には息が荒くなっていた。しかし体の奥からわき起こる興奮が彼をつき動かした。疲労よりもむしろ勝利の高揚を覚えながら、彼は謎に包まれたアヒルの内部を覗きこんだ。
初めのうちは、特に目ぼしいものはないように見えた。歯車やレバー、錆びついたチェーン、そして腸の機能を果たしていたゴム製のチューブの残骸があるだけだ。しかしよく見ると、奥まった一角に、表面に溝が刻まれた黒い球状の物体がおさまっていた。それは人間の眼球ほどの大きさの球体で、隣にはちょうど同じ大きさの空間があった。
体からどっと力が抜けた。ティドウェルは椅子にもたれかかって頭のうしろで手を組み、笑い声をもらしはじめた。まさにこれが、あのホームレスにそそのかされてたどり着いたものだった。ティドウェルの旅は、この時はじまったばかりだった。一方、私の旅は終わりを告げた。心奪われ、怯え、後ろ髪をひかれつつも。
やがてティドウェルの頬を涙がつたった。彼はヴォーカンソンのアヒルの内部に埋もれた黒い球体に、震える指先を伸ばした。だが、まるで炎にでも触れたかのようにすぐひっこめた。手を伸ばしては、ひっこめる。彼はなんども繰り返した。
私が知るかぎり、ティドウェルは今でもそうしている。
(訳:鈴木潤)
作品について
SF/F界でいまもっとも旺盛な活動を見せている作家の一人、ジェフ・ヴァンダーミアの短篇。管理社会の灰色の雰囲気を背景に、秘密警察の工作員と思われる語り手の目に映る、平凡な男の奇妙にくすんだ色合いの執念が描かれている。ジェフ・ヴァンダーミアは意欲的にスチームパンクに関わっており、妻であり編集者のアン・ヴァンダーミアと共にSteampunk(Tachyon, 2008)以下のアンソロジー・シリーズを編纂したり、The Steampunk Bible( Harry N. Abrams, 2011)というヴィジュアル本を編集したりしている。
この作品は世界初の自動人形(オートマトン)とされるヴォーカンソンのアヒルが題材になっていることから本特集で紹介したが、もともとイギリスのポストパンク・バンドThe Fallの曲を題材にした書き下ろし短篇を集めたアンソロジー、Perverted by Language: Fiction Inspired by the Fall(Serpent's Tail, 2007)のために書かれたものであり、同名の曲”A New Face In Hell”(1980年のアルバムGrotesque (After the Gramme)に収録)にインスパイアされたオマージュである。
作風や活動範囲の幅広さからもわかるように、ヴァンダーミアは同時代のSF/F界の中心的人物とも言える。日本への紹介が心から待たれている作家の一人だろう。独特のトーンを帯びた求心力のある作品は、日本の読者にとって魅力的な新しい体験になるはずだ。というわけで、〈26to50〉は現在〈ヴァンダーミア特集〉を検討している。(鈴木)