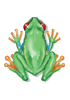クリストファー・レイヴン
シオドラ・ゴス
どうしてコリングズウッドに戻ってきたのだろう? 学園の本館につづく舗道に降りたったとき、わたしは自分の胸に問いかけた。舗道の先には樫の木に囲まれた灰色の石造りの校舎が見えた。かれこれ百年以上前からそこにある光景だ。鉄道の駅からは馬車でやってきた。遠いむかし、新学期を迎えたときとおなじように。あの頃は着替えや教科書がぎっしり詰まった、自分の体ほどもある大きなトランクをひきずっていた。今回は小さな旅行鞄ひとつだ。中身は普段着がもう一揃いと、晩餐用のドレスが一着、そして洗面用具。どうせ一晩泊まるだけだ。どうしてここに戻ってきたかって? 同窓会での講演を依頼されたから。もちろん、それだけの話だ。
「ルーシー!」ミリセント・トリヴァーが舗道のむこうからやってきた。
「ひさしぶり、トリー!」そう叫んでしまってからすぐ、学校時代の仇名で呼んだのはまずかっただろうかと思った。彼女はあの頃とほとんど変わっていなかった。相変わらずよれよれのブラウスを着ていたし、嬉しそうに抱きついてきたとき、頬にはインクのしみまで見えた。スカートの長さと後ろで束ねた髪型で――それだって今にもほつれそうだったけれど――かろうじて彼女が生徒ではなく教師なのだということがわかった。今回の同窓会にどんな顔ぶれが集まるのかは知らなかったが、すくなくともトリーがいることだけはわかっていた。わたしたちのうち、彼女だけはずっとコリングズウッドにとどまっていたのだ。
「エレノア・プレスコットが来てるわ。それから誰がいると思う? なんとメアリ・ダヴェンポートも来たのよ」彼女はわたしの旅行鞄をつかんで言った。「みんな上にいるわ。むかしのわたしたち四人の部屋に」
「どうしてあの部屋に?」わたしは彼女の後について入口の広間を抜け、階段を登った。階段に響くブーツの足音が懐かしかった。この階段を一階まで駆け下りては、遅刻ぎりぎりでフランス語や地理の授業に滑りこんだものだ。校舎はがらんとしていた。生徒たちの笑い声やひそひそ声もなければ、そこはかとない腐臭のように廊下に漂っていたキャベツの匂いもなかった。懐かしい音や匂いがあふれているものと思っていたが、校舎に漂っているのは夏休みの静けさと蜜蝋の匂いだけだった。
だが、階段を登りきったところで、見慣れた光景が目に飛びこんできた。乗馬用の上着に身を包んだコリングズウッド卿の肖像画だ。馬と猟犬を脇に従え、自分が主人であることを見せつけるように鞭を手にして、長い鼻のむこうからじっと廊下を見下ろしている。その下を駆け抜けていく何世代もの女生徒たちの姿に、きっと肝を潰し続けてきたに違いない。生徒たちのあいだには、彼を〈鼻でか卿〉と呼ぶ伝統があった。
「あら、わたしが頼んだのよ。三人とも来るってわかったとき、ハロウェイ先生にみんなであの部屋を使っていいか尋ねたの。もちろん許してくれたわ。そもそもわたしたちにあの部屋をあてがったのは先生ですものね。覚えてるでしょう?」
忘れるはずもない。そう申し渡されたとき、四人がおたがいを睨みつけたあの目つき。あれはわたしたちのコリングズウッドでの最後の年だった。よりによって天敵同士がいっしょの部屋を割り当てられてしまった。わたしはエレノア・プレスコットが嫌いだった。彼女のフランス製のドレスとか、高慢ちきな態度が気に食わなかった。いつもおどおどしているメアリ・ダヴェンポートのことは軽蔑していた。何を言うにも「ええと、よくわからないけれど……」ではじめるのにはうんざりだった。ミリセント・トリヴァーなんて問題外だった。彼女はわたしとおなじ奨学生なのに、何かにつけて必死でエレノア・プレスコットやその一派に取り入ろうとしていた。
わたしたちを部屋で出迎えたのは、ハロウェイ先生本人だった。新しく校長に就任した人で、なんでも進歩的教育理念の持ち主だということだった。「みなさん、これは名誉なことですよ」先生は言った。「ここは百年前にコリングズウッド夫人が寝室にお使いになっていた部屋です。テンプル校長のときは物置にしていましたが、今学期は生徒の数が多いためあらゆる部屋を使わなければならなくなり、こうしてきれいに片付けたのです。折しも屋根裏の整理をしていたらコリングズウッド夫人の肖像画が見つかったので、部屋に飾っておきましたよ。夫人がコリングズウッド学園の創設者であることはご存知ですね。きっとあなたがたをより深い学究の道にお導きくださることでしょう」先生はそう言って特にエレノアの顔をじっと見た。彼女は勉強よりも外で遊びまわることが好きで、もっぱらの関心事はラテン語よりもテニスだった。
わたしたちはおそるおそるコリングズウッド夫人の肖像を見上げた。透きとおるような白い肌で、見事な赤褐色の巻き毛を肩まで垂らした女性だった。瞳は灰色がかった青で、おなじ色のレースの袖のついたドレスを着ている。画家にむかって微笑みながら、膝の上で子犬をあやしている。美人というわけではない。そう呼ぶにはいささか癖のある、個性的な顔立ちだ。だがとても聡明そうな女性で、廊下の〈鼻でか卿〉よりずっと好感が持てた。
「夫人は芸術家の後援活動に熱心で、ご自身でも絵を描いたり詩を書いたりしておられました。それに素晴らしい園芸家でもあったのです。〈レディ・コリングズウッド・ローズ〉は夫人にちなんで名付けられたんですよ。そうそう、屋根裏からコリングズウッド家の歴史の本も出てきました。読んでみたいでしょう?」
わたしたちはもごもごと儀礼的な返事をした。誰もコリングズウッドの歴史に興味なんてなかった。敵同士ではあったが、おたがいが考えていることが手に取るようにわかった――もうそろそろお茶の時間じゃないかしら?
進歩的理念はさておき、ハロウェイ先生は年頃の生徒とその胃袋についても十分な心得があった。「わたしの部屋に置いておきますから、興味がわいたらおいでなさい。三十分後に食堂でお茶にしましょう。荷ほどきを終えたら降りてらっしゃい。先にいって待っています」
「お茶は何時からって言ったかしら?」エレノア・プレスコットが言った。わたしはびくっとして後ずさった。すっかり思い出に浸りきっていたところに、わたしの知っている女の子とは似ても似つかないエレノアが現れたのだ。彼女は今や〈トーリー党の恐怖〉の異名を轟かす、ソーントン・スミス卿夫人だった。物腰は学校時代に輪をかけて堂々とし、姿は長身で優雅だった。金髪は念入りにセットされており、寝台の上には豪華な羽根飾りつきの帽子が投げ出されていた。ドレスはどうやら今をときめく〈ウォルト〉のオートクチュールのようだ。ちょっとやそっとの人間では手の届かない代物だ。
「ルーシー!」目の前の彼女は言った。「あなたに会えるなんて、この上なく素晴らしいわ」彼女はわたしの両頬にキスをした。「わたし、あなたの書いた『現代のディアナ』を知り合いみんなに配ったのよ。自由恋愛と職業婦人について書かれた、この上なくセンセーショナルな本だって触れこんでね」
「正直に言うと、はじめは読むのが恐かったわ」メアリ・ダヴェンポートが言い、微笑みながらわたしを抱擁した。「でも、とても大切なメッセージが伝わってきた。神さまが与えてくださった才能を活かすということについてね」小柄でぽっちゃりしているのは変わらないが、少女時代よりも血色がよくなっていた。彼女の手紙によるところの「田舎暮らし」の賜物だろう。彼女は父親のもとで牧師補を務めていた男性と結婚した。夫は後にチャールズ・ボーモント牧師となり、一家でヨーク近郊に住んでいた。ちょうど夫がロンドンの聖職者会議に出席することになったので、「懐かしの我がコリングズウッド」を訪れることにしたのだという。
メアリには三人の子供がいた。本当は四人だったが、一人は亡くなっていた。エレノアには子供がなく、それを後悔している様子もなかった。「人間を――ひいては女性を抑圧から解放する法律。これこそがわたしの子供といえるでしょう」彼女はそう手紙に書いていた。トリーはずっと独身だった。こういったことは、十数年来の手紙のやりとりで知ったことだった。細々とではあったが、わたしたちはずっと連絡を取り続けていた。思えばコリングズウッド最後の年に経験したことが、わたしたち四人の絆を強めたのかもしれない。
わたしからも彼女たちに手紙を書いた。ルイスとの関係について。彼が結核で亡くなったことについて。幼いルイを女手ひとつで育てる苦労について。その息子が父親とおなじ病気にかかったことについて。『現代のディアナ』の売れゆきは良く、わたしは息子をスイスの療養所に入れることができた。でも、お金はいつか底をつく。コリングズウッドが汽車代と同窓会での講演の謝礼を申し出てくれたとき、わたしは二つ返事で引き受けた。そんなことでもなければ、ここに戻ってくるはずもない。
口火を切ったのはトリーだった。彼女は他の三人があえて口にしなかったことを言った。「みんなでこの部屋に集まれて嬉しいわ。またクリストファー・レイヴンの話ができるわね」
トリーがその夢を見はじめたのは、四人のうちでいちばん最後だった。だが例によって、口に出すのは誰よりも早かった。
「ねえルーシー、起きて! おかしな夢を見たわ」
わたしは瞼を開きかけ、またすぐに閉じた。「静かにしてよ。まだ夜が明けてないじゃない」
「だって、男の人が夢に出てきたの。あなた男の人が出てくる夢って見たことある? 黒い巻き毛で白いブラウスを着てたわ――すくなくとも、ブラウスみたいに見えた。女物みたいだったわ。それか海賊が着ているような。もしかして海賊なのかしら? それにしては何か――詩のような言葉を呟いてたけど。わたし、談話室の長椅子に座っていたの。本物の談話室の長椅子よりもずっと座り心地がよかったけどね。そしたら彼がやって来て、ひざまずいてわたしの手にキスをしたのよ!」
「あなたも彼の夢を見たのね!」エレノアが声をあげ、寝台の上で身を起こした。「じゃあもう彼の夢を見るのはやめようっと。〈ずぼらのミリー〉とおなじ夢を見るのはごめんだもの」
「ねえ、わたしも一週間前から彼の夢を見ていたわ」わたしは言った。「あなたはわたしたち二人とおなじ夢を見ていたことになるのよ。こういうことってよくあるのかしら? メアリは? もしかしたら彼女もおなじ夢を見ていたかも」
その時ちょうど目を開けたメアリが、毛布を頭までひっぱり上げた。
「あなたも彼の夢を見ていたの?」エレノアが尋ねた。「メアリ、答えなさいよ!」
「ええ」くぐもった声が聞こえてきた。「一週間前から」
「手にキスされた?」トリーが訊いた。
メアリは毛布の下から顔を出した。頬が赤く染まっていた。「いいえ。二人でこの部屋にいたの。でも、大きな寝台があった。彼はわたしの肩にキスをしたわ」
「わたしにはキスしなかった」わたしは言った。「彼はわたしを庭に散歩に連れ出して――わたしの髪や目のことを、詩みたいな言葉で語ったわ。トリーの言うとおり」
「ふうん。わたしはキスされたわよ」エレノアが言った。「わたしたちは塔のてっぺんからコリングズウッドを眺めていたの。彼はわたしが月のように移り気だ、とかそんなようなことを言ったわ。そしてわたしの“くちびるに”キスをした」
その日、はじめて四人は談話室に集まった。最上級年の生徒だけに許されている部屋だ。いったい何がどうなっているのか、そこで話し合うことにしたのだ。
「彼は幽霊なのよ。わたしたちはとりつかれているんだわ」メアリが言った。彼女の父親は心霊研究会のメンバーだった。
「ばかなこと言わないで」エレノアが言った。「幽霊なんてものいるわけないわ」
「いいえ、いるわよ」トリーが言った。「うちのハリエット叔母さんは死んだ叔父さんの幽霊にとりつかれたのよ。叔父さんは海で片足を失くしたの。叔父さんの幽霊は、ごつん、ごつん、ごつんって、木の義足の音を響かせて夜中に廊下を歩きまわったんですって」
「やだ」メアリが言った。「怖がらせないでよ!」
「でも、彼が幽霊だとしたら」エレノアが言った。「他の生徒にもとりついてるかもしれないじゃない。誰もそんな話してないわよ」
そこでわたしたちは、他の生徒たちに前の晩どんな夢を見たか尋ねてまわった。黒い巻き毛に褐色の肌の異国風の顔立ちの男、あるいは微笑みかけるような黒い瞳の男の夢を見たという子はひとりもいなかった。インドに住んでいるお兄さんの夢を見たという子がいただけだった。
やっぱり、あの夢を見たのは四人だけだった。
わたしたちは取り決めをした。毎朝、情報交換すること。おたがいにどんな夢を見たか教えあうこと。細かいところまでぜんぶ、どんなに言いにくいことでも包み隠さず話すこと。そして彼が言ったことをできるかぎり覚えておくこと。詩のような言葉は、目覚めとともに水のように頭からこぼれていってしまいそうになる。でも、それをなるべく忘れないようにすること。
「彼はわたしの瞳は輝く星のようだって言ったわ」トリーが言った。
「まあ、冗談でしょ」エレノアが言った。「あんたの目はふつうの目よ。彼はわたしの髪は森を焼きつくす炎のようだって言ったわよ。まあ、もっと別の言い方だったけど。それにたしか韻を踏んでたわ。思い出せないけど」
「覚えてなきゃだめじゃない」わたしは言った。「みんなメアリを見習いなさいよ」
わたしは毎日みんなが見た夢の内容と、そのなかで聞いた詩の一部と思われるものを帳面に書き記していた。
エレノア:高い塔で、月明かりの夜に「滝の白糸で編まれたガウン」「甘美なる服従」それから「恍惚に死す」とかそんなようなこと。
メアリ:暖炉の前で、首筋にキスをしながら「白鳥のような首」「誇り高く美しい」「その豊潤たる髪」
トリー:廊下ですれ違いざまに手紙を落として「愛する人、その胸もとに忍ばせたまえ」「我は闇夜にきみを訪れし月光のごとく」
ルーシー:何度か情熱的なキスをして「愛の真義」(ひょっとしたら「愛の遊戯」の聞き違えかも?)
この頃には、全員が彼とのキスを経験していた。わたしたちは頬を染めながら報告しあった。
「それはとても――柔らかかった」メアリは言った。「いけないことよね? いくら夢だっていっても」
「力強かったわ」エレノアは言った。「やめてって頼んでもやめなかったんじゃないかしら。夢だったら別にかまわないんじゃない?」
「男の子とのキスもあんな風なの?」トリーが尋ねた。
「ぜんぜん違うわ」従兄弟がいるエレノアが言った。「もっと気持ち悪いものよ」
「彼の正体を知る手がかりはまだひとつもつかんでないわよ」わたしは言った。「詩人だってことはわかった。言葉遣いからしてね。つまり、誇り高く美しいとかそんな言い方するところからして。もし彼が幽霊だとしたら、コリングズウッドで死んだ詩人がいたかどうか調べてみなきゃ」
「幽霊なんてものいるわけないわ」エレノアが言った。
「ハロウェイ先生の部屋にある本を調べたらどうかしら?」トリーが言った。
そんなわけで、わたしがハロウェイ先生のところから本を借りてくることになった。いちばんそういうこと――エレノアに言わせれば「つまらないものを読んだり」しそうな手合いだということで送り出されたのだ。
「喜んでお貸ししますよ、ルーシー」先生は言った。「学校の歴史に興味を持ってくれて嬉しいわ。他の子たちは、そうね、たぶん卒業したら家庭におさまるのでしょうね。でも、わたしはあなたにはもっと別な道を切り拓く能力があると思っています。何かもっと、知的な職業に就く才能がね。真剣に考えてみて欲しいの。現代の女性にはたくさんの機会があるのです。わたしがあなたの年頃にはあり得なかった機会がね」
「はい、先生」わたしはどうにかしてお説教を逃れたかった。この頃には、わたしたちはハロウェイ先生の進歩的教育理念の何たるかを心得ていた。これまで男の子だけのものだった教育を女の子も受けてしかるべきだ、という主張はそのひとつであり、先生はことあるごとにわたしたちに女性の進歩について語ってきかせた。結局、逃げおおせることはできなかったけれど、心配していたほど長くはかからなかった。先生は校長室を出るわたしの背中にむかって語りかけた。「ルーシー、大学進学のこと、真剣に考えてみてちょうだいね」最後の言葉は扉のむこうから聞こえてきた。
「それで、誰がこれを読むの?」エレノアが言った。わたしは『コリングズウッド家の歴史――十字軍時代から現在まで』をみんなの前にさし出していた。長年しまいこまれていた本を運んできたおかげで、わたしまですっかり埃まみれだった。
「何頁あるの?」メアリが言った。
それはすでにたしかめてあった。「792頁。しかも索引なしよ」わたしは言った。
三人の視線は『コリングズウッド家の歴史』を読むのが誰の役目かを明白に物語っていた。あなたは作文で賞を取ったことがあるし、それに英語の成績はクラスで一番じゃない? というわけだ。
やっと157頁まで進んだある朝、メアリがはっと大きく息を飲みながら目を覚ました。わたしたちはあの手この手を使って問い詰めたが、彼女はどうしても夢の内容を話そうとしなかった。
「言えないわ」彼女は言った。「わたしたちまた寝室にいたの。そしたら彼が――だめ、やっぱり言えない」
わたしたちは寝間着のままエレノアの寝台に集まっていた。毎朝恒例の告白会の光景だった。
「どんな風だった?」わたしは言った。みんな子供ながらも見当はついていたのだと思う。トリーとわたしは田舎育ちで農園の家畜を見慣れていたし、エレノアは使用人たちの噂話に囲まれて育った。
「ごめんなさい。どうしても話せないわ」
「そんなに恐ろしいものなの?」トリーが身を乗り出した。
「恐ろしくないわ。でも――言えないのよ。わかってちょうだい」結局、わたしたちは彼女から何も聞き出せなかった。
その日の昼下がり、わたしは絶望的な気持ちで分厚い『コリングズウッド家の歴史』を眺めた。もうこれ以上、〈主のご生誕より何々年のコリングズウッドの訪問客〉なんて記録をじっくり調べるのはうんざりだった。
「まどろっこしい本め」わたしは叫んだ。「いいからさっさとわたしが探しているものを出しなさい」わたしは目を閉じてでたらめに本を開き、その頁に目を走らせた。
1817年の秋、コリングズウッド卿はロンドンで知り合った詩人のクリストファー・レイヴンを屋敷に招待した。コリングズウッド夫人はこの好青年を大いに気に入った。作品についてはシェリーの二番煎じとの見方をする批評家もいたものの、詩人は英国のアドニスとたとえられるような容姿であったという。当時、コリングズウッド家の膨大な蔵書は混乱を極めており、卿はレイヴンにその目録の作成を依頼していた。しかし、作業が遂行される前に二人に不和が生じ、詩人はある真夜中に屋敷を出てシェリーやバイロンのいるスイスへとむかった。その道中のアルプスの山道で、雪嵐に見舞われ消息を絶ったとされている。わけても詩人や芸術家、子犬への恵愛が豊かだったコリングズウッド夫人はこれを嘆き悲しみ、何週間も床に臥せった。
とうとう詩人が見つかった。しかもまさに探していた詩人のようだ。アドニスはギリシア神話の人物だ。ギリシア人ということは、黒い巻き毛にちがいない。いわゆる「美少年ヒュアキントスの髪」というものだ。
「どうやら彼を見つけたみたいなの」その午後、わたしはエレノアとメアリとトリーに報告した。「名前はクリストファー・レイヴン。彼は詩人で、コリングズウッド夫人に恋をしていたようよ。そして夫人の方も彼に恋をしていた」
「どうしてわたしたちがその人の夢を見るわけ?」トリーが言った。「これまで誰か彼の夢を見た人がいたら、耳に入ってきたはずじゃない? つまり、彼がコリングズウッドにとりついている幽霊なんだとしたら、あの肖像画を〈鼻でか卿〉って呼ぶ習わしみたいに、生徒たちのあいだで語り継がれているはずよね」
「わたしたちが夫人の寝室を使っているからじゃないかしら」わたしは言った。「本には夫人が彼を気に入ったとしか書いていないけど、夢のなかでわたしたちが聞いたことは、彼が夫人に言ったことに違いないわ。だって、わたしたちの誰が白鳥のような首をしてるっていうの? それに燃える髪っていうのもそう。あれは夫人の赤毛のことよ。きっとこの部屋は半世紀のあいだずっと使われていなかったんだわ。だから彼の夢を見たのはわたしたちがはじめてだったのよ」
「問題は、これからどうするかってことよ」エレノアが言った。「彼はわたしを怖がらせたりしないわ。でも、メアリが見た夢は――ええ、どうしても言えないっていうんでしょ。でももうみんな何のことだか知ってるんだから。このまま彼とコリングズウッド夫人の夢を見続けたら、この先どうなってしまうのかしら?」
わたしたちには見当もつかなかった。いったいどういうつもりなの、クリストファー・レイヴン? わたしはコリングズウッドを出てから愛というものを知った。あなたは夫人に愛を、詩人の愛が往々にしてそうであるように、情熱的な愛を捧げた。その愛はときに独りよがりなものであり、ともすれば愛が詩にすり替えられてゆく。でも、あなたが彼女とならんで庭の小径を歩いたとき、彼女の傍らで塔の上から田園を眺めたとき、彼女を月にたとえ、みずからを月に弄される潮の満ち干にたとえたとき――あなたの愛は情熱にあふれ、いつも次の一行を考えている詩人の愛に他ならなかった。わたしたち四人は身をもってその愛を知った。まだほんの子供だった頃、教室で机にかじりついているべきときに、詩人の愛に溺れていた。暗闇での口づけを感じ、あなたの手が彼女の肩に触れるのを感じ、指先が鎖骨をなぞるのを感じた。あなたが彼女の体からくすんだ青い絹のドレスをそっと引きはがすのを感じ、そして、まだ知るべきではないもの、受け止める覚悟のできていない熱情を感じた。
数週間のうちに、わたしたちはすっかり変わってしまった。みんなずっと夢のなかにいるみたいにぼうっとしていた。授業にも身が入らなくなった。エレノアはテニスをやめ、トリーといっしょに部屋にこもっては、前の晩の夢をひそひそ話し合った。メアリは四六時中お祈りをしていた。あんな夢を見るのはやっぱりいけないことだわ、と彼女は言った。だが、他の三人とおなじように、もう二度と彼の夢を見たくないとは決して言わなかった。彼女は目の下にくまをこしらえ、時おり訳もなくびくっと震えあがった。まるで他の三人には聞こえない物音に驚いているようだった。わたしはというと、みんなとおなじように夢見心地ではあったけれど、そんな風に何かにとりつかれたようになることに怯えてもいた。メアリの変わりようを目の当たりにするにつけ心配は募った。まるでわたしたち四人はどこか夢の国に迷いこみ、ありふれた学園生活から切り離されてしまったみたいだった。
そしてとうとうハロウェイ先生がわたしに尋ねた。「ねえ、ルーシー」作文の時間、先生は机におおいかぶさるようにしていたわたしの肩に手をおいた。わたしは帳面に〈CR〉という頭文字を何度も書いていた。「いったいあなたたちに何があったのです? ミリセントはきのうのラテン語の授業で居眠りしそうになるし、近頃メアリの様子がどうもおかしいという話も聞きました。何かわたしに報告することはありませんか?」
正直に答えるべきだったのかもしれない。でも、あの口づけや黒い瞳の放つ熱っぽい視線を、わたしたちに「女神」や「愛しい人」と呼びかける、これまで聞いたこともないような甘い囁きを、どうして手放せただろう?
「お喋りに夢中になって夜更かししてしまったようです」わたしは言った。先生は怪訝そうにわたしの顔を見たが、それ以上は追求しなかった。
あるいはそんな状態がいつまでも続いたかもしれない。あの朝、エレノアが目を覚ますやいなや金切り声をあげなかったら。
「コリングズウッド卿が彼を殺したわ!」彼女は叫んだ。「彼が夫人と逢びきしているところを発見して、彼に杖で殴りかかったの! あたり一面が血だらけになったわ!」彼女は両手で顔をおおってしくしく泣きはじめた。あのエレノア・プレスコットが涙を流すなんて信じられなかった。わたしは背筋が寒くなった。
次の晩はトリーがその夢を見た。その次はわたしだった。まったくおなじ夢だった。真相が発覚し、後頭部に恐ろしい一撃がふるわれ、床に血の海が広がり、やがて何も見えなくなる――それが夢の幕切れだった。メアリだけはこの夢を見ていなかった。彼女はもうじゅうぶんだ。もしかしたら幽霊はそう考えたのかもしれない。たしかに、彼女はこれ以上の重荷には耐えられそうになかった。
今回ばかりはハロウェイ先生から呼び出しがかかった。「いったい何があったのです?」先生はわたしたち四人に言った。「夜中じゅう呻き声が聞こえたとか、朝には叫び声がしたとか、いろいろと報告を受けましたよ。それにあなたがたの顔といったら。まるで一週間ろくに寝ていないみたいじゃないですか」
「ハロウェイ先生」わたしは言った。「わたしたちとりつかれているんです――幽霊に」そして事の次第を洗いざらい話した。
「おやまあ」先生は言った。「わたしの目と鼻の先でそんなことが起こっていたなんてね! とりつかれているなんてばかげています。いいですか、ルーシー。幽霊なんてものは存在しません。もっとも、あの部屋の雰囲気が――それにコリングズウッド家の本を読んだことも手伝って――そんな夢を見させたのかもしれないわね。ただちにあなたたちを移動させます」
わたしたちはハロウェイ先生の自室に移され、そこでしばらく様子を見ることになった。だが夢は終わらなかった。
「目の前が赤い血に染まったと思ったとたん、何も見えなくなるの」トリーが言った。「彼がくずれ落ちた後は、音も色もなくなったわ。床に血の海が広がって、それからまるですべてが闇に包まれていくみたいに」
「わたしには音が聞こえたわ」エレノアが言った。「トリーの叔父さんがたてたみたいな、ごつん、ごつん、ごつんって音が」
「ハロウェイ先生」わたしは言った。「コリングズウッド卿が玄関広間で彼に襲いかかって、その後でエレノアが言ったような音がしたんです――卿が彼の死体をひきずって階段を降りていった音に違いないわ。地下の物置にむかっていったんです」
「どうやらいよいよ頭のお医者さんに診てもらわなきゃいけないようね」ハロウェイ先生は言った。
わたしたちは何も言わず先生の顔をじっと見つめた――メアリは特に、詰め寄るようなまなざしを先生にむけた。「まったくもう――わかりましたよ」先生は言った。「地下室ですね」
「ここには何もないわよ」トリーが言った。
「ちょっと待ってよ」エレノアが言った。「まだ〈司祭の隠れ場〉だって探してないじゃない。ヒリングドンのわたしの家にはそういう秘密の階段部屋があるの。まあもっとも、その手のものがない家に住んでいる人もいるんでしょうけどね。ともかく、わたしは慣れてるから」
わたしは数週間ぶりにエレノアをひっぱたいてやりたいと思った。でも声が妙に甲高くなっているところをみると、彼女は興奮しつつも怯えているようだった。それに手際がいいのは事実だった。彼女は地下室を歩きまわって壁を上から下までとんとん叩き、怪しい音がするところはないかたしかめていった。地下室の壁は建物の基礎の表面部分だった。歴史をさかのぼることノルマン時代に造られたものだ。わたしは『コリングズウッド家の歴史』を(すくなくとも157頁までは)読んでいたので、そのことを知っていた。ずいぶん頑丈そうな基礎だった。
だが、エレノアは言った。「この地下室、屋敷の面積にくらべて狭いと思わない?」たしかにそのとおりだった。
地下室に何もないなんて、あきらかにトリーの早とちりだったようだ。そこには石炭入れや薪の束、使い古しの箒やブリキのバケツなど、どこの地下室にもあるようなものがずらりとそろっているのはもちろん、〈女学校の残骸〉とでもいうべきがらくたが山のようにあった。床には壊れた椅子、松葉杖、運動用品がひしめきあい、壁にはスキー板がずらりと立てかけられ、さらに壊れたテニスラケットが驚くほどたくさんあった。
「ねえ!」エレノアが叫んだ。「聞いて。わかる?」
たしかに妙な音がした。ある方角の壁に、背の高い本棚がたてかけてあった。もともと図書館で使われていたもののようだったが、あちこちに水じみができて埃をかぶっていた。棚には玉葱のようなものが詰まった箱が置いてあったが、よくよく見ると、箱に〈チューリップ――早咲き〉〈遅咲き〉〈レンブラント種〉というラベルが貼ってあった。それからスケート靴が何足か詰めこまれていた。もちろん本もいくらかはあったが、生徒用にも使えないくらい傷んでいた。
「庭師のアミアスがチューリップの球根をねかせているんですよ」ハロウェイ先生が言った。「なんでも、保存するにはうってつけの場所なんですって」
「この壁のうしろは空洞になってるわ」エレノアが言った。壁を叩いたときに返ってきた虚ろなこだまは、わたしたちの耳にもしっかりと届いていた。
「わかりましたよ」ハロウェイ先生は言った。「本棚のうしろを調べてみましょう」
メアリがランプをかかげ、あとの三人はハロウェイ先生を手伝って、棚からせっせと本やスケート靴やチューリップの球根の箱を床に下ろした。「重そうだわね」先生は言った。「アミアスと手伝いの男の子を呼びましょうか?」わたしたちはいっせいに首を横にふった。このうしろに隠されたものを一刻も早く、できるかぎりわたしたちだけでたしかめたい――みんなの意見は一致していたのだと思う。「いいでしょう、それでは」先生は言った。「全身の力をかけていっせいに押すのよ」
わたしたちは力を合わせて本棚を押した。いったん息をついたとき、トリーとエレノアとわたしはふと顔を見合わせた。二人の顔には血の気がなかった。わたしもおなじように真っ青な顔をしているに違いない。壁を照らすランプの灯りが上下にゆらゆらと揺れていた。きっとメアリの手も震えているのだ。だが、ハロウェイ先生は毅然としてひるむ様子もなかった。その時わたしは思った。例のお説教にはうんざりだけど、先生には見るべきところがある。いろいろ考えてみれば、ハロウェイ先生みたいになるのもそう悪いことじゃないかもしれない。
本棚はぎしぎし音をたてながらすこしずつ壁から離れ、とうとう裏に隠されたものが見えてきた。それはぽっかりと開いたアーチ状の穴だった。奥には暗闇以外、何も見えなかった。
わたしたちのなんと果敢だったことか。全員で――メアリ・ダヴェンポートもふくめて――その暗闇に分け入っていったのだ。道の先には倉庫よりいくぶん狭い部屋があった。ワインの貯蔵室だったとみえ、壁には釣り棚が残っていた。
やがて、ランプの灯りの円のなかに男の骸骨が浮かびあがった。胴には糸のようになった白いシャツの繊維がかろうじて残り、足もとにはずいぶん前に鼠に齧(かじ)られたとみられる黒皮の長靴の欠片が残っていた。足首には鉄製の枷(かせ)がはめられ、そこから伸びている鎖は壁に繋がれていた。男の手が届きそうで届かないくらいのところに、水入れとおぼしき椀(ボウル)が転がっていた。
わたしたちは呆然とした。やがてメアリがかすかに息を漏らしたかと思うと、どさりと床に倒れた。ハロウェイ先生は彼女がくずれ落ちるすんでのところで、その手からランプをひったくった。他のみんなはただ突っ立っていた。その数分は永遠とも思われた。やがてハロウェイ先生がメアリを抱きかかえ、階段をのぼっていった。地上には秋の陽射しが降りそそいでいた。ランプのほの灯りしかない地下室から這い出てきたわたしたちは、異様な感覚に陥った。先生はメアリを長椅子に座らせ、気つけ薬をかがせて目を覚まさせた。他の三人にはシェリー酒を一杯ずつよこし、トリーはグラスに口をつけるとむせこんだ。
やがてハロウェイ先生が言った。「なんておぞましい話でしょう」
「夫人は知っていたんでしょうか?」トリーが言った。「彼があそこで――」
「死にかけていたこと」わたしが続けた。「幾日もかけて、すこしずつ」
「夫人は知らなかったのよ」エレノアが言った。「わたしたちの見た夢は、彼女が見たとおりの光景だったんだと思うわ。彼女はコリングズウッド卿が杖で彼を打ちのめした後のことは知らないのよ。気を失ったのかもね、メアリみたいに」
「彼が死んでしまったと思いこんだんじゃないかしら」トリーが言った。
「そしてコリングズウッド卿はみんなに、レイヴンと仲違いしたんだって言いふらしたのね。だから彼はスイスに旅立ってしまったんだって」わたしは言った。
「でも、夫人はそれからもここで変わらず暮らしていた――着替えをしたり、庭を散歩したり、夕食をとったり――真下で彼が死にかけているとも知らずに!」メアリは言い、しゃくりあげて泣きはじめた。ハロウェイ先生はふたたび彼女の鼻のそばに気つけ薬の瓶をかざした。
「去年の夏に校長に就任した後――」先生は言った。「あの本を読みました。ルーシーが投げ出した『コリングズウッド家の歴史』をね。もうすこし先までこらえていたら、あなたがたもコリングズウッド卿が事件の翌年の1818年に亡くなったというくだりに気づいたでしょうに。卿は心臓の病気で死んだということになっていますが、毒を盛られたという噂もあったようです。狐の手袋(フォックスグローブ)から抽出されるジギタリスという薬は、一定の量をこえると危険な毒薬になるのです。コリングズウッド夫人はこの学校を設立したとき、夫である卿の肖像画をいつまでも中央の階段にかかげておくよう申しつけたといいます。こうなってみるとわからないわね。夫人なりの冗談だったのかしら」
「夫人はその後どうなったんですか?」わたしは言った。
「フランスに移り住み、やがて画家になりました。並外れて高い評価を得たわけではないけれど、作品は国立美術館にも所蔵されています。好んで花の絵を描いたようです」そしてハロウェイ先生は一瞬黙りこんだ。「――彼をきちんと埋葬してあげなくてはね」先生は言った。「これで夢も終わりになるでしょう」
そうはならなかった。わたしたちはコリングズウッドを離れるまでずっと夢を見続けた。だが、これまでの夢とは性格が違った。地下室の一件のあとの夢では、わたしたちは彼とただ穏やかに寄り添っているだけだった。広間の暖炉の前で語らい、図書室をそぞろ歩き、本を手に取っては詩を朗読しあい、薔薇の花が咲き乱れる庭をならんで歩いた。そこには〈レディ・コリングズウッド〉と呼ばれる美しい白薔薇も咲いていた。彼は相変わらずわたしたちの耳もとに詩を囁き、わたしたちの手に、そしてときには肩に口づけをすることもあった。だがそこにはもう、以前のような激しさや切なさはなかった。わたしたちがあまりに早く体験してしまったもの、そしてわたしたちを永久に変えてしまったものは。やがてわたしたちはコリングズウッドを離れた。エレノアはロンドンへ社交界デビューに、メアリは日曜学校の教師をつとめるべく父親の教会へ。トリーはニューナムの師範学校に、そしてわたしはガートン・カレッジへ。わたしたちはもう、新学期におたがいを睨みつけた女の子ではなかった。成長し、世界の喜びと痛みを知り、そして友情という絆で結ばれていた。
クリストファー・レイヴンの遺骸は庭に埋められ、墓石にはこう記された。「ここに詩人クリストファー・レイヴン眠る――コリングズウッド夫人の思い人。1796年生、1817没」その下には彼の作った詩が刻まれていた。
夜空に輝く星のごとき、その瞳を道しるべに
我たどりつきし、詩のいずる場所に
大人になってから、わたしは彼の詩を読んでみた。彼は二冊の詩集――『オーロラ、あるいはその他の詩』、『人間の権利についての詩』を発表していた。とてもいい詩だった。生きていたらきっと素晴らしい詩人になっていただろう。もっとも、シェリーやキーツには及ばなかったかもしれない。だが、彼が暗闇で寄せる口づけや耳もとに囁く言葉を思い返すとき、そんな考えはどこかへ消えていた。きっと夫人もそうだったはずだ。彼女は彼を愛していた。詩人は彼という人間の一部にすぎなかった。すくなくとも今のわたしはそう思っている。愛というものを知った今――ルイスを愛し、詩人を愛することがどういうことかを知った今では。
「みんな変わったわよね」わたしは言った。「エレノアはずいぶん角(かど)がとれたわ」
「まあ!」彼女は笑った。「わたしは丸くなんかなっていないわよ。女性参政権をめぐる集会で腰抜けの議員どもを蹴散らした勇姿を見せてあげたかったわ! 今やわたしの政治的影響力には、あいつらだって縮み上がるんですから」
「それにメアリはいっそう信心深くなった」わたしは言った。
「そのとおりかもしれないわ」メアリは言った。「わたしはずっと怖かった。人生ってあんな風に、一瞬激しく燃えさかって突然闇についえるものなんじゃないかって、ずっと怯えていたの。だから父の信仰にすがった。人間の弱さというものに寛容になれなかった時期もあったわ。まだルイスが生きていた頃、いちどロンドンに用事で出かけたことがあった。けれどわたしはあなたを訪ねようとはしなかったのよ、ルーシー。ごめんなさい。チャールズ坊やを亡くしてはじめて、わたしは人間の弱さを受け入れられるようになった。神さまはちゃんと見てらっしゃる。神さまは光のなかだけでなく、闇のなかにもいらっしゃるんだということがわかったの」
わたしたち三人はメアリの顔をのぞきこんだ。「いつから哲学者になったの?」エレノアが言った。
メアリの頬が赤く染まり、みるみる完熟の林檎のようになった。「大人になっただけよ。みんなとおなじように」彼女はわたしの方を向いて言った。「愛するものを失くしてみて――あなたもきっとコリングズウッド夫人の気持ちがわかるようになったでしょう」
「たぶん、多少はね」わたしは言った。「でもルイスは誰かにとりついたりしない。わたしたちの愛はごくふつうの人間の愛だった。ああ、たしかにわたしに寄せて詩を書いてくれたこともあったけどね。でもわたしはコリングズウッド夫人ではないもの。いちど彼の奥さんをフランスに訪ねていったことがあるの。施設に入っているなんていうと不穏な想像をするかも知れないけど、本当にとても穏やかな生活を送っていたのよ。親切な看護婦に面倒を見てもらってね。彼女はわたしが誰なのかわからなかった。クリストファー・レイヴンとコリングズウッド夫人の愛は――情熱と詩だった。暴力で幕を閉じるしかなかったのかもしれない。だって他にどんな結末があり得たっていうの? 二人が人里離れた小屋に暮らしているところなんて――彼が薪割りをして、彼女が布巾に刺繍しているところなんて想像できる?」
「どちらが幽霊だったのかしら?」わたしたちはいっせいにトリーの顔を見た。思いがけない質問だった。「つまりね、わたしたちにとりついたのは彼だったのかしら? 彼女がわたしたちを通じてもういちどこの世を生きようとしていたんじゃないのかしら?」
「そんな風に考えたことはなかったわ」わたしは言った。
「コリングズウッドに戻ってきたとき、あるものを見つけたの」トリーは言った。「夏休みで学校にはひと気がなかった。わたしはこの部屋に入って、自分でもなぜかわからないけれど、コリングズウッド夫人の肖像画の裏をのぞいてみる気になったのよ。そうしたら、絵の裏にあるものが貼りつけてあった」
「何を見つけたの?」わたしは訊いた。わたしたちは好奇心旺盛な女生徒に戻ったように身を乗り出した。
「手紙か何かでしょう」エレノアが言った。
「いいえ、そうじゃない」トリーが言った。「今見せるわ」彼女は部屋の隅にある机の方に歩いていった――ずっとむかしにわたしたちが使っていたものだ。彼女はその古い机の上に寝せてあった額縁を取り上げ、わたしたちにかかげてみせた。
メアリがはっと息をのみ、エレノアが叫んだ。「彼だわ!」
人物の肩から上だけを描いた水彩画だった。だが、そこにはまごうことなき黒い巻き毛と褐色の頬、そして微笑みかけるような悪戯っぽい瞳があった。絵の右下には〈アデラ・コリングズウッド〉というペン書きの署名が見えた。
「夫人がどんなにか彼を愛していたかわかるでしょう」トリーが言った。「あの幽霊が彼女だったとしたら、きっと彼をきちんと弔って欲しかったんだわ」
「でも彼女は彼が地下室にいることを知らなかったのよ」わたしは言った。「いいこと、ここで問題なのは幽霊の性質よ。たぶん、あれは彼ら二人の幽霊だったのよ。二人の魂がわたしたちを通じてもういちどこの世を生きていたんだわ」
「あなたも変わったわね」エレノアが言った。「優等生でいることしか考えてなかったのに、あのことがあってから――物語を作るようになった」
「結局、わたしはまんまと彼女に“導かれた”みたいね」わたしは言った。「ハロウェイ先生が望んだとおり」
「でも、トリーは変わってないわね」エレノアは言った。「そうでしょう、トリー? あなたはあの頃のトリーのままだわ。肖像画の裏をたしかめてみるなんて、いかにもあなたらしいじゃない。わたしは絶対に思いつかないわ」
「どうかしら」トリーは言った。「変わってないかもね。生徒を叱りつけてばかりで、眉間の皺は増えたかもしれないけれど」
そのとき、ドアにノックの音がした。どうやらわたしたちは、はるか遠い過去の話に夢中になりすぎていたようだ。
「みなさん、あと三十分で晩餐会がはじまりますよ」ハロウェイ先生の声がした。
「そろそろ仕度しなきゃ」メアリが言った。「晩餐会に遅れたらたいへん」
「どうしてよ?」エレノアが言った。「待たせておけばいいじゃない。今夜の主役はここにいるのよ。まさか彼女抜きではじめるわけないでしょう。どう、ルーシー? わたしはまだまだ丸くなんかなっていないわよ」皮肉っぽく言いながらも、彼女の顔には微笑みが浮かんでいた。
やがてお喋りはドレスのことになった。エレノアはトリーに自分の荷物のなかから二番目にいいドレスを貸した。それでも、わたしの衣装が箪笥ごとそっくり買えるくらいの値段がしそうだった。もっとも、トリーは最後まで自分の灰色のメリノのドレスでじゅうぶん場にかなっていると言い張った。何はともあれ彼女も立派な淑女に変身したところで、わたしたち四人は階段を降り、廊下を睨んでいる〈鼻でか卿〉の視線をすり抜けて食堂にむかった。
わたしの講演――『女性の権利の重要性』はおおむね好評のうちに終わった。会場の拍手のなかから、「賛成!」とエレノアの威勢のいい掛け声が聞こえてきた。食事はわたしたちがいた頃よりもずっとよくなっていた――なんといってもキャベツが出てこないのだから! だが、こうしてたくさんの同窓生たちが食堂のテーブルを囲み、わたしの顔をのぞきこんでいるのはなんだか不思議な感じだった。見覚えのある顔もあったし、忘れてしまった顔もあった。他の学年にいた顔もあった。わたしは時おり彼女たちに少女時代の面影を見た。それはこだまのようにふっと彼女たちの顔に戻ってくるのだった。
晩餐会がおひらきになり、わたしはようやく息をついた。義務も果たしたことだし、これでやっと部屋に戻れる。ドレスを脱ぎ捨てて寝台にもぐりこめる――大むかしに眠っていた寝台に。
「きっとみんな今夜は彼の夢を見るわよ」トリーが言った。
「ごめんこうむりたいわね」エレノアが言った。「クリストファー・レイヴンは一生のうちにあれだけ経験すればもうたくさんよ」
あくる朝、メアリは汽車の時刻に合わせて早くに出発し、次いでエレノアが活動資金集めの会合のためにいそいそと帰っていった。わたしは汽車の時刻まで時間があったので、トリーと二人で庭を散歩した。遅咲きの薔薇の匂いにつつまれながらそぞろ歩くうち、やがて彼の墓石にたどり着いた。
「クリストファー・レイヴンか」わたしは言った。「もういちどくらい彼の夢を見てもよかったかもね、四人の再会の記念に」
「でも見なかったんでしょう?」トリーが言った。
「ええ」わたしは言った。「でもね、ちょうど次の本の構想を練っているところなの――出版社にせっつかれていてね。もちろんお金のためもあるわ。『現代のディアナ』みたいに売れる本を期待されているんだけど、コリングズウッド夫人のことを書こうと思っているの。そうね、タイトルは『アデラ――その自由と愛』きっとみんなをあっと言わせる本になるわ」
「ルーシー、あなたもエレノアの言うとおりだと思う? つまり、わたしは変わっていないって」
わたしは彼女の顔をしげしげと眺めた。「ほかの三人にくらべたらね。たぶんずっとコリングズウッドにいるからじゃないかしら」
「いいえ、それだけじゃないのよ」
トリーの声の調子を聞いて、わたしは思わず聞き返した。「トリー、何かあったの?」
「いいえ。ただ、他の二人の前では話したくなかったの――わたしはまだ彼の夢を見ているの」
「どういうこと?」わたしは言った。
「毎晩、彼が夢にあらわれるのよ。あの絵を見つけたとき、わたしは額に入れて三階の自分の部屋に飾ったの。そしたらまた彼が夢に出てくるようになった。あなたたち三人もあの部屋で彼女の肖像画の下で眠れば、きっとまた夢を見るだろうと思っていたんだけど。やっぱりわたしだけだったのね」彼女は口をつぐんだ。墓石の前に膝をつき、指先で石碑の文字をなぞった。「たしかにずっとここにいるからかもしれない。わたしはずっと独身で子供も産まなかった。あなたやエレノアやメアリが経験してきたようなことをしてこなかった。だから夢が戻ってきた。それがわたしの人生なのよ。毎年毎年新しい生徒を迎え入れ、そしておなじ夢を見続ける。ねえ、そんなのって気味が悪いって思う?」
「髪がほつれてるわ。直してあげる」わたしは彼女の髪をピンで留めなおした。そのまま隣にひざまずき、彼女の横顔をじっと見つめた。憐れみと共感が同時にこみあげてきた。しばらくの沈黙ののち、わたしは口を開いた。「いいえ、トリー。気味が悪いなんて思わないわ。愛を目の前にしてひるんではいけない。それがわたしがルイスから学んだことよ」
「ありがとう」彼女は言った。立ち上がりながら、手のひらでうしろ髪をそっとたしかめた。「どうやってもほつれてきちゃうのよ。あなたはずっといちばんの親友だったわね」
「よく言うわ。いつだってエレノア・プレスコットの後をついてまわってたくせに」そう言いながら、わたしは彼女の肩に腕をまわし、頬にキスをした。
そして出発のとき――馬車の音が舗道に響き、わたしはコリングズウッドの屋敷を振り返って、トリーに手を振った。彼女に会うのはこれが最後かもしれない。もう二度とここを訪れることはないだろう。わたしには戻るべき大きな世界がある。そこには悲しみや、喪失や、孤独がある。でも同時に、成功が、そして友情がある。ロンドンの馴染みのカフェがあり、書店のウィンドウにはわたしの名前が刻まれた赤い革張りの本がならんでいる。そしてアルプスがある。わたしはスイスの療養所にいるルイのことを思った。小さな肺を震わせて咳をしながら、わたしを見上げる息子のことを。父親から受け継いだ、その世界でいちばん美しい瞳のことを。わたしの住む世界はここよりずっと過酷なところだ。でも、彼女の世界と取り替えたいとは決して思わない。
きっと思い出すこともあるだろう。永遠に少女時代の世界に住むトリーのことを。彼女がクリストファー・レイヴンの夢を見続け、その詩に耳を傾け、暗闇で彼の口づけを感じ続けていることを。自分もまたあの夢を見たいと願うこともあるかもしれない。でも、わたしには生きるべき人生があり、書くべき本がある。わたしの記憶のなかの彼女は、いつまでもこうしてコリングズウッドの屋敷の前で手を振り続けているだろう。百年前からある樫の木の下で、いつまでもずっと。
(訳:鈴木潤)
作品について
シオドラ・ゴスはハンガリー生まれのアメリカ人ファンタシイ作家。2008年に”The Singing of Mount Abora”(「アボラ山の歌」SFマガジン09年12月号で紹介)で世界幻想大賞を受賞したほか、作品はたびたびファンタシイ系の賞の候補に挙げられてきました。ここに訳出した「クリストファー・レイヴン」は、ロマンスとスチームパンクの味付けがしてあるファンタシイとホラー作品、いわゆる〈ガスライト・ファンタシイ〉を集めたGhosts by Gaslight: Stories of Steampunk and Supernatural Suspenseに収録され、後にオンライン誌Fantasy Magazineの2011年11月号に掲載された作品です。
SFマガジン2012年7月号の〈ネオ・スチームパンク特集〉で紹介した「マッドサイエンティストの娘たち」(Strange Horizonsの2010年1月号に初出)とおなじく、物語の主人公はヴィクトリア朝の女の子たち。ブロンテ姉妹やG・エリオットなどの読書体験が心によみがえるようなクラシックな背景に、キャラクターの際立った女の子たちの会話が弾みまくって、懐古趣味のパスティーシュにとどまらない、斬新でオリジナルな雰囲気を創りあげています。
ゴスは18、9世紀の英文学を敬愛し、ボストン大学で英文学の教鞭もとっている才媛。前述の「マッドサイエンティストの娘たち」は産業革命期の空想科学小説の名作を下敷きにし、本作では19世紀英国の詩人にまつわるゴースト・ストーリーを描いて、古典への造詣と愛着をうかがわせています。どちらの作品もいわば「物語や詩への愛を語るメタフィクション」とも読めて、作家が虚構(フィクション)の創作を心から楽しんでいる様子が伝わってきます。でもやっぱりゴス作品の一番の魅力は、登場人物たちがさりげなく発するどきっとするような真実や、彼らが垣間見せる、みぞおちにずきんとくるような切ない想いではないでしょうか。まちがいなく、同時代を生きている作家の声がその創作の喜びといっしょに胸に響いてくる、新しい小説なのだと思います。
実際、ゴスは「ドラ」の愛称で呼ばれSF/Fの作家仲間に愛されている、おしゃれですてきな女性とのこと。これまでに、The Rose in Twelve Petals and Other Stories(2004)と、In the Forest of Forgetting(2006)の二冊の短篇集を、そして2011年には中篇、The Thorn and the Blossomを発表し、作家としても乗りに乗っています。ちなみにこの新刊、ゴスらしいウィリアム・モリス調のクラシックな装丁なのですが、主人公の男女それぞれのストーリーが文字どおり表裏一体になっているという、凝った造本で話題になりました。本サイトでもレビューする予定ですので、どうぞお楽しみに。(鈴木潤)
追記:シオドラ・ゴスの待望の初長篇『メアリ・ジキルとマッド・サイエンティストの娘たち』が、2020年7月に早川書房より刊行されました。(鈴木潤)