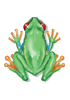死んだ女の子の結婚行進曲
キャット・ランボー
昔、死んだ女の子がほかのゾンビたちといっしょに、タバトの港の下にある洞窟に暮らしていた。その海辺の町の下にある都市、名前のない都市に。何千年も前、魔法使いスルーマンがその都市を建物ごと地中深くに沈め、名前を消し去ったのだ。何かの侮辱への報復だったのだが、幽霊となった魔法使い以外は誰もそのことを覚えていない。そこでも生活は続けられた。
死んだものたちのなかには日々の用をこなすふりをする意義を見いだせずに、いつまでも眠りにつくものもいた。だが、かつて決まった日々を過ごしていたのと同じように、決まったとおりに過ごすものもいくらかはいた。
死者の都市で本当に生きているものは、銀色の毛並みがつやつやとしたネズミだけだった。彼らは影を裏返したように通りを駆け抜けていった。そんなふだんと変わらないある日、一匹のネズミが死んだ女の子に声をかけた。
その子の名前はズレイカといい、黒い髪に黒い瞳をもっていた。さほど墓場の臭いを漂わせていないのは、窓の下を静かに流れる川で、毎晩水浴びをしていたからである。
「ぼくと結婚してよ」とネズミはいった。後足で直立し、尻尾もきちんと足のまわりに巻きつけていた。
女の子は朝食をとるふりをしているところだった。テーブルの上ではポットが湯気をたてていた。彼女は見せつけるようにホット・チョコレートをカップについでから、話した。
「どうしてあんたと結婚しなきゃならないのよ?」
ネズミは彼女を見つめた。「たしかに」とネズミは認めた。「ぼくのほうが、あなたよりずっと得るものが多いでしょう。あなたのような高さをもった人を花嫁に迎えられたなら、いってみれば、ぼくのほうもずっと高められるでしょうからね」といって、ネズミは笑い、前足で髭をなでつけた。
「申し訳ないけど、お断りするわ」と女の子はいった。
マフィンで自分を慰めているネズミを残して、女の子は客間にいった。父がいつもの朝と同じ新聞を読んでいた。その紙面は真っ黒な長方形だった。
「いまプロポーズされたの」と彼女はいった。
父は新聞をたたみ、それを置くと、むずかしい顔になった。「誰からだね?」
「ネズミよ、たったいま。朝食のとき」
「いったい何が狙いなんだ? 持参金代わりのチーズか?」
女の子は生きているときもあまり父が好きではなかったことを思い出した。
「だめっていってやったわ」
父はまた新聞に手を伸ばした。「そうこなくてはな。おまえはこれまで恋したことなどないし、これからもない。この都市には変化はないんだ。じっさい、そんなことにでもなれば、わたしたちはみんな破滅する。出かけるときはドアを閉めていきなさい」
女の子は買い物に出かけた。買い物籠は川岸に沿って生える白い葦を編んで作ったものだった。
ごみごみした露店のあいだをとおりながら、彼女は雑然と置かれた生地にふれてみた。安眠へといざなう柔らかなヴェルヴェット、水のように指からするりとすべり落ちるシャルムーズ、ネズミの耳のように感触のよいスウェード。どれもが黒か灰色の生地ばかりで、そのあいだにぽつんぽつんと取り残された月光のように白が置かれている。
ネズミが台の端に乗っていた。
「食べるのには困らせないから」とネズミはいった。「タバトの港の埠頭で処分された魚のはらわたや、路地端に捨てられている腐った肉とか。果樹園の取り残しももってくるよ。水っぽく溶けかかったアプリコットや、腐った桃や、骨みたいに茶色くなって、婆さんの乳房みたいにしなびてぺしゃんこになった林檎も。なめし革工場の駄目になった革の落とし屑ももってきてあげよう、鳩の糞の入った水に漬けて肉みたいに柔らかくしたやつをさ」
「どうしてわたしなの?」と女の子は訊いた。「そんな誘いに乗ると思えるような素振りをあなたに見せたことがある?」
ネズミは困って髭を撫でた。「ないよ」と白状して、「きみが川で水浴びしているところを見かけて、手足が虹色の光を帯びてるみたいなのを目にしたんだ。水に浮かぶふっくらとした真っ白なモッツァレラチーズみたいでね。強烈な欲望に襲われて、思わず漏らしちゃった、骨が溶けて体から流れ出ていくみたいな気がした。どうしてもきみを奥さんにもらいたいんだよ」
女の子は死んでからずっと三日ごとに訪れている市場を見まわした。けっして変わることなくただ永遠に並べ替えられつづける商品の載った台を。そして、またネズミを。
「いっしょについてきていいわ」と女の子はいった。
ネズミは買い物籠に飛び乗ると、二人はこうして黙って歩いた。やがてネズミが話しだした。
彼が話したのは名前のない都市のネズミの歴史だった。あまりにも長いこと魔法のそばで暮らしてきたために、魔法が皮膚からも目からもしみこんで、腹の奥底にまで入りこんでしまったこと。何世紀ものあいだにいくつもの文明が興っては滅んだこと、一族の妖術師や魔術師は巧みな魔法を学んだものの、文明が未開の状態へと退行していくたびにそれも奪われてしまったこと。いまの社会は白い毛皮のネズミの貴婦人たちが支配し、言い寄ってくるオスたちに食料をもってこさせ、貴婦人たちはその社会的重みを増すため、せっせと食べに食べていること。
「それで最初にこの考えを思いついたのさ」とネズミはいった。「人間の花嫁ともなれば、連中よりずっと重みがあるからね。でも、きみを目にしたら、そんなことは意味のないくだらない打算にしか思えなくなった」
彼女は胸のどこかにどきどきするような温もりが広がってくるのを覚えた。考えてみると、それは死ぬ前にも感じたことのない感情だった。興味でもあり、好奇心でもあり、虚栄心でもあり、それでも何か別のもの――自分のすべてを捧げると約束してくれるネズミへの、疼くような思いだった。
「もってのほかだな」と彼女の父はいった。「そんなことをしようものなら、この都市に変化が起きてしまう」
「それが何なの?」
「それが何なの、だと! ここを滅ぼしたいのか? わたしたちは魔法使いの呪いをかけられているんだぞ――つかのまの時間のなかに封じこめられ、変わることができないために死にかけ、変わることができないがゆえに死ぬこともないんだ」
ズレイカはむずかしい顔つきになった。「訳がわからないわ」
「それはおまえが子供だからだ」
「父さんだって、五千三百十二歳のわたしより四十歳年上なだけじゃない。これまで生きてきた歳月を考えれば、わたしだってもう大人よ」
「そう思うのも無理はないな、おまえがいつまでも十五歳のままだということを忘れてしまえれば、だが」
女の子は地団駄を踏み、頬をふくらませたが、何世紀もの歳月はいかに娘に甘い父親の心をも萎えさせてしまう。父は医者を呼んだ。
医者は飛んできた。新しい患者など珍しく、久しぶりのことだったからだ。医師は頭のてっぺんから爪先まで、とことんズレイカを調べ、父が反対しなければ服まで脱がせていたことだろう。
「わたしの見立てでは健康体のようですが」医者はがっかりして告げた。
「娘は恋していると思いこんでるんだ」
「おやおや」医者は驚いて奇声をあげた。「そういうことですか。恋患いねえ。それを治してくれというんですか?」
「病がこれ以上広まったり、われわれ全員を危険にさらしかねない行動を娘にとらせたりすることのないように、な」
ズレイカは何もいわなかった。自分がネズミに恋などしていないことはよくわかっていた。でも、変化という考えは熱病のようにすっかり彼女に取り憑いていた。
医者は彼女の頭に銀線で編んだネットをかぶせた。ネットのあちこちからぶら下がる磁石が、漆黒のオニックスと灰色の長石の結晶のなかにまぎれこんだ、さえないガラス玉のように見えた。
「微妙な刺激を与えるものです」と医者はつぶやいた。「でも、恋は微妙どころではない力をもっているからなあ。まあ、じゅうぶん時間をかければきっとうまくいくでしょう」
医者はズレイカに、三日間はネットをしたまま、客間の椅子にじっとしているように、と指示した。
三日はのろのろと過ぎていった。ズレイカは目をずっと窓に向けていた。雲も、太陽も、空もない世界を切り取った窓を。磁力のせいで考えがあちこちに引っ張られてゆくような気はしたが、全体としては、自分では何一つ変わったように思えなかった。
三日目にネズミがきた。
「ぼくのきれいな婚約者さん」とネズミは彼女が坐っている場所を見つめて、呼びかけた。「いったい何を着けているの?」
「愛を取り除く装置よ」と彼女はいった。
髭が前にぴんと伸び、ネズミはうれしそうな顔をした。「じゃあ、きみは恋をしているんだね?」
「違うわ」と女の子はいった。「でも、父はそう思いこんでいる」
「ふうん」とネズミはいった。「じゃあ、恋をしていないのなら、その装置の効果って、いったいどうなるの?」
「わからないわ」
ネズミはぼんやりと尻尾を振りながら、考えこんだ。
「きっと逆向きに作用するんじゃないかな」
「わたしもずっとそのことを考えてた」と女の子はこたえた。「たしかに、時がたつにつれてあなたへの好意がふくらんできたみたいだけど」
「あとどれだけそれを着けていなければならないの?」
彼女は時計に目をやった。「あと一時間」
「じゃあ、それまで待つことにしよう」ネズミはあたりの臭いを嗅いだ。「おたくでは、きょうの朝ごはんにマフィンを食べた?」
「わたしはここに三日間坐りどおしなのよ。朝食はとっていないわ」
「じゃあ、三十分ぐらいでもどるね」といって、ネズミは消えた。
時間になると、ドアが開いて、父と医者が入ってきた。ネズミは顎をひと舐めすると、こっそり椅子の下にもぐりこんだので、スカートの陰に隠れて見とがめられずにすんだ。
「さあ、娘や」医者が装置をはずすあいだ、父は娘の背中を軽くたたいて、訊いた。「元にもどれた感じはするかね?」
「すっかりもどったわ」と女の子はこたえた。
「よしよし!」父は医者の肩をたたいて、うれしそうな顔をした。「よくやってくれた。じゃあ、向こうで謝礼の話をしようか」
医者はズレイカを見た。「また別の検査をしたほうがいいかもしれませんが……」といってみる。
「必要ない」父はきっぱりといった。「愛は取り除かれ、すべてがうまくいった。われわれの都市はこれまでの千年間と同じように続いていける」
二人が去ると、ネズミは椅子の下から這い出てきて、彼女を見つめた。
「それで?」
「この地下では結婚したくないわ」
「地表に出て、タバトで結婚の誓いをしよう」とネズミはいった。「地下道のことならすべて知ってるし、それがどこに行き着くかもわかってる」
そこで彼女は庭にかかっていたカンテラを取った。それまで太陽の代わりに、魔法の力で育つ青白い植物に淡い光を投げかけてきたのが、このカンテラだった。ネズミを肩に乗せて、二人で最初の地下道にたどり着くと、彼女は地表に向かった。うしろから大きな倒壊と地割れの音が響いてきた。
「あれは何なの?」とネズミが訊いた。
「何でもないわ」とズレイカはいった。「もう何でもないの」
彼女はどんどん上へと進み、その背後では名前のない都市がとめどなく崩壊していった。
(訳:小川隆)
作品について
キャット・ランボーのことを最初に意識するようになったのは、不見識なことに、作家としてではなかった。作者ホームページの著作リストを見ると、すでに90年にはデビューしているようなのだけれど、実際に誰もが読めるようなメディアで作品が発表されだしたのは2006年ぐらいからだから、無理もなかったのだ、と言い訳しておこう。というのも、彼女が本格的に作家への道を歩むようになったのが、SFではおなじみのクラリオンというワークショップで2005年に学んで(ついでにコネをつけて)からのことだったのだ。もちろん、ぼくが最初に読んだのも、Fantasy Magazine2006年12月号に掲載されたこの作品で、わっ、すごい作家を見逃していた、と驚いて、あわてて、そのころ発表されたStrange Horizonsの掲載作を見たりしたものだ。もちろん、ジェフ・ヴァンダーミアとの共著であるチャップブック・スタイルの短い短篇集The Surgeon's Tale & Other Storiesもヴァンダーミアの名前に惹かれて注文済みだったので、それからはしっかりと目を配るようにしている。じゃあ、それまでは何で知っていたかというと、ブログとかでだったのだろうね。Codexという作家グループに入っていたり(ほかにはローレンス・M・シャーンとかケン・スコールズとかがいる)、編集者のブログに名前が出たりしていたんだろうなあ。最近、とみに記憶が不確かになっているけれど、困ったものです。でも、若い作家だとは思わなかったから、どこかで会っていたのかもしれない。ともかく特徴的な名前だから、購読しはじめたばかりのFantasy Magazineの目次に作品が載っているのを見て思い出し、はじめて、ああ、作家だったのかと思ったのだ。それまで何をしていたかというと、かなり熱心なゲーマーだったらしい。たぶんワールドコンで会っていたとすれば、そっちの関係で参加していたのじゃないかな。ゲームはいまだにクリエイターとして熱心に活動しているようだ(この作品でも出てくるタバトというのは、彼女が友人と作ったゲーム世界にある都市で、短篇集の半分近くがこのタバトを舞台にした話だ)。それ以外は、謎だといっておこう。本人もあまり語りたがっていないし(じつは45歳だ)、前半生には何か秘密があるような気がする、と伝説を作っておきたいところだ。
でも、彼女の名前をもっとも有名にしたのは、そのFantasy Magazineの小説部門の編集者をまかされてからだろう。2007年から正式に編集職につくと、ウェブジン化した同誌の名前をクォリティの高い新人ファンタシイ作家の活躍の場として定着させたのだ。以前のプリント・マガジンだったころもきれいで、おもしろい雑誌だったけれど、有名になったのは無料でウェブで読めるようになってからだ。つまらないウェブジンはすぐにつぶれるから、これは彼女の功績じゃないだろうか。
今年になって、ここに掲載した作品(原題は"The Dead Girl's Wedding March" )を含む、初のソロ短篇集Eyes Like Sky and Coal and Moonlightを発表し、いよいよ作家としても本格的に始動しはじめた。遅咲きの作家かもしれないけれど、ぜひ注目してもらえたらうれしい。(小川)
Eyes Like Sky And Coal And Moonlight
-
Her Eyes Like Sky, and Coal, and Moonlight
-
The Accordion
-
I'll Gnaw Your Bones, the Manticore Said
-
Heart in a Box
-
In the Lesser Southern Isles
-
Up the Chimney
-
The Silent Familiar
-
Events at Fort Plentitude
-
Dew Drop Coffee Lounge (次回訳載予定)
-
Narrative of a Beast's Life
-
Eagle-haunted Lake Sammammish
-
Sugar
-
A Key Decides Its Destiny
-
The Towering Monarch of His Mighty Race
-
In Order to Conserve
-
Rare Pears and Greengages
-
A Twine of Flame
-
The Dead Girl's Wedding March (本作品)
-
Worm Within
-
Magnificent Pigs