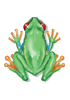A greeting for my readers in Japan - I hope you enjoy "The Janitor In Space." The story is one of my favorites from my collection, THE UNFINISHED WORLD AND OTHER STORIES. I'm very excited to have a story translated into Japanese for the first time, and I hope it won't be the last! (日本の読者のみなさんへ――「宇宙の清掃員」をどうぞお楽しみください。短篇集、The Unfinished World: And Other Storiesのなかでも、とくに気に入っている作品です。初めて日本で紹介されることになって、とても嬉しいです。これをきっかけに、ひきつづき紹介されるといいなと思っています!)
宇宙の清掃員
アンバー・スパークス
清掃員は黙々と通路を進んでいく。宇宙ステーションのちょっとした隙間に溜まった宇宙塵や人間が出したごみ屑を、丁寧に吸いこみながら。手際のよい仕事ぶりだ。壁を押しては、空中に放物線を描いて、すべらかに移動していく。いちいち向きをたしかめることもない。彼女の視線は窓と、その向こうで信じられないほど明るく輝く星々に注がれている。
宇宙飛行士はいい人たちだけれど、きれい好きではない、と清掃員は思う。たとえば今日、ある宇宙飛行士はキッチンのいたるところに液体塩の滴をまき散らしていった。女性宇宙飛行士たちが、血まみれのタンポンをきちんと始末しなかったり、こぼれたおしろいを宙に浮かせたままにしておくこともある。居住区画のモジュールに、汚れた下着を泳がせておく男性宇宙飛行士もいる。擦り切れた靴下からは、チーズと古くなったシロップのにおいがする。それから、剥がれ落ちた皮膚の破片――掃除しても掃除しても出てくるものだから、いったい筋肉や骨をちゃんと包んでおけるくらいの皮膚が残っているのだろうかと首をかしげてしまう。もちろん、宇宙飛行士たちに会うことはほとんどない。だから、皮膚はちゃんと残っているはずだと彼女は思っていても、ことによったら彼らはすっかり脱皮して、柔らかい皮膚のかわりに、奇妙な昆虫のような、黒光りする固い外殻をまとっているかもしれない。
顔を合わせるのは夜間警備員くらいだ。年のいった聾唖の男で、たいてい警備室でポルノを観ている。でも彼のよからぬ習慣について、苦情を申し立てたことはない。だいたい、誰に訴えたらいいかもわからない。それに、宇宙飛行士だってきっとポルノくらい観るだろう。あるいは、観ないのかもしれない――いい人間は、下劣なものを観たりはしません。地球にいたときに、そう聞かされたことがあった。
いい人間であることと、きれい好きであることはべつのことだ。たとえば、彼女はとてもきれい好きだ。でも、とてもいい人間とはいえない。まだそこを目指す道の途上にいる。牧師には、神様にすこしでも近づくために宇宙にいきたいのだといった。でもほんとうは、地球を離れたかっただけだった。もううんざりだったから。誰かに気づかれるかもしれないと、身構えながら生きることに。いまにも誰かが彼女の名前を聞いて振り返り、目を大きく見開いて何か聞きたそうにしたり、油断のならない好奇のまなざしを向けたりしてくるのではないかと、ただ身構えているだけの人生にはもううんざりだったから。
宇宙にいきたいだなんて、ずいぶんと思い上がったもんだって思われるぜ、とたった1人の友人はいった。彼は州営の酒屋の店員だった。毎週火曜日の朝、病院での夜勤明けにミラーライトを1箱買いに寄っていた店だ。仕事はいつも夜間にしていた。たいていみんな寝ているから、煩わしいことに巻き込まれることもすくない。もともと人と話すのは苦手だったし、ぎゅうぎゅうづめの刑務所の暮らしのあとには、いっそう騒がしいところを避けるようになっていた。
宇宙ステーションのスタッフは、面接で彼女のことを気に入ってくれた――礼儀正しく、物静かで、余計な好奇心を抱くこともなさそうだから。これはとても重要なことだった。面接に立ち会った、顎ひげを生やした優しい目のロシア人宇宙飛行士は訊いた。宇宙で孤独な思いをなさるんじゃないですか? 目のまわりと額に、細かな皺が見える。きっと家庭があるんだろう。たぶん、まだ小さい子供のいる。そうですね、と彼女は答えた。でも、孤独なのには慣れていますから。宇宙飛行士はうなずいた。彼女の言っていることを理解してくれたようだ。宇宙飛行士は鷲鼻の横顔を見せ、画面には映っていない誰かの方を向いた。どうやら採用されそうだ、と彼女は思った。
宇宙飛行士たちはときどき夜中に起き出してくることがある。そういうとき、清掃員は陰のように、灰色の鳥のようになろうとする。彼らが部屋に入ってくると、身を縮めて視界からすり抜ける。体を浮かせて天井に張りつき、怯える。人工的に作られた宇宙の夜に、いつもと違う彼らの姿を見てしまうのではないか。そしたらきっと、自分も違って見えてしまうだろう。星明かりが年月を剥ぎ取って、砂利道にひとりぼっちでたたずんでいる13歳の少女を照らし出してしまうだろう。顔に痣をつくり、ぼろぼろの拳でモップの柄を握りしめている少女を。あの出来事、悪夢のような出来事を、恐怖がつきつけてくる。重苦しい痛みが全身をめぐる。鋭い痛みが体の奥深くまで貫く。いくつもの顔が追いかけてくる。いまなお、何も育たない、ささやき声すらも聞こえない、宇宙の最果てまできてもなお。生も死もなく、ただ宇宙の始まりに生み出されたものしか存在しない場所まできてもなお。自分ははたして神を信じているのだろうか。牧師にはいつも信じていると答えてきたけれど、ほんとうはわからなかった。はたして女というものは、神を信じていいものなのだろうか。
刑務所にいたたいていの女たちは信じていなかった。彼女たちは神の名を口にし、そして男たちの名を口にしては、唾を吐き捨て、歪んだ怒りを押しこめるように奥歯をくいしばった。モップのかけ方と掃きそうじの仕方を教わったのは刑務所にいたときだ。そこで役立つ人間になる方法を身につけたのだ。世の中の役に立つことをするのはいいことです。あるいは、と彼女は言い直してみる。宇宙の役に立つことをするのはいいことです。ときには苦労することもあったが、新しい物の見方にも、2つめの月みたいに地球のまわりにふわふわと漂っている暮らしにも、やがて慣れていった。ここにいると、罪と犠牲に費やした人生のごみの山から解放された気がした。このろくでもない人生で初めて、人々のあいだで生きていくという重荷から解放された気がした。自分が小さく、明るく、ダイヤモンドのように硬い、天空の星々の1つになったような気がした。
宇宙ステーションはいつでもひどく明るい。外に広がる宇宙の暗闇とは対照的だ。いたるところに蛍光灯がともり、星雲のように乳白色の光を放っている。計器パネルの上では赤や緑や黄色の光が点滅している。ふり仰げば、ほの青く光る地球が見える。心が和んだ。まるで地球のクリスマスの季節の街にいるように――まどろむような七色の電飾は、故郷を遠く離れた流れ者にも輝いてみせた。
わが人生の光よ――あの男は彼女を膝にのせ、歌ってきかせた。彼女は丸顔で何も知らない、まだほんの子供だった。それに、誰からも愛されたことのない人間にそうやって甘い言葉をかけるのはたやすいことだった。すぐに、あいつらがあくどいことをやってのけるのを黙って見ていられるようになった。彼女は尿の滴を残らず吸い取りながら、銃の感触を思い出した。銃を構えたとき、少年と少女はこちらの顔すら見ていなかった。彼女は蛇でもつかんでしまったみたいに、銃を取り落とした――突然、正しくないものに思えたから。とても頼もしいもののように見せかけて、弾倉にあいた2つの空洞が、ひどく卑劣なものに映ったから。あの男はそんな彼女をせせら笑い、銃を拾い上げた。まるで、そのために生まれてきたみたいな手つきで。男の両手はその鋼鉄と木をすみずみまで撫で上げていった。ちょうど、あいつらが彼女のことをそうしたみたいに。
彼女は計器パネルの指紋を拭き取りながら、ランプがちかちかと揺れたりかすんだりするのを眺めた。いったいどれだけの雑巾を使い、どれだけのものを磨き上げれば、過去をすべて拭い去ることができるのだろう。比喩というものはよくわからない。でも、人間はとてもちっぽけな器だけれど、はてしなく悲しみを積みこむことができるというのはほんとうだと思う。肺も心臓も焼きつくしてしまうくらい、たくさんの悲しみをためこむことはできないだろうか? どうやったら正しく罪を償えるのだろうか?
一生けんめい、真面目に働くこと、と彼女は思った。それが償いになるかもしれない。だから毎晩、塵を吸い取り、掃き清め、モップをかけ、ワックスをかけ、敷物の埃を払い、トイレをこすり、備品を補充し、洗濯をし、ベッドを整え、ごみを集めて処理し、照明を取り替え、金属面を磨き上げ、壁や天井を洗い上げた。機器についた糸屑や埃や油汚れや皮脂を拭き取った。ガラス容器や研究室の装置を磨いた。シンクの汚れを落とし、顕微鏡を消毒した。チューブやボトルの中身を詰め替え、丁寧な手書き文字でラベルを書いた。彼女は毎日、宇宙ステーションをぴかぴかに輝くまで磨き上げた――まるで未来のように。
空の彼方にいると、とても心が落ち着いた。神様に近づくためだと嘘をついてここにきたけれど、こんなに神様から遠く離れている気がしたのは初めてだ。子供時代を過ごした畑や農場には、いたるところに神様がいた――神は人々の口先や、本や、壁にいた。神は炎であり、歪んだ顔であり、いかれた説教師だった。神は畑からたちのぼる靄のなかに、ガソリンスタンドの敷地にこぼれた油のなかに立ち現れた。神とは、幼い息子をポリオで亡くした隣家の池に沈んだ冷たい小石だった。神とは、あたりの農家で使われていた鉄の人工呼吸器だった。シューシューと音をたてて収縮し、みんなそのなかで死んでいった。
いちばん幸せなのは、ステーションの隅にできる深緑の陰のそばで、どこまでも静まり返った星々のあいだに響く、かすかな機械音に耳を傾けているときだ。それは神様よりもずっと心を安らかにしてくれる気がした。嘘偽りのないもの、人間の考える天国とはまったく関係のないもののように思えた。
ある夜、窓の汚れをこすっていると、顎ひげを生やしたロシア人宇宙飛行士が、角を曲がってふわふわとこちらにやってきた。パジャマの裾を引きずり、眠たそうな瞼はほとんど閉じかかっている。彼女は腕の力で体を持ち上げると、天井に張りついて、息をひそめた。だがロシア人は、顔を上げようともしなかった――彼女の真下を通り過ぎ、ガラス張りの広い壁に向かうと、子供みたいに顔を押しつけた。どこにいる(グデ・ヴィ)、と彼はつぶやいた。言葉の意味は知らなかったが、彼女には理解できた。牧師はかつて、死は叡智あふれる神様の贈り物だと言った。ほんとうにそう信じているのだろうかと、不思議に思ったものだ。彼女には、死は叡智や神秘とは正反対のもののように思えた。この広漠とした驚きに満ちた場所にくることとは似ても似つかないことのような気がした。死は孤独と正反対のものだ。そして、孤独は彼女が持っている唯一のものだ。彼女のものだといえるたった1つのものだ。だからこそ孤独は、ひんやりとした、光り輝く始まりのものにかこまれた孤独は、こんなにも美しいのだった。
(訳:鈴木 潤)
作品について
アンバー・スパークスを知ったのはデビュー短篇集May We Shed These Human Bodiesが出た2012年のこと。ベン・ローリー(なぜか日本ではルーリー表記で紹介されているけれど)やアミリア・グレイといった好きな作家の推薦文に惹かれたのだ。パブリッシャーズ・ウィークリーの書評ではティム・バートンにもたとえられていたし。フラッシュ・フィクションが多かった(というか、推薦文を書いている作家から類推すれば、予想はついたはずだけど)ことを含め、SFっぽい科学を小説に取り入れている書き方と、カルヴィーノっぽい寓話の印象が強く、ちょっとケヴィン・ブロックマイヤーを連想したり、マイクル・ビショップやスコット・ラッセル・サンダーズやジーン・ウルフの70年代ポスト・ニューウェーヴ短篇を思い起こしたり、おもしろく、愛読する作家の一人になった。翌年に出た次の作品The Desert Placesは共作のチャップブックだったが、16年に出た第2短篇集The Unfinished World: And Other Storiesで格段に小説がうまくなったように思う。その巻頭を飾るのがこの短篇だ。ウェブジンAmerican Short Fiction2014年7月1日に発表されたヴァージョンを改稿したもので、やはりこちらのほうがよくなっている。どうもそれまでの小出版社から大手に版元が変わったことにより、よい編集者にめぐり会えたのではないかと想像してしまう。ともあれ、まだ30代半ばの若い作家だ。出身地はミネソタらしい。どうやら日本の怪獣映画が大好きらしく、ディックをはじめ、SFやノワールも愛読しているようだ。メッセージの動画にも協力していただけたのも、親日家だからなのかもしれない。デビュー長篇も書きあげたという。いまもっとも勢いを感じる期待の若手だ。こうしてここに紹介できるのはうれしいかぎりである。(小川隆)