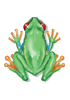はじめに
小川隆

ニュースを見て凍りついた。嘘だ。そんなに悪かったなんて。
口惜しくて、自己嫌悪に陥った。いったい何をやっていたんだろう。なぜもっとがんばらなかったんだろう。
バディこと、ルイス・ノーダンが去ってしまった。もういない。亡くなったんだ。なのに、ぼくときたら十日もたつまで知らなかった。
初めてルイス・ノーダンを知ったのは1989年、第二短篇集The All-Girl Football Team: Stories がゲアリー・フィスケットジョン編集の〈ヴィンテージ・コンテンポラリーズ〉から刊行されたときだった。まだサイバーパンクのムーヴメントが最終段階にあるころで、ぼくはブルース・スターリングやルイス・シャイナーといろいろ情報交換をしていた。とくにその年は、ブルースがジャンルの枠から逸脱する小説をさす〈スリップストリーム〉という用語を作った年だ。ルーはルーで(同じルイスでも、こっちの愛称はルーだ)、〈ヴィンテージ〉のフィスケットジョンの編集が気に入っていて、ぼくもそこから出ていたバリー・ハナやトーマス・マッゲインが好きだった。ぼくたちみんな、新しい方向性と、何かおもしろいことを探していた。だから手にとってみて、それが〈ルイジアナ州立大学出版局〉の1986年刊の再刊だと書いてあるのに気づいて、ぼくは小躍りした。〈LSU〉はジェイムズ・リー・バークの最初の出版社だ。そこの編集の好みなら信用できる。それに、ぼくが好きな南部作家の短篇集じゃないか。でも、冒頭の短篇「シュガーと鶏」を読んで、ぶっとんだ。魔術的リアリズムというか、イタロ・カルヴィーノみたいな幻想小説だったからだ。すっかり夢中になって、すぐにもう一つの短篇集も手に?れた。どの短篇も神話的なミシシッピ州の架空の田舎町アロウ・キャッチャーが舞台で、不思議な野生動物や、悲しくて風変わりな、人間くさい人間であふれていた。愛とユーモアにあふれていた。音楽にも。フィスケットジョンはすでに他社に移籍していたから、それが彼が選んだ本なのかどうかはわからない。でも、二つの短篇集は間違いなく傑作だった。ほかの〈ヴィンテージ〉刊の短篇集、たとえばレイモンド・カーヴァーのものをはるかに凌駕していた。
それから、事態は一変した。出版社の多くが大手に買収、吸収され、文学系の出版物は古典的なものか、フィスケットジョンがやっていたような若者向けの都会的作品に偏るようになった。ルイス・ノーダンの小説はニューヨークの大手出版社から見放された。そこに、南部から独立系の小出版社が登場した。ノースキャロライナ州の〈アルゴンキン・ブックス・オヴ・チャペルヒル〉が創設されて、ルイス・ノーダンの本を出しはじめたのだ。すばらしかった。しかも、長篇だ! だって、最悪の90年代だったんだよ。みんな話題にするのはお金のことばかり。日本がバブル崩壊後の景気後退にあえぐ一方で、アメリカもヨーロッパもソヴィエトへの勝利に酔いしれていた。資本主義が世界を制し、頂点をきわめたつもりでいた。アメリカ南部に古くさい魔法なんてあるはずがない。もうそこは第三世界じゃない。新しい南部、ニュー・サウスなのだから。そんなときに、バディの珠玉の長篇が出てきたんだ。最高じゃないか。
バディは90年代のあいだずっと傑作長篇を書きつづけたのに、誰からも見向きもされなかった。日本の出版社にいくら訳させてくれといっても、無駄だった。ミニマリズム以外の短篇集なんて、興味をもってくれなかった。どこもサイバーパンクやミニマリズム以後の新しいトレンドを探していたから、バディのようなユニークな作家には時期が悪かった。それに、日本では南部小説は商業的に成功しない、長い伝統があった。『ハックルベリー・フィン』は売れない本の代表だったし、アメリカではみんなが好きな小説のナンバーワンにあげる『アラバマ物語』は、映画化されてもなお無名のままだった。ぼくが話をした編集者はみんなノーダンが南部の作家、それもミシシッピ・デルタ出身だと知ると、首を振るだけだった。
でも、長篇を読んでぼくはノーダンが好きでたまらなくなり、会ってみたいとまで思うようになった。それまでおもにSF畑で仕事をしてきたので、文学系の作家へのつてはなかった。だから、まず版元の〈アルゴンキン〉にいってみた。2001年の秋のことで、9/11の直後だったけれど、ぼくにとっては前の年にノーダンのフィクション的回顧録が出たからという理由でしかなかった。車の運転ができなかったし、テロのあとで公共交通機関は混乱していたから、その出版社にいくのはけっこう大変だった。でも、ようやく〈アルゴンキン〉がある複合住宅を目にしたとき、うらやましくなった。独立系の小出版社にとって理想的な場所に思えた。こぢんまりして落ち着いて、都会の喧噪やせわしさとは無縁で、緑に囲まれていたのだ。
担当編集者のシャノン・ラヴネルは歓迎してくれたけれど、彼女の口から出たのは悲しい知らせだった。ノーダンは神経障害をわずらっていて、話したり読んだりするのに支障はないのだけれど、もう書けないの。だから電話してあげて。その旅行中にぼくは二度ダイヤルしたけれど、運がなかった。一度はお話し中で、一度は留守だった。ぼくはさっさとあきらめて、彼の作品が好きだというメールを送ってみた。すぐに「ありがとう」という返事がきた。でも、連絡を取りあったのはそれだけ。世界のすべての作家のなかでトップ5に入る大好きな作家だというのに、それしかできなかった。だって、悲しくて、何をいっていいのかわからなかったから。「もう書けないの」という言葉が耳について離れなかった。
やがて、2003年、〈オックスフォード・アメリカン〉誌に彼の新作短篇が載った。いい話には違いなかったけれど、これまでのノーダンのきらめくようなイメージも、音楽的な高らかな響きも感じられなかった。まだすばらしい素材をもっているのに、それを魔法にしあげる魔法使いの杖はもうなかった。何かおもしろい作品はありませんか、といって編集者が取材にくるたび、ぼくは新しい作家の名前をえんえんと挙げたあと、いちばん好きな作家といえばこれなんだけれど、といって彼の短篇集を推薦することを欠かさなかった。でも、もうそれはただいってみるだけだった。
4月にこの悲しい訃報を知ったあと、調べてみて、バディがまだ小説を書いていたことがわかった。ファンや友人が集まって、2009年には彼の作品をさかなにお祝いするバディ・フェスという催しが開かれ、そこから本まで生まれていたことも知った。彼の小説を読んだ読者はみんなファンになり、彼を読むことの楽しさを表明していた。
ぼくは償いを果たすことにした。まだもう一度、彼の作品を日本に紹介するチャンスがある。サイトの上で、バディとその作品を偲ぶセレモニーをしよう。くよくよ悲しんだり、悔やんだりしていてもはじまらない。
ねえ、バディ。ぼくはもてるありったけの力を傾けて、あなたをここにお迎えしたいと思います。最後のお別れをいう前に、あなたとあなたの作品への思いをすべてぶつけ、世界中に知ってもらいたいのです。どんなところにもあなたの読者はいる、たとえ極東のこんな小さな島にだって。あなたとそのすばらしい小説と同じ時代にめぐり逢えた喜びを祝う二カ月の催しになります。だから心からいわせてください。ようこそ。