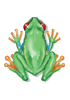追悼文
訳:小川 隆
シャノン・ラヴネル
ルイス・ノーダンとジョン・アップダイクとわたし
わたしが初めてルイス・ノーダンの小説と出会ったのは1983年だった。彼が〈ハーパーズ・マガジン〉に短篇――「シュガーと鶏」を載せたのだ。それはわたしがその年にThe Best American Short Storiesの編集者としての仕事で読んだ1500篇の雑誌掲載短篇の一つにすぎなかった。アメリカ南部文化を内側から描いた愉快な作品で、最初読んだときには声をあげて笑い、すぐにまた最初から最後まで読み返してみた。時間が足りるなどということがない仕事をしていたので、まずしたためしのないことだった。最終的にBASS1984年版のゲスト編集者に送るわたしの“ベスト”120篇を選びおえたとき、わたしは「シュガーと鶏」を山のてっぺんに載せ、ゲスト編集者が1984年版のアンソロジーに再録する20篇の短篇の一つに選んでくれるようにと祈った。
祈りはつうじなかった。その年のゲスト編集者はジョン・アップダイクだった。作家としては、それぞれが住んでいたマサチューセッツ州イプスウィッチとミシシッピ州イッタビーナぐらい、ルイス・ノーダンとかけ離れたタイプだ。アップダイクはノーダンの短篇を再録作品からはずしただけでなく、「1983年のその他のすぐれた作品」のリストからもはずせといってきた。「馬鹿みたいな」話だと思ったのだ。ジョン・アップダイクは当時はとても有名だった。ルイス・ノーダンは違った。ジョン・アップダイクはボスだった。わたしは違った。
わたしはアップダイクの要求を呑んだ自分がいやになった。何とか埋め合わせをすることを自分に誓った。
たまたま、1983年は〈アルゴンキン・ブックス・オヴ・チャペルヒル〉が創立され、最初の5冊を刊行した年でもあった。わたしは恩師であるルイス・ルービンの誘いに応じて、その小さな出版社の創設者の一人となった。会社は小さく、十分な資本もなく、アメリカ出版界の中心であるニューヨークからは遠く離れ、ベストセラーではなく〈文学〉専門だった。〈アルゴンキン・ブックス〉の上級編集者の席に着いた最初の日に、わたしはルイス・ノーダンのことを調べはじめた。契約したかったのだ。残念ながら、彼にはすでに出版社がついていた。同じ1983年に、〈ルイジアナ大学出版局〉が彼の最初の本、Welcome to the Arrow-catcher Fairというタイトルの短篇集を刊行していた。
やがてニューヨーク・シティの出版界も彼を見いだし、1989年、〈ヴィンテージ〉は彼の第二短篇集The All-Girl Football Teamを出版した。1年ぐらいたって、わたしはどこかの出版イヴェントで、さまざまな版元の編集者たちと同じテーブルを囲んでランチをとることになった。その一人、〈ヴィンテージ〉の編集者が短篇集を売るむずかしさを話題にした。「わたしたちが出版した最高の短篇作家はルイス・ノーダンなのに、最初の本はまったく売れず、決定が下された――もう彼の本はやらない」
わたしは公衆電話に直行して(当時はまだiPhoneもグーグルもなかったから)会社に電話し、ルイス・ノーダンとどうすれば連絡がとれるか、調べてもらった。わかったと聞いて、すぐわたしは電話した。おかげで〈アルゴンキン・ブックス〉は残りの彼の作品5冊を、1991年のMusic of the Swampを皮切りに2000年のBoy With Loaded Gunで終えるまで、刊行することができた。「シュガーと鶏」は1996年の短篇集Sugar Among the Freaksに収録された。
そういうことよ、ミスター・アップダイク。
ほんとうは、ルイス・ノーダンの天才に気づかなかったジョン・アップダイクの不明に感謝しなければ。アップダイクがわたしの趣味を侮辱してくれたおかげで、わたしはノーダンを追っかけつづけることができたのだから。彼の担当編集者になる前には作品は短篇小説を一本読んだきりで、その重要性のごくわずかな片鱗しかのぞいたことがなかった。“フィクションをまじえた回顧録”とされる彼の最後の作品を出版するときには、〈アルゴンキン〉がアメリカ文学における一大現象といえる作品を出版する特権と栄誉に浴したことがわかるようになっていた。
ルイス・ノーダンはこれまでも、これからも誰も書かないようなものを書いた。ほかの作家とはまったく異なるスタンスで、異なる状況で作品を書いた。その特異な才能は複雑すぎて、じょうずに語ることなんてまず誰にもできそうにない――ルイス・ノーダン本人でなければとても無理なことだ。
「……ぼくの狙いと意図は、自然界をありのままに、そして同時にこの世のものではないみたいに描くことなんだ」*
*ルイス・ノーダンのエッセー"Growing Up White in the South"より。
シャノン・ラヴネルはサウス・キャロライナ州チャールストン出身のヴェテラン編集者。長年、〈ホルト・ラインハート&ウィンストン〉、〈ホートン・ミフリン〉などの編集者をつとめ、1978年から90年まではBest American Short Storiesという年間短篇傑作選の編集をつとめ、1983年〈アルゴンキン・ブックス・オヴ・チャペルヒル〉を創設。2003年からは同社のインプリント〈シャノン・ラヴネル・ブックス〉の編集にあたっている。このエッセイはこの特集のために、特別に書き下ろされたもの。
ジョン・デュフレーン
アメリカ文学の至宝の一つが失われた。ルイス・“バディ”・ノーダンがきょうこの世を去った。
アーカンソー大学の教師をしていたバディに教わることができて、わたしはこの上なく幸運だった。さまざまな作品のなかでも、『トリストラム・シャンディ』を教えてもらったことには永遠に感謝している。わたしがシンディといっしょにフェイエットヴィルをあとにしたとき、最後に会ったのが彼だった。彼は公立図書館にいて、ピッツバーグで仕事が見つかって町を離れるといっていた。わたしたちのほうもルイジアナに向かうところだった。面接はちょっと厄介だったと彼は語った。学部長に履歴書に2、3年の空白期間があることを指摘されたのだ。バディはこういったそうだ。「だんじて、家に引きこもってウォッカを飲んでいたわけじゃありません」バディの著書へのリンクをつけよう。(訳注1)
2009年1月、わたしたちは何人かでオーバーン大学に出かけた。バディフェスという、またの名を「ルイス・ノーダンと、超越と希望の胸が張り裂けそうな笑い」というシンポジウムにいったのだ。バディもきていた。神経障害で動きは緩慢だったが、上機嫌で、これまでどおり機知に富み、楽しませてくれた。ピッツバーグを舞台にした書きかけの長篇の一部を朗読してもくれた――指一本でタイプしたのだ。アラバマ大学出版局がそのシンポジウムの論文を新刊として刊行してくれた(Lewis Nordan: Humor, Heartbreak, and Hope)。
“The Talker at the Freak Show”(訳注2)の一節でバディが歌っているのを聞いてみよう。
「きれいなリンネルの布を見ると、ママは列車を思い出し、列車を思い出すと、ときどき気持ちがなごむことがあった。糊の利いた白い上着姿の黒人ポーターや、猛スピードで雪原を疾走し、夜明けに名もない小さな駅を通過して大都市に向かうプルマン機関車のことを考えていた。汚れたリンネルのことや――寝台車の通路に積まれたシーツのこと――イリノイ・セントラル鉄道のエンブレムや、〈シティ・オヴ・ニューオーリーンズ〉や〈パナマ・リミテッド〉や〈ルージアン〉といったIC鉄道の列車の名前がエンボス加工された食堂車のテーブルクロスのことを考えていた。ママはそういった列車の名前を口にするのが好きだった。名前を歌ってくれた夜もあった。それらの列車を歌う、自分で作った悲しくせつない曲を。物心ついてからずっと、それがぼくの子守歌だった」
もしバディの短篇や長篇をまだ読んだことがないのなら、あなたはこれまで書かれたもっとも正直で、すてきで、胸が張り裂けそうになる小説を読んでいないことになる。
さようなら、わが友よ。
(訳注1)デュフレーンはこの空白期間のことを執筆にいそしんでいたからだと好意的に解釈していますが、本人はアル中と戦っていて仕事ができなかった時期があることを告白しています。
(訳注2)初出は〈グリーンズボロ・レヴュー〉誌ですが、第二短篇集The All-Girl Football TeamおよびSugar Among the Freaksに収録されています。
ジョン・デュフレーンは1948年生まれのアメリカの作家。マサチューセッツの出身だが、アーカンソー大学を卒業後、南部に住み、最初の長篇Louisiana Power & Light (1994)以来、ほとんど南部を題材にした作品を発表している。この追悼文はノーダンの死の直後に著者のブログに掲載されたもの。著者のご厚意により訳載を許された。
はじめにお断りしておく。
ぼくはタトゥーをするような男じゃない。みっともないとは思わない。きれいだよね。友達の足に彫られたイカロスの墜落をまじまじと見ることもある。知り合いの腕の恐竜に見とれているのに気づかれて、あわてることだってある。結婚している身なので、女性がタトゥーを入れているところのことを考えようものなら。ああ、だめだ。のぞいちゃいけない。
違うんだ、タトゥーを入れないのは、哲学的な意味で臆病だからなんだ。タトゥーを入れようと思ったら、自分の根源的なことを堂々と主張する気にならなきゃいけない。とてもだいじなことで、子供が夜中に起こしにきたり、高校でトラブルに巻きこまれて相談にきたり、人生の最後に棺に横たえてくれるようなときに、タトゥーに入れた絵柄や言葉のことを真っ先に考えてもらいたいと思うぐらいじゃなくては。ぼくにはとても重すぎる。
そうお断りした上で、ぼくがタトゥーを入れようかという気になったときのことをお話ししよう。
十年近く前のミシシッピ州での出来事だ。その世界にはたった5人しか存在していない。作家のトム・フランクリンと、4人の教え子。2人は北部出身で、2人は南部人。オックスフォードにあるフランクリン家の裏のパティオに集まって、アイスボックスにはビールがきんきんに冷えている。ぼくたちがつづけてきた、この週に一度のこの授業は“南部短篇小説”というお題で、とりあげる本は最高だった。バリー・ハナに、ウィリアム・ゲイに、デイル・レイ・フィリップス。あまりにすばらしい書きっぷりに、肝臓にがつんと一発くらったような気分になるほどだ。
やがて、ある晩、奇跡が起こってぼくたちの人生は一変する。
課題として与えられた本は小さく、5×7インチというポケットに収まるくらいのサイズで、手に取った感じも不思議なら、中身の短篇が読み手に与える印象も不思議だった。ぼくたちはそわそわしながら、先生の奥さんとお子さんが床について、授業がはじまるのを待つ。やがてひそひそ話がはじまる。だって、それは信じられない作品で、ぼくたちだけの秘密みたいに思えるから。ミシシッピ州イッタビーナ出身の、ルイス・ノーダンという人がいて、Music of the Swampというとんでもない傑作を書いたんだ。
それはぼくがこれまで出会った最高の作品だ。なのに、ぼくが狂おしいほど妻を愛している理由をうまく説明できないように、ノーダンがいかにすばらしいかを人に説明しようとしてもなかなかうまくいかない。「やさしいまなざし」とか「抱腹絶倒」とか「冴えわたる技巧」とかいってみたとしても、漠然としてるだけでつまらない。ほんとうはかんたんなことなのに。南部小説というハウス・パーティを考えてみよう。死をもたらす使者や、飲んだくれや、髭もじゃの猛者どもがうようよいるなかで、ルイス・ノーダンは庭の片隅にぽつんとたたずんでいる。お母さんに真っ青なスーツを着せられてきた少年のように。彼が描く南部もぼくたちのと同じ、過去の亡霊に取り憑かれた南部だ。ノーダンも同じ苦難を目にし、同じ悪魔と闘ってきた。でも、彼の目をとおして描かれると、南部は変身を遂げる。池には人魚があふれ、みすぼらしい隣人たちはキャベツ畑でアリアを歌いだす。塞ぎの虫に取り憑かれたアル中の父は魔法を帯びている。作家の心は開かれ、正直で、千々に乱れ、うれしいことに、それを進んでぼくたちに見せてくれる。
Music of the Swampのなかに“Owls”という短篇がある。わずか7ページの小品で、深夜、少年がビールを何杯か過ごした父と夜道をドライブする話だ。これがぼくの人生でいちばんたいせつな話になるのだ。あらすじを説明しよう。少年は父の運転が気になって、カーブのときに無視して猛スピードで通り越してしまった黄色い標識のことを口にする。父も標識には意味があるといって、車をUターンさせる。というのも、父が見た標識は〈Slow(速度落とせ)〉ではなく、〈Owls(フクロウ)〉と読めたのだ。この小説の最初の魔法は、標識を改めて見て、少年が父が正しかったのを知るところだ。たしかに〈Owls〉と書かれていたのだ。父はエンジンを切って、ウィンドーをおろす。ほかの作家なら見え見えの展開になるところで、ノーダンは二つ目の魔法を放つ。あたり一面から、ミシシッピ・デルタの切り株畑から一斉にわきあがるように、フクロウの群れが地面を蹴って舞いあがり、車のまわりに輪を描いて飛びだすのだ。空気をうつ羽ばたきの音、喉の奥からそっと呼び交わす鳴き声が聞こえて、少年は初めて、それまで近寄りがたかった父と気持ちがかよいそうな気がしてくる。
どうなると思いこんでいたのかはわからないけど、父さんの手の指が腕に、シャツの袖のあたりにふれてくるんじゃないかと思った。振り向いて、生まれて初めて、どういえばいいのかわかるような気がした。これまでの秘密をみんな打ち明けるのだ。すると、父さんはきっといってくれる。「愛しているよ」すべてはそういうことだったんだ。真夜中に父親と二人、車のなかに閉じこもって、フクロウの群れの鳴き声を聞きながら菱形の標識を、〈Owls〉と書かれた標識をじっと見つめることになったのは。
でも、父さんはやがてウィンドーを閉め、ぼくもそれにならう。暗闇のなかで父さんはいう。「なあ、おまえの母さんときたら、家のこととなるとからきしだな」
ぼくたちはじっと〈Owls〉の標識を見つめるだけだった。こうなってしまったからには、もうどうにもならないことがわかった。
小説には先がある。場面は数十年後に切り替わり、少年は大人になり、このエピソードを愛する女性に聞かせているところだ。二人は人生の穏やかなひとときを味わっている。ベッドに横になり、腿には日射しが帯を作り、女性はなかなか信じてくれない。静かに細かな事実を問いただされるうち(記憶のなかの月の大きさや、暗い田舎道で見かけた兎の目の色を)、彼はフクロウの話が自分の創りあげた夢物語だったことを悟る。父とのつながりを、事実とは異なる、こうあってほしかったと思うものにするために。ノーダンがぼくたちに見せようとしている本当の魔法はここだ。彼はいまその偽りの記憶を解き放つことができる。真実の愛を一人の女性に見いだし、そのためにようやく、もうとっくに死んでしまった父への愛に気づくことができたのだ。
ミシシッピのパティオで、ぼくたち5人は知る。物語のなかでも、そこから離れたところでも、人が人生と記憶とをずっと取り違えていたことをこれほど巧みに説明できたものなどないことを。だから、希有のことではあるけれど、この小説はただの小説ではなくなり、ぼくたちの生涯にこの先ずっと、彩りを添えてくれることになる。その色は、もちろん、〈Owls〉と書かれた交通標識のあざやかな黄色で、ぼくたちはそのマークを身体のどこに記そうかと計画を練りだす。そうすれば、誰かに訊かれたときに、ノーダンやフクロウや小説や愛を語ってきかせる幸せを味わえるから。でも、不思議なことが起こる。時がたつにつれ、胸にしるした下書きが皮膚からしみこんで、心臓にまで広がると、もう実際にタトゥーを彫る必要なんてなくなってしまったのだ。
でも、まだ一つ、いっておかなければならないことがある。
先週、かつての恩師、トム・フランクリンからメールが届いた。悲しい知らせだった。「バディ・ノーダンが亡くなった。昨日のことだ。ほかのフクロウにも知らせてくれるかい?」
ぼくがコンピュータの前に突っ伏しているのに気づき、悲しい知らせを聞いて、妻はうなじに手を置いて慰めてくれた。そのうち、彼女は語りはじめた。最近、夢で母が死んで幽霊になって現れるのを見たのだという。夢の話を、作り話をするうちに、本当に不安になってきたのだろう、妻は泣きだした。ぼくは彼女の髪にふれた。この先ずっと、いつもそうしてもらいたいと思ってくれたら、と必死に念じながら。やがて、妻が母に電話をかけようとして受話器をはずすのを見て、これまで小説で目にしたなかでもっとも真理をついたと思える一節が心に浮かんだ。Music of the Swampの本を締めくくる最後の一文だ。「すべて愛は大きな痛みをともなう。でも、それでいい、それだけの価値はある」
そんなわけで、いま、ぼくは新しいタトゥーを入れようかと考えているところだ。ただ一言。〈そうだね、バディ〉と。
誰か、どういう意味なのか訊いてくれたらいいんだけれど。
ぼくは喜んで説明するから。
ミルトン・オニール・ウォルシュ(M・O・ウォルシュ)はルイジアナ州バトン・ルージュ出身の南部作家。デビュー短篇集The Prospect of Magic(2010)はルイス・ノーダンに「こんなに満足させてくれた本は久しくなかった。ぼくもこんなふうに書けたらいいのに」といわしめた傑作。ゲーム・テーマの連作をDaily Science Fictionなどにも執筆していて、SFも書くいまどきの南部作家でもある。この追悼文は雑誌〈オックスフォード・アメリカン〉2012年夏号(77号)に掲載されたもの。著者のご厚意により、訳載を許された。
クリストファー・バルザック
いまでも、ルイス・ノーダンの小説に出会ったときのことは覚えている。それはまったくの偶然で、ぼくがまだ20歳の英文科専攻の大学生だったときのことだ。文芸批評とエッセイと短篇小説の入ったアンソロジーをもとにして、授業にエッセイを提出するようにいわれて、ぼくは教授から渡された本を読んでいた。指定されたエッセイ三本を読むようにいわれたものの、ぼくはその三本以外に何が入っているのか、ぱらぱらとアンソロジーをめくってみた。なかにはルイス・ノーダンの短篇が2本入っていることがわかり(あとでわかったのだが、そのアンソロジーの編者はピッツバーグ大学でバディ・ノーダンと同僚だった)、最初の“Music of the Swamp”を読みだして、いきなり数ページで笑いころげては涙が止まらなくなった。次の短篇を読みだすと、また笑って泣くことを繰り返した。読み終えると、ぼくは当時つきあっていた恋人に、寝室においでよと叫ぶと、一人で黙読したばかりだというのに、彼女にそれを2つとも読み聞かせた。彼女も同じように大声をあげて笑い、同じように泣いた。2人とも一休みして呼吸を整えなければならなかった。本を読んでこんな複雑な感情的反応が起こったことなんてなかった。思わず吹き出したり、悲しくなったり、ある状況やあるタイプの人物のことを深く考えさせてくれる作家ならいる。複雑な情緒や雰囲気を作り出せる作家だって、ふつうにいる。でも、1ページめくるあいだに、ときにはたった1つのフレーズを読んだだけで、自分がちっぽけに見えたかと思うと、悲しくなったり、笑えたりといったことがつぎつぎと瞬時に切り替わってしまうような力をもった作家はそうはいない。ぼくはたちまちルイス・ノーダンの虜になって、すぐに手に入る著書をすべて買い求め、ファンになって数年後にはじかに会う幸運にも恵まれた。ぼくの大学で講演をしてくれたのだけれど、それはやはりその晩の聴衆の涙と笑いも誘うものだっ?。
彼にはもっと大勢の読者がいてくれたらよかったのに、と思う。間違いなくその価値がある作家だ。でも、南部作家というだけでなく、彼は物静かな人で、ぼくが知るかぎり、今日ソーシャル・ネットワーキングの広い世界で見られる作家のように、せっせと自分を売りこむのに血道をあげるような作家ではなかった。多くの意味で、彼は「ぼく好みの人」だったのだ
クリストファー・バルザックはSFマガジンでも何度か紹介したことがある知日家SF作家。映画化の話もある第一長篇One For Sorrowに続く第二長篇The Love We Share Without Knowingは日本を舞台にした連作短篇集でもあり、いずれの作品も一部は邦訳されている。最新刊は短篇集のBirds and Birthdaysが出たばかり。詳しくはSFマガジンの2006年6月号(「少年が死体で見つかって」)、2008年8月号(「卵の守護者」)、2010年9月号(「きみよりもリアルに」)の各掲載作を参照していただきたい。この追悼文は本特集のために書き下ろしてもらったもの。