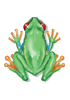作品紹介
小川 隆
『シュガーとフリークたち』(1996)

アメリカ南部のおぞましい現実を描く2つの長篇を書いたいま、ルイス・ノーダンはリアリズムの作家としての地位を確立していた。もう音楽的な文章やシュールなイメージを得意とする、ただのギークな作家ではない。何だって書けるはずだった。売り上げこそ目を見張るものではなかったけれど、いまでは忠実な愛読者がついていた。でも、驚きが待っていた。そこでノーダンと編集者のシャノンが選んだのは、初期の短篇集2冊を合本にすることだった。そこにはちょっと仕掛けがあった。目次を見てみよう。
Introduction by Richard Howorth
Foreword by Lewis Nordan
Part I
Storyteller
The Sears and Roebuck Catalog Game
John Thomas Bird
The Sin Eater
Wild Dog
One-Man Band
Rat Song
Welcome to the Arrow Catcher Fair
Part II
The Attendant
Wheelchair
Part III
Sugar Among the Chickens
The Talker at the Freak-Show
Sugar, Eunuchs, and Big G.B.
The All-Girl Football Team
Sugar Among the Freaks
序文が2つついていることにお気づきだろう。1つはミシシッピ州オックスフォードの書店〈スクウェア・ブックストア〉の経営者でのちにオックスフォード市長にもなる(2001-09年)リチャード・ハワースのもので、もう1つはバディ自ら書いたものだ。Welcome to the Arrow-Catcher Fairに入っていた“Mr. Nordine, Pentecost, and the Oral Tradition”と“The Copper Balloons”、The All-Girl Football Teamに入っていた“The Farmer’s Daughter”の3本の短篇がカットされていることにも気づいていただけるはずだ。そして、本の構成がMusic of the Swamp同様3つのパートに分けられていることにも。編集者シャノン・ラヴネルがこの本の成り立ちに大きく関わっていることが推測できる。彼女自身、表題作“Sugar Among the Freaks”を読んで初めてノーダンを知り、編集者として関わりたくなったことを述懐している。
でも、「まえがき」で、ノーダンもまたこの表題作が作者にとっても重要な作品だったことを告白している。この短篇を書いたことによって、メクリン家の小さな世界が見えてきて、やがてシュガーものの連作とアロウ・キャッチャーを舞台にした2つの長篇を書くことにつながっていったのだ。ここでのシュガーは24歳で、住んでいる場所もアーカンソー州だけれど、彼が語る家族や家の話はすべてシュガーもの連作で語られるのと同じメクリン家のものだ。連作として書かれていることを考えると、最初の短篇集に1つだけぽんと置かれているのは、バディ本人も認めているように、どうにも収まりが悪かった感じがする。新しい版元で新たな短篇集として編みなおしたくなったのも納得できる。それに、バディはこの短篇で描いた障害者ウィンストンの話をほかでも書いている。第1短篇集の“Wheelchair”と第2短篇集の“The Attendant”で、後者ではシュガーはハリスという名前で登場する。たしかに、この表題作はノーダンにとって重要な作品だったに違いない。合本になったこの新作で、2つの関連作品はパートⅡに入れられて、ほかの作品と区別されている。同様に、シュガーが登場する短篇はすべてパートⅢに入れられ、その最後を飾るのが“Sugar Among the Freaks”だ。これが短篇集のタイトルにもなっていることをみても、重要な作品だということがわかる。
シュガーは障害をもつ車椅子の詩人ウィンストンの介護人をつとめたことがある。いまウィンストンの介護にあたっているのは、とんでもなく不細工な黒人フロイドだ(黒人が登場する話はノーダンにとってはめずらしい)。ウィンストンから久しぶりに連絡があり、人生にうんざりしていたシュガーは何もかも投げだして、いっしょにドライブ旅行に出ることに同意する。オクラホマに向かって旅しながら、シュガーはこれまでの人生を振り返る。いつも彼のまわりにはどうしようもない人ばかりがいた。なぜかいつもダメ人間を引き寄せてしまうのだ。彼の人生はできそこないのフリークたちに囲まれた人生だった。シュガー自身がフリークなのだ。誰もが無力で、それでも孤独な人生を生きていかなければならない。結びの言葉はグレイトフル・デッドの歌詞のような一文だ。「そうさ、ぼくたちが生きているのはおかしな時代なんだ」
最初の2つの短篇集と次の連作短篇集を読んだときには、バディが紡ぎ出す魔法に、シュールなイメージや音楽的な文章や、ユーモアや孤独や、作者自身を含めてギークな人物に魅せられた。それはまったく新しいアメリカン・マジック・リアリズムに思えたものだ。スティーヴ・エリクスンや、ドン・デリーロや、デニス・ジョンスンといったゲアリー・フィスケットジョンが好きな都会的なアメリカ作家たちとはまったく違っていた。バディの魔法はそうした若い作家が描くハイテクや資本主義的な進歩にあるわけじゃない。魔法は沼のなかに人魚を見いだし、頭に雄鶏を戴くことのできる目や心にあるのだ。とりわけ、あるがままの形で人生を肯定していく、すてきで力強い決意の表明のなかに。ぼくたちは壊れてなんかいない、愛は永遠につづくんだという、「シュガーと鶏」などの作品に描かれているような気持ちに、ぼくは惹かれていた。
でも、2つの重いテーマの長篇を読んだあと、ぼくはバディが自分にとっての現実を、時代を、人生を描いていることに気づいた。最初はそれが南部という特別なところに改めて目を向けたものだと思って、ちょっとショックだった。長篇でふれられる過去の短篇のエピソードがまったく違ったニュアンスを帯びてくるのにもまいった。でも、こうしてふたたび初期短篇に向かい合ってみると、また新たな気持ちがわいてくる。バディが描いていたことは、やはり南部という特異な世界だったわけじゃない。それは暴力や不条理や孤独に支配された現代のアメリカだ。そして、バディ自身の世界なんだ。バディが力強く語る生への賛歌は、苦闘の末、つらく絶望を味わいながら、それでも勝ち得ることのできた真実なんだ。
そこに到達できたバディへの畏怖を禁じ得なかった。なぜバディの小説をアメリカン・マジック・リアリズムだと思えたのか納得できた。描かれていたのはただの南部にとどまらない、バディにとってのアメリカであり、現実の世界であり、現実の人生だった。魔法とユーモアはそこに立ち向かうためにバディが創りあげた武器だったんだ。ああ、バディ、ぼくはどうしようもなくあなたのことがまた好きになっていた。
『ガンマン・ブルーズ』(1995)

『指笛』Wolf Whistleは大成功だった。全米図書館協会の推薦図書や、ミシシッピ作家協会賞、南部文芸評論家協会賞に選ばれ、いまやルイス・ノーダンは南部の注目すべき新人作家となった。その流れのままに、彼はもう一つの南部の汚点に目を向ける。銃社会の問題だ。
またしても、新作にはこれまでの短篇のエピソードが利用され、ぼくはそれまでの彼の小説世界、アロウ・キャッチャーの見方を変えざるを得なくなった。これはちょっと厄介だった。なにしろ、これまででいちばん悲しい話で、死や嘆きが満載で、最初に読もうとしたときは途中で投げてしまったくらいだ。いまにしてみれば、その理由がわかる。それはバディが息子の自殺を小説化したものだったんだ。
19歳のテキサスのガンマン、モーガンが街にやってくる。伊達男のファッションと、プロのショーにも誘われた百発百中の射撃の妙技に、子供たちは夢中だ。だが、その自慢の射撃の腕を見せられても、ハイドロには関係なかった。デビュー短篇集の収録作“Stroyteller”にも登場していたこの頭の弱い20歳の元高校フットボール選手も、同じくらい射撃の腕はたしかだからだ。高校を出たハイドロは、いまは食料品店の店番をしている。といっても、大半の時間は年下の友人ルイスといっしょになって漫画を読みふけるだけだ。だが、その日店番をしているところに、姉弟の若い強盗2人組が銃を手に、押し入ってくる。金と食料品を奪ったあと、なんと姉はハイドロをレイプする。頭の弱いハイドロは呆然とするだけで、何がどうなっているかわからない。そのとき、モーガンのトラックが店の前に止まる。姉弟の注意がそれたとき、ハイドロはピストルを奪って2人を射殺する。
そこに胸騒ぎを覚えて、ハイドロの父、レイニー氏がやってくる。死体を見て、レイニーは強盗から息子を助けてくれたと思いこんでモーガンに感謝し、警察を呼ぶ。警察署長は現場を一瞥して、強盗事件と見抜き、モーガンをほめる。モーガンはわけがわからぬまま、そそくさと恋人のもとに出向く。だが、それまでずっと倉庫に隠れていたルイスが出てきて、モーガンが罪もない若者をいきなり撃ち殺したのだと嘘をつく。モーガンはルイスの母と不倫関係にあり、ルイスはそんな母や、不倫を黙認して何もいえない父や、まだ子供なので何もできない自分に腹をたてて、モーガンを罪に陥れようと考えたのだ。やむなく、署長はモーガンを拘留する。だが、ハイドロは2人の命を奪った罪の重荷に耐えかねて、自殺してしまう。一方、モーガンはよそ者の自分が罪を着せられてしまうことを恐れ、署長のピストルを奪って脱獄しようとする。誰もがちょっとした秘密をかかえ、その重さに引きずられてますます事態を悪化させていく。バディのいつものユーモアは控えめで、魔法にも悲劇が影を落としている。
最初はバディの私生活の悲劇のことを知らなかった。ふつうの人間を描いたふつうの小説に思えた。すべては銃のせいで、銃を偏愛するアメリカの悲劇に思えたんだ。いまでもよくわからない。個人的な悲劇を小説に描くことで、バディは救われたんだろうか。ともかく、これまでに読んだいちばん悲しい小説であることに変わりはない。
ああ、いま読みなおしてわかる。タイトルにもあるように、これはブルーズだったんだ。南部の香りをもち、悲しくて、ほんのちょっとのユーモアと大仰でシュールなイメージをまじえて語られる、現実の生活と現実の人間のソウルフルな表現だ。これまでもノーダンは作中でさまざまなブルーズに言及してきた。たぶん、南部のブルーズだけでなく、白人ミュージシャンによって世界中に広められたシカゴのブルーズも好きだったんじゃないかな。黒人音楽でありながら、白人やぼくたちアジアの人間までをも魅了してしまう、素朴ではあっても想像力豊かな音楽だ。バディは小説のマジシャンとしてだけではなく、まるでミュージシャンのように、この情念に満ちた音楽をみごとに奏でている。
『指笛』(1991)

ノーダンにとっての次のステップは、もちろん、ふつうの意味での長篇で、書かれた作品をみてぼくはびっくりした。驚くようなことじゃなかったのに。この長篇もいつものようにミシシッピ州アロウ・キャッチャーが舞台だし、これまでの短篇集で描かれてきたさまざまな出来事もふれられていて、シュガーとパパのギルバートも特別出演している。シュガーものの短篇の発展形といえるだろう。前作でふれた結びの台詞を思い出していただけるだろうか? そっくり同じ文章がいきなり最初のページで繰り返されていて、そこにも驚かされる。
その台詞は、ここでは主人公のアリスが大学を卒業して新任教師としてアロウ・キャッチャーにやってくる前に、彼女の恩師であり恋人であるドクター・ダストが彼女にささやいたものだ。彼女はいまだにその恋をひきずっている。もっとも、若い教師として理想に燃え、新しい教育理念のもとに深南部の田舎町を変えたいと思ってもいる。担任になった四年生のクラスを、葬儀屋や、裁判所や、あちこちに引き連れて課外授業に励み、病気や死やさまざまな人生の悲しい出来事に立ち会わせ、社会のありのままの姿を見せていく。暗くなりそうな話だけれど、このくだりは無邪気な子供たちの感想がユーモラスに描かれ、むしろ絵本の〈げんきなマドレーヌ〉を思わせる。ただ、時代は1955年で、人種差別は根強く、暴力と不正があちこちにはびこっている。とある黒人少年が若い白人女性に軽口をたたいたとき、悲劇は起きる。
この小説は実際に起きた歴史上の事件をもとにしている。エメット・ティル殺人事件として知られるもので、ノーダンは証言に基づくおおよその史実を忠実になぞっている。少年はシカゴから伯父を訪ねてきていて、地元の黒人少年たちとおしゃべりをしているうちに、北部での女の子たちとのつきあいを自慢したくなる。そこにたまたま若い女性を見かけて、声をかけてしまう。彼女はその晩、夫に黒人が指笛を吹いて冷やかしてきたという話をする。夫は激怒して、少年の居場所をつきとめ、伯父の家から引きずり出して、目玉をくりぬき、射殺する。このアメリカ南部のおぞましい現実を、人種差別と暴力が支配する世界を見せつけられると、これまで神話世界のように見えていたアロウ・キャッチャーがまったく違った姿を現してくる。たしかに、相変わらずそこには魔法や驚異があふれている。もっとも印象的なのは少年を殺した犯人を裁く全米が注目した裁判の場面だ。一羽のオウムが廷内を飛びまわったあげく、犯人の頭に止まって糞をする。前の短篇集で書かれているシュガーの頭にのった雄鶏を連想させずにはいない光景だ。それでも、バディはそれまで禁じていた南部方言や独特のいいまわしの表記を用い、ブルーズなどの南部の音楽から多く引用して、ここに描かれているのが架空の世界でも架空の物語でもないことをぼくたちにつきつけてくる。この本格的な長篇第一作で、作者は愛や世界の不思議といった普遍的な知恵を伝えるための虚構世界を離れ、自身の出自と現実に向かい合っている。これはまさしく〈南部小説〉なのだ。
読み終えて呆然としたことを覚えている。たしかに、版元もこれがティル殺人事件をもとにした話だと宣伝していたし、それが60年代の公民権運動につながる大きな出来事だったことは知っているつもりだった。しかも、バディはこの重い現実を、いつもどおり軽やかに、犯人側の白人貧困層の絶望も織りこみながら描いている。シュガー・メクリンものにさらに奥行きを与える話だということもたしかだ。湖で少年の死体を発見するのは“Music of the Swamp”に描かれているとおり、シュガーとスイートだし、ここで描かれるアリスは、デビュー短篇集の“Rat Song”の若い女教師を彷彿とさせもする。でも、けっきょく誰もが有罪だとわかっている白人は無罪となり、現実は理想を打ち砕く。アリスは一年で学校を去ることになる。ハッピーエンドも、生きることを励ましてくれるようなメッセージも、語られることはない。
前作で愛の不思議とすばらしさを見せてくれたあと、バディはここでは彼にとっての現実と過去に向き合っている。力強い作品であり、自分が属する時と場所の恥ずべき一面を描いたバディの勇気と率直さは賞賛に値する。ああ、それがバディの人生だったんだ。
『沼沢地の音楽』(1991)

シュガー・メクリンものをシリーズ化することでスタイルを確立する一方で、ルイス・ノーダンは生涯にわたる自分の編集者をも見つけていた。〈アルゴンキン・ブックス・オヴ・チャペルヒル〉のシャノン・ラヴネルである。彼女が見つけたノーダンの問題点はただ1つ、売れないことだった。そこで彼女は短篇を年代記風に配列して、長篇と謳うことをもちかけた。エピソードで構成された長篇というか、連作短篇集である。商業的な意図ではあったけれど、結果としてこれが大成功だった。短篇特有のすばらしい文章の密度と叙情性を維持しながらも、読者にはストーリーの流れも提供したのである。以下、目次を記そう。
Part I
Music of the Swamp
Part II
Cabbage Opera
A Hank of Hair, A Piece of Bone
Train, Train, Coming round the Bend
The Cellar of Runt Conroy
Porpoises and Romance
Field and Stream
Part III
How Bob Steele Broke My Father's Heart
Creatures with Shining Scales
Epilogue
Owls
すごい! タイトルを見ているだけでわくわくしてくる! 音楽が聞こえてくるし、映像が浮かんでくるし、いろいろなイメージが喚起されてくる。実際、シュガーとアロウキャッチャーの世界は、タイトルどおり華麗なものだ。ここでのテーマはシュガーの成長だけれど、その世界には妖精やら人魚やら、驚異と魔法があふれている。そうしたファンタスティックな風景のなかに、病気や暴力や悲劇が見え隠れしてはいるものの、それでもシュガーもぼくたちも愛や希望を見いだすことができる。
巻頭を飾る、表題作がいい例だ。ある朝、シュガーはいつになくご機嫌だ。頭のなかには沼に人魚がいるとかいった、すてきなイメージがあふれてくる。でも、親友のスウィート・オースティンが沼にボートを出すと、2人が見つけるのは人魚ではなく、死体だ。スウィートの父はずっと前に家を出ていったきりもどってこないので、スウィートはそれが父だったらどうしようと心配になる。2人はシュガーの家に駆けもどって、事態を知らせる。でも、ママはいつものようにシアーズ&ローバックのカタログを前にして空想ごっこにふけっている(この空想ゲームは前の短篇集に描かれている)。パパは酔っ払って、ベッシー・スミスの音楽に夢中だ。シュガーは気づく。2人とも負け犬なんだ、現実を直視できずに夢想の世界に逃避しているんだ。パパが大好きな曲の歌詞みたいに、みんな死にたいほど孤独なんだ。絶望にとらえかけられたとき、ママがかわいそうなスウィートを慰めにきてくれて、たちまちシュガーは両親への愛に胸を詰まらせる。世界はそんなかんたんに割りきれるものではなく、ここ南部ではあらゆることが入り混じっている。いま流れているベッシー・スミスの曲〈マディ・ウォーター〉の歌詞のように。
ここには南部の現実が投影されている。南部では南北戦争以来、誰もが敗残者だ。現実はまだ幼いシュガーの小さな肩にになうには重すぎて、早く大人にならなければと悲壮な決意を固めざるを得ない。何しろ、両親はそろって現実の重荷から逃避しているのだ。この冒頭の短篇が長篇(連作短篇集)全体の基調を定めている。成長小説としての性格を、だ。やがて大人になったシュガーは父の死と直面する。でも、そんなときになってもまだ母はうっかりとシュガーの出生の秘密を漏らしてしまう。素朴に喜びや悲しみにひたっていられる瞬間などどこにもない。あらゆることの底に秘密や隠された現実がひそんでいる。短篇集の最後はこんな印象的な文章で締めくくられる。「愛はすべて苦痛をともなうものだけれど、それでいいんだ。それだけの価値はあるんだから」
その前の短篇集の結びの言葉と比べてみよう。「(ぼくは思った)……きっとぼくたちは年をとることもなく、愛は永遠に続くんだ、と」夢に満ちた、力強い、すてきな台詞だ。でも、この連作短篇集では、バディはよき編集者を得て、さらに誇らしげなメッセージを示している。ついに、シュガー・メクリン・シリーズは完結をみたのだ。
『女の子だけのフットボール・チーム』(1986)

ルイジアナ州立大学出版局版
ぼくが初めてルイス・ノーダンのすてきな世界にめぐり逢ったのがこの短篇集だ。1986年にルイジアナ州立大学出版局から刊行されていたものを、1989年にヴィンテージ・コンテンポラリーズで出しなおした版で知ったのである。この年、ジョー・モンタナはまだ最盛期にあって、スーパー・ボウルを制し、89-90年シーズンのMVPにも選ばれる。ぼくはザ・クールと絶賛されたモンタナのプレーに惹かれ、それまでバート・レイノルズ主演の映画〈ザ・ロンゲスト・ヤード〉以来もっていたアメフトへのマッチョなイメージを一新させていた。隔年で参加していた世界SF大会が開かれるレイバー・デイの週末がNFLの開幕日に重なることが多かったこともあって、まずタイトルにそそられた。もちろん、ゲアリー・フィスケットジョン編集のヴィンテージ・コンテンポラリーズは大好きだったし、サイバーパンクの人工的な文体にも少し飽きてきたところでもあった。とはいえ、さほど期待していたわけじゃない。なにしろ、125ページという超スリムな短篇集だ。タイトルと版元から連想して、ちょっと風変わりでかっこいい小説が読めればと思っていただけだ。
何よりもまず、目次を記そう。
Sugar Among the Chickens
The Talker at the Freak-Show
Sugar, the Eunuchs, and Big G. B.
The Sears and Roebuck Catalog Game
The Farmer’s Daughter
Wild Dog
John Thomas Bird
The Attendant
The All-Girl Football Team
ともかくぶっ飛んだ。巻頭作品の「シュガーと鶏」(ここで訳載予定)はそれまでに読んだなかでもっとも忘れられない作品だし、同じ南部作家のケヴィン・ブロックマイヤーなどは世界の名作短篇トップ50の1つにあげているほどだ(ちなみに、お気に入りのトップはJ・G・バラードの「時の声」だそうだ)。家の裏庭で鶏を釣ろうとする少年の話で、なぜそんなことになったかといえば、ちょっと心を病んでいる母は一人では遊びに出してくれないし、アル中の父はあまり外に連れ出してくれないからだ。思わず噴き出す場面もあるのに、直後には涙がでそうな逸話だったことがわかるという、忙しい話だ。そんな悪戯をするくらいだから、けっしていい子ではないのだけれど、パパとママが大好きでこの壊れかけた家庭を何とかしようと必死な、けなげな少年だ。頭のてっぺんに真っ赤な雄鶏を載せて誇らしげに歩く男の子のシュールなイメージは、ぼくにとってはいつまでも、必死に生きていく人間のシンボルになった。表題作もすばらしかった。その愛すべき少年、シュガー・メクリンもいまでは高校生になっている。舞台となるミシシッピ州アロウ・キャッチャーの町には年に2回女装のイヴェントがあって、父は熱心な参加者だ。シュガーはそこに加える新しいイヴェントを思いつく。女の子にフットボールをさせるのだ。当然の報いか、少年は女装してチア・リーダーをするはめになる。この子が胸に抱く気恥ずかしさも、誇らしさも、愛も、すごくよくわかった。ぼくもバンドをやっていたころ、学園祭ノリで女装してプレイしたことがあるのだから。この短篇集はそんなシュガー・メクリンものを中心に作られている。いまにもばらばらになりそうな家庭に育つ10歳から11歳ぐらいの男の子の話だ。
ルイス・ノーダンはようやく書くべき話の焦点を見つけたんだ! ミシシッピの田舎町を舞台にして、男の子とその家族が繰り広げるささやかな悲劇と喜劇――悲しみと孤独に彩られながら、そこには不思議も愛も喜びも、つまりは魔法があふれている。パーソナルな味わいをもった魔術的リアリズムの小説だ。デビュー短篇集ではギークさにとどまっていたシュールな雰囲気は、ここでは魔法にまで高められている。ノーダンは自分のスタイルを確立したんだ! いいぞ、いいぞ、バディ!
『アロウ・キャッチャー祭りにようこそ』(1983)

ルイス・ノーダンの初短篇集であり、刊行は1983年、ルイジアナ州立大学出版局から出ている。ぼくが読んだのは1989年、ヴィンテージ・コンテンポラリーズ叢書から出た再刊のほうで、第2短篇集The All-Girl Football Teamを読んだあとだった。以下、目次を記そう。
Mr. Nordine, Pentecost, and the Oral Tradition
The Sin Eater
Rat Song
Wheelchair
Storyteller
The Copper Balloons
One-Man Band
Sugar Among the Freaks
Welcome to the Arrow-Catcher Fair
ぜんぶで129ページという薄さで、序文も後書きもない、およそ飾り気がまったくない本だった。“どうぞ新人作家の文学作品を試食してみませんか”みたいな、宣伝のしかたも決めかねたまま出してしまう、よくある短篇集だ。収録作はいずれもアメリカ南部の田舎町を舞台にしていて、まだアロウ・キャッチャーという名前も特定されていなかった。老人から子供まで視点人物もいろいろなら、文体もさまざまだ。キリスト教や、暴力や、貧困や、無知といった伝統的な南部小説で扱われてきた問題も取りあげられ、実際、フラナリー・オコナーなどの南部小説の影響も見てとれる。
目次を見てもわかるように、ハイフンが目立つ。音楽的要素はルイス・ノーダンの文章の特徴だが、ここでもそれはすでに異彩を放っている。第2短篇集と比べると、焦点が定まっていない感は否めないが、バディの短篇の特徴はすでにそろっている。ぼくが引きこまれた巻頭作は、死に化粧をほどこす葬儀屋の話だが、これはテレビドラマ〈シックス・フィート・アンダー〉や、SF界でスリップストリーム愛好家が大騒ぎしたデイヴィッド・プリルの『葬儀よ、永久につづけ』(東京創元社刊)というジャンルの枠を越えた作品が登場するはるか前の作品だ。“Sugar Among the Freaks”(ここで訳載の予定)は障害をもっているせいで見下している“フリーク”とドライブする若者の話だ。表題作にいたっては、自分に向かって射られた矢を素手でつかむ、インディアン由来の伝統競技が描かれる。“Rat Song”も好きな作品だが、娘にはじめてパパ、パパと甘えてせがまれて、ペットに薄汚い鼠を飼うことになる男の話だ。かわいいハツカネズミでもハムスターでもない、ただのドブネズミだ。ペストを持ちこまれないかと心配しながらも、娘にそれを押しつけてきた若い女性教師が気になってしかたない、という、いかにもなダメ男のうろたえぶりがおかしい。
いずれも風変わりな作品だ。ただ、いわゆる南部ゴシックでもなければ、バリー・ハナの小説のようなヒップなかっこよさとか、タガの外れた自由奔放なゴンゾっぷりとも違う。バディの小説の特徴となっているシュールな異色さは、英語の“ギーク”という言葉がぴったりだ。というか、ずっとサイバーパンクでオタクっぽい(ギークな)SFを訳していたころのぼくには、そんなふうに思えた。ハイフンの多用も、専門用語や新語で使われるように、特異性や、特別な存在であることを強調している――現代におけるふつうさとはひと味違うものを。かといって、南部小説でよく取りあげられる時代遅れで、迷信がかった旧弊ぶりを示すものではない。ノスタルジーでもない。バディは人間がうっかりのぞかせたり、振る舞ったり、出会ったりする、奇妙なものを、そしてその奇妙さをかかえていくしかない人間のありようを、肯定しているのだ。焦点の定まらない、ばらばらな寄せ集めの短篇集デビュー作ではあっても、バディはすでにバディらしい生の賛歌を歌っているのである。