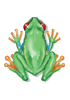海賊対ゾンビ
アミリア・ビーマー
ゾンビが人を食べるときにたてる音は、酔いに浮かれて潮を吹かせながらセックスするときの音にそっくりだ――うなり声とうめき声とぴちゃぴちゃという音。 ケリーは下の手漕ぎボートで人を食べている。いやでも耳に入ってくる。船に打ち寄せる波の音といっしょに。
下に手漕ぎボートがいたなんて知らなかった。あいつがゾンビになるなんて知らなかった。どうすればよかったっていうんだ? 友達がゾンビになっちゃったら、何とかしなきゃならない。ぼくたちは両端からケリーの手足をつかんで、ちっちゃな子をぶらんこして振りまわすみたいに勢いをつけた。そして海にほうりこんだ。でも、水しぶきはあがらなかった。どしんという音がした。船の手すりから見下ろして、ぼくたちは悪態をついた。落ちた先にいた相手はひどくつぶれていて、男か女かもわからなかった。ボートにいたもう一人も気絶していた。
「ごめんなさーい!」とぼくたちは声をかけた。
ボートの人たちは2人とも死ぬ前に意識を取りもどした。2人は絶叫した。ぼくたちも絶叫した。それから舷側から吐き、胃のなかが空っぽになって、鼻水と涙がとまらなくなった。
「水はもってきた?」ぼくたちは訊きあった。「水はどこ? ティッシュペーパーは誰かもってる?」
「いつ水なんてもってくることになってた?」とぼくたちは訊いた。「客が暴れだす前かい、後かい? 車に逃げこんだときかよ? 埠頭に逃げてきたときか?」
ぼくたちは船を点検した。船首から船尾までは10歩。船室なし、諸設備なし、備蓄なし。水なし。残っていたたった1隻の船だった。コロンブスが乗っていた船〈ニーニャ号〉のレプリカだ。盗んだときには、看板にそう書かれていた。
ケータイはつうじなかった。ぼくたちがこんなところにきているなんて誰も知らない。ぼくたちは袖で顔をぬぐって、つばを吐いた。1人はカッターナイフをもっていた。いざというときには、それで手首を切れるかもしれない。ぼくたちは坐って助けがくるのを待った。日は傾き、寒い夜になりそうだった。
人1人を食べ終えるには時間がかかった。ケリーからものを教わるのもこれが最後だろう。スーパーマーケットの〈トレーダー・ジョーズ〉でぼくたちを指導し、あちこちに紹介し、誰が親切で誰がそうじゃないかを教えてくれた。みんながコーヒー売り場でゾンビに変身しだしたあとだって、ぼくたちを湾に連れてきてくれた。ゾンビだって泳げるかもしれないが、船の上でなら身を守るのははるかに楽だ、といって。
いまでは手漕ぎボートの上のゾンビは3人だ。彼らは静かだったけど、ときどきかすかにうめいている。みんな二日酔いのときにやるみたいに。サンフランシスコ湾は霧に覆われ、悲鳴しか聞こえなかった。ありとあらゆる大きさの船がエンジンの有無を問わず、水上にひしめいていた。エメリヴィルの岸辺からも、バークリーの岸辺からも、もっと南の内陸のオークランドからも悲鳴が聞こえたし、ベイ・ブリッジやトレジャー・アイランド、さらには対岸のサンフランシスコからも聞こえるような気がした。世界は終わりを迎えたんだ。まだ2012年になってもいないというのに。
喉が渇いた。舷側から、ぼくたちはボートを見た。離れはじめていた。そこには水が何リットルも入っていた。安全なプラスチック容器に。それに、きっと服や救急セットや食料が詰まったバックパックが。寝袋が。オールが。あの連中のほうがぼくたちよりずっと用意ができていたのに、それでもあんなことになってしまった。ぼくたちは顔を見合わせたけれど、もう腹は決まっていた。助けはこない。生き残りたかったら、品格を落とさなければ。
ぼくたちは長いロープをおろし、甘い声でゾンビを誘った。ケリーが飛びつき、よじ登りだした。眼鏡はなくしていたけど、ゾンビは近眼じゃなくなるのかもしれない。ぼくたちはロープをボートから遠ざけてから、手を離し、あいつを海に落とした。
ゾンビは泳げないのがわかった。そこで、同じことをほかのゾンビにもしてみた。彼らも沈んだ。これだけはこっちの船にもあった。ロープだ。ぼくたちは交替でロープをつたい降り、小さなボートから水や備品をもってきた。グリンチがクリスマス泥棒をしたみたいに。ともかく、気分はクリスマスだった。少なくとも数日分の生活必需品が手に入ったんだ。それに、ぼくたちは仲間を落としたりはしなかった。
ぼくたちは片づけ、さらに秘密のことをした。自分たちに海賊名をつけたんだ。ジューシー・リュウ、ハイウォーター・マーク、ジャスティン・ケース。ぴったりに思えた。ボートを略奪したんだし。ケリーを殺したし(2回も)。もうりっぱな海賊だ。
もう自分たちが思っているような人間じゃなくなっているんだから、何かを捨ててしまわなければならなかった。
ジューシーが最初の見張りを引き受けると申し出た。どっちにしろ寝れそうにないもん、というのだ。でも、ぼくとハイウォーターを寝かせてくれるわけじゃなく、繰り返し〈ギリガン君SOS〉の主題歌を歌った。サビしか歌詞を知らなかったので、そこばかりを。それに飽きると、今度は〈ボートを漕ごう〉だ。近くのボートからも歌声が加わった。最初の数分間は、これなら人類は生き残れるのかも、と思えた。
うとうとしてから、彼女に足でつつかれて目が覚めた。歌は終わっていた。ジューシーはぼくの寝袋にもぐりこんだ。ぼくは甲板を歩きまわり、なぜ歌いたくなるのかわかった。ハイキングのときに、ガラガラヘビを近寄らせないように音をたてるのと同じだ。歌っていれば、おかしなやつと思われてどこからもちょっかいはこない。
だからぼくも歌いだした。クリスマス・ソングを、だってほかに覚えている歌なんてなかったから。それからジェイムズ・テイラー、ビートルズ、ボブ・ディラン。50セントの〈イン・ダ・クラブ〉の歌詞はぜんぶ覚えていたので、何度かがなった。ケリーがぼくに合わせてラップしているのが聞こえたような気がした。あり得ないことだけど、ともかく探してみた。水は静まり、そこから出てくるものは何もない。
空がやさしい青に変わりだすころ、ハイウォーターを起こした。夜明けなんてこの10年ほど拝んだためしがなかった。高校のブラスバンドの早朝練習以来だ。空が温まるのを見守りながら、ぼくはハイウォーターの寝袋にもぐりこみ、思い出した。みんな、かわいい女子までが、バンドのユニフォームを着るとダサく見えたことを。女子はユニフォームの帽子をかぶって、司書みたいに髪をアップにしていた。顎紐をつけた司書だ。クラリネットの代わりに本を口にくわえ、隊列を守って行進するんだ。
「コロンブスがこんなもんに乗って大海原を航海したはずはないわ」とジューシーがいった。「横帆を張れる人だって見たことはないわよ。船外モーターがついてなきゃ」
ぼくは日射しに目をこらした。ジューシーはきれいだった。おかしいな、彼女のそれまでの名前が記憶にない。思い出したいとも思わない。何だか知らないけど、似合ってなかったんだろう。
「でも、おれたち、どこにいくんだ?」ハイウォーターは日焼けして、夜の営業が終わるころのシーフード・チェーンの〈ロング・ジョン・シルヴァーズ〉の厨房みたいな臭いがした。
空っぽの波止場が左舷船首のずっと先にいまでも見えている。右舷船首っていうんだっけ? どっちから見てどっちというのかがわからない。舞台の言い方と同じだっけ?
「待て(アヴァスト)!」呼び止める声がした。下のほう、海面に、小型モーターボートに乗った小柄な男がいた。男は小型のピストルをぼくたちに向けていた。
警察ドラマでたたきこまれていたせいで、ぼくたちは両手をあげた。
「手を下ろせ。武器を持っていると思ったら、わざわざ寄ってくると思うか?」と男はいった。闘犬のような笑みを浮かべていた。「備品をおろしてくれればいい、水と食料、毛布、救急セット、何でもだ。とくに、日焼け止めだな」やつはサングラスをかけていたが、禿げた頭は痛々しいほど真っ赤になっていた。「こっちは本気だぞ」と男はいった。「弾を無駄にしたくないんだ」
「わかった、わかった、ちょっと待って」とハイウォーターはいった。いつだって頭の回転が速いやつだ。「どうする?」と彼はささやいた。
ぼくはひどく喉が渇いていることに気づいた。「ぼくたちは海賊だ」とぼくはいった。
「だから?」とジューシーが訊く。「博打を打つの?」
ぼくはもぞもぞと寝袋から這い出し、船の縁にきた。「手を組もうぜ」とぼくは呼びかけた。「こっちにはさまざまな能力がある、味方にしておきたくなるぞ。ここのはみんなぼくたちが盗んだもので、あれも……3人片づけた。あいつらだよ!」まだゾンビという言葉は誰も使っていなかったし、言い出しっぺにはなりたくなかった。
小柄な男はピストルを撃った。〈ニーニャ号〉のぼくたちは甲板に倒れこんだ(ヒット・ザ・デック)――床に倒れる(ヒット・ザ・デック)って言葉はここからきたのか?――そして待った。耳がわんわんと鳴った。
「おれは本気だ」小柄な男が叫んだ。
「わかった、そっちの勝ちだ」とぼくは呼びかけた。
かくてぼくたちは必需品を失い、小柄な男はエンジンをかけて離れていった。
「これは正規な大きさの船じゃないわ」とジューシーがいった。「船首から船尾までだいたい10から12歩よ」
「縮尺模型なんじゃないの」ぼくは推理を口にした。
ぼくたちは渇きで死にそうだった。いきなりケリーみたいに、誰かがゾンビになったりしたら別だけど、そうなったら、同じ死ぬにしてもゾンビになるんだ。喉の渇きで死ぬのは最悪な死に方じゃないのかもしれない。ぼくが考える最悪の末路とは、腐敗した骸骨とじかにつながれて、餓死するまでほうっておかれることだ。そんなことがまだあたりまえで、テロリストが裁判にもかけてもらえなかったころには、敵にそんなことをする王様がいた。それでも、きっと喉の渇きで死ぬほうが先かもしれない。
ぼくたちは日があるうちに船内を探検した。水はなかったけれど、デッキの下の壁にくくりつけられた鞭が見つかった(正規な大きさの鞭なのか縮尺版なのかはわからない)。大きかった。見せびらかそうとして、ぼくは自分の耳をぶってしまった。ビシッという音もしなかった。
電話やインターネットがまだ使えたころ、ツイッターでみんながいっていた。鞭を使えばゾンビをコントロールできるって。それに、ゾンビは性病の一種で、発症するまでに潜伏期間があるって。そんなことをいっていた連中は、よたを見きわめる能力がまったくないせいで、いまごろはきっとゾンビになっているんだろう。でも、こっちは喉が渇いてたまらなかったから、何だってやってみる気だった。ジューシーはぼくから鞭を取りあげた。彼女は自分にあてることなく、打ち鳴らした。インディ・ジョーンズみたいにパシパシと音がした。彼女はケリーに呼びかけた。
数分後にケリーが水中から顔を出した。じゃあ、ゾンビは泳げるんだ。ただ、ものぐさなだけなのかもしれない。外部からの動機付けが必要なのかも。ジューシーは彼に話しかけ、節目節目で鞭を鳴らした。彼の名前を呼んだ。彼はいまでもそれにこたえた。ぼくは気にならなかったけど、気にすべきだったのかもしれない。彼はある時点ではぼくたちの名前を知っていた。そんなやつだってどこかにいてくれたんだ。
ケリーはぼくたちがおろしてやったロープからあがってきた。デッキにポタポタと水をしたたらせ、100人の清純な乙女を前にするみたいな目でぼくたちを見つめた。そんな感じでぼくたちを見つめていたから、きっとジューシーも頭にきたんだろう。彼女とつきあっていたことも覚えていないみたいだったから。でも、もどってきてくれてよかった。ぼくはそういってあげたけど、彼のほうはろくに口もきかなかった。
「彼らを襲ってほしいの」といって、ジューシーは指さした。選んだのはすてきな小型モーターボートだった。冷蔵庫とベッド付きの船室があって、大きな貯水タンクがついてるやつだ。ケリーは超人ハルクみたいな音をたてると、エルヴィスみたいに腰を振った。いまでもジューシーを愛してるんだろうね。
彼女は彼に水中で待機し、おぼれているふりをしろと命じた。運がよければ、死んでいるようには見えないかもしれない。彼はジューシーに微笑みかけてから、水に入った。
バイオテロリズムみたいなものだったよ、ぼくたちがやろうとしていることときたら。天然痘菌に汚染された毛布をネイティヴ・アメリカンに配るみたいなものだ。自分のタオルが濡れているからといって、誰かがシャワーを浴びている隙に、ロッカールームにかかっている他人のタオルを勝手に使ってしまうみたいなものだ――まったくたちが悪い。
ぼくたちはモーターボートに手を振った。そしてケリーを指さした。ぼくたちは索具を指さした。あるいは円材(スパー)というのか。後檣(ミズンマスト)だったかも。ともかく帆がついているところをさした。風はなかった。
年配の夫婦は気づいてくれて、ケリーがプカプカやりながら手を振っているところにモーターボートを寄せていった。ほんとうにいい人たちだ。見ず知らずの他人を助けようなんて。いまはやるかやられるかだということをぼくたちは肝に銘じなおした。
夫婦はロープを投げた。黒い水からケリーを引きあげて、そのロープを取り落として後じさったときには、やつは甲板の上に這いあがっていた。あとはもう、しっちゃかめっちゃかになったL・L・ビーンのカタログみたいで、フランネルのシャツはちぎれるし、趣味のいい靴は飛んでいくし、たいへんな騒ぎだった。
ケリーが食べているあいだ、ぼくたちは違ったやり方があったんじゃないかと議論した。
新しい家は〈スーパーボール〉と呼ぶことにした。それまでは違った名前がついていたのかもしれないけど、ジューシーがボートを〈ニーニャ号〉のそばに引き寄せたとき、ペンキがぐちゃぐちゃになってしまったんだ。もともと彼女は縦列駐車が得意じゃなかった。でも、あの姿は一見の価値があった。大胆にも鞭をくわえて、ボートまで泳いでいき、服は濡れて体に貼りついていた。ボートに移ったとき、ぼくとハイウォーターは彼女に襲いかからないように必死だった。ぼくは彼女を見るあいつの視線に気づいていたし、あいつも彼女を見るぼくの視線に気づいていた。2人ともケリーの彼女を追っかけるなんて、自分が恥ずかしかった。やつにはもう彼女の面倒をみることはできないかもしれないとはいえ。それにやつはいつもほかの女の子にもモーションをかけていた。噂ではやりまくりって話だった。
年配の夫婦は追い出さずにおいた。ケリーと同じで、鞭には従順だったし、そもそも彼らのボートだったのだから。2人はホーマーとマージと呼ぶことにしたけど、考えてみると、ひどく古めかしい名前だった。髪は薄く、細く、色も褪せていて、2人とも禿げかけていた。2人は嘆きながら甲板をうろついた。いつも2人いっしょだった。互いの体をまさぐってもいた。ケリーにあとをつけまわされていたけど、2人は気にしなかった。
ぼくたち海賊は船室に閉じこもった。そうすれば、まわりをとおるほかの船も、ここがもうすでに幽霊船になっていると思うだろう。ぼくたちは安全ってわけだ。
岸では、これまでに見たゾンビ映画をすべて実演しているみたいになっていることだろう。ここは平和だ。占い盤(ウイジャボード)が見つかったので、やってみたけど、死者とコンタクトすることはできなかった。まわりでこれだけ大勢死んでいたら、喜んで話してくれる幽霊ぐらいいそうなものなのに。無線もあたってみたけど、こっちも誰とも話はできなかった。もしかしたら、バッテリー切れかもしれない。『オー・ブラザー』で覚えた賛美歌をいくつかジューシーに教えてやった。ローディーっていうバンドの〈ナイト・オヴ・ザ・ラヴィング・デッド〉という曲のすげえコーラスも、歌詞はタイトル部分しか覚えちゃいなかったけど、歌ってやると彼女は微笑んだ。
そのときにはもうわかっていた。彼女がハイウォーターのほうを選んだって。まだキスもしていなかったけど――ともかく、ぼくの前では――わかっていたんだ。気にすることじゃなかったけど、気になった。
ジューシーに、外に出てみたら、といわれた。ドアを閉めたときの彼女の目で、ぼくの気持ちなどお見通しだったのがわかった。彼女の目は欲望に濡れていた。それとも、悲しみで。それとも、切迫した思いで。自分でも抑えられないんだ、それを告げようとしているんだ。
ぼくは歩きまわりながら、彼女がドアを開けてくれるのを待った。彼女の名前を呼びたかった――本当の名前のほうだ――でも、覚えているのはケリーのだけだった。やがてうなり声とうめき声とぴちゃぴちゃという音が聞こえてきた。
(訳:小川 隆)
解説
アミリア・ビーマーはミシガン州生まれのSF作家。クラリオン・ワークショップ出身で、ミシガン州立大卒業後にカリフォルニアに移住し、SF情報誌〈ローカス〉で編集者として活躍するかたわら、小説を書き、2010年にデビュー長篇The Loving Dead を発表して大きな話題を呼んだ。ここに掲載した作品はその長篇からのスピンオフで、ゾンビ小説アンソロジーThe Living Dead 2 (2010)に収録されている。80年代生まれのまだ若い作家で、今後の活躍が楽しみである。ちなみにいま来日中だ。(小川隆)