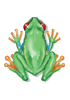ポスト・ホック
レスリー・ホワット
二カ月前に捨てられてからこっち、ステラはまだうまいことボーイフレンドに受話器を取ってもらえずにいる。発信者番号通知サービスのせいだ。発明したやつを訴えてやりたい。だって二人には話し合う必要がある。少なくとも、ステラには。クリストファーのほうは、もう言いたいことは言ってしまったそうだ――本人の口からはっきりそう聞かされた。最後に会ったとき、二人はどちらがコンドームのことを思い出すべきだったかで口論をした。「だからきみだったんだって」とクリストファーは説明した。自分は赤ん坊がほしいとは思っていなかったのだから、と。ステラだってほしいと思っていなかったが、じきに一人、生まれてくる。
ステラはまたクリストファーに電話をかけて、返事が来るあてのないメッセージを残す。彼女の声を聞きさえすれば、彼も情にほだされるはず。いま会えば、肉体の変化に気づくはず。つわりによる腹痛――医者の話ではごく一般的なものらしい――のせいでほんの少し猫背になった長身の体、そばかすくらい色が濃くなった乳首、誇らしいほど大きくなった乳房。この姿を見れば、同情するにちがいない。ステラはじっと電話を見つめ、彼がかけてくるよう念じる。が、念力は通用しない。向こうはびくともしない。
そこでステラはさらなる必勝法に出て、〈ピッツァ・シュミッツァ〉の短縮ダイヤルを押し、ピザを注文する。“二人の”ピザを。スライスした赤タマネギとブラックオリーブとアンチョビをたっぷり載せたやつを。なにかの代金を払うとき、携帯電話でクレジットカード払いにすべきじゃないのはわかっている。なにしろ犯罪者に個人情報が盗まれかねない。だけどカード被害に遭うほうが、“だれも話を聞いてくれない”というこの感覚よりましに思えた。配達人をやる気にさせるべく、チップ五ドルを上乗せする。万が一、受け渡しのときになにかあった場合に備えて。
玄関を開けたクリストファーが、甘いトマトとこんがりときつね色に焼けたモッツァレラチーズの抗しがたい香りを吸いこんだときの顔を、ステラは一人、想像する。きっと彼女のことが頭に浮かんで、クリストファーはちょっとためらってから箱を受け取るだろう。それから家中のドアに鍵をかけてスライド錠を差し、すべての窓のブラインドをおろしたら、ようやくソファに腰かけて、出どころ不明のピザを食べるのは賢明かどうかと思いめぐらすだろう。箱のふたを開けたい衝動をこらえるものの、ピザ特有の塩味と香ばしさと甘みに誘われて、ついにお腹が鳴りだすはずだ。屈するのは時間の問題。クリストファーが口を開け、チーズの層の下からあふれそうになるソースを舐め取るところを、ステラは想像する。きっと彼はもぐもぐと口を動かしながら、彼女のことを思うだろう。ステラはそのタイミングを見計らって、もう一度電話をかけるのだ。今度はクリストファーも受話器を取る。二人はよく話し合って問題を解決する。そして結婚する。新婚旅行はハワイ島一の観光地、ヒロ。シュノーケリングにハイキング。妊娠線なしでビキニを着られる最後のチャンスだ。急がないと、結婚式には妊娠第二期に入っているかもしれない。となると、妊娠線ができている可能性が高くなる。ドレス代だって高くなるはずだ。布が余計に必要になるから。ステラが生むのは男の子で、坊やはパパそっくりだ。クリストファー・ジュニア。その長く濃いまつげには、年配の女性たちがこぞって目をみはり、騒ぎ立てるだろう。「男の子ばかりがまつげが長いのはどうしてだろうね?」と。まれに見る賢さとやさしさを兼ね備えたこの坊やは、ステラと家族とのあいだにいまも広がりつづけている溝を埋めてくれるにちがいない。ステラは家族から、若かりし日にいくつも愚かな選択をしたと思われていて、いまは形を変えた愛のむちをふるわれている。
そんな夢想にも一つ問題があった。ピザを思い描いたせいで吐き気を催してしまい、結局その夜はずっと便器に寄り添って、バスルーム用に振り付けられたバレエ〈白鳥の湖〉よろしく、腰を二つ折りにして過ごすはめになったのだ。千載一遇のチャンスも、ホルモンバランスが崩れたせいで、ぶち壊し。あまりにも気持ちが悪いので、煙草で神経を落ちつかせることさえできない。が、それでいいのだろう。煙草は赤ん坊のためによくないと医者が言っていた。
別の計画を練らなくては。キャンディーつきのメッセージカードもEカードも、わざわざほかのサーバーから愛を宣言するメールを送るのも、もうおしまい。残る選択肢はただ一つ――ステラ自身を郵便で送りつけるのだ。いまの時代、手続きはオンラインで済ませられる。五分もあれば、ジャジャーン! だ。自分に五〇ドルの保険をかけるには一ドル三五セント必要で、補償額を五〇ドル増やすごとに、支払う保険料は倍額になるしくみだ。そもそもステラはすっからかんなのだから、最低額でも丁寧に扱ってもらえることが保証されているときに自分の価値について気をもむなんて、ばかげている。郵便配達人に集荷してもらうよう、手続きをする。よかった。なにしろ来週には料金があがる。世の中には変わらないものもあるけれど、郵便料金はその一つではない。
ラベルにクリストファーの名前と住所と郵便料金を印字して、つややかな裏紙はリサイクルに回す。少しばかり早まった。おかげでいまや、ぺたぺたくっつくラベルと格闘しながら、どこに貼るかを考えなくてはならない。鏡に向かって思案する。胸かおでこに貼ったほうが、まだ威厳があるように見えるだろうか。ボーイフレンドに自分を送りつけようとしているときに、威厳はなかなか醸しだしにくい。元ボーイフレンド、か。少なくとも、クリストファーに言わせれば。
おでこだ。
ポーチに腰かけて待っていると、正午に配達人が――ジョーという男だ――やって来て、ステラが一学期だけ通ったコミュニティカレッジの要覧を差しだす。それと、支払い期日が過ぎたことを知らせる医療研究所からの通知も。うさぎ三羽がすべて死んでしまったのだが、ステラとしては、原因をたしかめずにはいられなかったのだ。ジョーがおでこのラベルに気づき、二秒で彼女のもくろみを理解する。同情をこめてうなずいてから、こう言う。「今日の配達が終わるまで、後ろに乗っててもらわなくちゃならないんだが」
「かまわないわ。お仕事だもの」ステラは答える。ジョーの態度から、必死の手段に訴えたのは自分が最初ではないのがわかって、がっかりする。
郵便局のバンは歩道のところでアイドリングしている。「ついでと言ってはなんだけど」とステラは言う。「出したい手紙があるの。引き受けてもらえる?」送ろうと思っていたはがきと、雑誌〈ワーキング・ママ〉のお試し定期購読申込書があるのだ。
「喜んで」ジョーが言う。ステラを抱きあげてドライブウェイにおろし、バンの後部ドアを開ける。
メディアメールがいっぱい詰まった白いプラスチック製の容器のなかに、ステラはうずくまる。よくある、持ちあげやすいように両側に手を突っこむ穴があいているやつだ。いくつかの容器は小さめで、サイズ10の封筒が詰まっているものの、大きいのは電子レンジでも入りそうなほどだ。どの容器の側面にも、米国郵政公社〈USPS〉の青いワシの現代的なシルクスクリーンが施されていて、混沌のなかにも秩序があることを示している。
ジョーが前の運転席に陣取り、車はカタカタと通りを走りだす。「好きに雑誌を読んでいいよ」ジョーが言う。「ただしレシピカードだけは破り取らないでくれ。苦情を言われるから」ジョーは次の郵便受けで車を止めて、容器の中から郵便物の束を拾いあげると、丁寧に配達する。そしてまた走りだす。運転席の足元の床にはチャールズ・ブコウスキーの『ポスト・オフィス』が置かれている。
ステラは妄想にふける。いまは新婚旅行の真っ最中だ。クリストファーと一緒に温かい砂浜を歩いている。砂は細かくてさらさらで、肌にへばりついたり、お尻の割れ目に入りこんで取れなくなったりしない。現実世界では、新聞や排気ガスや試供品洗剤のキノコみたいなにおいから逃れようと、ステラは袖口のなかで呼吸をする。二人分の体臭は、くさい。
五時にはジョーの仕事が終わる。郵便局の通用口に車を止めた彼は、白い容器をベルトコンベヤーに移していく。それからステラの頬にスタンプを押す。赤いインクで“ハンドキャンセル”。「おっと」ジョーが言い、親指を舐めてくるくるとステラの肌を擦る。「すまん、にじんだ」
「いいのよ」ステラは言う。そんなふうに意識を向けられると、少し気まずい。
「これでよし」ジョーが言って擦るのをやめる。「じゃあ、おやすみ」
「おやすみなさい」ステラは答え、自然界と郵便局とをさえぎるゴム製のカーテンの向こうに吸いこまれていく。コンクリートをたたく足音のこだまが、郵便番号別に束を吐きだす仕分け機械の低いうなりに合の手を入れる。ベルトコンベヤーに載せられたステラは、勤勉で謎めいた郵便局の夜の世界を運ばれていく。窓もドアもない。まるでテーマパークの乗り物だ。外に腕や手を出さないでくださいと言われるような乗り物。〈イッツ・ア・スモール・ワールド〉の曲がエンドレスでかかっているふりをしていたら、そのうち音楽がこびりついて離れなくなってしまったので、どうにか頭のプログラムから振り払う。居心地のいい体勢を見つけられないうえ、容器のなかで横たわるには、体をメビウスの輪のようにねじるか、肘から先と膝から下を両端から突きだすほかない。夜はゆっくりと過ぎていき、あきらめて家に帰ろうかという思いが頭をよぎるものの、寂しすぎて一人になりたいとは思えない。時計をにらみ、秒を数える。夜勤の監督者が、ステラが眠れないのに気づいて言う。「なにかいい方法がないか見てみよう」キャビネットの鍵を開け、分厚く巻かれたエアークッション(バブル・ラップ)のロールを取りだすと、あるていどの長さを切り取って、ステラの白い容器に二重(ダブル)に敷いてくれる。「ダブル・バブルだ」彼が言う。
しつこいほど甘いピンクのチューインガムのにおいを思い出したステラは、吐き気がこみあげてくるのを感じる。目がひどく乾いているので、がんばらなくては閉じられない。眠ろうにも、疲れすぎていて無理だ。頭はいまもあれやこれやの事実を整理しようとしているけれど、きちんと分類できないし、ステラの人生にはすべてを正しい場所に落ちつかせるための郵便番号がない。
夜勤の監督者が言う。「いいことを思いついた」そしてステラの容器に別の容器をかぶせ、小屋のような、というより箱のようなものをこしらえる。不透明なプラスチックは光を通し、プライバシーと起きあがれる空間を作りだす。小屋はじゅうぶん快適だが、自分のベッドのなかとまではいかない。ステラはまどろんでは目覚め、またうつらうつらするのをくり返した。朝になると、ほかの市内郵便物と一緒に処理されはじめた。スキャナーにおでこをぶつけたものの、まだ住所が読みとれるから行ってよしと通される。移された先の箱には、特殊扱いが必要なほかの郵便物が入っている。差出人の住所がないスカンクの剥製、“あなたのことを考えています”というメッセージカードが添えられた、腐った――いまにもはち切れそうな――ポークソーセージ、ラベルに“アラスカ産鯨脂”と書かれた、脂で汚れたダンボール箱。みんな一緒くたになっているのかと思うと、ぞっとする。
ジョーがぶらぶらと通り過ぎていく。パーマネントプレスした半袖シャツは、青のズボンと揃いだ。制服姿の男がかっこよく見えるのは、いったいどういうわけだろう? 初めて会ったとき、クリストファーはスイスのミニマリズム・デザイナーが表現したようなライフセーバー姿だった。スピード社の赤い水着、赤い紐でさげた白いホイッスル、大きな白い字で“RESCUE”とプリントされた赤いプラスチック製のレスキュー用浮き輪。初めての心肺機能蘇生法を施されたあと、ステラはすっかり彼に参ってしまった。クリストファーは命を救ってくれた。あとになってぶち壊すだけのために。
小さな町で匿名でいるのは難しい。郵便配達ルート上では不可能といえる。クリストファーは近くに住んでいるから、ほかのいろんなものに加えて配達人もステラと同じだ。
「調子はどうだい?」ジョーがステラに尋ねる。彼は詩人だが、覚えておくに値することはなにも言わない。
訊かれてみると、おっぱいにしこりがあって重たい気がする。どうにか眠れた二十五分のあいだに、だれかが大粒の散弾を詰めこんでいったみたいだ。「あんまりよくないわ」と答える。
「そりゃ気の毒に」ジョーが白い容器を次々とバンに運んでいく。ステラのが最後だ。「こいつと一緒で平気?」ジョーが言い、スカンクをあごで示す。
ステラは肩をすくめる。「くさくないし」と言う。「でもありがとう」
ボーイフレンドの家はルートの最後近くにある。ステラは――いまの状態ではとくに――郵便受けに入り切らないので、ジョーが玄関まで運んでいってベルを鳴らす。何度か鳴らしてから、コンクリート打ちっ放しのポーチにステラをおろす。「さて、どうする?」ジョーが尋ねるものの、答えを期待していないのは明らかだ。案の定、ジョーはポケットからPS3605‐Rという用紙を取りだして、空欄を埋めはじめる。紙は黄色だ。郵便番号を書き写して、受け取りを必要としている荷物があると知らせる欄にチェックを入れる。
「ただ置いていくわけにはいかないの?」
「悪いね。きみを受け取ったことを証明する、だれかのサインが必要なんだ」
ステラは反論しない。規則や厳格さについてなら、知っている。母は公務員だった。父は職業軍人。「官僚仕事に民主主義はない」と父が言っていた。政府のために働いているなら、引退するまで耐えるしかないのだと。だからステラは引きさがる。エアークッションを二重に敷いた箱に戻ると、夜勤の人たちがこれ以上ないほど親切にしてくれる。バニラ・ウエハースとクラッカーを分けてくれ、従業員用のバスルームを使わせてくれる。なんだか特別な存在になった気分だ。郵便局に住む猫になったような。ステラは受け取りが来るのを待つ。さらに待つ。ジョーがデイヴィッド・ブリンのSF小説『ポストマン』を持ってきてくれるが、読書はそれほど好きではないので、バスルームを使うあいだ、とりあえずカウンターに載せておく。しばらくして思い出したときには、もうそこにはなくなっていた。親しくなったミシェルという名の仕分け係は、封筒を閉じるのに使う糊のせいで持病のぜんそくが悪化している。ステラは二度、彼女のロッカーまで吸入器を取りに走り、喘鳴が落ちついて楽に呼吸ができるようになるまで、そばについてめんどうを見た。こうしてステラは、自分より悪い状態にある友達を持つことの賢さを知る。
ミシェルは子ども二人の母親で、夫が眠る夜間に働いている。仕事を終えて家に帰ると、子どもたちに準備をさせて学校へ送りだす。四時間眠ったら、今度は下校した子どもの世話と料理だ。「たいした人生じゃないけど」ミシェルは言う。「収入口は二つよ」
一週間後、ジョーが不穏な知らせを持ってくる。「きみはもう、ここにはいられない」と言う。「家へ帰らなくちゃならない」
「彼は来るわ」ステラは言う。「あと二、三日だけ」腕時計を見おろすものの、理にかなわない行動だ。とはいえステラの人生に、理にかなっていることなど見あたらない。あってくれたらいいのに。
「すまないね」ジョーが言う。「規則なんだ」マニュアルをめくって、あるページを指差すものの、ステラは〈メール・リカバリー〉という見出し――ジョーの話では、かつては配達還付不能郵便取扱課〈デッド・レター・オフィス〉と呼ばれていた――を見たとたん、悲しくなって、肝心の文章を読むふりをしながら、うなずくしかできなくなる。翌朝、ジョーは彼女をバンに載せてルートを回り、ステラの家に着くと、玄関まで運んでいく。彼がポーチに置いていけるよう、ステラは自分でサインをしなくてはならない。
でも、そうしない。
ジョーは別の用紙を取りだして記入する。今度のは黄色がかった薄緑色で、PS941‐Xと記されている。「新しい書式だよ」二人で郵便局に戻り、受け取り拒否の郵便物があったことを記録する。ジョーが湯を沸かし、インスタントスープをこしらえてくれる。彼の声はやさしい。「必要なだけ、いるといい」と言う。「きみはおれの担当ルートにいる。ここではちょっとした意味のあることだ」
「ありがとう」ステラは答える。ふくらはぎが引きつるのでストレッチをしたいと言うと、保管室を自由に歩くことを許された。地球の中心みたいに、新鮮な空気も自然光も入ってきたことがない空間だ。
「足元に気をつけろ」ショッピングカートのとなりの、緑のカンバス地の簡易ベッドに寝そべった老人が言う。カートのなかは、ごつごつした黒いビニール袋とつぶれたソーダの缶でいっぱいだ。脂で汚れた〈ケンタッキーフライドチキン〉のバケツが、老人の陣地のまわりに砦を築いている。老人は腐ったミルクとすえた煙草のにおいがする。髪にはカエデの枯葉がからまっている。
「ここに住んでるの?」ステラは尋ねる。
老人が肩をすくめる。「ああ。そんなに悪くないぞ。おれは四〇年、ここで働いたんだ」穏やかな南部訛りで言う。「その前は兵役についていた」
頭のなかで計算してみると、どうやらベトナム戦争のことらしい。案の定、老人が黒いTシャツの上にはおったジャケットには、険しい目つきのイヌワシと、こう宣言する金色の文字が施されている――“POW(捕虜)を忘れるな”。
「名前は?」ステラは尋ねる。
「バートルビー」老人が言う。「メルヴィルの『代書人バートルビー』と同じさ。だがバートと呼んでくれてかまわない」
「『シンプソンズ』のバートと同じね」ステラは言う。メルヴィルにも代書人にも詳しくない。それから自己紹介をする。
「ステラ・コワルスキーのステラか」バートが言う。「おれは昔、ディザイア通りに住んでたんだ」
「ちがうわ」ステラは言う。「だれのステラでもない」これは事実ではない。だれにちなんで名づけられたか知らないだけだ。知っていれば、自分が郵便局で暮らすはめになった理由もわかるのかもしれない。ふと、奥の壁の向こうで影絵人形のように踊る、ぶかっこうな人影が目に留まる。「あの人たちもここに住んでるの?」ステラは尋ねる。
老人がシーッと人さし指を立てる。「そのことには触れないほうがいい。尋ねも話しもしないほうが」と言う。「さもないと、不法居住者の書式に記入させられるぞ」自分の冗談にくっくと笑うと、守るかのようにカートに片手を載せたまま、ふたたび横になる。「まず最初に」と言う。「自分のカートを手に入れることだ。まあ、ロッカーをくれるよう青シャツ連中のだれかを説得できりゃ話は別だが」
「ロッカーのほうがいいわ」ステラは言う。
「冗談だよ。すまんな、ちょっとした郵便局ジョークだ。今度、食料品店に行くついでに一つ取ってきてくれるよう、若いやつに頼んどいてやるよ」
ステラはぶらりと外に出て、休憩室を見つける。煙草を吸いたいが、自動販売機に残っているのは〈スニッカーズ〉と〈ウィンターミント・ガム〉だけだ。胃が暴れる。十五分ほど脚のあいだに頭をかがめていたら、ようやく立てるようになったので、休憩室をあとにして話し相手を探しに行く。バートがなぜここを好きなのかわかってきた気がする。
「差出用の郵便物の仕分けを手伝ってみるかい?」夜勤の監督者が尋ねる。「なにかやってるほうが、時間が経つのも早いだろう?」そう言って、ステラの体が収まるサイズの青い制服を探してくる。
一時間ほど働いたころ、ステラはボーイフレンドの名前が流れていくのを見つけて、その封筒をポケットに突っこむ。自分の犯罪行為に恥ずかしくなるが、その羞恥心は同じ行為をもう一度くり返さないほど強くはない。さらにもう一度。一週間も経たないうちに、ステラは深刻な郵便物連続窃盗犯になり果て、彼女の容器はクリストファーが投函した手紙でいっぱいになる。盗んだものは、光熱費の支払い、〈テキサコ〉の代金、ダイレクトマーケティング会社〈パブリッシャーズ・クリアリングハウス〉の懸賞への応募。電話代は払わせておく。
ステラは朝の四時から正午まで眠り、日によっては午後に軽い昼寝ができることもあるけれど、眠りはしばしば生々しい夢に阻害され、疲れ果てて目が覚める。たとえば今日は、ワタリガニになった夢を見た。酸素を吸おうと水面に浮かびあがったまさにそのとき、スイス・アーミーナイフの化け物――腕と脚がナイフになっている――に襲われるという内容だ。別の日に見た夢では、バートが郵便為替を届けてほしいとジョーに頼むものの、郵便番号を教えるのは規則に反すると断られていた。またあるときは、クリストファーの郵便受けに自分の名前をつけ足そうとするのだが、油性マジックが見つからないという夢も見た。最後の一つは白昼夢で、まぶたがぴくっとして目を覚ますと、ちょうどバートがなにごとか尋ねてきたところだった。「もう一度言ってくれる?」ステラは無意識で問い返したのだろう、バートが後じさりしながらつぶやいた。「邪魔して悪かったよ」
ステラは彼にすまないと思いながら、その一方で警戒心も抱く。二日前、バートはある男に腹を立て、男の体が吹っ飛ぶほど強く蹴りつけたのだ。その男は、近づかないようステラが警告を受けた影の人々の一人だった。彼らはとても悪い人たちで、クリスマスカードを開けて子ども宛てのお金を盗もうとしたところを捕まったという。罰として、郵便物が詰まった重たい袋を引きずりながら、闇のなかを歩かされることになったのだ。袋には重たい金属製の錠がかかっており、それが鎖に当たって音を立てる。影の人々は重みにうめき、うなる。とても不気味だ。バートが男を蹴り飛ばした夜は、ステラの友人で仕分け係のミシェルが、郵送用のダンボールの筒と、切手の自動販売機から取った二五セント硬貨を援軍に、どうにかけんかをやめさせて、バートに言った。また同じことが起きたら出ていってもらう、と。
「八六年に郵便配達人のパトリック・シェリルが起こした事件、覚えてる? もっとまじめに働かないとクビにするって上司に脅されて、むかっ腹立てて同僚一四人を殺しちゃったってやつ。あれ以来、キレるって意味でゴー・ポスタルというようになったらしいけど、本当にキレやすいのは復員軍人よ」ミシェルは言った。「彼のかんしゃくには気をつけたほうがいいわ」
そういうわけで、ステラは半分眠っていてバートを傷つけたことを申し訳なく思いつつも、彼を放っておく。バートはかつて結婚していたが、妻は子どもたちを連れて出ていったそうだ。バートがつらい人生を歩んできたのは知っているし、知っているおかげで物事を客観的にとらえられるようになった――すなわち、いまの状況がどんなにひどくても、もっと悪くなっていた可能性はある、ということ。心のどこかでは、流産してもとの服を着られるようになるのではと期待しているものの、妊娠第一期を終えてしまうと、そんなことはますますありえないように思えてくる。ステラは決断しないことで決断したのだ――これが初めてではないけれど。周囲からああしろこうしろと命じられる、軍人の家庭で育ったせいかもしれない。
夜勤の監督者がみんなに呼びかけて賭をまとめ、あっと言う間に一千ドル以上を集める。半分はステラのものになる金だ。「おれは二月三一日に賭けるよ」彼は言い、ウインクをする。
ジョーが雑誌を取っておいてくれる。定期購読者が引っ越したので配達できなくなった手芸誌だ。
ステラは保管室で梱包用の組み紐を見つけて、スカーフの編み方を覚える。この組み紐は機械のなかで繊維がからまるため、いまはもう使われていない。さらに鍋つかみ一式とバスマットも編みあげる。すると清掃係のリンダが毛糸を何巻きか持ってきてくれたので、今度は黄色と白の縦じまの、赤ん坊用のブランケットを編みはじめる。じきにだれもが余りものの毛糸を持ってくるようになり、ステラは取り憑かれたように編みつづけた。ドライブ編み。作り目。裏編み。編み針のなめらかな感触や、針同士がぶつかってカチカチいう音や、指に触れる編み目のやわらかなこぶが心地いい。編み物がもたらす実感のある喜びは、煙草に負けないくらい満足のいくものだった。
夜勤の監督者からメールオーダービジネスの始め方を教わったステラは、一人用の膝かけが売り物になることを思いつく。問題は送料だが、幸い膝かけは〈タイベック〉社のファーストクラス封筒に収まるので、普通郵便として発送できる。たまたま見かけただけの人なら、ステラにとって状況は上向いていると思ったかもしれない。ある晩、仕分け箱の迷路の真ん中に座っているステラを見つけたのはバートだった。ステラはクリストファー宛てのはがきを書いており、その枚数はかなりの数にのぼっていた。“楽しんでます”と〈ディズニーワールド〉の鉄道駅を写した絵はがきの裏にしたためる。“あなたがここにいればいいのに”。
「赤ちゃんが産まれたときのためよ」ステラは説明する。「これで、まだわたしが彼を想ってるってわかるでしょ? だってそのときになったら、彼に手紙を書く暇がなくなってるかもしれないもの」
バートがうなずく。「だれかに忘れられたからってだけで、そのだれかを忘れられるもんじゃない」そう言うと、一つの箱を見せてくれる。なかにはシアトルに住む息子に宛てた手紙がどっさり入っている。「もしかしたらあんたにも」バートが言う。「そういう手紙を書いたり投函したりしなくなるときが来るかもしれない。おれには来た」
ステラは反論しない。二人の人生が郵便室で交差したからといって、自分の道を捨てて彼の道をたどらなくてはならない、ということにはならない。
バートがジーンズのポケットから、丸めた本を取りだす。『ポストマン』だ。「勝手に借りて悪かったかな」と言う。バートの指は本の背をしっかりとつかんでいる。持っておきたがりこそすれ、返す気はなさそうだ。
「おもしろかった?」ステラは尋ねる。
バートの顔が輝く。「すばらしかった」と言う。「そのうちもういっぺん読んでみたいね」
「持っておけば?」ステラは言う。本をつかんだバートの手は、すでに半分ポケットへ戻りつつある。
「ありがとう」バートが言う。「恩に着るよ」
老人は衛生兵だった。「あんたにはビタミンがいるな」翌日、配達人のジョーが郵便物の山のなかから、格安のビタミン剤を紹介したカタログを探しだす。
日勤の女性の一人は、おさがりのマタニティ服を持ってきてくれる。夜勤の監督者が見つけてきたマットレスは、清潔な白い容器にぴったり収まるので、完ぺきなベビーベッドができあがる。
ある晩、ステラが郵便物を仕分けしていると、一通の封筒が機械にからまり、角の尖ったハート形に折りたたまれてしまう。手書きの住所を見ると、ポートランド通りのカーラ・Gからエメラルド通りのダニー・Lに宛てた手紙だ。どういう内容だったにせよ、もう失われてしまった。こういうことは、ときどき起こる。差出人がきちんと封をしておかないからだ。ステラは夜勤の監督者に報告して、“申し訳ありませんが取扱の過程で破損が生じました”という判を押してもらわなくてはならないが、だめになった手紙が気になったので、クリストファーの記念品群に加えることにする。手紙にはなにが書かれていたのだろう。自動車事故にかかった費用の写し? なんらかのサービスに対する苦情? もしかしたらダニーは猛烈な庭師で、アザレアを台なしにしたのかもしれない。あるいは愛か。カーラはもう一度、手紙を書くだろうか。それとも返事がないとあきらめる?
失われた手紙のことでステラの頭はいっぱいになる。次の夜、好奇心に負けた彼女は、いけそうな手紙を何通かそっと開いて、盗み読む。ある子からおばあちゃんへ、自転車のお礼を伝える短い手紙。マリーから建設業者へ送られたのは、入札の前に夢のファミリールームを説明するためのイラスト。ジェイムズからマーサ宛ては、大学院への推薦状を依頼する内容。最初こそステラは慎重に中身を戻し、糊づけしなおしていたが、週の終わりには、もう気にしなくなっている。取っておきたいと思うものがあれば、中身を抜いて封筒だけを監督者のところへ持っていくか、丸ごと隠してしまうかだ。こういうことは、足がつきにくい。
ある日バートに見つかって、ステラは告げ口されるのではないかと案じるが、彼はただ、赤ん坊の名付け親に立候補したいとだけ言った。「うれしいわ」ステラは言う。「すごくうれしい」もうバートを恐れてはいない。
老人がステラを抱きしめる。初めて会ったときよりも、バートの服は汚れてぼろぼろになっているが、においはあのときほど気にならない。彼に手袋を編んであげようとステラは決心する。
赤ん坊の名は、男の子ならクリストファー、女の子ならクリスティーンがいい。通信制の学校やメールオーダーの学位について、どこかで読んだことがある。ここでの暮らしに不満はない。子どもが育つには悪くない環境だ。妊娠最終期に入ると足首がむくんでいつも疲れを感じるようになる。「働く時間を少し短くしたらどうだ?」夜勤の監督者が声をかける。「もっと休みなさい」
妊婦というのは休みなしの仕事みたいなもので、エネルギーを根こそぎ奪われる。ステラは勤務時間を二時間に短縮し、『レイト・ナイト・ウィズ・デイヴィッド・レターマン』の最後のジョークに間に合う時間にベッドに入るようにする。ある晩、ミシェルがお手製のシナモンロールを焼いて持ってくると、バートがステラのぶんを卑怯な夜間襲撃から守ってみせると約束する。ミシェルのぜんそくは、ステラが注文したタイムとユーカリとセージとレモンを混ぜたアロマオイルのおかげでよくなってきた。バートにもラベンダーのオイルを注文したが、別のにおいをごまかすためにときどき使ってみたらとは、まだ言いだせずにいる。
バートがふとんをかけてくれて、父親のような手つきでステラの髪を撫でおろす。「いい夢を」ステラは眠りに落ちる。一般に、家族は選べないと言われているし、実際そうなのかもしれない。だけどときには運に恵まれて、家族のほうから選んでもらえることもあるのだ。
(訳:石原未奈子)
作品について
記念すべきレスリー・ホワット単独作品の初翻訳作、いかがだったでしょうか(注1)。訳者が一読で恋してしまった、すっとぼけたような、ちょっぴり意地悪で皮肉っぽいような独特の語り口と、淡々としていながらも読者を前へ運ぶ力に満ちたストーリー展開、そして訪れる意外な温もりのある結末を楽しんでいただけたなら、なによりです。
タイトルの「ポスト・ホック」は after this、つまり「このあとの、このあとに」という意味ですが、郵便のポストにもかけてあるのは言うまでもありません。
さて、本作が収められているのは、作家のデリア・シャーマンとシオドラ・ゴスが編者を務めたアンソロジーInterfictions(2007年)で、サブタイトルにはan anthology of interstitial writingとあります。interstitial は「隙間の、介在性の」という意味ですから、interstitial writing(直訳すると「間の作品」)のアンソロジーInterfictionsは、まさに「(カテゴリーとカテゴリーの)間(inter-)の小説(fiction)」、つまり「文学ともジャンル小説とも言い切れない、どのカテゴリーにもきっちり収まらない小説」、さらには「なんとなく行き場のない迷子の小説」といえるかもしれません。
ところで、このアンソロジーInterfictionsを企画したのはThe Interstitial Arts Foundation(IAF)というNPO団体で、彼らは小説だけでなくさまざまな芸術活動において、ジャンルやカテゴリーという既存の枠に収まりきらない作家や作品を支持すると同時に、そうした作家たちに場を提供することを目標としています。いまやジャンルは(極論すれば)マーケティングを楽にするために存在しているようなものでしかなく、作家/作品と受け手とをよりよく結ぶためのものではないと考えているからです。彼らの主張はテリ・ウィンドリング「境界なき芸術家たち」(小川隆・訳。SFマガジン2003年6月号)として紹介されているので、よければ参考になさってください。小川隆氏がSFマガジンの〈スプロール・フィクション〉特集号で「間隙芸術」としてずっと紹介してきたものです。
ちなみにIAFの代表は、作家にしてミュージシャンでもあるエレン・カシュナー(訳書『吟遊詩人トーマス』、『剣の輪舞』、『剣の名誉』いずれも井辻朱美・訳。早川文庫)で、メンバーには短篇小説家として日本でも人気、知名度ともに高いケリー・リンクの名前も含まれています。
本作以外に収められている作品も、興味深いものばかりです。恋人を拉致された女性がひとり待ちつづける不安と苛立ちを、幻想的なイメージとからめて描いた、ホリー・フィリップスの"Queen of the Butterfly Kingdom"(「蝶の国の女王」黒沢由美・訳。SFマガジン2009年6月号所収)、『眠れる森の美女』を下敷きに、伝説的なパンクロック・バンド、セックス・ピストルズのベーシストだったシド・ヴィシャスと悪名高いその恋人、ナンシー・スパンゲンとの物語を描いた、ヴェロニカ・シュノーエスの"Rats"、夜ごと訪れるワタリガラスの夢をきっかけに、双子の兄が死産だったことを思い出していく、ファンタジックなK・テンペスト・ブラッドフォードの"Black Feather"、インド人女性のある一日を独特の視点で描いた、ヴァンダナ・シンの"Hunger"など。これらの作品も、機会と要望があれば(なおかつ権利がクリアになれば)、訳してみたいところです。
以上、本作が収められているアンソロジーとNPO団体IAFについてざっとご説明したところで、今回ご紹介した「ポスト・ホック」の最後に添えられた作者からのメッセージをご紹介したいと思います(順序が逆のように思われるかもしれませんが、アンソロジーの趣旨を知らずに読んでしまったら、なんだかよくわからない文章と受け取られかねないので。ご容赦ください)。
わたしが「はざまの存在」になったのは、三歳で妹が生まれて、「妹」から「三人姉妹の真ん中の子」になったときのことだ。ご存じない方のために申しあげておくと、真ん中の子というのは、はざまの存在特有の、人との関わり方についての本を、つまり悲喜こもごもの回顧録を著しているものだ。あるページでは長女と結託して無敵のコンビを組み、容赦なく末の妹をいじめる。ページをめくると今度は長女が末の妹の側について、同じくらい恐ろしいペアとなって真ん中の子をいじめる。つまり真ん中の子は、はざまの少女なのだ。片足は謎めいた未来と姉の新しいハイヒールに突っこんで、もう片足は、大人になるというのは母親のまねをすることだと思っている末の妹と、おめかしをして遊ぶ。引かれていたはずの線は、もうぼやけてよくわからない。言い忘れたかもしれないが、わたしは乱視でもある。
多くの読者と同じで、わたしも郵便局のはざま性についてはユードラ・ウェルティ(注2)から教わった。多くの作家にとってと同じで、わたしにとっても郵便局は芸術的な努力と読者とをつなぐパイプだ。この非現実的な場所では、私信が大量の郵便物となって積み重なり、公務員が通常求められる以上の仕事をこなす。世界をつないでおくために。郵便配達人のジョーに感謝を。
レスリー・ホワット
どうやら著者のホワットは、作品だけでなく本人もinterstitialだったようです。
Interfictionsに話を戻しますと、第2巻Interfictionsが2009年に刊行されて、アマゾン.com では09年度のSF&ファンタジー部門のトップ10に入りました。こちらの編者はデリア・シャーマンとクリストファー・バルザックで、作家陣にはInterfictionsで編者を務めたシオドラ・ゴスをはじめ、アラン・デニーロ、アミリア・ビーマーなどが名前を連ねています(バルザック、ゴス、ビーマーについては、当サイトで作品やエッセイをご紹介できる予定です)。
さらに詳しく知りたい方は、下記リンク先をご覧ください。
https://interstitialarts.tumblr.com/
余談になりますが、この文章を書くにあたって、ない知恵をうんうんと絞っているときに、「間(はざま)の小説」ってどこかで聞いたような、いや、聞いたというより、ものすごくよく知っているような……としばし考えて思い出したのが、当サイトの自己紹介文でした。自分でもきれいに忘れていたのですが、あそこにはっきり「ジャンルを特定できないような、はざまの作品が好きです」と書いていたんですよね。どうりでこの「間(はざま)の作品」に一読で恋してしまったわけだ、といまさら納得したしだいです。
さて、本作でレスリー・ホワットに興味を抱いてくださった方々、あいにく今回の解説では著者についてほとんど触れられませんでしたが、2008年に発表された彼女の短篇集Crazy Love からも一作、近々こちらにアップできる予定ですので、そのときに詳しくご紹介したいと思っています。どうぞお楽しみに。
Interfictions : An Anthology of Interstitial Writing
-
Heinz Insu Fenkl, Introduction
-
Christopher Barzak, "What We Know About the Lost Families of - House"
-
Leslie What, "Post hoc"(本作品)
-
Anna Tambour, "The Shoe in SHOES' Window"
-
Joy Marchand, "Pallas at Noon"
-
Jon Singer, "Willow Pattern"
-
K. Tempest Bradford, "Black Feather"
-
Csilla Kleinheincz, "A Drop of Raspberry" (translated from Hungarian)
-
Michael J. DeLuca, "The Utter Proximity of God"
-
Karen Jordan Allen, "Alternate Anxieties"
-
Rachel Pollack, "Burning Beard"
-
Veronica Schanoes, "Rats"
-
Mikal Trimm, "Climbing Redemption Mountain"
-
Colin Greenland, "Timothy"
-
Vandana Singh, "Hunger"
-
Matthew Cheney, "A Map of the Everywhere"
-
Léa Silhol, "Emblemata" (translated from French)
-
Adrián Ferrero, "When It Rains, You'd Better Get Out of Ulga" (translated from Spanish)
-
Holly Phillips, "Queen of the Butterfly Kingdom"(「蝶の国の女王」黒沢由美・訳。SFマガジン2009年6月号所収)
-
Catherynne M.Valente, "A Dirge for Prester John"
-
Delia Sherman and Theodora Goss, Afterword; The Spaces Between
訳注1: 書籍、CD、DVDなどが通常より安く送付できる郵送方法。日本のゆうメールのようなもの
訳注2: 104.8×241.3mm
訳注3: 機械ではなく手で消印を押したという意味
訳注4: 一九二八年より製造が始まった風船ガムの商標名。それまでのガムより噛みごたえがあって大きくふくらませるところから名づけられた
訳注5: 『欲望という名の電車』の主人公ブランチの妹で、粗野な男の妻
注1: アイリーン・ガンとの共作「ニルヴァーナ・ハイ」は、早川海外SFノベルズ刊の『遺す言葉、その他の短篇』収録
注2: ユードラ・ウェルティ……メールソフト「ユードラ」の名の元になったことでも知られるアメリカ南部の女性作家。デビュー短篇集『緑のカーテン』には「わたしはどうして郵便局で暮らすようになったか」という作品が収められている。アメリカ南部の小さな町で郵便局長をしている偏屈な女性主人公が、たび重なる家族の無理解に怒り心頭、ついに家を出て勤め先の郵便局で暮らしはじめる、という話。