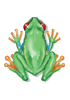モリーと赤い帽子
ベンジャミン・ローゼンバウム
モリーは赤い帽子が大のお気に入りだった。ふっくらとして丸みを帯び、色鮮やかだった。とってもすてきで、飾りなどなかった。その帽子は見かけと違っていろんなことを知っていた。テントウ虫になったり、トマトになったり、口紅のように真っ赤なファイアー・ドラゴンになることもできた。なのに、じっとしてただの帽子でいてくれたので、モリーはますます好きになった。
ところがある日、モリーのママが小さな青い帽子を買ってきた。わざとらしい、見かけ倒しのもので、秘密など何一つもっていなかった。モリーは礼儀正しく笑顔を浮かべて、ありがとうといった。ママにも青い帽子にも気を悪くしてもらいたくなかったのだ。モリーは帽子掛けに赤い帽子をかけると、その日は青い帽子をかぶった。でも、出かける前に赤い帽子に口を押しあててささやいた。「大好きよ、ずっとあなたを離さないわ」
庭に弟のビリーが出てくると、ビリーも同じような新しい青い帽子を買ってもらったのがわかった。モリーは礼儀知らずではなかったので、それをどう思ったかは何もいわなかった。
でも、モリーのママが鍵をジャラジャラいわせて家から飛び出してくると、ビリーがわっと泣きだした。「ママといくー!」とビリーはいった。
「弟に意地悪したの、お姉ちゃん」モリーのママはきつい口調で叱りながら、車のドアを開けた。
モリーは公園のブランコの鎖がからまってドサッと地面に投げ出され、土が鼻に入って、息ができなくなったときと同じような気分になった。少女は両手で青い帽子をつかむと、悪口が聞こえないように耳の上に引き下ろした。
ビリーに意地悪をしたことなんて、パパが出ていってからは一度だってないのに。
「もう時間がないの」とママはビリーにいって、頭にキスすると、コートをつかんでいた小さな手をふりほどいた。「モリーが送ってくれるわ。その帽子、すてきじゃない?」ママは車のドアを閉めて、モリーにはいってきますもいわずに、ブルーンと走り去った。
幼稚園でモリーは青い帽子をお荷物棚にしまい、何もかぶらずに席に着いた。テリヴェラー先生は驚いて眉をあげてみせた。テリヴェラー先生は魔女モルガン・ル・フェイの時代から脈々とつづく力ある幼稚園の先生の系譜のなかで、いちばん若い先生だった。先生は馬鹿ではなかった。モリーは二度ウィンクして、帽子はまた帰ってくるわと伝えた。
帽子がないとモリーはかなり力を失い、ほかの子供たちにもそれがわかった。悪童デニースはモリーの描いたタコの上に紫のクレヨンを塗りたくったけれど、モリーはされるがままだった。弱虫クリストフと最低ウンベルトは緑の積木をぜんぶもっていってしまい、モリーには分けてくれなかったし、お転婆エミリーといんちきスーはお昼のとき、モリーが並ぶ列の前に割りこんできた。帽子さえかぶっていれば、誰もそんなことをしようとしなかったのに。
だから、モリーが幼いビリーの手を引いて家まで飛んで帰ったのも無理はない。ビリーは二度も転んで泣きだしたけれど。モリーはあやまって、〈線路はつづくよ〉を歌ってあげ、少しゆっくり弟を引っ張るようにした。
でも、帽子掛けのところにいってみると、赤い帽子は消えていた。
「あたしの帽子はどこ?」とモリーはママに訊いた。
「古い帽子のこと? あなたには小さすぎるわ。新しい帽子が気に入らないの?」
「どこにあるの?」とモリーはいった。
ママはこたえた。「捨てちゃったわ」
モリーはかんかんになった。
許せない。
言い訳なんてきかない。
あり得ない。
我慢できない。
ぜんぜんよくない!
モリーは青い帽子を地面に投げつけると、蹴飛ばした。ママはモリーを部屋に閉じこめ、出してくれなかった。
ああ、赤い帽子さん!
ああ、赤い帽子さん!
ああ、赤い帽子さん!
夕食のとき、モリーはまだ腹を立てていたけれど、ママがいった。「ごめんね、あなたの赤い帽子を捨てちゃって」モリーは大人があやまるのが苦手なのを知っていたので、こたえた。「いいわ」
そこでモリーはその晩、めちゃくちゃに早く歯磨きをすませ、自分でパジャマに着替えた。ママがまだビリーの歯磨きをさせているあいだに、モリーはベッドの特別な場所で飛び跳ね、
窓から飛び出し、
松の枝に乗って
はずみをつけ
屋根を飛び越えて電柱の上におり、
電線をつたって
森に
梟の女王に会いにいった。
梟の女王は金属のカップでお茶を飲んでいた。頭のあちこちから白い髪が飛び出ていた。上着を十二枚も着こみ、手袋の穴からは曲がった赤い指が突き出ていた。古いペンキ缶で焚き火をし、まわりを十二羽の梟が輪になって取り巻いていた。雪梟、大角梟、泥炭梟、ホーホー梟、キーキー梟、夜空の梟、コリアンダー梟、チクタク梟、見ようとすると見えない梟、喧嘩梟、友達梟、梟じゃない梟たちだ。
モリーは寒かったけれど、梟の女王の火に断りもなくあたってはいけないことぐらい知っていた。彼女は雪のなかに足を突っこんだまま、いった。「赤い帽子を探しているの」
「ふーん、そうなの」といって、梟の女王はお茶を飲んだ。「こっちにきて、火におあたり」
「いいの?」とモリーは訊いた。
「ああ、いいとも」と梟の女王はいった。
「帰りたくなったら帰ってもいい?」とモリーは訊いた。
「ああ、もちろんさ」と梟の女王。
「あたしには何も悪いことは起こらない?」とモリー。
「どうしてもというのなら」と梟の女王。
そこでモリーはチクタク梟の前を駆け抜け、友達梟の膝に坐ると、友達梟は彼女を守るように翼を広げて巻きつけてくれた。
「いい場所を選んだね」がっかりした顔で梟の女王はいった。チクタク梟は爪を引っこめた。
「ありがとう」とモリーはいった。「それで、あたしの赤い帽子は?」
梟の女王はお茶を飲みほすと、カップをのぞきこんだ。火がはぜ、夜の寒気がモリーの足の指を刺し、友達梟の羽根が頬をくすぐった。
「捨てられたのさ」ようやく梟の女王がいった。
「取りもどしたいの」とモリーはいった。「どこにあるの?」
「もちろん、捨てられたゴミの国さ」と梟の女王はいった。「でも、おまえにはいく勇気はないね」
「あるわ」とモリーはいった。
「たとえあったとしたって、おまえを連れてってやる勇気のあるものなんかいないさ」と梟の女王。
モリーは友達梟に訊いた。「連れてってくれる?」でも、梟は悲しげに瞬きすると、くるっと首を反対までまわし、うしろを見てしまったので、モリーには羽毛しか見えなかった。
モリーはコリアンダー梟に目を向けたけれど、反応は同じだった。キーキー梟も、ホーホー梟も、泥炭梟も、大角梟も同じ。雪梟も、夜空梟も、勇敢な喧嘩梟も同じだった。モリーはチクタク梟には目を向けなかった。梟じゃない梟も翼でない翼で目を隠した。
そこでモリーは友達梟の膝から立ちあがり、雪のなかに駆けだした。火には背を向け、目をぎゅっと閉じて両手で覆い、呼びかけた。「連れてってくれる、見ようとすると見えない梟さん?」
見ようとすると見えない梟の小さな爪にパジャマの肩がつかまれたのをモリーは知った。小さな翼が羽ばたく音がして、彼女は空に舞いあがった。
「モリー!」と梟の女王が心配そうな声で呼びかけた。「赤い帽子以外のものを持ち帰っちゃだめだよ!」
モリーと見ようとすると見えない梟は長いこと夜空を飛んだ。月の嘆きも聞いたし、星が軌道をとおるときの摩擦音も聞いた。マルハナバチの夢がブーンと音をたてているそばもとおりすぎ、パンだねの国に雨を降らせようとしているミルクの雲のなかも飛んでいった。モリーはぎゅっと目を閉じていた。
とうとうゴミの臭いがした。たくさんのゴミだ。失くしたり、捨てられたものがこの世にもどりたくて泣いたり嘆いたりしている声が聞こえてきた。
モリーの足が地面についた。目を開けると、そこにあったのは――
片方ずつ不揃いになった靴下の山
案山子と鐘楼
新聞がちょっとと古聞がいっぱい
日時計、ジェニー紡績機、レーニンの胸像
去年流行(はや)った人形とチューインガム
間違いなく人間こそ世界の中心だという信念
オクラホマのファーストフード店のがっかりした店主たちのテニスシューズとバスケットボール
進歩への信頼
十億ページの宿題
……それに、まだまだたくさんのもの。
モリーはがらくたの山の上を飛び越えながら呼びかけた。「赤い帽子さん! 赤い帽子さん! モリーよ! あたしはここにいるわ!」
「モリー!」と叫ぶ声がし、モリーは昔のわが家の屋根に降りたった。それは巨大で、ぼやけ、切妻や斜面がたくさんあった。モリーのパパに似た人がいたけれど、青ざめ、体の真ん中にセロファン・テープで張り合わせた破れ目があった。
「モリー!」と男の人はいった。「連れて帰っておくれ!」
「あなたはパパじゃないわ!」とモリーはいった。「パパはサンフランシスコにいるんだから」彼女は屋根の上を煙突めざして走った。
「わたしはおまえのパパに対するママの愛情だ!」男の人は追いかけながらいった。「連れて帰ってくれ!」
「だめ、だめ、だめ、だめ、だめ! 捨ててなんかないもん、嘘つき! 赤い帽子のほかは何も持ち帰らないのよ!」といって、モリーは煙突から飛び降りた。
リビングにつくと、彼女は暖炉から這い出て、お人形やワイングラスやママの学位証書の前を駆け抜け、階段を駆けあがった。「赤い帽子さん! 赤い帽子さん!」
彼女はベビー・ルームのドアを開けた。昔のビリーのベビーベッドがあって、昔のビリーが寝ていた――初めて病院からやってきたときと同じ、新しくて、しわくちゃで、よだれだらけで、真っ赤な顔をしている。そのわきに、ベッドの手すりにつかまっているのは、怒りの炎をめらめらと燃やしているちっちゃな緑のモリーだ。
「ねえ、モリー!」と怒りに燃える緑のちっちゃなモリーがいった。「あたしを連れて帰って!」
「だめよ!」と大きいモリーはいって、帽子掛けに駆け寄った。モリーの赤い帽子がかかっていた。モリーはそれをひったくると、頭にかぶった。そして窓から飛び出すと、通りの向かいの家の屋根に飛び乗った。昔のおうちに背を向けて、目を閉じ、手をかざして、彼女は呼びかけた。「おうちまで連れてってくれる、見ようとすると見えない梟さん?」
見ようとすると見えない梟の小さな爪に、パジャマの肩をつかまれるのがわかった。小さな翼が羽ばたく音がして、モリーは宙に舞いあがった。
でもそのとき、怒りに燃える緑のちっちゃなモリーが窓から飛び出し、向かいの屋根を蹴って、燃える緑の手でモリーの踵につかまった!
目をあけるわけにはいかなかった。踵が焼けるようで、むずむずした。足をバタバタさせてみたけれど、緑のちっちゃなモリーはしっかりしがみついていた。こうして三人は夜空という沼を飛んでゆき、いまではすっかり焼けてあたりにクッキーの匂いをふりまいているパン種の国の上を過ぎ、彗星の笑い声や明日の夜明けをどんな色に染め分けようかとつぶやく地の精の声を聞いた。
ついにモリーの足が、寝室の窓の前にある松の木の枝にふれた。見ようとすると見えない梟は彼女の肩を放し、燃える緑のモリーも足をつかんでいた手を離した。
「ありがとう、見ようとすると見えない梟さん」とモリーはいった。「梟の女王様にもありがとうと伝えてね」目を開けると怒った緑のちっちゃなモリーは木を這いおりているところだった。大きなモリーは赤い帽子を耳までしっかり引き下ろして、寝室の窓からベッドに飛びこんだ。
すっかり冷えきっていたので、彼女はカバーの下に素足をすべりこませた。
ちょうどそこへ、ママがビリーと歯ブラシを抱いてやってきた。ママはハッと足を止めて、モリーの赤い帽子を見つめた。
「見つけたの」とモリーはいった。
「変ねえ」とモリーのママはいった。「捨てたはずなのに。あなたにはもうちっちゃいでしょ」
「ママ、お願い!」とモリーはいった。
「明日、話しましょう」とママはいった。ビリーをもう一つのベッドに横たえて、おでこにキスしてやった。そうしてから、ママは電気を消して、出ていった。
モリーは赤い帽子の下に手を入れて、ママがキスしてくれなかった場所をさすった。
またビリーに目を向けると、めらめらと燃える緑のモリーがいっしょにベッドに入っていた。
「覚えていないのね」と怒った緑のモリーがいった。「だからそんなことをするんだわ」
「何のこと?」大きなモリーは体を起こした。
「ママもパパもあたしたちだけのものだったのよ」と怒った緑のモリーがいった。「だっこも、キスも。お話も、歌も。くすぐりっこも笑い声もみーんな。そこにこいつがやってきたんだ」
「モリーに――モリーだ!」といってビリーは笑った。
「とたんにママがだっこするのはこいつだけになった。いつだってだっこよ。こいつったら、吸血鬼みたいにママの力を吸い取っていった。パパも追い出しちゃった」怒った緑のモリーはそういうと、ビリーの口と鼻を手で塞いで、揺さぶった。ビリーは息が詰まって、暴れた。
モリーはベッドから飛び起きて、怒った緑のモリーをビリーからひきはがした。ビリーは息をはずませて、泣きだした。
「うるさい!」とモリーはいった。怒った緑のモリーをつかむ両手がひりひりと痛んだ。「黙らないと、ぐちゃぐちゃにたたきのめしちゃうから」
「わかったよ」怒った緑のちっちゃなモリーは、大きなモリーの手からすり抜けた。「それなら鴉さんたちを味方につけてくるもん」そういって、彼女は窓から飛び出した。
ドアがバタンと開いて、モリーのママが入ってきた。「いま何ていったの、モリー!」とママは怒鳴った。ビリーが泣きやまないので、ママは抱きあげた。
「何のこと?」モリーは部屋の真ん中に立ちつくした。
「あなたがちっちゃな弟に何ていったか、はっきり聞こえたわ。本当にぎょっとしたわ」
「違うわ」とモリーはいった。「そんなこと――」
「この上、嘘までつこうっていうの?」とママは訊いた。
モリーは口をつぐんだ。
モリーのママは窓を閉めて、ロックした。「このことは明日また話しますからね」とママはいった。「いい子ね、ビリー、もうだいじょうぶ、ママのベッドで寝ましょう」
「いやだ!」とビリーはぐずった。「モリーと――いっちょに――寝る」
モリーのママは眉をしかめて考えこんだ。そしてビリーをベッドにもどした。「ちっちゃな弟がどれだけあなたを信頼しているかわかるわね?」とママはいった。「これからはそれにふさわしい行動をしてちょうだい」
そういって、出ていった。
モリーはビリーと自分を守ってくれるように赤い帽子を窓際に置き、象のババールとセレストとルンペルシュティルツヒェンのお人形にドアを守らせた。これですべて手は打った。モリーはベッドに入って、目を閉じた。ビリーはもう眠っていた。
翌朝の朝食の席では、ママは疲れた顔をして、赤い帽子の話など忘れていたので、モリーは帽子をかぶった。
モリーはビリーを連れてゆっくり慎重に幼稚園に向かい、〈ワーキングマン・ブルース〉を歌ってあげ、ビリーが郵便受けのつららを折ってしゃぶるのを許してあげた。うきうきと浮かれていたので、怒った緑のモリーが駆け寄って赤い帽子をひったくるまで、まったく気がつかなかった。
「返せ!」と叫んで、モリーは追いかけた。
怒った緑のちっちゃなモリーは笑い声をあげて逃げたけれど、モリーのほうが足が長いので、すぐに追いついた。彼女は怒った緑のちっちゃなモリーを押し倒して馬乗りになり、赤い帽子を取り返した。
でも、燃える緑のちっちゃなモリーが笑いつづけるので、大きなモリーは嫌な予感がした。
通りを振り返ると、鴉の大群がビリーをつかんで宙に飛びあがっていた。
「ビリー!」モリーは叫んで、飛びあがった。煙突の高さまで飛びあがったけれど、鴉には届かなかった。そこで近くの煙突に跳びあがり、さらに鴉の群めがけて飛びかかった。襲いかかりながら一羽の鴉を殴り、ビリーの腕を放させたけれど、ほかの鴉たちにすぐにまたつかまれてしまった。モリーは雪の積もった屋根に落ち、ちょっとした雪崩にすべり落とされた。雪から這い出ると、鴉たちはもっと高くにいってしまった。ビリーが蟻のように見えた。
モリーは赤い帽子を脱いで、両手でもった。「赤い帽子さん、赤い帽子さん、帽子でいたいのはわかってるけど、何かできるのなら、いますぐそうして!」そういって、高く帽子を投げあげた。
赤い帽子は身震いしてから
止まったかと思うと
ひと揺すりして
体をうねらせ
広がって
みるまに――
真っ赤なきれいなシルクでできた真っ赤な口紅色のドラゴンになった。
それは鴉の群に向かって飛び、尾でなぎ払った。バン! ガン! ヒュー! バシッ! 鴉は逃げ出した。帽子のドラゴンは尾でビリーをつかまえると、そっと降りてきた。でも、ドラゴンが降りだすと、鴉が追いかけてきた。ドラゴンの頭をかいくぐり、嘴でちぎった。ビリッ! ベリッ! ザクッ! ズタッ! 帽子のドラゴンはやっとのことでビリーを雪だまりにおろすと、尾で反撃した。
モリーは雪だまりに走ったけれど、燃える緑のちっちゃなモリーも走った。先についたのは、燃える緑のちっちゃなモリーだった。ビリーの手をつかむと、道まで引っぱってゆき、左右も見ずに彼女はビリーを突き飛ばした――
でも、モリーがひきもどした。
そして燃える緑のちっちゃなモリーをつかんで、高くもちあげた。
「あんたは勝てっこないのよ、モリー!」と燃える緑のちっちゃなモリーはいった。「あたしを連れもどしちゃったんだから! あたしはあんたのものなの! どこにもいかないんだから!」
「そのとおりよ」といってモリーは燃える緑のちっちゃなモリーの額に口をあて、大きく、大きく深呼吸した。まるで、月ほどの大きさもあるお誕生ケーキのローソクを吹き消そうというように。燃える緑のちっちゃなモリーが「助けて!」というまもなく、モリーは息を吸い、彼女を呑みこんだ。
そしてビリーを雪だまりから出してやり、顔についた雪をはらって、手をしっかりつかんだまま、赤い帽子に駆け寄った。
鴉たちは消えていて、赤い帽子は跡形もなく、真っ赤な口紅色のシルクの切れ端が少し残っているだけだった。
モリーはしゃがみこんで泣きだし、ビリーも隣にしゃがんで泣きだした。
テリヴェラー先生はモリーが姿を見せないので、何かあったことに気づき、探しにきてくれた。モリーと並んで歩道に坐り、バッグからティッシュと携帯電話を探し出すと、すぐにモリーのママの仕事先に電話した。先生はやさしく、モリーのママにもわかるようにいっぱい説明してくれた。
モリーのママは会社を早退して、モリーとビリーを家に連れ帰った。ビリーには床で積み木遊びをさせておくと、ソファでモリーを膝にだきあげ、長いこと泣かせてくれた。
とうとうモリーが赤い絹の切れ端をにぎったまま寝入ってしまうと、ママはモリーの髪に唇を押しあてて、ささやいた。「大好きよ、ずっとあなたを離さないわ」
それ以来、モリーもときには幼稚園に青い帽子をかぶっていくことがあった。ビリーをからかい、喧嘩になることもあった。気分が悪くなることもあったりして、そんなときはもう一人のモリーが胸のあたりを這いまわっているのがわかった。ひどく腹がたったときには、目からもう一人のモリーがのぞいているのが見えることもあった。
でも、毎晩寝るときには、ママがおやすみのキスをしてくれた。モリーのママは二度と忘れないでくれた。そして一晩中、モリーはおでこのあたりに温かく柔らかなキスの感触が、自分を守ってくれているのを感じていた。
(訳:小川隆)
作品について
ローゼンバウムを初めてきちんと読んだのは、たぶんウェブジンのストレンジ・ホライズンズ[*1]に載った〈ほかの都市の物語〉連作だったように思う。当時、まだサイフィクション[*2]が健在で、ストレンジ・ホライズンズはがんばっているもののまだトップ・クラスの小説誌ではないような気がしていた。ただ、ときおりおや、と思うような傑作もまじっていて、〈ほかの都市〉のシリーズもその一つだった。ショートショートというか、フラッシュ・フィクションに近いこの連作短篇は、明らかにカルヴィーノやボルヘスの影響下にあるものの、ブラッドベリやその他SFやファンタシイの影響もかいま見え、楽しく読むことができた。ローゼンバウムという新人作家にも興味を覚え、ほかの作品を探すと、SF雑誌F&SFに「蟻の王」という、スターリングのユーモア近未来風刺作品を思わせる楽しい作品が見つかった。たしか、掲載時にざっと目をとおしたつもりだったが、そのときは、サイバーパンクのパスティーシュにしか見えていなかった。トレンドばかりを意識して、きちんと作品と向かい合っていないと、そうした誤読も起きる。なんのことはない、当時の若手作家予備軍の多くがそうであったように、作者自身がITバブルの中、主人公と同じソフト開発に携わっていて、そのときの体験をもとに書いた風刺小説だったのだ。再読してみて、初めて楽しめた。そして思ったのは、ユーモア小説から文学的メタフィクションまで書いてしまえる、その作風の幅広さだ。当時、ローゼンバウムは文学もジャンルの一つと考え、さまざまなジャンルを書き分け、それぞれで活躍したいと思っていたようだ。ジャンルをまたがる小説のタイプについての論議がまだ広がっていない時期だったからなのだろうか。このころ活発におこなわれていた新しい小説論争にはローゼンバウムもかなり積極的に参加していたのだが。
その後、「抱擁もて新しきもの迎ふる神」のようなファンタシイ色の強い作品から、「あなたの空の彼方の家」のような宇宙物理学のM理論[*3]を元にした本格SFまで、ますます幅広い作風で、いずれも水準以上のできの作品をコンスタントに発表し、多くがSFやファンタシイの賞の候補にも推され、若手作家の代表格の一人になった。ぼくもことあるごとに紹介につとめてきたつもりだ。2008年に出た初の本格的短篇集は(じつはそれまでに小出版社のチャップブックと呼ばれる形式の小型本短篇集を二冊発表しているのだが)世界幻想文学賞の候補になるなど、ジャンルの中で評価が高かったのは当然としても、ニュージャージー州にの独立系放送局WFMUが年間ベストブックの一冊に選ぶなど、幅広い作風に見合った幅広い読者がいることを印象づける作品集だった。
ベンジャミン・ローゼンバウムは1969年ニューヨークに生まれたものの、子供時代はヴァージニア州のアーリントンで過ごした。作家になりたいと思いながらも生活のためにプログラマーとしてコンピュータソフトの会社に勤め、ゲームの制作などにたずさわる。このときの経験は「蟻の王」の元になっている。世界中を旅し、長期にわたってスイスのバーゼルで暮らし、夫人ともそこで知り合って結婚している。2000年に長女が誕生するころに、ふたたび作家への夢を蘇らせ、翌年F&SF誌に「蟻の王」が掲載されて作家デビューを果たすと同時に、クラリオン・ウェストというシアトルの夏期作家養成講座に参加して、実力を認められ、同期の若手作家との連携やSF出版界へのコネを強め、以後順調に短篇を発表している。2003年にはアメリカに帰国、長男もこの年に生まれている。この子育て経験がここに掲載した作品を生むことになる。現在はF&SF誌に2002年に発表した短篇を元にした長篇を執筆中である。ここに掲載した作品"Molly and the Red Hat"は、イギリスのSF雑誌インターゾーン213号(2007年)に掲載されたもの。シュールだったりSF的だったりすることが難解だと思われるなら、幅広い作風を活かして、このようなかわいらしい作品も含めた日本オリジナル短篇集を編むことも可能だろう。ぜひもっと多くの読者に楽しんでもらいたい作家だ。ぼくも翻訳した『紅はこべ』(『スカーレット・ピンパーネル』[*4] )に登場する貧しいユダヤ人も同じベンジャミン・ローゼンバウムという名前だが、それはまったく関係ない。彼の場合は本名である。
なお作者がいちばん日本での刊行を望んでいる短篇集の目次は以下のとおり。ごらんのように既訳もかなりあるので、ぜひ出版に結びつくよう、応援していただければ幸いだ。
The Ant King and Other Stories (Small Beer Press, 2008)
-
The Ant King: A California Fairy Tale 「蟻の王」(SFマガジン2008年6月号)
-
The Valley of Giants
-
The Orange
-
Biographical Notes to 'A Discourse on the Nature of Causality, with Air-Planes', by Benjamin Rosenbaum
-
Start the Clock
-
The Blow
-
Embracing-the-New 「抱擁もて新しきもの迎ふる神」(SFマガジン2005年6月号)
-
Falling
-
Orphans
-
On the Cliff by the River
-
Fig
-
The Book of Jashar
-
The House Beyond Your Sky 「あなたの空の彼方の家」(SFマガジン2007年8月号)
-
Red Leather Tassels
-
Other Cities 「ほかの都市の物語」(SFマガジン2004年6月号)ただし13篇中7編のみ
-
Sense and Sensibility
-
A Siege of Cranes (近日中にこのサイトに掲載予定)
*1 スリランカ生まれの作家メアリー・アン・モハンラジが2000年にはじめたSF思弁小説のウェブジン。 http://www.strangehorizons.com/
*2 SFからホラーまで幅広くジャンル小説の最先端を紹介する編集者エレン・ダトロウがSFテレビ専門局サイファイ・チャンネルをスポンサーに創刊した小説専門のウェブジン。原型は雑誌オムニの小説部門を発展させたオムニ・オンラン。なお、サイフィクションは2005年末に廃刊された。
*3 超ひも理論の発展形で、宇宙を構成するのは粒子でも紐(弦)でもなく、2次元ないし5次元の膜であるとする新しい宇宙論。膜(membrane)を省略してブレーン宇宙やM理論と呼ばれる。 https://ja.wikipedia.org/wiki/M%E7%90%86%E8%AB%96
*4 バロネス・オルツィが書いたフランス革命を背景とする冒険活劇ロマンス。ブロードウェイでミュージカル化され、最近宝塚でも上演された。終盤に登場する貧しい荷馬車引きの名前が、同じ綴りながらフランス語読みでバンジャマン・ローゼンバウムという。 >>Amazonサイト