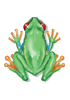失踪した曙涯(しゅうや)人花嫁の謎
アリエット・ドボダール
「失踪人調査をお願いするならあなただとうかがってまいりましたの」といって、女はオフィスにひとつだけある椅子を引いた。着ているものは絹で、麒麟の刺繍がしてあるところからみて、分瘤(フェンリュウ)でも最高位のキャリアウーマンだということがわかる。
マニキュアをした長い爪や、シミひとつない黄色い肌や、たおやかでいて無駄のない完璧な振る舞いをみて、おれにはわかった。「あんたのような身分の方からの仕事は受けないことにしているんだが」とおれはいった。
「あら、そう?」女は片方の眉をあげてみせた。「仕事がむずかしすぎるからかしら、ブルックスさん?」最後の台詞は曙涯(しゅうや)語から英語に切り替えてみせた。流暢なものだ。きっと大メヒカの言語であるナワトル語もしゃべれるのだろう。本物のキャリアウーマンだ、北アメリカならどこにいっても困ることはないのだろう。
「いかにも」とおれはこたえた。「とびきりむずかしいことをもちこんでくるのが金持ちばかりだってのもおかしなもんだがね」
「困らせるつもりはないから安心して」と女はいった。「ややこしい話は抜きにするわ」
おなじみの手口だ。「あとはこっちにまかせてもらえるってことなんだろうな」毎度繰り返されるダンスのリズムをとりもどしかけていた。愛想よく応対しているうちに話がまとまるってわけだ。曙涯人はやっかいな相手だが、こっちは連中相手の仕事には慣れている。
驚いたことに、彼女は手の内を明かしてきた。「駆け引きにかまけている暇はないのよ、ブルックスさん。引き受けていただけないのなら、ほかの探偵を雇うわ」
金には困っていた。おかげで、ロッキー山脈の西側、曙涯の領内に越してきたことを後悔していたところだ。断れるようなゆとりはなかったし、どうやら彼女も剝げかけたペンキやデスクの初心者用(エントリー・モデル)パソコンに気づいたはずだ。だが、彼女は素知らぬふりをした。うまいもんだ。たいした役者だ。
「用件を教えてくれ」とおれはいった。「引き受けるかどうかは聞いてからだ」
彼女は長い睫毛の下からおれを見あげた。「何嬋李(ヘ・チャンリ)と申します。〈雷鳴(レイミン)テック〉に勤めているわ。娘を捜してほしいの」
おれは無言で彼女を見つめた。その目を見つめると、必要なことはすべてわかった――どこまで話せるかを考えているのだ。ふたたび口を開いたとき、完全な信頼は得られなかったことがわかった。
「何珍(ヘ・ジェン)が7日前の晩から帰ってこないの」と何嬋李はいった。「婚約者のところにも音沙汰無しらしくて」
「7日じゃ行方不明と決めつけるにはちょっと早すぎるんじゃないか」とおれはゆっくりときりだした。
何嬋李はおれと目を合わせようとしなかった。ようやく口を開いた。「あの子には位置追跡インプラントをつけていたの。分瘤の南の空きビルに捨てられているのを見つけたわ」
追跡インプラントか。さして驚くにはあたらない、分瘤の上層階級の大半が誘拐を恐れて子供たちにつけているのだから。とはいえ……婚約者の話を思い出した。「何歳なんだ?」とおれは訊いた。
「16歳よ」と何嬋李はいった。
16歳なら若いとはいえなかった。16歳は曙涯の女性にとっては成人年齢で、もう追跡するような歳ではなかった。どのみち、ティーンの連中はたいてい、追跡装置があろうがなかろうが、勝手にふるまうものだ。だが、おれは口をつぐんだ。
「なぜ私立探偵なんだ? 民政軍にいけば――」
何嬋李は首を振った。「だめ。これはうちうちのことだわ、ブルックスさん。軍警を呼ぶつもりはありません」
「なるほど」つまり、ワケあり、か。おれはつきとめてやるつもりだった――それもすぐに。「手がかりは? 家出かもしれないが――」
「違う」と何嬋李はいった。「あれはそんな子じゃありません。それに、追跡インプラントはどう説明するつもり? あの子はあんな場所にはいったこともないのよ」
追跡インプラントがそこにあった理由ならいくつか考えられる。曙涯のティーンだってアメリカ人より分別があるわけでも、お行儀がいいわけでもないのは知っていた。だが、おれは何もいわずに、たんに「家出」もあり得る解釈のひとつにとどめておいた。
「あの子の部屋を見ていただきましょうか」と何嬋李はいった。「婚約者の温毅(ウェン・イ)とも話していただけるようにします」
おれは少し考えてみた。返事をしないでいると、何嬋李はいった。「お礼はしますよ、ブルックスさん。たっぷりはずませていただくわ」その口調はどことなくおかしかった――もう隠しきれない気持ちが――心配なのだろうか?
おれはこたえた。「引き受けるよ。だが、何も約束することはできない」
彼女はほっとしたようにうなずいた。「これは最近撮った写真なの」
おれは光沢紙を受け取って、明かりにかざした。何珍はどこの世界にもいるティーンの子らしく屈託のない笑みを浮かべ、きれいな真っ白な歯をのぞかせていた――整形かもしれないが、手を加えられているようには見えなかった。じゃあ、きっと値のはるやつだったのだろう。
「これしかないのか?」とおれは訊いた。
「ええ。追跡インプラントはうちにある。それを警備保障会社が見つけてくれた場所の住所も教えるわ。それでいいかしら?」
おれは肩をすくめた。「贅沢はいえないようだ」
「いいわ。うちにご案内しましょう、ブルックスさん、ご自分の目でたしかめてみて」
おれは首を振った。「こっちの都合のいいときに寄らせてもらうよ」正直なところ、出かける前にやらなければならないことがいくつかあった。彼女には見られたくないことだ。
何嬋李は眉をひそめた。「そんな言い方を聞いたら、お高くとまっていると思う人だっているわ」
おれは肩をすくめた。むかし、恋人の梅琳(メイリン)に教えこまれた愛想の良さを見せることはできたが、長いことはもたなかった。気持ちはまだアメリカ人のままだったので、曙涯流の微妙な“機微”というやつはどうしても身につかなかった。「そんなやり方しかできなくてね」
何嬋李は不満そうだったが、わずかに口元をこわばらせただけで、そんなことはおくびにも出さなかった。「みたいね」何かいうのを待っているようだったが、おれは無言だった。ようやく彼女は席をたったが、その笑顔は作り物だった。「おいでになるころには、わたしはいないかもしれないわ、ブルックスさん。仕事の打ち合わせがあるの」
おれはうなずいただけで、何もいわなかった。
「誰か、わかるような人間を手配しておくわ」と何嬋李はいった。
オフィスを出ていこうとしたとき、ほんの一瞬だが、彼女が隠そうとしていた気持ちがふっとのぞいた。
心配なのではなかった。むき出しの、まぎれもない恐怖がのぞいているのだ。強すぎて、恐怖の臭いがしてくるような気がした。
そのあと、おれはしばらくオフィスの壁を見つめたままだった。依頼は断るべきだった。わからないことが多すぎたし、依頼人から無理に聞き出さなければならないことが多すぎた。だが、金は必要だった。
アメリカ人で曙涯にいるということは――本物のアメリカ人だ、教会にいくプロテスタントで、道教や仏教に改宗したような手合いではない――自分の力でやっていかなければならないということだ。どんな会社からも雇ってもらえない。部屋を貸してくれる数少ない家主はとんでもない家賃をふっかけてくる。やっていくのはたいへんだった――だから、分別には目をつむって何嬋李の事件を引き受けたのだ。
何珍がどこにいるのかはわからなかった。だが、分瘤から出ていない可能性が大だった――金持ちの娘だから、誘拐犯に狙われてもおかしくない。だとすればよいが。外国にはいきたくなかった――大メヒカにはきびしい入国審査があって、血縁か宗教上の関係を証明しなければならず、貧しい合衆国のほうなら入国は容易だとはいえ、逮捕状が出ているところにもどるのもいやだった。
何嬋李の家に出かける前に、パソコンで検索し、何嬋李と婚約者の名前を入れてみた。ネットワークだけでなく行政の記録もさらったので、完全に合法的な検索というわけではなかった。運がよければ、帰ってくるころには何らかの結果が出ているだろう。
何嬋李の家は富裕層の住む分瘤の郊外にあった。おれはいまいるおんぼろビルからリニアモーター鉄道に乗り、都心とガラスの高層ビル群を抜けて――曙涯の北米経済支配の中心だ――住宅地に入った。車窓の外の風景は赤や黄色の提灯をぶら下げたアパートになり、それも屋根の傾斜した白壁の一戸建てへと変わっていった。
何嬋李に教わった住所は藤の花飾りで覆われた分厚い煉瓦塀のなかにあった。ドアが開くと、出迎えた老女が伝統的な曙涯の民族衣装を着ていることにおれは驚いた。桃の刺繍をふんだんにほどこした長衣で、桃は大昔から長寿のシンボルとされている。そのうしろには目立たないよう、制服姿の従僕がひかえていた。
老女が口を開いた。「わたしは何莱(ヘ・ライ)といいます。娘からあなたがおいでになると聞いていますよ」何莱の顔は日焼けして熟成した梅干しのように皺が寄っていた。そこから醸し出される落ち着きは、おれには不気味に映った。
「何嬋李の話では誰かに応対してもらえるということだった。てっきり使用人だろうと思ったよ、ご家族に案内してもらえるとは思ってもみなかった」
何莱は肩をすくめた。「お客様をお迎えするのは召使いの仕事ではありませんからね」
水面に百合と蓮の花が咲き乱れ、枝垂れ柳の長い枝が水面にまで達している池があった。別の時代、別の場所の美しさだ。だが、警備システムを制御する目立たない小さな制御パネルを目にして、ここが美しい庭園などではないことにおれは気づいた。ここは要塞なのだ。
「そこが」何莱は大きな建物のわきにある小さな翼棟を指さした――大きいほうは母屋だろう。「あそこが孫娘の部屋だわ。出ていってから手をふれていないの――使用人を遠ざけておいたから」
「どうも」そういってから、おれは彼女に見つめられているのに気づいた。何かを待っているのだ。
「あの子を見つけていただける?」声に不安がにじんでいた。
「どこか心当たりはないのか?」
「わたしには何でも相談してくれたけれど、家を出ていくなんてきいていなかった。考えが足りなかったわ。あの家で暮らす危険はわかっていたはずなのに。2年前にギャングが娘のメイドを拐かして、身代金を要求してきたことがあったんだから」
「それで?」
彼女は目を合わせようとしなかった。では、最悪の結果だったのだ。「ベストは尽くすよ」とおれはいった。「でも、何も約束はできない」
「わかっています。でも、わたしの気持ちはわかっていただけるでしょう」
待合室で恋人の梅琳の診断結果が出るのを待っていたときのことを思い出した。どれだけ、何でもないことを、梅琳が生きられることを祈ったことか。何もわからずにいることがいかに恐ろしいものか、おれにはわかっていた。
だから、おれは何もいわず、いい加減な気休めも口にしなかった。ただ、何莱に一礼しただけだった。そして引き戸を開けて、何珍の部屋に入った。召使いがついてきたのは、間違いなくおれが何も盗まないよう目を光らせるためだ。
思っていたのと寸分違わぬ、いかにも曙涯人の部屋だった。低い黒檀の寝台には漆塗りの枕とシーツ。数少ない家具は長寿を願って配置されている。マホガニーのデスクにはラップトップ。部屋の片隅には祖霊を祭る小さな祭壇があって、香炉には灰がたまっている。
祭壇を調べようと跪くと、上のネオンがともって青い光が降りそそいだ。灰は古いものだった。失踪した女性が部屋にもどってきた形跡はなかった。思ったとおりだ。
壁にはいくつか彫り物が飾られていた。明朝の絵の複製――宦官司彊嗎(シジャン・マ)の船団が南京を出港して、ヨーロッパが到達するはるか前にアメリカを発見することになる、あのよく知られた旅立ちの絵もあった。
ベッドサイド・テーブルの引き出しを開けると、真珠や翡翠のペンダントが詰まった宝石箱と、きちんとたばねられた元(ウォン)紙幣の札束があった――おれの家賃を数か月まかなえるだけの額だ。
翡翠のペンダントのなかをひっかきまわしていると、手に何かあたるものがあった――引き出しの底に慎重に隠されていた小さなものだ。おれは明かりに近づけてみた。抽象的な形によじれた結び目を作った翡翠だ。見覚えがあるのに、なぜかはわからない。伝統的な曙涯のペンダントではなく、ほかの宝石とは似つかわしくなかった。
それ以外に変わったものはなかった。
だが……
おれは振り返ってもう一度室内を見た。しっくりこない些細なものがないかと。ほかの人間なら見落としたかもしれないが、このての部屋ならいやというほど見てきたので、どこがおかしいか、おれには微妙な感覚がついていた。おれより前に誰かここに入ったものがいる。何もかも元にもどそうとしたが、すべてきちんともどすことはできなかった。
何莱の話では、使用人は手をふれていないということだった。何嬋李かもしれなかったが、そうは思えなかった。
奇妙だ。このての、最先端セキュリティで守られている場所に入りこむのはたいへんなことだ。なぜわざわざそんなまねをしたのか?
おれはラップトップを開いた。大メヒカの最新流行タイプだ。なめらかな金属製の外観にトウモロコシ色のキーボードが内蔵され、タッチパッドには様式化した蝶の飾りがついている――知識とコンピュータをつかさどるメヒカの神、ケツァルコアトルのシンボルだ。起動すると、ラップトップはビーッと鳴ったものの、パスワードや指紋照合は求めてこなかった。
ああ、知ったことか。やってみないことには。誰であれ、部屋を調べた人間がハードディスクの情報もすべて消した可能性はあるが、それでもうっかりして消し忘れたものがあるかもしれない。
おれはラップトップをもつと、刺繍入りのケースにもどした。ペンダントもとって、おれが調べているあいだ、ずっと黙って隅にたっていた使用人を振り返った。「これはもっていっていいか?」
男は肩をすくめた。「ご主人様に訊いてください」
部屋を出る前に、おれは高解像度写真を何枚か撮った。直感が何か見落としていることを告げていたが、何かはわからなかった。
外で何莱が待っているかと思った。だが、いなかった。代わりに別の曙涯人がいた。真っ赤なシルクの長衣を着た伊達男だ。肩書きを示すような肩章はつけていなかったが、おれはだまされなかった。その身のこなしと視線には鋼のような冷たさが感じられた。敵にまわしたくない人物だ。
「何珍の行方をつきとめさせに母が雇ったという調査員はきみだな」と男はいった。
おれはそいつの何嬋李の呼び方を聞きのがしはしなかった。曙涯語ではその意味はたったひとつ。「婚約者さんだな?」
男は黄色い歯をのぞかせてニッと笑った。「温威だ」
「ジョナサン・ブルックスだ」おれはなおも男を見つめながら、しぶしぶ名乗った。純粋な曙涯人ではあるまい――肌は曙涯人特有の黄色い光沢を帯びていたが、顔立ちには分瘤の先住民族であるチュマシュ・インディアンの特徴がはっきり出ていた。「ここで何をしている?」
温威はまた微笑んだ――天使のような笑みはだんだん鼻についてきた。「きみと話がしたくてね」
「話しているじゃないか」
彼はおもしろそうな顔をした。「きみたちアメリカ人はまったく失敬だな。どうして曙涯にやってくるのかわからなくなることがあるよ」
おれは精一杯笑顔らしきものを浮かべてみせたが、とことん作り笑いだった。「ここが気に入っているやつもいるんでね」まったく本当というわけではない。おれだって、ヴァージニア州で懲役15年の懸賞首がかかっていなければ、ロッキー山脈を越えてきたりしなかった。アメリカ合衆国は外国への同化をゆゆしき問題と受け止め、梅琳は半分しか曙涯人の血は流れていないというのに、州警察はおれたちの恋を犯罪と断じたのだ。「こんなところで何をしているんだ?」とおれは訊いた。
温威は驚いた顔をした。「ぼくは家族だ」
「まだ違うだろう」
「もう同然だ」と温威はいった。「結婚は1か月後におこなうはずだった」
彼の口ぶりにはどことなくひっかかった――その文にひそんでいるのは絶対の自信などではなかった。それは――怒りだろうか? 曙涯人の気持ちは読めるようになっていたので、アメリカ人の目には落ち着き払った穏やかに見える表面の下にひそむものまで読み取れた。温威が感じているものが何かと訊かれたら、おれは激怒とこたえただろう。だが、どうしてだ?
「何珍に最後に会ったのはいつだ?」
「彼女とは……7日前の晩に会う約束になっていたのに、こなかった」
「会うというのは?」
「さあ」と温威はいった。「だいじな話があるということだったが、詳しいことは話してもらわなかったから」
嘘だ。平気な顔で笑ってはいても、嘘には変わりない。その晩、彼女に会っている、賭けたっていい。
「彼女のことを教えてもらえるか?」とおれは訊いた。
「愛らしい女性だ」と温威はこたえた。
「そんなことしかいえないのか? 二人は婚約していたんだろう?」
彼は肩をすくめた。「家同士で決めた結婚だからね、ブルックスさん。曙涯でのしきたりは知っているだろう?」
「〈雷鳴テック〉のための結婚ということか?」とおれはいった。「何珍がいなくなってもあまり心配じゃないみたいだな」
彼は温厚そうな目をあげたが、その奥に怒りがたぎっているのが見てとれた。「心配しているさ、ブルックスさん。忘れないでもらったほうがいい」
「脅しているのか? そんなことしかいえないのなら――」
温威はおれと目を合わせようとしなかった。「美しくてすてきな子だった。彼女が笑うと、部屋のなかに陽がさすようだった」
「誘拐されたと思うか? 家出か?」家出のはずがなかった。家出をするなら計画がいるし、そうしていたのなら何珍はラップトップもベッドサイド・テーブルの引き出しに入っている金も、いっしょに持ち出しただろう。
彼は口を開いた。「いや。家出はない。親孝行な子だったから」
「なるほど」
「彼女の居場所に関する情報が何か入ったら、教えてくれ」彼は光沢のある名刺をよこした。「電話をくれ」
どうやらそれが男がきた理由だった。恋にのぼせた婚約者の演技はお粗末だった――だが、失踪した彼女への心配は違った。それだけは本音のようだった。だからといって、何かわかるわけではない――心配しているのは、すべて自分が仕組んだものと突き止められてしまうことかもしれないのだ。
温威の後ろ姿を見送り、いなくなるのを待って母屋に入ると、何莱が待っていた。手には漆の箱をもっている。「娘からこれをわたすようにいわれたので」
箱の中身は位置追跡インプラントだった。おれはお辞儀して謝意を示し、訊ねた。「その子のことはよく知っていたのか?」
何莱の目が何の表情も浮かべずにおれを見つめた。「たった1人の孫娘だったから。知らないわけがないわ」
「失踪する前はどんなだった?」
「元気だったわ、でも、1年がかりでようやく婚約がまとまったから――」
「結婚のことをどう思っているようだった?」とおれは訊いた。
「喜んでいたわ」と何莱はいった。「温威はコミュニティ内での地位もある人だから。あの子も一人前になれるし――」
「この家を出ていけるってことか?」彼女が顔をしかめたので、図星だったのがわかった。「じゃあ、娘さんとはうまくいっていなかったんだな」
「珍はいつだってちゃんということをきいていたわ」何莱は有無をいわせぬ目でおれをにらんだ。
「それを疑ったわけじゃない」そういったものの、服従しない方法ならいくらでもある。とはいえ、何珍が家出した可能性はますます低くなった。母との確執が何であれ、何珍はあと1か月もすれば何嬋李の手の届かないところにいっていたはずだ。分瘤で騒動を起こすのは非生産的なはずだ。
それに、何珍に何があったにせよ、部屋が探されているのはなぜだ? 何が見つかると思って、何を見つけたんだ?
すべて謎ばかりで、答は見つからなかった。
おれは引き出しで見つけたペンダントを持ち出し、何莱の目の前でぶら下げてみせた。「これは何かわかるか?」とおれは訊いた。
何莱の顔がゆがんだ。「珍のお気に入りだわ」
「曙涯のものじゃない」とおれはいった。
「ええ。珍の父が仕事でテノチティトランにいったときに買ってきたの。象形文字はナワトル語で“吉”と書かれているわ」
「父親が亡くなったとき、何珍はまだずいぶん小さかったと思ったのだが」
何莱はしばらく無言だった。「忘れられないものもあります。珍は父親が大好きだった」
意味は明らかだった。何珍は母親が好きではなかったのだ。
何莱はいった。「おもちになってください、ブルックスさん。もし何珍を見つけたら――」
「それは約束――」おれがいいかけるのを彼女はさえぎった。
「自分がしていることぐらいわかります。受け取ってください。いつでもあとで返していただけますから」
その口調ではっきりわかったのは、おれがそれを返すようなことにならないことを彼女が望んでいるということだった。
ラップトップを見せると、彼女は肩をすくめた。「それもおもちになって」気もそぞろといったようすで、ペンダントが思い出したくない記憶を呼び覚ましたのかと思えた。いつもいつも娘と孫娘のいさかいを見せられるのは悲しかっただろう。
しばらく何嬋李の家の使用人たちに質し、彼女の行方に心当たりがないかどうか訊ねてまわったが、気になる話は何も出てこなかった。
家を出て、おれは追跡インプラントが見つかったところまで電車でいった。薄汚いリニアモーターカーで、走行中は揺れ、いつ脱線するかとハラハラさせられた。
隣に坐ったのはよくいる連中だった。アヘンに酔って目を血走らせた若者、酒の臭いをプンプンさせた馬鹿な物乞い、疲れた目をして誰かに盗まれはしまいかと子供たちをひしと抱きかかえる子連れの母親。多くが白人か黒人で、曙涯にいけばもっといい暮らしが待っていると夢見て西へ西へと駆りたてられてきたものの――この異質な社会には適合できないことを知っただけだった。少なくとも、おれには助けてくれる梅琳がいた。癌に命を奪われるまでの短い数か月ではあったが。連中には誰もいないのだ。
同情している余裕はなかった。おれだってもう自分のことで精一杯だ。だが、それでも障害を負った物乞いがとおりかかるたびに、漠然とした後ろめたさを感じてしまう。
おれは福苑で降りた。大気汚染と煤で黒く汚れた小さな駅だ。あたりには小便の臭いがした。おれはそっと駅から出た。
追跡インプラントが見つかったという場所は数多くある福祉施設のひとつで、分瘤の前の県令がはじめたものの、恩庖(エン・パオ)長官が着任してからは民政府の職員が総入れ替えになって廃棄されていた。おれはつぶれた提灯やビニールの包装をまたぐたびに、おぞましいものを踏んで顔をしかめた。きっと物乞いだってこんなところでは寝泊まりしないだろう。
ようやく5階について、未完成のアパートを見わたした――作業員はまだ窓を作っていなかった。目を惹くものは何もなかった。
いや、そうでもない。おれは跪いて、指で床をこすった。茶色いペンキに思えたのは乾いた血痕だった。外壁を見あげてみた。かつては桃の花と燕の模様で飾られていたのだが。
色あせた文字の下に、探していたものが見つかった。かろうじて見えるか見えないぐらいの小さな穴が2つ、同じ赤っぽいしみがついている。弾痕だ。
おれはあらゆる角度から穴の写真を撮ると、血液のサンプルを採った。紫外線でざっとスキャンしてみて、床に髪の毛が数本落ちているのもわかった。それも袋に入れた。
だが、必死になって探しても、薬莢は見つからなかった――つまり、誰かが持ち去ったということだ。銃を使うのに慣れている人間だ。
なぜ何嬋李があれほど恐れていたのかがわかってきた。退屈したティーンの家出などではないのだ。本当のところ、もし、おれの考えどおり、血痕が何珍のものだとしたら、生きていないことだってあり得るのだから。
アパートにもどったのは深夜になってからで、おれはくたくただった。何珍のパソコンをベッドに投げ出すと、かんたんな食事を作った。インスタントラーメンと酢豚だ。
食べ終えてから、手際よく箸とプラスチックの丼を洗い、コンピュータの前に坐って、何嬋李の家に出かける前にはじめた検索の結果を見た。
何嬋李に関しては驚くようなことは何もなかった(〈雷鳴テック〉の創業者の1人で、いまでは筆頭共同経営者、麒麟の紋章を許されたビジネスマン・エリート49人の1人)。だが、笑顔の婚約者、温威に関しては……
うわべは小さいながらもきわめて業績のよい個人向け老人介護会社をやっていた。だが、〈白蓮会〉とのつながりがあった。曙涯で中国本土と戦った反乱組織で、やがて独立後は犯罪組織となっていた。
温威には嫌疑はかかっていない――驚くにはあたらない。明白な証拠もないし、彼の金が恩庖長官の都市再開発キャンペーンの資金源となっていたのだから。
明らかに銃を手に入れられるし、使うのもためらわないたぐいの男だ。
溜息をつきながら、放棄されたビルで見つけた血液と髪の毛のサンプルと、弾痕の写真を分析にかけた。
結果が出るまで45分間、おれはせっせと何珍のパソコンを調べ、彼女の個人用フォルダーをあさった。たいしたものはなかった。何珍と友人との写真では、彼女はカメラに向かって屈託のない無邪気な笑みを浮かべていた。母との写真はもっとおとなしいものだった。その姿を見れば、子供時代が幸福ではなかったことがわかる。麒麟の地位を得るような女性実業家は、かならずしも親として最良でも、思いやりがあるわけでもない。
だが、フォルダーは異常なほど空っぽだった。たしかに、何者かがメモリからほとんどすべてを消去していた。だが、1つだけミスを犯している。ハードディスクから何かを永遠に消去したかったら、物理的サポートを破壊するしかない。そうしていなければ、消去されたファイルは何とか見つかるかもしれない。だが、それには膨大な時間がかかるし、まして何を探しているのかわかっていないのだから、なおさらだ。
おれのパソコンがピーッと鳴って、分析が終わったことを告げた。おれは何珍のパソコンから自分のに移動し、結果を見た。
まず弾痕だ。〈憶森(イセン)〉のオートマティックで、銃身は改造されている。〈白蓮会〉の手先が好む銃だ。残りも驚くようなことはさしてなかった。異なる2つのDNAが見つかった。血液は何珍のだが、髪は笑顔の温威のものだ。もちろん、2人とも7日前にそのビルにいく理由などなかった。
温威に電話して説明を求めようか悩んで、そんなお粗末な方法はやめることにした。温威は明らかにいまでもおれが味方だと思っているのだから、悩ませるようなことはやめたほうがいい。
何珍のパソコンを標準的な分析にかけてみた――プロテクトのかかったファイルと消去されたメールを。それだけでもほぼたっぷりひと晩かかる。
ベッドにもぐりこむ前に、何珍の部屋の写真を自分のラップトップに移し、豪華な部屋をながめてみたが、いくらやっても見逃したものは見つからなかった。
目覚ましが鳴るずっと前に目が覚めた。ラップトップのタッチパッドについていた蝶のマークが繰り返し夢のなかに現れて、どこがおかしいのかはっきりわかったのだ。メヒカの神ケツァルコアトルの蝶は羽に模様などついていないのに、これにはあった。
おれは起きあがると、パジャマの上にコットンのローブをひっかけ、またラップトップを開けて、注意して羽を調べた。マークのように見えるが、角度を調整すると何かが……
何か見たことがあるものだ。何珍のお気に入りのペンダントと同じ、このマークはメヒカの象形文字だ。
大メヒカの言語、ナワトル語はしゃべれなくても、インターネット時代にそんなことは問題にならない。おれはビルのルーターにつないで、メヒカの検索エンジンでナワトル=曙涯語辞典を呼び出した。
象形文字はすぐにわかった。煙を吐く鏡だ。
煙を吐く鏡か。さらに検索すると、メヒカの戦争と運命の神のよく使われる別称だということが確認できた。テスカトリポカといって、好んでするのが夜に旅人に風変わりな競争を挑むことだった。
壁を飛び越えてみたら、深い峡谷が姿を見せ、橋はどこにも見当たらない、そんな気分だった。
パスワードか?
考えてみろ。なぜ何珍はこれをここに残したんだ? ラップトップが安全ではないと知って、誰か、メヒカの風習にくわしいものにメッセージを残したのか? 何珍の部屋で見つかったメヒカのペンダントとつながりがあるように思えたが、いくらペンダントをひねくりまわしても、つながりは見えてこなかった。
ようやくその件は先送りにすることにして、ラップトップのリカバリーがどうなったか見てみた。たいして期待してはいなかったが、わかったことは参考になった。何珍のパソコンはいまオープン・セッションになっていた。あとは電源を入れるだけでいい。だが、いつもそうなっていたわけではない。8日前の晩、何者かがコア・ルーティンをIDでプロテクトされているセッションから(つまり、ログインとパスワードと指紋照合をしなければパソコンは起動できない状態から)、オープン・セッションに切り替えていたのだ。
妙なやり方だ。何珍にプロテクトしたいファイルがあったなら、逆だろう。おれはもう少しパソコンをいじりまわし、ログ履歴を呼び出そうとした――もちろん消去されていた。だが、ログ履歴はつねにハードディスクの同じ場所にある――おかげでうまいこと、別のリカバリーをはじめられた。
パソコンから離れるときに、スクリーンの待機バーが検索には2時間かかると表示し、残り時間表示がどんどん長くなっていった。誰か、そのパラメータを変更して見つからないように骨を折ったものがいるのだ。
おれは分析をパソコンにまかせて、顧客に電話した。何嬋李に。
スクリーンに現れた姿はもう仕事服を着ていた。化粧もしっかりすませ、素肌の部分は微塵も残さず、しゃれた長衣で身体の曲線を強調し、麒麟のマークを目立つようにつけていた。「それで?」と彼女はいった。「何か進展があったの、ブルックスさん?」
「ああ」とおれは単刀直入に切りだした。「なぜ民政軍を呼ばなかったのかはわかった」
彼女は眉をつりあげた。「どういうこと?」
「温威の正体は知っているんだろ? それで恐れているんだ」
彼女はそっと、ソフトな白に塗られた壁を背にしてたちあがった。そのまま動かず、おれのほうを見もしない。曙涯人にとっては、それは認めたも同然だった。
「何珍は知っていたのか?」とおれは訊いた。
何嬋李はこたえた。「会社は――困っているの。資金面での問題があって。そこに温威が――」
「支援を買って出たのか」口調に皮肉がにじまないように気をつけた。「代わりに従順な妻を差し出したわけだ。彼女は温威のほかの仕事を知っていたんですかね、何さん?」
ようやく答を返してきたときの彼女の口調には何の感情もこもっていなかった。「いいえ。珍はとても正直な子でした。あの子は――」
「認めなかっただろう。そして温威は断られるのも拒んだだろう。そうなったと考えているのか?」
何嬋李はおれを見つめただけで、こたえなかった。
「追跡インプラントが見つかったという場所には血がついていた。娘さんの血だ」
厚化粧のせいではっきりとはわからなかったが、その下の顔は青くなったようだ。「まさかそんなこと――」
「本当にそう思っているのか?」訊きながら、彼女の目を見た――そこによぎる、わずかな感情のゆらぎを見つめた。
ようやく、彼女はこたえた。「珍にはわからなかったんだわ――わたしたちがやっていけるのは会社のおかげだということが。子の努めということがわかっていなかったわ」苦り切った口調だった。
そのとき、おれは気の毒になった。娘のことをわかっていなかったのは、彼女のほうだったのだ。おれはただうなずいた。「なるほど」
「もしかして――」何嬋李は息を呑んだ。「見つかったの?」
亡骸のことだ。「いや。まだいくつか調べている最中だ。連絡はたやさないようにする」それ以上つらい思いをさせないうちに、おれは会話をうち切った。
しばらく、坐ったまま考えこんだ。もしも本当にあの晩、温威が何珍を殺したのだとすれば、どうしてあれほど心配していたのだろう? 彼女の部屋に証拠を残していたはずがないのだから。
見方を変えてみよう。何珍の血が彼女が死んだ証拠だとしたら、なぜ温威は殺したのだろう? 母親の同意も得られているし、曙涯の法律では結婚にはそれでじゅうぶんなはずだ。花嫁が聞き分けがなかったとしても、そう、服従させる方法ならいくらでもある。そんな不快な例ならいやというほど見てきた。
おれは調べた部屋や何珍の消去されたラップトップを思い出してみた。彼女に文句をつけられたからといって、やつが殺したはずがない。殺したとすれば、彼女に脅迫されたのだ。彼女には彼を失墜させられる唯一のものがあった。彼と〈白蓮会〉とを結びつける証拠、民政府も見過ごすことのできない証拠だ。
当てずっぽうもいいところだが、的外れというわけでもなさそうだ。
煙を吐く鏡か。もし本当に証拠を手に入れていたとしたら、自分のパソコンに入れっぱなしにしておくほど何珍は馬鹿じゃなかったはずだ。彼女にオンライン・ストレージのアカウントを開けるようなネット上の場所なら、いくつか思いつく。
おれは片っ端からやってみた。ユーザー名に「メヒカ」や、「テスカトリポカ」や、「煙を吐く鏡」と入れてみたのだ。
15回目で当たりが出た。treasurechest.xyで2年前に「煙を吐く鏡」のアカウントが開かれていた。パスワード解読プログラムを1時間必死にいじりまわして、ようやくアクセスが認められた。
だが、何珍が隠していたお宝は思っていたようなものではなかった。〈白蓮会〉とのつながりが出てくると思っていたのだ――殺したくなるほど温威が脅威に感じるようなものだろうと。
代わりに見つかったのは、メヒカ文化を祭った祭壇だった。
誇らしげな笑みを浮かべて垂直の石のフープの下で跳びあがる球技の優勝チームの写真や、大ピラミッドでおこなわれ、最後は血まみれの生贄でしめくくられる宗教的儀式のビデオや、三国戦争で米軍のライフルの前に身を捧げるジャガーの騎士の像や、見る側にくり抜かれた目を向ける神や女神の偶像があった。
しばらくして、やっとデータの集積から目をそらし、おれは保存容量をたしかめた。アカウントはほぼいっぱいだった。すべてを見ようと思ったら、数日がかりになってしまう。そんなことになるずっと前におれは投げ出しているだろう。
メヒカの自己犠牲精神と非情な献身ぶりに感心するものもいる。おれにいわせれば、それは病んだ宗教だし、病んだ文明で、血に飢えている以外にさした理由もなく毎年何千人の犠牲を出しているのだ。
ともかく、蝶の羽の意味はわかったものの、たいして進展があったとは思えなかった。おれはパソコンを切って、ログ修復状況を調べ――表示では、まだあと4時間となっていた――それから、昼食を作りにキッチンにいった。冷蔵庫からコリアンダーを出していたとき、窓に何か光るものが目に入った。おれは手にした束を置いて、カーテンをもちあげた。
うちのビルの下でエアカーが待っていた。しゃれた真っ赤なリムジンで、ウィンドーは黒く、運転手と客の姿を都合よく隠している。
肩胛骨のあいだがぞくりとした。おなじみの危険のサインだ。おれが何かつかみかけているというサインでもある。
あとはそれが何かをつきとめるだけだ。
昼食は手早くかんたんに済ませた。エアカーを気にしないようにしながら卵かけご飯をかっこみ、デスクにもどってみると、何珍のパソコンが点滅していた。ログ履歴の修復が完了したのだ。
おれはモニターを、ログ履歴の最後の数行を見つめた。最後にログインしているのは何珍で、それは8日前の零時を数時間過ぎたころ――未知のルーター・アドレスを使って遠隔から操作されていた。
他人のしわざだろうか? しばらく考えてみて、それはないと思った。誰か何珍のログインを、パスワードから指紋認証までできるものがいたとすれば、わざわざセッション・システムを変えたりはしないはずだ。
ルーター・アドレスをたどってみると、福苑にほど近いネットワーク・センターにいきついた。何珍はいったい何をしていたのだろう? パソコンのデータを消去していたとか?
タイムスタンプをにらんでいるうちに、接続が30秒後に切れているのに気づいた。ログインして複数のファイルを消去できる時間ではない――何か前もって何珍がスクリプトを用意していたなら話は違うが。だが、彼女が家出をする気がなかったことはわかっていたから、そんな準備ができたわけがない。
電話が鳴っていた――数分間受信に気づかなかった。
「もしもし」とスクリーンのボタンを押して、おれはこたえた。
温威だった。今度は紫のシルクの服で、袖に蛇のような動物の刺繍がついている。動物は中国の龍に似ていたが、不敬にあたるほどではなかった――曙涯では龍を使っていいのは皇帝の親族だけだったから。
「ブルックスくんか? 進捗状況を知りたくてね」英語で話しているが、おれがちゃんとした曙涯語を話せることは知っているはずだ。だが、こうすることで、さりげなくおれの身分をおとしめようというのだ――移民のなかでも最低ランクの、曙涯社会に溶けこめない人種に。
「調べているじゃないか」とおれはぶっきらぼうにいった。「あの赤いエアカーはあんたのか?」
彼は笑った。「まったく、アメリカ人ときたら――」
あからさまな侮辱であり、こたえたが、おれは怒りに屈しはしなかった。それではやつのおれへの見方をますますこり固めてしまうだけだ。「お役に立てることでもあるかね?」
「どうなっているか教えてくれ」
「それはできかねるな」とおれはいいかけた。「依頼人は――」
「わたしはそう無下にしていい相手じゃないはずだぞ、ブルックスくん」
「そうだろうな。それでも、進捗状況はおれの胸のうちだ」
温威はいった。「きみはがんばっているそうだ。それはいいことだ、ブルックスくん。だが。覚えておきたまえ、調査がうまくいったら、最終的にきみへの金がどこから出てくるのかってことを」
何をさしているのかは間違えようがなかった。彼は何珍の未来の夫であり、婚約が成立した以上、家族同然なのだ。「うまくいったらな」とおれはいった。
「いくとも」といって、温威はぼんやりと、爪を伸ばした指を短剣でもながめるようにもちあげた。「きみには――根性があるからね、ブルックスくん。それをなくさないようにな、さもないと――いろいろなことがもちあがってくるだろう」
「なるほど」とおれはいった。「いろいろなことがね」やつがいおうとしているのは、何があろうとおれは何珍の捜索をつづけなければならないということだ。つまり、ということは、彼女はまだ生きているのだ。
そこにまつわる諸々にかかずらっている暇はなかった。頭をフル回転させなければならなかったからだ――曙涯人との、それもとりわけ権力をもつ相手との会話は、いつだって硫酸をばらまかれたなかを進むような緊張感がある。
「あまり身の安全を過信しないことだよ、ブルックスくん。男が進む道はさまざまだからね」
またしてもさりげない脅しだ。調査を打ちきれば、何珍は守ってやれない。おれのやった程度のことなら、ほかにできるやつを雇えばいいのだ。
「なるほど」とおれは繰り返した。これ以上刺激したくなかった。
温威はなおもおれを見つめていた。「残念だな。きみは賢い男だ。なのに、われわれのなかに溶けこむのを拒んでいるとは。曙涯人のお友達にもわれわれの社会の基盤をきみにたたきこむことはできなかったようだな」
会話に梅琳のことを持ち出す権利はない、彼女の思い出を汚す権利など、おまえにはない、といってやりたかった。だが、それは愚行だった。だから、おれは首を振っただけだった。
「われわれのあいだには輝かしい未来が待っていたかもしれないんだ」
おれは無言をとおした。やつを満足させるような返事はしたくなかった。
温威はいった。「われわれが北米を支配しているのは根拠のないことではない。母国中国がアジアで白人に勝利したのも故なきことではないのだ」
「あんたたちの力は知っている」とおれはゆっくりと切りだした。「力を疑ってはいないさ。だが、おれにはおれのやり方がある。おれにとって曙涯ではたいして得られるものなどないんだ」そう口にして、おれは気づいた。それは真実だった。その分瘤のみすぼらしいオフィスにおれをつなぎとめておくものなど、梅琳の思い出と、ほかに行くあてがないこと以外には何もないのだ。
そうした興ざめなことを考えるのにふさわしいときではなかった。
温威の表情は変わらなかった。だが、その目はより暗い陰を帯び、語りだしたときの口調は早口で簡潔だった。「いいだろう。きみはもっと目の前のチャンスをつかむことのできる男だと思っていたよ、ブルックスくん。まあいい。金を払っているのだから、それだけのことはやってもらおう。じゅうぶんな額になるはずだ」
そして彼は会話をうち切り、残されたおれはキッチンで震えた。
なるほど。いくつかおれにもわかってきた。大半が不快なことだ。梅琳はむかし、いまとなっては別の人生に思えるほど遠いむかしに、〈白蓮会〉にはかかわるなと教えてくれた。いろんなことがそうだったように、彼女が正しいことはわかっていた。
ひとつ、注目すべきは、温威が何珍を探していることを認めた点だ。つまり、何珍は生きていて、〈白蓮会〉を恐れながら潜伏しているということか――
違う。
おれなら、そうやって会いに出かけて、怪我までしたあげく、家に帰っても母親に黙って将来の夫の元に差し出されてしまうのがわかっていたとしたら、分瘤に残ったりしないだろう。〈白蓮会〉の手の届かないところにいっているはずだ。
大メヒカか、アメリカ合衆国に。
これまでにわかったことを考えれば、大メヒカのはずだ。
だが、国境を越えなければならなかった。かんたんなことじゃない、まして大メヒカにいくのは。ほとんど国境を閉ざしているのだから。入国審査は国境の町ではきびしく、南にいくほどさらにきびしくなる。首都テノチティトランに非メヒカ人が永住しようというのは、よほどの好材料でももっていないかぎり、不可能に近い。
外部からの手助けが必要だ。
外国人を大メヒカに入国させる仕事をしている人間なら何人か知っていた。必死になればすぐに見つかるような手合いだ。だが、やり方もいい加減だった。連中が国境を越えさせた人間は年季が明けるまでクアウパモックかイツォワカンの売春宿で働くか、どこかの銀鉱で粉塵まみれで窒息するまで働かされることになった。
おれはテーブルに置いた何珍の写真をつかむと、外に出た。福苑にもどり、8日前の晩に何珍が接続したネットワークセンターに向かうことにしたのだ。
そこから少しずつ輪を広げていって、片っ端から見つかった密入国支援業者に何珍の写真を見せて、聞きこみをしてみた。ぽかんとした表情しか返ってこなかった。
だが、13人目ぐらいの相手が肩をすくめて、教えてくれた。「それなら、ドック・スミスに訊いたほうがいい。ドックはいつもはみ出し者を受け入れてるから」
ドック・スミスはアメリカ人だ――その印象的なもじゃもじゃのモップのような赤毛を見れば、生まれはアイリッシュなのだろう。彼は芳仙地区のうすぎたないバーで見つかった。貧困白人層の地域だ。震える手で米酒のカップをかかえていた。写真を見せると、目をしょぼしょぼさせながら見つめた。「ないな」とやつはいった。「見たことがない」
嘘だ。写真をあまりに長く見過ぎていた。「8日前にここにきたんだ」とおれはいった。「たぶん怪我をしていた。国境を越えようと必死だったはずだ」
「あんたに何の関係がある?」と彼は訊いた。
「彼女の家族が会いたがっている」
「たいした家族だな」男は鼻で笑った。「死んだ子の歳を数えたってしょうがない。お互いにそのほうが楽だぜ」
おれは首を振った。「そうできたらいいんだがね、ドック。仕事なんだ」
「いわせてもらえば、くだらねえ仕事だ」
ああ、くだらない仕事だ。〈白蓮会〉のためにあとをたどるのも、何珍を助けようとすれば、ほかに手がないからだ――おれの身を救うためでもある。おれは目の前の仕事に集中した。「おたくの仕事のほうがましだっていうのか? 客にいんちきな約束をするだけじゃないか?」
やつは首を振った。「客をだましたことはねえさ。これからもそうするつもりはない。あの女には望みどおりのことをかなえてやった」
「それは何だったんだ?」
やつは笑った。「身の安全さ。それ以上は話さないからな。ドック親父は馬鹿じゃない」
「おれは連中の側の人間じゃない」
「そう思わされているだけだ」そういって、やつは自信ありげにゆっくりと微笑んだ。「信じろよ。あきらめて、うちに帰るんだな」
おれはしばらく自分の手を見つめて、何珍のことを、その偽りの人生のことを考えた――長年、別の場所を夢見てきた末に、結婚が救いにならないことを知ったことを。「そういうわけにはいかない」とおれはこたえた。「おたくが送り届けた場所では彼女は安全じゃない。安全にはなれないんだ」
「じゃあ、ちょっかいを出すのか? 不健全な仕事だな」とドック・スミスはいった。
おれはテーブルの上に両手を広げた。梅琳のことを思い、死が彼女を奪うまでの曙涯での幸福な数か月のことを思った。「ほかには何もないんでね」とおれはいった。
ドックは微笑んだ。飲んでいた米酒のマグをおれのほうによこしたが、おれは首を振った。「忘れにきたわけじゃない。答がほしくてきたんだ」
「わかってる」やつに見つめられて、そのしょぼくれた目が見せかけよりずっと深く見とおせていることにおれも気づいた。「甘っちょろい気持ちでやっていけるところじゃないのさ、曙涯は。みんなが出ていきたくなるのも無理はない」
「彼女の住所を教えてくれ」とおれはいった。「じゃなきゃ、ここに民政軍を呼ぶ」
「虚仮威しだな、それぐらいあんただってわしと同じぐらいわかっているはずなのに。この地区に入ってこようとする中国人などいやせんよ」
「彼女を追っておれがここまでやってこれたんだから」とおれはいった。「ほかのやつだってできる。ほかの誰かがやってきて、おたくから彼女の住所をむしりとっていくぞ。せめて、彼女に警告ぐらいはしてやったほうがいいんじゃないか」
やつはおれを見つめ、獲物に飛びかかる前の梟のように首をかしげた。「接触先のアドレスなら教えよう」とやつはいった。「そこまでだ。あとは勝手にやってくれ」
「助かるよ」
彼の手がおれの手首をつかんだ。「あんたを信じてるんだからな。あんたには情も知恵もあると信じているぜ。がっかりさせんでくれよ」
おれは何もいわなかった。もうどんな約束もできなかったのだ。
ドックが教えてくれたアドレスは電子メールの一時フォルダで、おれはそこに簡潔な何珍あてのメッセージを残し、彼女の家族としての情に訴えた。ほかにも残しておいたものがある。サーバーへのアクセスをモニターするスパイ・プログラムだ。
そして待った。
2日かかり、そのあいだに、温威は少なくとも3回電話してきた。おれは出なかった。
返信が、無署名で届いた。「ほうっておいて」おれは消去した。興味があったのは、そのメールがどこから出されたのかだったから。
思ったとおり、大メヒカからだった。詳しくいえば、テノチティトランの近郊のネットワーク・センターだ。
やれやれ。どうやらおれ自身のコネもいくつか使わなければならないようだ。
おれは芳仙にもどって、いかわがしいバーの1つに入り、金を払って偽造旅行書類を手に入れた――おれがメヒカの宗教の敬虔な信者であることを証明した偽造電子ビザだ。ビザにはおれがテノチティトランの大ピラミッドに巡礼旅行に出かける資格があると書かれている。
ビザを慎重に調べて、騙されていないことを確認すると、そこから数日間、メヒカの神々と生贄のことを読んで勉強した――国境での厄介な質問に備えたのだ。
それから旅行の支度をした。見せかけのものだ。2日のうちに、おれはエアカーをレンタルして、南への道に向かい、ずっとうしろから2台の赤いエアリムジンが追跡してきた。
大メヒカは美しい国ではない。北部は砂漠で、カジノと売春宿が点在している。南に進むにつれて、風景は湿地と大メヒカの富の大半をもたらすエレクトロニクス工場群に取って代わる。
進むのははかどらなかった。メヒカの入国審査はきわめて厳重だった。おれは2、3人の羽根の記章をつけた役人に止められて、書類を求められた。尾行してくる真っ赤なエアカーも停止させられていたらと思ったが、それが虚しい期待だということぐらいわかっていた。
乾燥しきっているとはいえ、そこは豊かな国だった。どのホテルにも蝶のマークのついた最新のパソコンがあり、とくに課金されることなくネットワークにつなぐことができる公衆無線LANがあった。地下の光ケーブルのコミュニケーションが飽和状態になっていくのが、足の裏で感じとれるほどだった。
5日目に、テノチティトランの入口に着き、おれは入国審査を受ける車の列にならんだ。5日目の夜は車中で、大都会の明かりに向かってノロノロ運転をしながら、過ごすことになった。
入国管理官に少し手間取らされたが、たいしたことはなかった。“休暇”が明けたら間違いなく大メヒカを離れるよう、おれは血のなかにナノ追跡装置を注射された。
外人がテノチティトランの中心街に泊まることは禁じられていた。おれは中心街から30キロほど離れた郊外のツォパリで宿を取り、ネットワーク接続を使って何珍の電子受信ボックスにメッセージを入れた。
翌朝になると、おれはネットワーク・センターに出かけ、近くのバーを探して、ホットココアのマグを手に入れて腰を据えた。受信ボックスにはまだスパイ・プログラムが入れてあるから、誰かがアクセスしたとたんにメッセージが入ることになっている。
何珍の特徴と一致する人間はこなかったが、ともかくスパイ・ウェアがメッセージをくれた。おれはこっそりネットワーク・センターを調べたが、10歳ぐらいの幼い子供しか見つからなかった。奴隷の四角い金属製の首輪をしている。じゃあ、お遣いか。
子供を尾行して、テノチティトランの路地や運河をたどったが、黒い艀に飛び乗られて見失った。艀は速度をあげて遠ざかっていった。
サボテンと鷲の紋章がついた艀だ。
尊い演説者こと、大メヒカ皇帝の家紋だ。
やれやれ。
いくつか遠回しな質問をしてみて、その船がヤオトル・ツィンのものであることがわかった。皇族のなかでは低位のもので、テノチティトランから15キロほど南にいった島に住んでいるという。その家については悪い噂も聞いた。秘密の乱交パーティのために大メヒカや外国から処女が集められているという噂だ。
腹のあたりにぽっかりと穴が開いたような頼りなさを覚えながら、おれはドック・スミスにいわれたことを思い出した。「望みどおりのことをかなえてやったんだ。身の安全をだ」もし安全というのがこういうことなら、やつにはひどく気味の悪いユーモア感覚がある。
少し意気消沈して、おれはヤオトル・ツィンへの面談を申しこんだ――回想録を執筆するという名目で、ヤオトル殿下にだ。期待してはいなかったが、ヤオトル・ツィンは頼みを聞きいれてくれた。
約束の日、黒い艀がテノチティトランの船着き場に迎えにきた。乗り組んでいたのは10人あまりの奴隷で、屈強な男たちは操縦に忙しく、会話しようとしても無視された。
都市の岸辺が遠ざかっていくのを見ながら、おれはいまさらながら、自分が誤りを犯したのではないかと思いだした。おれが姿を消したとしても、誰も探してくれはしない。大メヒカに入ってからはずっと何珍のペンダントは手放さずにきた。ときどき、気を静めたくてそれにふれずにはいられなかった。
ヤオトル・ツィンの館というのは湖畔の宏大なヴィラだった。メヒカのフレスコ画がかかったパティオと屋根付き廊下が迷路のようにつづいていた。おれは案内役に連れられるまま、松の植わった中庭をいくつか抜け、エルナン・コルテスと征服者(コンキスタドール)との短い戦争から――中国製の銃と大砲の火力のせいであっというまに終わった――三国戦争と、シリコンチップと高性能エレクトロニクスによるメヒカの覇権につづく、大メヒカの歴史を描いた襖絵のついた廊下をとおっていった。
とおされたリビングにはガラスケースに絵文書が陳列されていた。窓際には曙涯製の黒檀のデスクがあり、書類と使い捨てICが載っていた。籐の椅子があったので、どうしていいかわからないまま、おれはそこに腰をおろした。
待った。見えないラウドスピーカーからメヒカの聖歌が流れ、フルートと太鼓が歌詞に不思議なアクセントを与えていた。
ドア代わりのカーテンが開いて、鈴が鳴ったので、おれはたちあがり、ヤオトル・ツィンに見えすいた口実をぶつけようとした。
だが、ヤオトル・ツィンではなかった。
メヒカの服を着た女性だ。凝った作りのブラウスに、それに合わせて走る鹿と鸚鵡の模様がついたスカートという姿だ。髪はメヒカ風に肩まであり、肌はトウモロコシ色という、メヒカではたいそう好まれている黄色で、若い娘たちは肌にまで化粧をするという。だが、染めたものではないのがわかった。
何しろ、明らかにおれの前にいる女は曙涯人なのだ。
「頑固な方ね、ブルックスさん」と女は訛りのある英語で話した。
おれは曙涯式に両手を袖のなかにいれてお辞儀した。「何珍さん」とおれはいった。
彼女は首を振った。「もう違うわ。ここではトラソショチトル、たいせつな花という名前で知られているの」
「お似合いだ」皮肉ではなかった。彼女はメヒカ人に見えた――静かに自信に満ちたしぐさは曙涯人というよりはメヒカ人のもので、まるで本当にここで花開いたのかと思えた。
「どうしてここにきたの?」と彼女は訊いた。
「あんたはどうして?」
彼女は肩をすくめた。「わかるはずよ。どうしようもなかったの。あんな男と結婚するつもりはないわ」
「それが解決になるとでも?」とおれは訊いた。「しゃれた売春宿で売春婦をすることがか?」フェアな言い方ではないことはわかっていたが、もうどうでもよかった。利用された気がした――彼女を見つけるためにしたことがすべてここに〈白蓮会〉を呼び寄せてしまうのがわかった。
彼女は微笑んだ。ゆっくりと秘めやかな笑みは寺院の仏像を思わせた。「わたしは売春婦じゃないわ。この館の主人よ」
「そうやってドック・スミスはあんたに国境を越えさせたのか?」とおれは訊いた。
「当然よ、ブルックスさん。宮廷では流行なの、かわいくて、社交界で振る舞える曙涯人の妻をもつのが。ヤオトルは一族のパーティで披露できる書類上だけの妻が必要だったの。わたしなら申し分ないと思ったのよ」
「申し分ないか」おれはゆっくりといって、彼女を見つめた。
彼女は微笑んだ。「家族はかならずしも骨肉の絆でつながっていなくてもいいことを忘れているのね。どうしてここにきたのか教えて」
「わかってるはずだ。あんたの母親に雇われたんだ」
彼女の表情が曇った。「ええ。でも、あなたは馬鹿じゃないわ。本当の理由は知っているはず。なのにきたのね」
「ここにいちゃ危険だ」とおれはいった。「温威はあんたを探している。やつと会うことになった証拠が必要なんだ」
彼女は胸の前で腕組みをした――片方の腕はまだ不自由だった。銃で受けた傷がまだなおっていないのだろう。「なぜ?」
「やつの正体をあばきたいんだ」
「その気になればいつだってあばくことはできたわ」と何珍はいった。「それより、わたしはこっちにくることを選んだの。わたしは安全よ。ブルックスさんだろうと、誰だろうと、わたしには必要ない。母が工夫するものより、ここのほうがずっと安全な砦なの」彼女は窓のほうに向かった。あとにしたがうと、中庭で曙涯人たちが屈強なメヒカ人に引き倒されて膝をつかされているのが見えた。メヒカ人は自動小銃をかまえて、曙涯人の頭をつぎつぎと撃ち抜いていった。「〈白蓮会〉はここには手が届かないし、これからだって同じよ」と何珍はいった。
「そうだな」やっとのことでおれはこたえた。平然と暴力がふるわれていることに胃がきりきり舞いをはじめた。相変わらず何珍は表情を変えなかった。「なあ、それだけの価値があることだったのか、何珍? 身の安全がその代償に見合うものだったのか? あんたが幸福なのかどうか教えてくれ」
彼女は微笑んだが、その表情には苦渋が浮かんでいた。「政略結婚からまた別の政略結婚に鞍替えして、幸福かっていうの? わからないわ、ブルックスさん。ここにいれば、館のなかでは自由に力をふるえる。ここでなら、家の財産を守るために人身御供になって売られたわけじゃない。あなただったら、どうしたかしら?」
「わからない」とおれはいった。「だが、おれが父親だったら、娘にそんな歳でそんなつらい思いをさせたりはしなかった」
「でも、あなたはわたしの父親じゃない。幸運だったわね」何珍はガラスケースのあいだをとおり、美しい絵文書の上に手を置いた。「わかってくるのよ。母の家にいれば、あっというまにわかってしまうわ」
「それほどひどかったわけでもないだろう」おれは反論し、よくわからない本能に訴えて何嬋李を弁護しようとした。
彼女はまた微笑んだ。「わかっていないのね。あなたは運のいい人よ、ブルックスさん」
「婚約者があんたを殺そうとしたことはわかる。逃げ出すのが手っ取り早い解決策だと思ったのか?」
彼女の顔がまた暗くなった。「わたしは臆病じゃないわ」
「じゃあ、証明してくれ」
「虐殺現場に小鳥みたいに舞いもどれっていうの? わたしは馬鹿じゃないわ」
溜息が出た。「ああ、あんたは馬鹿じゃない。じゃあ、あの晩はいったい何が得られると思ったんだ?」
彼女は肩をすくめた。「馬鹿みたいなことよ。あなたのいうとおりだわ。自分の力で結婚を破談にできると思ったのよ。人生はそれができないことを教えてくれた」
「おれなら、あんたを撃った男をつかまえられる」おれは母親がわたしてくれた何珍の写真を思い出していた。輝くような屈託のない笑顔を思うと、何をやったところであれはもどってこないのがわかった。
何珍は死んだように無表情な目でおれを見つめた。「なぜあなたに手を貸さなきゃならないの?」と彼女は訊いた。「あなたは自分の身を救うためにここにきたのよ」
「あんたのためにきたんだ」自分でも嘘だとわかった。
「あなたなんか必要ない」
「それはもう聞いた」
「だからといって、答が変わるわけじゃない」と彼女はいった。「帰って」
「だめだ」とおれはいった。「証拠なしでは出ていかない」
「帰って。隠れられる場所を見つけなさいよ、ブルックスさん。〈白蓮会〉の手が届いていないところを。そういうところはまだあるから」彼女の笑顔には皮肉があった。
むかし、10年前、おれも逃げたことがある。真夜中に梅琳とならんで国境を越え、何が見つかるかも知らずに暗闇のなかに突き進んだのだ。
あれ以来、世界は狭くなった。梅琳は死に、おれはおれなりの道をたどってここ、メヒカ帝国の心臓部にきて、もう幼くはない娘と向かい合っている。「おれは逃げたりしない」おれは歯を食いしばっていった。「正義がおこなわれるのを見届けるんだ」
「じゃあ、あなたは勇敢なんだわ」と何珍はいった。「いくら演説をふるってみたところで、愚かでもあるけれどね」
おそらく彼女のいうとおりだろう。だが、出ていくことはできなかった。ここまでやってきて手ぶらで帰るわけにはいかない。
おれには最後の切り札があった――彼女を説得できる最後の賽が。「あんたは温威の仕打ちを気にしないでいられるかもしれないが、ほかのものはそうはいかない」
「母のこと?」何珍は笑った――ぞっとする、悟りきった笑いだった。
「あんたにはお祖母さんがいる」彼女がひるむのが見えた。
だが、それでも彼女はびくともせずにこっちを見つめた。「いたわ」と彼女はいった。「ここでは、もう関係ないの」
おれはポケットのなかを探り、分瘤からテノチティトランまでずっと手放さずにきた1つのものを取り出した。何莱がくれた、何珍のお気に入りという翡翠のペンダントだ。おれはそっとそれをガラスケースの1つに置き、何珍の視線がすばやくそこに向かうのを見た。
「お祖母さんはあんたにこれを返したいと思っていた」とおれはいった。「おれが持ち帰ることにならないように望んでいたんだ」
何珍は何もいわなかった。その目は内側に向いていて、銅像のように冷たかった。
「お祖母さんには何といえばいい?」おれはそっと訊ねた。
「どうでもいいわ」何珍は繰り返したが、もう力は失われていた。初めてその声に感情がのぞいていた。彼女はしばらくペンダントを見つめ、唇を噛んだ。
やがてそろそろと、じれったくなるほどゆっくりと手を伸ばし、ぱっとそれをつかんだ。表情はまだ何も浮かんでいない。
おれは無言のまま、ただ彼女が自分自身と闘うのを見守った。
ようやく彼女が口を開いた。「わかったわ。断りきれないようね、ブルックスさん。召使いに必要なものをわたさせましょう。お好きになさって。受け取ったら、出ていってください」
「助かるよ」とおれはいった。
黙っておれは戸口に向かい、彼女は開いた窓の前にたたずむシルエットになって残された。見おろす中庭には〈白蓮会〉の手先の死体が横たわっていた。
部屋を出ようとしてカーテンをもちあげると、彼女の声がした。「ブルックスさん?」
おれは振り返らなかった。
「幸せじゃないわ」とても静かな口調だった。「でも、それはいわないで。お祖母ちゃんにはわたしは何もないなかで、精一杯やったっていってください。それでじゅうぶんだって。ともかく、ほかのみんなには何も変わらなかったでしょう?」それははじめて、16歳のとまどう女の子の口調だった。自分がしたことが正しかったのか悩んでいるのだ。
おれはこたえなかった。本当のところは、答などもちあわせがなかったし、彼女もそれをわかっていた。おれは振り返ることなく、立ち去った。
大メヒカを離れる前に、おれはホテルにもどり、コネを使って少し細工をした。何珍にもらった証拠は分瘤の民政府に送った。自分の名前で送り、温威と直接会って最後の打撃を加えた相手を教えてやりたいとさえ思ったが、それが馬鹿げたことだとはわかっていた。そんなことをすれば、おれにとって分瘤に身の安全をたもてる場所は、いや曙涯のどこにだってなくなってしまう。〈白蓮会〉はかならず身内の復讐はするのだ。
だから、痕跡を隠すため、おれはルーター・アドレスをいじり、何珍自身が犯罪の証拠を送ったように見せかけた。
久しぶりに会心のできだった。
曙涯に向かって車を走らせながら、おれは成り行きを興味深く見守った。分瘤ではなくても、大メヒカでさえ温威の逮捕は報道された。キャスターによれば、少なくとも絞首刑になるという見通しだった――曙涯は政府職員の汚職を軽く見る国ではなかった。
分瘤に着くと、レンタル会社に車を返し、リニアモーター鉄道に乗って何嬋李の家に出かけた。真夜中だったが、彼女はまだ起きていた。
彼女はまだビジネススーツのまま、玄関まで出てきておれを迎えた。うしろには母親の何莱が前にこの館にきたときと同じ伝統的な衣装でひかえていた。「ブルックスさん。困ったときにきてくれましたね」と何嬋李がいった。
「わかっている」〈雷鳴テック〉の株価は暴落し、銀行はたちまち手を引きはじめていた。「ここにきたのはお嬢さんが無事だと、でも家にもどるつもりがないことを伝えるためだ」
何嬋李は表情を動かすことはなかったが、憎しみがあふれ出ているのが感じられた。「あの子には家というものがわかっていないのよ」
「そうだな」とおれはいった。「生きていると知ってうれしくはないのか?」だが、答はもうわかっていた。なぜ何珍が家であれほどつらかったのかがわかった。
何嬋李はこたえなかった。おれに背を向けて、家のなかにもどっていった。
あとには何莱が残って、おれを静かに見つめていた。
「わたしはうれしいわ」そっとこたえるので、おれはその手に何珍がくれたもうひとつのものをにぎらせた。赤い蓮の花の形をしたペンダントだ。曙涯では孝心のシンボルだ。
ようやくおれも口を開いた。「何珍のパソコンのファイルを消去したのはあんただね? だから彼女も自分のアカウントではなくオープン・セッションに切り替えなければならなかったんだ、パソコンに指紋照合を求められてしまうから」
何莱はおれと目を合わせなかった。「あの子はたった1人の孫娘なの。ほかにどうすればよかったかしら? わたしたちの道はときとして真実とは思えない方向に導いてしまうこともあるけれど、それでもそれが神々がわたしたちにお命じになる道なんです」彼女は目に涙を浮かべ、それを隠そうともしなかった。
「わかっているよ」とおれはいった。「お気の毒に」
「ありがとう。お支払いはちゃんとさせるから」
「金のことじゃない」とおれは反論しようとした。
「たいていのことはお金のためよ」と何莱はいった。「それでよかったと思っていただけるはずだわ。さようなら、ブルックスさん。二度とお目にかかることはないでしょう」
ああ。おれもないと思った。
リニアモーター・カーでアパートに向かいながら、おれは高層ビル街の隙間の空を見つめた。夜もこれだけ更けると、乗客はおれくらいなものだった。聞き慣れた電車の唸りは、お帰りという挨拶代わりの交響曲のように耳に響いた。アパートにもどって、翌朝目覚め、また日々の日常にもどり、梅琳が死んで以来ずっと繰り返してきたように昼と夜を埋めていくのだろう。それだけの価値があることなのか、それともほかにどうしようもないからそうしているだけなのか、おれは自問した。どうでもいいことかと思って、何珍の言葉を思い出した。
わたしは何もないなかで精一杯やったわ。それでじゅうぶんなはずよ。
そうさ。それでじゅうぶんだろう、毎日、毎晩その繰り返しで。
それでいいはずだ。
(訳:小川隆)
解説
アリエット・ドボダール(Aliette de Bodard)についてはすでにアンケートとエッセイで紹介したので、ここでは作品についてふれたい。これまでに出ている長篇は、いずれもアステカ帝国が世界帝国になっている世界を描いた歴史改変もので、本人はいまインカにも興味を覚えて調べているというから、システム・エンジニアの割には考古学好きのようだ。フランスには異国趣味の伝統があり、しかも作者は多言語をあやつるので、いろいろな世界観を取り入れるのには抵抗がないのかもしれない。アステカの世界観の核になっているのは占星術と運命主義なのだが、細かな描写にもそれが取り入れられていて(たとえば、日が昇るという代わりに、太陽が座を変えたというような描写が用いられる)、作者の思い入れがうかがえる。そうした異なる世界観を提示するというのも、SFの醍醐味だろう。ここに紹介した曙涯もののシリーズは、それとはまた別に、アステカ帝国と中国とが覇権を争い、イギリスの清教徒ではなく中国にいられなくなった宦官が率いる移民団がアメリカを発見して、中国の影響下にある独立国曙涯(東の果てという意味で、曙の字をあてている)を建国した、という歴史改変ものだ。まだ短篇だけのシリーズだが、その主眼はむしろ宇宙開発を非西欧型でおこなうとどうなるか、という未来史の部分にあり、アステカ型の生贄を模したバイオテクノロジーを使ったタイプも(マキャフリーの『歌う船』のシリーズのような生体宇宙船に似ている)描かれている。いずれもその異質な世界観にもとづくテクノロジーの考察や、宇宙観がおもしろく、最近多くの賞の候補になっているドボダールだが、選ばれるのは、ほとんどこのシリーズのものだ。その根底にある、どうしてそんな世界になったのかという背景がはっきりと描かれている作品を読んでいただいたほうがわかりやすいのではないかと思い、ここでは現代に対応する部分を描いた本作品をご紹介した。初出は2009年にティドハーが編んだ、そもそもこの特集のきっかけを与えてくれたアンソロジーThe Apex Book of World SFだ。今年は初の短篇集が出たり、シリーズ3作の合本が出たりと、いかにも旬の作家を思わせる刊行ペースがつづく。ぜひ書籍の形でも紹介しておきたい作家である。