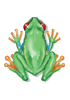オレンジ畑の香り
ラヴィ・ティドハー
屋上のソラー・パネルは内側にたたみこまれ、まだスリープ状態ながら、間近に迫った日の出を感知したかのように、落ち着きなく震動していた。ボリスは屋上の縁に立った。屋上は平らで、同じビルに暮らす父の隣人たちは、長年にわたってさまざまな植物を素焼きやアルミや木製の植木鉢に植えてここで増やし、屋上を高層ビルの熱帯植物園に変えていた。
ここまであがってくれば静かだし、いまならまだ涼しかった。彼は遅咲きのジャスミンの匂いが好きだった。それはビルの壁を這うようにしがみつきながら高く登り、セントラル・ステーションの周囲の旧市街に広がっていく。彼は夜の大気を大きく吸いこむと、ゆっくりと、つかえながら吐き出し、スペースポートの明かりをながめた。形はテルアヴィヴの砂地からそびえたつ砂時計のようで、亜軌道高度の発着便がゆっくりと離着陸している。星が動くように、夜空を彩る宝石の航跡を描きながら。
彼はこの匂いが、この町が好きだった。西に広がる海の匂い、あの潮と果てしない水の、海藻とタールの、日焼け止めローションと人々の匂いが。早朝のソラー・サーファーを見るのが好きだった。透明な翼を広げて風に乗り、地中海の上を飛ぶ姿が。窓からこぼれてくるエアコンの冷えた匂いが、指でもむと広がるバジルの匂いが、通りからたちのぼってくるシャワルマの、ターメリックやクミンを中心としたスパイスのいりまじる刺激的な匂いが、いまはもうテルアヴィヴやヤッファの市街からはずっと遠くまでなくなってしまったオレンジ畑の匂いが好きだった。
かつては一面オレンジ畑だった。彼は旧市街を見渡した。ペンキの剥げたむかしのソヴィエト様式の箱形アパートが壮麗な20世紀初期のバウハウス建築とごちゃまぜにひしめきあっている。曲線で作られた優雅な長いバルコニーと甲板を思わせる平らな屋根をもつ、船形のビルで、いま彼がたっているのもそんなビルのひとつだ――
古い建物にまじって新しい建築もある。火星様式の共同住宅で、エレベーター代わりに投下シュートがついていて、小さな部屋はなかでさらに狭い部屋に分けられ、大半が窓もなかった――
何百年も前から洗濯物は洗濯紐や窓から吊されている。色あせたブラウスやショーツがゆらゆらと風に揺られている。はるか下の通りに浮かんでいた光球はもう暗くなりはじめ、ボリスは夜が明けようとしているのを知った。地平線の縁にピンクや赤の色がさすのを見て、朝日が昇ろうとしていることがわかったのだ。
彼は一晩、父の通夜をしていた。ヴラド・チョンはウェイウェイ・ジョン(中国式に姓を先に書くと、鍾威衛だ)とユリア・チョン(旧姓ラビノヴィッチ)の息子だった。一家の伝統を守って、ボリスもロシア名をつけられた。また一家の別の伝統にのっとって、ユダヤ式のセカンド・ネームもつけられた。考えてみると、皮肉な笑みが浮かぶ。ボリス・アーロン・チョンか。3つの共通する古くさい歴史が彼のもう若くはない細い肩にのしかかっているのだ。
気楽な夜にはならなかった。
このあたりはかつては一面オレンジ畑だった……彼は大きく息を吸って、古いアスファルトと、いまだに残る内燃機関の排気ガスの臭いを嗅いだ。オレンジのようにいまはもう消えてしまったものの、なぜかまだ記憶に残る臭いだ。
彼は捨てていこうとした。家族の記憶を、ときどき自分のなかでは〈鍾家の呪い〉とか〈威衛の愚行〉と呼んでいるものを。
いまでも思い出せる。当然だ。遠いむかしのある日のこと。ボリス・アーロン・チョン自身がまだ思いつかれてもいないころ、自己ループがまだ形作られていなかったころのことを。
それはヤッファでのことだった。港を見おろす丘の上の旧市街だ。〈他者〉の地区だ。
鍾威衛は熱気に包まれて汗だくになりながら、坂道を自転車でのぼっていた。彼はこうした狭く曲がりくねった道を信用していなかった。旧市街のものも、ようやくその遺産をとりもどしたアジャミの道も。威衛はここをめぐって争奪戦がおこなわれたことをよく知っていた。アラブ人もユダヤ人もいて、同じ土地をほしがったので、戦いになった。威衛は土地のことも、そのためなら喜んで人が死ぬことも知っていた。
だが、土地という概念が変わることもわかっていた。土地などというものはもはや物理的なものというより、精神的な概念にすぎなかった。最近、彼は〈アシュケロンのギルド〉というゲーム世界のなかの全惑星系にお金を少し投資していた。彼ももうすぐ子供たちをもつようになるだろう――ユリアはすでに妊娠後期に入っていた――やがては孫、曾孫というように、何世代も続いていくが、みんな始祖である威衛のことは覚えているだろう。彼のしたことに感謝してくれるはずだ、現実と仮想と両方の不動産を残してくれたことに、そして、きょう彼が達成しようと望んでいることのために。
この鍾威衛が、分断されたこの地で王朝を興すのだ。何しろ、彼はもっとも根源的な面を理解し、彼だけがセントラル・ステーションという外国の飛び地の意味を見抜いているのだから。北にはユダヤ人(彼の子供たちもユダヤ人になるのだろう、そう思うと不思議で、落ち着かない気分になってくる)、南にアラブ人――もどってきたアラブ人はアジャミとメナシーヤをとりもどし、ニュー・ジャッファという空に向かってそそりたつ鋼鉄と石とガラスの都市を建設中だ。北にはアッコやハイファのように分断された都市、そして砂漠に続々誕生するネゲヴやアラヴァといった新しい都市もある。
アラブ人だろうとユダヤ人だろうと、みんな移民を、外国人労働者を必要としていた。タイ人やフィリピン人や中国人やソマリア人やナイジェリア人を。彼らがもたらす緩衝が、セントラル・ステーションという中間地帯が必要だった。旧南テルアヴィヴだった貧困地区、活気にあふれ――何よりも境界となってくれる場所が。
彼はそこを根城にするつもりだった。彼と子供たちと、子供たちの子供たちの故郷に。ユダヤ人もアラブ人も、少なくとも家族というものを理解していた。そういう意味では中国人といっしょだ――英米人とは違う。核家族で、人間関係はストレスがあり、みんな別々に離れて孤独に暮らしているのとは。そんなことを子供たちにさせたりはしない、と威衛は誓った。
丘のてっぺんで彼は自転車を止め、そのために用意してきた布のハンカチで額の汗をぬぐった。車が次々と彼を追い越してゆき、いたるところから建設中の槌音が響いてくる。彼自身もそこに建設中のビルの1つで働いている。集団移住(ディアスポラ)してきた、小柄なヴェトナム人や背の高いナイジェリア人や色白でがっしりしたトランシルヴァニア人の建設労働者が、手振りと小惑星帯ピジン語(まだ、このころはそれほど普及していなかった)と埋めこまれたノードの自動翻訳機能を駆使して、意思を伝えあっている。威衛自身はパワードスーツを利用して、その蜘蛛のような把握力で高層ビルのブロックをよじ登り、はるか眼下に広がる都市を観察しながら、海へ、さらにははるか沖の船へと視線を移した。
だが、きょうは休みの日だ。彼は貯金していた――毎月、成都の家族に送金し、もうじき増えていくことになるここの家族のためにも少し蓄えた。残りはここで使う。〈他者(アザー)〉たちに頼み事をするのだ。
ハンカチをていねいにたたむと、彼はせっせと自転車をこぎ、ヤッファの旧市街にあたる、迷路のようにはりめぐらされた細い路地に入っていった。古代エジプトの砦の遺跡はまだ残っていて、城門は1世紀前に修復され、吊り下げられたオレンジの木はいまでも卵形の重い石の籠に植えられて、鎖で城壁の陰に吊されている。威衛は足を止めずにこぎ続けて、ようやく巫女の場所に着いた。
ボリスは日の出をながめた。疲れてくたくただった。その晩はずっと父に付き添っていた。父のヴラドはもうほとんど眠ることはなく、何時間も肘掛け椅子に坐ったままだ。すり切れて穴だらけの椅子だが、もう何年も前のある日(ボリスの頭のなかではいまでも鮮明に思い出せる)、ヤッファの蚤の市から苦労して引っぱってきた、誇らしいものだ。ヴラドの手が宙をさまよい、見えないものを動かして並び替えている。そのヴィジュアル・フィードへのアクセスはボリスには与えてもらえなかった。もうほとんど意思の疎通がなかった。並び替えているのは記憶ではないかとボリスは思った。ヴラドがどうにかしてそれをつなぎあわせようとしているのだろうと。でも、たしかなことはわからない。
威衛と同じように、ヴラドも建設作業員だった。彼も完成前の巨大な骨組みに登って、セントラル・ステーションを建てた1人だった。その宇宙港もいまではそれ自体が一個の存在を主張し、テルアヴィヴとヤッファのいずれもが完全に支配することのできない、ミニチュア・モール国家となっていた。
だが、むかしのことだ。いまでは人間はずっと長生きするようになっているが、それでも心はやはり老いてゆき、ヴラドの心は肉体より老いていた。屋上で、ボリスは扉のわきの片隅にいった。ミニ椰子の木の作る日陰があったし、いまではソラーパネルも開いて華奢な翼を広げ、朝日の光を受けて、植物に日よけと傘の役を果たそうとしていた。
ずっと前に居住者組合がそこにテーブルとサモワールを設置し、週ごとに違う階が当番で紅茶とコーヒーと砂糖を出すことになっていた。ボリスは近くの鉢植えのミントの葉をそっとちぎって、紅茶を入れた。沸騰したお湯をマグにそそぐ音は心地よく、ミントのすっきりしたさわやかな香りがあたりに広がって、眠気も飛んだ。ミントが出るのを待って、マグを手に屋上の端までいって見おろした。セントラル・ステーションは――眠ることなどなかったのだが――音をたてて目覚めだしていた。
彼はお茶をすすり、巫女に思いをめぐらせた。
巫女の名前はかつてはコーエンといい、噂では〈他者〉の聖コーエンの親族だといわれていたが、誰もたしかなところは知らなかった。今日ではもうそんな噂もささやかれなくなった。何しろ、彼女は3世代にわたって旧市街に、あの暗く静かな石の館に暮らしていたのだ。彼女の〈他者〉とふたりだけで。
〈他者〉の名前やIDタグも知られていなかったが、それは〈他者〉に関してはふつうのことだった。
家系のつながりの可能性とは関係なく、石の館の外には聖コーエンをまつる小さな社があった。社といってもささやかなもので、金色をした雑多なものや、古い壊れた回路のようなものが適当に並べられ、四六時中蝋燭がともっていた。その扉の前にきて、威衛は社に向かってしばらく足を止めてから、蝋燭に火をともし、お供え物を置いた――むかしの故障したコンピュータ・チップで、丘の下の蚤の市で大枚はたいてあがなったものだ。
きょうの目標に達するようお力を貸してください、と彼は念じた。家族をひとつにし、私が死んだらわたしの心を引き受けてもらえるよう、お力をお貸しください。
旧市街に風はなかったが、古い石の壁からは心地よい冷たさが伝わってきた。威衛は最近になってようやくノードを装着していたので、呼び鈴を鳴らすと、ドアはすぐに開けてもらえた。彼はなかに入った。
そのときのことをボリスは静寂として覚えていたものの、逆説めいてはいるが、同時に移動の感覚もあった。突然の不可思議なパースペクティヴの変化が。頭のなかで祖父の記憶が光った。さまざまにポーズを装ってはいても、威衛は未知の国に挑む探検家に似て、感触と直感をたよりに進んでいた。彼はノードをつけて育ったわけではなかった。〈会話〉についていくのは大変だった。あの人間とマシンのフィードの際限ないおしゃべりも、それがなければ現代人は目も耳も奪われたようなものだった。だが、彼はさなぎが成虫になるときを感じとれるように、直感的に未来を感じとれるような人間だった。自分の子供たちが別の人間になることも、そしてその子供たちもさらに別の人間になっていくこともわかっていたが、同じくらい、過去がなければ未来もないこともわかっていた。
「鍾威衛」と巫女がいった。威衛は頭を下げた。巫女は驚くほど若く、ともかく見た目は若く見えた。黒髪をショートにし、顔には特徴がなく、肌は白く、親指は黄金の義手だったので、威衛は思わず身震いした。それが彼女の〈他者〉なのだ。
「願い事があります」と威衛はいった。ちょっと躊躇してから、小さな箱を差し出した。「チョコレートです」というと――気のせいだろうか?――巫女は微笑んだ。
室内は静かだった。それが〈会話〉のせいだと気づくのが一瞬遅れた。〈会話〉がやんでいたのだ。部屋は俗世間のネットワーク通信から隔絶されていた。隠れ家/隠遁地になっていて、〈他者〉の高度な暗号化機関で保護されているのだ。巫女は箱を受け取って、開け、慎重にひとかけ取って、口に入れた。しばらく考えるように噛んでから、首をほんの少し動かして、同意を示した。威衛はまたお辞儀した。
「どうぞ」と巫女はいった。「お坐りなさい」
威衛は腰をおろした。背もたれの高い椅子は古く、すり切れていた――蚤の市で買ったものだろうと思うと、不思議な気がした。巫女が露店で買い物をするなんて、まるで人間みたいじゃないか。だが、もちろん巫女だって人間だ。そう考えると、もっと気楽になれるはずなのに、そうはならなかった。
やがて巫女の目の色が微妙に変化し、聞こえてきた声も別の、さっきよりもしゃがれて低い声になったので、威衛はまた息を呑んだ。「われわれにどんな願いがあるというのだね、鍾威衛?」
彼女の〈他者〉だ、それがいましゃべっているのだ。人間の身体に相乗りする〈他者〉だ。巫女と合体して、あの金の親指のなかでは量子コンピュータが稼働している……威衛は思いきって、切りだした。「架け橋がほしいのです」
〈他者〉はうなずいて先をうながした。
「過去と未来のあいだにかかる橋です」と威衛はいった。「その……連続性が」
「不死か」と〈他者〉はいった。溜息がもれた。それは手をあげて顎をかき、金の親指が女の白い肌に食いこんだ。「人間はみな不死を求める」
威衛は首を振ったものの、否定はできなかった。死を、死ぬのだということを考えると怖かった。信仰が欠けているのはわかっていた。多くのものが信仰をもっていたし、信じることで人類はやっていけた。輪廻転生でも、死後の世界でも、アップロード神話でも、〈転写〉と呼ばれているものでも――どれも同じ、彼がもっていない信念が必要だった。もちたいとは思っていたのだが。死んでしまえば、それで終わりだとわかっていた。鍾威衛というIDタグをつけた自己ループはあっさりと、そのまま存在しなくなって、世界はそれまでのように続いてゆくのだ。そう考えるのは恐ろしかった、自分の無意味さのことを。人間の自己ループにとっては、それ自体が世界の中心であり、すべてがそこを中心にまわっている。現実とは主観的なものだ。とはいえ、それは幻想だった。わたしという幻想と同じように、人格とは何十億という神経繊維でできた合成装置で、人間の脳という灰色物質のなかで半独立的に作動する精妙なネットワークでしかないのだ。機械は補助にはなっても、それを保存することはできない。永遠という期間では。だから、そうなのだろう、と威衛は思った。彼が求めているのはむなしいことだ。だが、実行できることだ。彼は大きく深呼吸してから切りだした。「子供たちにわたしのことを覚えていてほしいのです」
ボリスはセントラル・ステーションを見つめた。いまでは宇宙港の向こうに太陽が昇り、下ではロボットニクたちが配置につき、毛布を広げて手書きのちゃちな看板を掲げて、部品のスペアやガソリンやウォッカをせびっている。あわれな連中だ。忘れ去られた戦争の名残で、サイボーグになった人間でありながら、必要がなくなると使い捨てにされたのだ。
ロボット教会のブラザー・R・パッチイットが巡回しているのが見えた――教会はそのささやかな人間信徒の世話を焼くように、ロボットニクを世話しようとした。ロボットは人間と〈他者〉のあいだの謎のミッシング・リンクで、どちらの世界にも属していない――物理的に肉体によって形作られたデジタル存在で、多くはそれぞれの不思議な信念により、〈アップロード〉を拒否していた……ボリスはブラザー・パッチイットを子供のころから知っていた――ロボットは割礼師(モーヘール)を兼ねていて、地域のユダヤ人の男子に誕生から8日目に割礼をほどこした。誰がユダヤ人になるかという問いは鍾家だけの問題ではなく、ロボットの側の問題でもあり、とっくに解決をみていた。ボリスには断片的な記憶しかなかった。母方からのもので、威衛より前のものだ――エルサレムでの抗議運動や、マット・コーエンの研究所と最初の原始的な培養地。あそこではデジタル存在が非情なまでのサイクルで進化していた。
キング・ジョージ通りではプラカードが打ち振られていた。〈隷属拒否!〉とか〈強制収容所を破壊せよ!〉とかいったもので、怒れる人間の群衆が最初の脆弱な〈他者〉を閉鎖ネットワークに隷属させようとしていることに抗議して集まっているのだ。マット・コーエンの研究所は包囲されていた。そこで働く科学者は、次々に国を追われてようやくエルサレムに身を落ち着けることのできた、寄せ集めの学者だというのに。
彼はいま、〈他者〉の聖コーエンと呼ばれていた。ボリスはマグを口につけてから、中身が空になっていることに気づいた。カップをおろして目をこする。寝ておくべきだった。もう若くないのだし、何日も不眠不休で、刺激物とじっとしていられない若さというエネルギーのおかげで動けていたころとは違うのだ。ミリアムといっしょにこの同じ屋根の下で手に手を取りあい、そのころですら守れないとわかる約束をかわしてひっそりと隠れていたころとは……
いま、彼女のことを考えて、彼はセントラル・ステーションの古いパビリオンのネーヴェ・シャアナンを歩く彼女の姿を探した。そこに屋台を出しているのだ。彼女のことを考えるのはつらかった。こんなふうに、少年時代のようにせつなくなるなんて。帰ってきたのは彼女のためではないとはいえ、心のどこかではそうだったのかもしれない。その思いが……
首筋では補助体(オーグ)が静かな吐息を漏らしていた。火星の丹雲市であがなったものだ。アラファト街から引っ込んだ裏通りの中国系火星人三世の名前もないクリニックで、院長の王(ウォン)氏が装着してくれた。
ミクロバクテリウムに似た火星生命体の化石化した残滓から培養したということだったが、本当のことかどうかは誰にもわからなかった。オーグを着けているのは不思議な感じだった。寄生体で、ボリスから養分を取り、首でそっと脈動しながら、いまでは彼の一部となっている。付属肢がもうひとつ増えたようなもので、異星の考えと異星の感覚を与えてくる一方、また逆にボリスの人間的な見方を取り入れて、微妙に変化させている。おかげで、自分の考えが万華鏡のフィルターをとおってくるような感じがした。
彼は手をオーグにあて、温かく驚くほどざらざらした表面の感触をたしかめた。それは指の下で動き、そっと息をしていた。オーグはときとして不思議な物質を合成することがあり、それはボリスの体内システムにドラッグのような作用をもたらして、驚かす。視覚の距離感に作用することもあり、ボリスのノードに干渉してくることもある。ノードとは彼の脳のデジタル・ネットワーク・コンポで、生後まもなく装着され、それがないと視覚や聴覚を奪われるより悲惨で、〈会話〉から切り離されてしまうのだ。
逃げようとしたことはわかっていた。家を出て、威衛の記憶から逃れたというか、しばらく逃れようとしたのだ。セントラル・ステーションにきて、エレベーターでてっぺんまで昇り、その先にまで向かった。地球を離れ、軌道も離れ、小惑星帯(ベルト)に、さらには火星にいったものの、記憶は追いかけてきた。威衛の架け橋は永遠に過去と未来とをつないでいた。
「わたしが死んでも、記憶には生きつづけてもらいたいんだ」
「人間はみなそうだ」と〈他者〉がいった。
「わたしは……」勇気をふるいおこして、彼はつづけた。「家族に覚えていてもらいたいんだ」と彼はいった。「過去から学んで、未来への計画をたてるために。子供たちにわたしの記憶を残してやりたいし、そうやって子供たちの記憶も引き継がれていってほしい。孫たちやそのまた孫たちというようにずっと、未来永劫にわたって、このときを覚えていてもらいたい」
「そうなるだろう」と〈他者〉はいった。
そうなったのだ、とボリスは思った。記憶は彼の心のなかでは鮮明で、水滴のように完全で不変だった。威衛の望みはかない、彼の記憶はいまではボリスのものであり、ヴラドのも、祖母ユリアのも、母のも、残りみんなの記憶もそうだった――従弟も、姪も、伯父も、甥も、叔母も、誰もが鍾一族の中央記憶プールを共有し、誰もが瞬時にその深い記憶の池にもぐって、過去の大洋に乗り出せるのだ。
威衛の架け橋、と一家のなかではいまでも呼ばれていた。おかしな働きをすることもあって、ずっと遠くにいても、彼がセレスの出生クリニックで働いていたときも、火星の丹雲市の通りを歩いていたときも、不意に頭のなかに記憶が、新しい記憶が形成されたことがある――従姉のオクサーナが小楊を産んだときの初産の記憶――苦痛と喜びに脈絡なくさまざまな思いが入り混じっていた。誰か犬に餌をやってくれただろうか、と思いながらも、医者は「いきんで、いきんで!」と訴え、汗の臭いや、モニターのピッピッという音がし、ドアの外では人々が声をひそめてしゃべり、そして赤ん坊がゆっくりと出ていくあの何ともいいようのない感覚が……
彼はマグを置いた。眼下のセントラル・ステーションはいまや目覚め、付近の露店には真新しい農産物が並び、市場は喧噪と煙草と焼き串でゆっくりと鶏が焼ける匂いと通学の子供たちの叫び声でにぎわっていた。
彼はミリアムのことを思った。いまはジョーンズおばさんと呼ばれている。父親はナイジェリア人で母親はフィリピン出身だ。世界は若く、2人は愛し合っていた。子供のころの母語だったヘブライ語で愛し合ったが、2人のあいだを裂いたのは洪水でも戦争でもなく、ただ生活であり、それが人に及ぼす作用によってだった。ボリスはセントラル・ステーションの出生クリニックで働いていたが、そこには思い出が多すぎた。幽霊のような思い出で、とうとう彼も反発し、セントラル・ステーションに赴くと、そこをのぼり、再使用型宇宙往還機(RLV)に乗って地球周回軌道にあがり、〈ゲイトウェイ〉と呼ばれる場所にいくと、そこからまずルナ・ポートに旅立った。
彼は若く、冒険がしたかった。逃れようとして、ルナ・ポートや、セレスや、丹雲にいったものの……記憶は追いかけてきて、なかでも最悪だったのは父の記憶だった。それはにぎやかな〈会話〉を縫って彼を追いまわし、圧縮された記憶が次から次へと〈鏡〉に反射し、光速で宇宙空間を越えてきた。おかげで彼が向こうで彼らのことを忘れられなかったように、ここ地球でも彼のことを忘れてくれなかったので、とうとう彼もその記憶の重みに耐えかねてもどってきたのだ。
それが起きたとき、彼はルナ・ポートにもどってきていた。歯を磨きながら、顔をしげしげと見つめていると――若々しくも年老いてもいない、どこにでもある顔で、目は中国人、顔立ちはスラヴ系で、生え際は少し後退している――記憶が彼を襲い、彼を満たした――歯ブラシが落ちた。
父の記憶ではなく、甥の楊のだ。ヴラドはアパートの椅子に坐っていた。父はボリスが覚えているより老けて痩せていて、漠然とだが何かが宇宙空間を越えて届き、彼の胸を締めつけ、苦しめた――父の目の色を曇らせている何かだ。ヴラドは坐ったまま、押し黙り、甥や訪ねてきたほかのものにも挨拶は返さなかった。
坐りながら、手が宙にさまよい、誰にも見えないものを並び替えた。
「ボリス!」
「楊か」
甥がおずおずと微笑む。「現実とは思えなかったよ」
時間差が月と地球を、ノードからノードへと往復するために生じていた。「大きくなったな」
「ああ、そうだね……」
楊はセントラル・ステーションで働いていた。第5層にあるウイルス広告を作る研究所が職場で、空中にひろがって人から人へと感染するその微小媒介物はセントラル・ステーションのような空調された密室環境で増殖し、特定の個人に向けられたオファーを提供するように暗号化された、ノード装置とインターフェースのある有機物であり、ひたすら「買え、買え、買え」と叫んでいる。
「お父さんのことだけれど」
「何かあったのか?」
「わからないんだ」
そう認めるのは楊にとってつらかっただろう。ボリスは待った。沈黙が周波帯を呑みこんだ。地球・月間の帰路の沈黙が。
「医者には診せたのか?」
「診せたことはわかっているよね」
「それで?」
「医者にもわからない」
沈黙が2人のあいだに、光速で宇宙空間を進みながら広がった。
「帰ってきてくれ、ボリス」と楊はいった。ボリスはあの子が大人になっていることに驚いた。そこにのぞく大人の男性は彼が見知らぬ他人だが、その人生ははっきりと思い出せた。
帰ってきてくれ。
その日のうちに、彼はわずかばかりの身の回りのものをまとめ、リブラを出て、シャトルで月軌道に向かい、そこから船で〈ゲートウェイ〉までいって、ようやくセントラル・ステーションにまで降りてきたのだ。
癌の成長を思わせる記憶。ボリスは医者であり、〈威衛の架け橋〉をその目で見ていた――その不思議な半有機的成長体は鍾の大脳皮質に入りこみ、2人の灰白質に入りこんで、ノードとのインターフェースを築き、成長する。異物質の不思議で精妙な螺旋であり、禁断の進化したテクノロジーである。〈他者〉だ。それは父の精神から成長して、どういうわけか制御がきかなくなり、癌のように成長して、ヴラドはその記憶のせいで動くことができなかった。
ボリスも推測はしていたものの、つきとめることはできなかった。この願い事に威衛がどれだけ支払ったのか、どれだけそれが高くついたのかわからなかったように――その記憶、その部分だけはすっかり消去されていた――ただ〈他者〉がそうなるだろうといっただけで、次の瞬間にはもう、威衛は外に出され、扉は閉ざされていた。彼は眼をぱちくりさせながら、古い石壁の前で、はたして願いはかなったのかどうかと考えた。
かつて、ここは一面のオレンジ畑だった……そう思ったのを思い出した。彼は地球帰還後、セントラル・ステーションのドアを出て、重力にとまどい、不快感を味わいながら、外の蒸し暑い大気のなかに入った。庇の下で足を止め、深呼吸をする。重力に押しつぶされそうになっても、気にしなかった。覚えていたとおりの匂いで、もうなくなっているかどうかに関係なく、オレンジはいまでもあった。ここがテルアヴィヴでもセントラル・ステーションでもなく、そのすべてが存在していたころに生えていた有名なヤッファのオレンジ畑だ。ひたすらオレンジ畑と砂と海が広がり……
彼は足が向くまま道路を渡った。足には記憶があり、セントラル・ステーションの大玄関から旧市街の中心部にあるネーヴェ・シャアナンの遊歩道に渡ると、そこは記憶よりはるかに狭くなっていた。子供のころは全世界に思えていたのに、いま見ると……
人々があふれ、ソラーパワーのトゥクトゥクが道を走り、観光客はうっとりと見とれ、記録員(ミームコーディスト)は見たり聞いたり感じたりするすべてをネットワークで放送しながら、そのフィードの数値をたしかめていて、一瞬、ボリスをとらえた画像が太陽系の何百万という無関心な視聴者に送られた――
スリもいれば、退屈顔のCS警備員も目を光らせ、片目を失い胸にひどい錆を浮かせたロボットニクは物乞いをし、黒ずくめのモルモン教徒は猛暑に汗を搔きながら、パンフレットを配り、道路の反対側ではエルロン教団も同じことをしている――
小雨が降りだした。
近くの市場の売り子たちがとりたてのザクロやメロンや葡萄やバナナを勧める声、その先のカフェでは老人たちが小さな陶器のカップで苦いブラックコーヒーを飲みながらバックギャモンに興じ、ナルギーラをくわえている――羊革製の水パイプだ――R・パッチイットは喧噪のなかをゆっくりと歩く。やかましく汗臭い人だかりのなかにあって、ロボットは平安のオアシスだ――
光景や匂いや音や、思い出に夢中で、最初は気づかなかった。道路の反対側にたっている女と子供に、あわやぶつかってしまいそうになるまでは――
ぶつかってきたのは向こうのほうからだったかもしれない。浅黒い肌をしてとびっきり青い眼をした男の子――女のほうはどことなく見覚えがあり、たちまち彼は不安になった。男の子は期待にあふれて訊ねた。「ぼくのパパなの?」
ボリス・チョンは大きく息をついた。女がいった。「クランキ!」怒りと心配がいりまじった口調だった。それが少年の名前かあだ名だろうとボリスは思った――アステロイド・ピジン語で“クランキ”というのは気むずかしい、奇人、変人を意味していた。
ボリスは少年のわきにひざまずいた。周囲のせわしない動きは忘れ去られていた。彼はその目をのぞきこんだ。「そうかもしれない」と彼はいった。「その青なら知っている。30年前には流行っていたからな。わたしたちはアルマーニの商標登録されたコードからオープンソース版を作ったんだ」
ごまかしだな、と彼は思った。なぜこんなことをしているんだろう? その女が、彼女に見覚えがあることが、気になってしかたなかった。頭のなかを見えない蚊のように唸りをあげて、オーグから映像がどんどん形になって押し寄せてくる。男の子は脇で凍りつき、笑顔を向けてくる。どぎまぎさせるような満面の、訳知り顔の笑みだ――
女が叫んでいる。遠くからでも彼には聞こえた。「やめなさい! 彼に何をしているの?」
男の子はわたしのオーグとのインターフェースをとっているんだ、と彼は気づいた。わっと言葉があふれ出た。「きみには親はいないよ」と彼は男の子に告げた。記憶に恥ずかしさがいりまじった。「きみはここで合成されたんだ、公開されているゲノムに闇市場で入手したノードを少しまぜて作られたんだ」彼の精神にしがみついてくる男の子の力が弱まった。ボリスは息をついて、背筋を伸ばした。「ナカイマスだ」といって、急に恐怖がこみあげ、彼は後ずさりした。
女はおびえ、怒っていた。「やめて」と彼女はいった。「そんなんじゃないわ――」
ボリスは急に恥ずかしくなった。「わかってる」とまどい、面食らっていた。「悪かった」感情がせめぎ合い、急速にいりまじっていくのは自然ではなかった。どうやったのか、男の子はオーグにアクセスし、オーグはボリスの精神に入りこんできた。彼は集中しようとした。女を見た。なぜか、彼女にわかってもらうのがだいじなことに思えた。「この子はわたしのオーグに話しかけられるんだ。インターフェースをつながなくても」そのとき、クリニックのことが、そこを出て宇宙に去る前に彼自身がやったことが思い出せた。彼は静かにいった。「思ったより、あのときの仕事はうまくいったということか」
男の子はあどけない青い目で彼を見つめた。そんな子供たちのことをボリスは思い出した。大勢の、本当にたくさんの子供を作ったのだ……セントラル・ステーションのクリニックは雲南省のそれと比肩するとさえいわれたものだ。だが、ここまでは予想していなかった。小惑星帯や丹雲で、噂は耳にしていたけれど、こんな干渉ができるとは。向こうで噂話に囁かれていた言葉がかつて黒魔術を意味したナカイマスだった。
女は彼を見つめ、その目に彼は気づいた――
2人のあいだに何かが、ノードもデジタル・エンコードも必要のない、もっとむかしの、もっと人間的で素朴な、ショックにも似た何かがかわされた。「ボリスなの? ボリス・チョン?」
彼も彼女と同時に気づいた。驚きが懸念に取って代わり、女の正体に気づかなかったことへの、その驚きも、不意にこの女性のいる同じ空間を2つの身体が占めているような感じへと移り、その年齢不詳の像がまだ世界が若かったころの若い女性へと形をとった。
「ミリアムなのか?」と彼はいった。
「わたしよ」
「でも、きみは――」
「わたしは離れなかったわ」と彼女はいった。「いってしまったのはあなたのほうよ」
いますぐ彼女のところにいきたかった。世界は目覚め、ボリスはひとり古いアパートの屋上にいた。ひとりきりで自由ではあったけれど、記憶がつきまとっていた。父をどうすればいいかわからなかった。むかし、まだ小さかったころ、父と手をつないだことを覚えている。ヴラドはとても大きく、自信にみち、堂々として、生気にあふれているように見えた。その日、2人は海に出かけたのだ。よく晴れた日で、メナシーヤ地区ではユダヤ人もアラブ人もフィリピン人もいっしょにまじわり、ムスリムの女性は黒衣をまとい、子供たちは下着姿で歓声をあげながら駆けまわっていた。テルアヴィヴの女性は小さなビキニ姿で、静かに日光浴し、誰かが吸う強烈な大麻の匂いが潮の香りにまじっていた。ライフガードが監視所から3カ国語で呼びかける――「安全区域から出ていかないでください! 迷子のお子さんに心当たりの方は? 至急、ライフガードのところまでおいでください! そこのボートはテルアヴィヴ港方向に向かって、遊泳区域から出ていってください!」――さざめきのなかにその声は埋もれ、誰かが車を止めると、ステレオからやかましいビートが響きだす。遊歩道わきの芝生ではソマリア人難民がバーベキューをしているし、ドレッドロック頭の白人男性はギターを弾いている、そんななか、ヴラドはしっかりと守るようにボリスの手を引いて、水に入った。ボリスは何も怖くないと思った。いつだって、何があろうと、父がいつもいて守ってくれるのだ、と。
(訳:小川隆)
*Clarkesworld誌掲載の同作を底本としています。
解説
ラヴィ・ティドハー(Lavie Tidhar)は1976年生まれのイスラエルのSF作家。執筆はほとんど英語で、ノヴェラGorel and the Pot Bellied Godで2012年の英国幻想小説賞を受賞したほか、多くのSF賞の候補に繰り返し選ばれている気鋭の新人である。邦訳は「ストーカー・メモランダム」(小川隆訳)が〈SFマガジン〉2012年7月号に掲載されている。掲載作はウェブジン〈クラークスワールド〉2011年11月号に掲載された。いま作者はこのセントラル・ステーションを舞台にした連作短篇を雑誌〈インターゾーン〉などで精力的に発表している。(小川隆)
追記:この作品は2020年9月に竹書房より刊行された『シオンズ・フィクション イスラエルSF傑作選』に収録されています。(26to50)