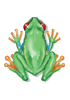鶴の群れ(前篇)
ベンジャミン・ローゼンバウム
マリシュは生い茂る向日葵(ひまわり)の緑色の茎に囲まれていた。人の背丈ほどもある茎の先には、晴れがましい黄色の花が咲いている。大きな葉は血で黒く染まっていた。
葉っぱをかきわける音が聞こえた。マリシュは足の痛みをこらえてしゃがみこみ、様子をうかがった。一匹の針鼠(はりねずみ)が向日葵の茎を鼻先でかきわけて姿を現し、右に左に鼻をくんくん言わせた。
マリシュの胃袋がうずいた。まるで棒の先でじりじり突かれているようだった。かれこれ三日間、何も口にしていない。わが家が破壊され、焼きつくされているのを発見した日以来、何も。
針鼠は緑の茎のあいまをせわしなく進み、やがて踏みにじられた向日葵と燃えがらの道に出た。マリシュはじっと待ちかまえ、それがとうとう向日葵の茂みから姿を現すと、勢いよく飛び出した。そして片足をその鼻先に、もう一方を尻尾のすぐ後ろに着地させ、針鼠の逃げ道を断った。はたして針鼠は体を丸め、全身の棘を逆立てた。
ふと思い出した――まるで卵のようにぐしゃりと潰され、黒煙をあげていたわが家。藁敷きの床は血の海ができていた。その光景を前に、彼は獲物の兎を片手からぶらさげたまま、恐ろしいほどの静けさのなか、独り呆然と立ちつくした。何とか声をふりしぼって妻のテムールと娘のアスザの名を呼んだが、それは虚しい絶叫となって響くだけだった。彼は焼きつくされた破壊の轍(わだち)を無我夢中で走りだした。兎をどこかに落としてしまったことにも気づかなかった。
三日三晩走り続けてきた。水溜まりの水を飲み、やむをえず睡魔に屈する時は向日葵の茂みのなかで眠った。
マリシュは針鼠の真上にナイフをかざした。お伽話にはよく、不思議な力を持つ針鼠が出てくる。「言葉を話せるなら話せ」彼は言った。「殺されたくなかったらそう言ってみろ。おれの望みを叶えてくれ! さもないと晩飯にしちまうぞ」
針鼠は何も言わなかった。あるいは、体をぴくっと震わせたかもしれない。
マリシュは針鼠の体にナイフを突き刺した。針鼠はのたうちまわり、血まみれの向日葵に、さらに血をまき散らした。
もう火を熾す力もわいてこなかった。彼はそれを生のまま食べた。
痛めつけられた大地の道は、ゆうに二十頭の馬が横並びに走れるほどの幅があった。焼かれ、踏みしだかれた向日葵の残骸のなかに、マリシュは子供の手のひらほどの大きさの、ぼろ布でできたちっぽけな人形を見つけた。
おつむの弱い(マッド・ガール)マグドが作ったものだ。彼女は手作りの人形と引き換えに切り落としの肉をせがんだり、レズールのパン屋の裏口で硬くなったパンをせしめようとした。彼はかつて銅貨一枚で人形を買ってやったことがある。
「どうしてあんな薄汚い娘にわたしたちのだいじなお金をやったりするの?」テムールは声を荒げ、きれいな瞳にするどい光が宿った。イルマク・デールの村人は、決してマッド・ガールに手を差しのべようとはしなかった。それどころか通りすがりに唾を吐きかける者もいた。「ぶすの(バッグ)マグドは逆さにふってもぼろしか出さん」酒場への道すがらにファッツが囃したてると、みんな声をあげて笑ったものだ。マリシュも一緒になって笑いはしたが、ふり返って彼女を見る時にはふと笑顔を消した。
結局、テムールの怒りはおさまった。アスザが人形をいたく気に入ったのだ。彼女はそれを胸に抱いて歌を歌ってやり、オートミールを食べさせようとしては、指でぼろ布の口になすりつけた。両親が自分のことを「愛しい灯(ともしび)」と呼ぶのを真似して、腕に抱いた人形に「いとちいともちび」と呼びかけもした。
彼は人形に鼻を押しつけ、愛しいアスザの匂いを嗅ぎとろうとした。牛乳と森の土と芳しい香辛料がまじったような、あの子の匂い――だが、嗅ぎとれるのは焼け焦げた布きれの、鼻をさす悪臭だけだった。
あふれてくる涙をこらえて目を上げると、ぼんやりとした人影がこちらに向かってくるのが見えた。彼は油断した自分を呪いながら人形を投げ捨て、ナイフを抜いて体の脇に構えた。袖口で顔を拭うと、決して屈することのないイルマク・デールの民の英姿を見せつけるようにすっくと立った。だが、やがて口のなかが干上がり、髪の毛が逆立った。こちらにむかって来るのは、人間ではなかった。
背丈はふつうの大人の男よりもやや高いくらいだ。濃い灰色の毛に覆われてはいるが、胴体は人間のものに見える。だが頭はどうみてもジャッカルの頭だ。身につけているのは青銅と革でできた甲冑で、留め金や円盤状の金属板には凝った彫り物がほどこされている。手にしているどっしりした黒い槍の両端には、鋭い刃が禍々しく光っている。
この世にはありとあらゆる種類の奇妙な人種がいるとは聞いていた。だが、こんな珍妙なものを目にするのは初めてだった。
「大いなる苦痛をもて死に至れ」その生きものは妙に落ち着いた、親しみのこもった口調で言った。
「貴様こそ今すぐ地獄に落ちろ!」マリシュは声を荒らげた。脅しにひるんでいるとは思われたくなかった。
その生きものは重々しくうなずいた。「私は虚都(エンプティ・シティ)のカダス=ナーン」生きものは続けた。「ひとつきみの力を貸してもらいたいのだが」 マリシュはどう答えていいのかわからなかった。その生きものはじっと返事を待っていた。
やがてマリシュは口を開いた。「言ってみろ」
「私はその、ぜひとも話をしたいのだ……」生きものは眉間に皺を寄せて言った。「どう言えばいいものか。気分を害させたくはないのだ」
「それならどうして」マリシュは思わず口走った。「苦痛のうちに死ねなんて脅したんだ?」
「脅すだって?」それは言った。「挨拶しただけだ」
「『大いなる苦痛をもて死に至れ』って言ったじゃないか。脅しか罵倒にしか聞こえなかったぞ。そんなことを言われてもうれしくもなんともない」
その生きものは眉をひそめた。「いや、これは祝福の言葉だ。厳密に言えば、祝福の言葉の一部だ。『大いなる苦痛をもて死に至れ。聖なる戦慄と神なる恐怖を知れ。卑小なる思考と幻想を脱ぎ捨て、骨白の父祖に見(まみ)えるに備えよ。さらば汝栄光のもとに葬られ、その名忘らるるまで讃えられん』というのが全文だ」
「それは……」マリシュは言った。「まあ、ちょっとはましに聞こえるが」
「われわれはこれを幼犬の時分に教えこまれるのだが」その生きものは意外そうに言った。「初めて聞いたのか?」
「当たり前だ」マリシュはそう言って構えていたナイフを下ろした。「それで、何をして欲しいんだ? 大して役に立てるとは思えないが――おれはこの土地の者じゃないからな」
「では無礼を承知で言わせてもらおう。死体処置人か埋葬人か、ともかくその筋の専門家と話がしたいのだ」
「そいつらが何なのか、おれにはさっぱりわからんな」マリシュが言った。
その生きものは目を大きく見開いた。ジャッカルの顔に表情というものが浮かべられるかぎりで精いっぱい、信じがたい事実を徐々に受け入れていく者の表情を浮かべた。
「きみの故郷では死者をどう扱っているんだ?」それは言った。
「土に埋めるのさ」
「何らかの準備をするだろう? 儀式や記念碑は?」
「木の箱を用意できる者はそれに入れて葬ってやる。できない者は亜麻布にくるんでやる。そして西風に祈りを捧げる。石も一緒に入れてやるな。死者の魂はその石に宿ると言われているから」彼はしばし考えこんだ。できることならこんな話はしたくなかったが、袖口で鼻を拭って続けた。「墓に石を積むこともある。村の名士なんかの場合にはな」
ジャッカルの頭をした男は弱り果てたように地面にしゃがみこみ、両手で頭を抱えた。しばらくしてやっと口を開いた。「どうやらここできみを殺して、正しい埋葬の仕方を教えなくてはいけないようだ」
「やってみろ」マリシュはふたたびナイフを構えた。
「そうして欲しいのか?」それは顔を上げて言った。
ひどく落ち着いた顔つきだった。マリシュが思わず目をそらすと、視界に向日葵の茎に絡まった、焼け焦げたぼろ布の人形が映った。
「すまない」エンプティ・シティのカダス=ナーンは言った。「誘惑するようなことを言うべきではなかった。きみにも果たすべき務めがあるようだ。大いなる虚(エンプティネス)への帰還を許可される前にな。きみの村がどこにあるか教えてくれ。この目でたしかめてこよう」
「おれの村は――」マリシュの目の裏が熱くなり、こみ上げてくる嗚咽で喉が締めつけられた。だが彼は必死でそれを飲みこんだ。「村はなくなった。何かがやってきて、踏み潰していった。おれが狩りに出かけているあいだのことだった。帰ってきたら、何もかもが火に包まれていて、そこらじゅうに血の匂いがたちこめていた。この道は、その何かが向日葵の野を踏み潰して進んでいった跡なんだ。そいつはものすごい速さで進んでいる。追いつけるかわからない。だが、おれはあきらめない」一介の農民が悪魔を追うなど、何をたわけたことを言っているのだと思われるだろう。マリシュは悔しさに奥歯を噛みしめた。
「なるほど」その奇怪な生きものは言った。「それはどこからやってきたのだ? 北からか?」
「どこからでもない。おれの村が突然めちゃくちゃになって、そこから道が伸びているんだ」
「死体は――」カダス=ナーンは慎重に口を開いた。「彼らの亡骸は――木の棺に入れてやったのか?」
「死体なんてない」マリシュは言った。「村人の死体なんてどこにもないんだ。一面の血の海と骨がいくつか残されているだけで、あとは黒焦げになった豚や馬の死体が散らばっているだけだった。だからこうして追っているんだ」彼はうつむいた。「そのうちみんなを見つけ出してやる」
カダス=ナーンは眉をひそめた。「こういうことはよくあるのか?」
マリシュは思わず吹き出してしまった。「まさか。後にも先にもこれが初めてだ」
ジャッカルの頭をした生きものは身を乗り出した。「では、死体が正しく――きみが何を正しいと思っているかはさておき――埋葬されたかどうかもわからないというんだな」
「そんな丁重な扱いを受けているとは思えない」マリシュは答えた。
カダス=ナーンは村の方角をふり返り、それからマリシュが向かおうとしている方角を 見やった。やがてその顔に決意の表情が浮かんだ。「どうだろう。私がきみの旅に同行すると申し出たら、受け入れてくれるだろうか」それは言った。「私には私の務めがあるが、どうやらきみの務めの方が……より重大なもののようだ」
マリシュはその生きものが携えている大槍をまじまじと見て、やがて口を開いた。「いいとも」彼は手を差し出して言った。「イルマク・デールのマリシュだ」
道をたどっていくと、またひとつ破壊された村に行き当たった。いたるところに血の海ができているが、村人の死体はひとつも見当たらなかった。家屋の木材は粗朶(そだ)さながらに粉々に打ち砕かれていた。マリシュは鍛冶屋の金床がまるで巻き毛のようにねじれ、鋤が高熱に溶かされ、鉄の水溜まりと化しているのを見た。彼らはその村を越え、折れ曲がった山査子(さんざし)の木陰で夜を過ごした。野を渡る秋風がふたりのまわりの草地をなで、蒲公英(たんぽぽ)の種と、かすかな煙の匂いと、家畜の死体の腐臭を運んできた。
次の日の夕方、彼らは川沿いの小高い丘にたどり着き、頂上から川沿いに広がる大きな町を見下ろした。マリシュはこんなにたくさんの建物を見たのは初めてだった――あまりに多すぎて数えきれない。ほとんどは彼の村の家屋と同じように木や泥でできているが、なかには石でできた立派な建物もあり、三層にも四層にも重なって空にそびえている。家の上に家が建てられ、下から上の階の戸口には梯子がかけられているようだ。町のまわりに広がる麦畑では、生い茂る麦穂が夕暮れの光を浴びて金色に波打っていた。農民たちがそこで労働歌を口ずさみながら大鎌を振るっているのが見えた。
破壊の轍はまるでこの町を避けるように、町の外壁に沿って曲がっていた。
「この町の防御がよほど固かったと見える」カダス=ナーンが言った。
「たぶんな」マリシュはうなずいたものの、どろどろに溶けた鉄と粉々になった木材をふと思い出して、首をかしげた。「ここはナブズの町だろう。おれはこんなに南に来たのは初めてだが、商人たちはハルデの市(いち)からこっちの方角に向かっていったものだ。ナブズに仕入れにいくと言ってな」
「きっと敵について何か教えてくれるにちがいない」カダス=ナーンが言った。
「おれが行く」マリシュは言った。「あんたが行くと騒ぎになるかも知れん。ナブズにはあんたみたいな客はそうそう訪れないだろうからな。ここで待っててくれ」
「ひとつ頼んでもよければ……」
「もし親切な人たちだったら、彼らの埋葬の仕方を聞いてくるよ」マリシュは言った。
カダス=ナーンは重々しくうなずいた。「されば、使命と死に赴かん」
きっとこれも祝福の文句なのだろう。それでもやはり、マリシュは背筋が冷たくなるのを感じた。
日が傾きつつあった。農民たちは馬車に麦穂の束を高く積み上げ、ゆっくりと低い声で歌いながら畑を後にした。町の門が開き、彼らを迎え入れた。
町の周囲には、石や木や泥でできた外壁がめぐらされていた。人間の背丈の倍ほどの高さがあり、大きな門は鉄製だった。だが、完璧な防壁というわけではなさそうだ。マリシュは背の高い草むらのあいだをぬって、外壁のやや低いところに向かった。ごみと瓦礫の山が、その壁にもたれるように積まれていた。
馬車がきしむ音が門を通り過ぎ、農民の歌声が小さくなっていった。ナブズの農夫たちは大声で挨拶を交わしながらそれぞれの家に消えてゆき、やがて通りは静かになった。
マリシュは草むらから這い出して全力で走った。がれきの山をよじ登って外壁に飛び乗り、平らな壁のてっぺんに腹這いになった。そして誰にも見られていないことを祈りながら、そっと町のなかをのぞきこんだ。
玉石の敷かれた通りには人影がなかった。いや、町全体が静まりかえっていた。イルマク・デールのような小さな村でさえ、夕暮れどきは騒々しいものだ。犬は吠えたてるし、豚がやかましく鼻を鳴らす。男たちは町角で声を張り上げて議論し、女たちは噂ばなしに花を咲かせ、あるいは軒先で子供たちの名前を呼ぶ。ナブズは酒と女と喧嘩の都(みやこ)のはずだ。ハルデの商人たちはいつも南の大都会に待ち受けている歓楽のことを――田舎者からうまいこと巻き上げた金で得られるお楽しみのことを――うっとりしながら話していた。なのに驢馬のしわがれた鳴き声も赤ん坊の泣き声も、咳払いも囁き声も聞こえてこない。町にはただ夜の静寂が広がっているだけだった。
彼は外壁のてっぺんから飛び降り、できるだけ音をたてないように着地すると、通りの端を忍び歩きはじめた。十歩も歩かないうちに、その光に気づいた。
家々の窓からちらちらと光がもれていたが、どうやらロウソクの灯りでも暖炉の灯りでもなさそうだった。それは冷たく青い光だった。
彼は頑丈そうな木箱を引きずっていちばん近くにある家の高窓の下に運ぶと、それを踏み台にしてなかをのぞきこんだ。
ぼさぼさの顎髭を生やした太った男が見えた。仕事を終えた陶器職人だろうか。傍らに妻とおぼしき肉づきのよい若い女と、九歳か十歳くらいの骨ばった男の子が見えた。木製の長椅子に腰かけているが、夕食は済んだようで、食器は脇にどけられていた(焼きたてのパンの匂いに、マリシュの胃袋が暴れ出した)。たしかに呼吸はしているが、彼らの顔に生気はなく、目を大きく見開いたまま、くちびるをかすかに動かしていた。その彼らに青い光が降り注いでいた。陶器職人の妻は、赤ん坊をあやすように腕をゆっくりと揺らしていたが、抱いている毛布のなかは空っぽだった。
ふとマリシュの耳に不気味な声が響いた。かろうじて聞き取れるような、無機質な低い声で、まるで自分の頭のなかで響いているようだった。その声は青い光の点滅にあわせてマリシュに語りかけ、彼はいつのまにかその囁きに引きこまれていった。陶器職人の一家の食卓にまぜてもらったらどうだ? 彼らはきっと迎え入れてくれるはずだ。ここにとどまればいいじゃないか――声は囁いた――故郷の村など忘れてしまえ。悲しみなど忘れてしまえ。炉辺で焼きたてのパンを食べ、石炭の火で温まったベッドで眠ればいい。陶器職人を手伝って土をこね、泥漿(でいしょう)をかき混ぜ、パンとチーズの夕食にありつけばいい。青い光に耳を傾け、それの言うとおりにして暮らせばいい。イルマク・デールの泥道のことは忘れてしまえ。ペルダンや“痩せっぽ”デリやチバールたちが酒場で響かせる笑い声も、村に夜明けを告げる雄鶏の甲高い鳴き声も忘れてしまえ。美しいテムールの、軽やかに流れ麦穂のように輝く髪のことなど忘れてしまえ。毅然とした肩とほっそりした腰のことなど忘れてしまえ。くちびるを近づけるとふいと横を向く、サテンの布地のような頬のことなど忘れてしまえ。あの粉挽き小屋に響く、水車のきしむ音も水しぶきの音も忘れてしまえ。マグドのやわらかな藺草(いぐさ)の床のことも忘れるんだ。ナブズの陶器職人には気立てのいい嫁入り前の姪がいる。青い光があればすべてを埋め合わせる愛と幸福が手に入る。“太っちょ”デリの鍛冶場の熱気も、鉄を打つ音も忘れてしまえ。親父の魂が宿った緑色の石、みずからの手で親父の屍衣の上に置いた石のことも忘れてしまえ。アスザのことなど忘れるんだ。この胸にしがみつくかわいいアスザのことなど……
マリシュはアスザのことを思い出し、陶器職人の妻が抱いている空っぽの毛布に目をやると、突然、はずみをつけて家の壁から飛びのいた。勢いで木箱はひっくり返り、彼は転げ出した林檎のなかに大の字に倒れた。
すばやく身を起こして耳を澄ましたが、あたりに人の気配はなかった。彼は林檎を五つ拾い上げ、背嚢(はいのう)に詰めこんでナブズの町の中心に急いだ。
太陽は沈み、銀色の月明りが通りに降りそそいでいた。どの家の窓からも、冷たく青い光がもれていた。
ふと視界の隅に、背後から迫ってくる物影が映ったような気がした。彼は急いでふり返りナイフを引き抜いた。だが何も見当たらなかった。林檎が五つ、手がかりはなし。これ以上のものをナブズの町に期待しても無駄だ。理性がそう告げているような気がしたが、かまわずに進んでいった。
やがてたどり着いた大きな広場には、いくつもの影が入り乱れていた。木の影かと思ったが、よく見ると背の高い鉄製の枠の影で、その枠には数人の男女が上下逆さまに磔(はりつけ)にされていた。彼らの体に打ちこまれたねじ釘には、干からびた血がこびりついていた。
すぐそばの男はまだ息があるようで、かすかな呻き声が聞こえてきた。マリシュは男の口に水を含ませ、頭を持ち上げてやったが、男は飲みこむことができなかった。むせこんで吐き出した水は顔をつたって流れ、もともと眼球がおさまっていた、血まみれのくぼみにしたたっていった。
「赤ん坊を」男がしわがれた声で言った。「どうしてあの女に赤ん坊を渡すなんてことができたんだ?」
「誰にだって?」マリシュが言った。
「白い魔女だ!」男はしわがれ声を張り上げた。「あの忌々しい女! あいつと戦わせてくれさえしたら――」
「いったいなぜ……」マリシュが言った。
「何が赤ん坊は永遠の命を授かる、だ――ふざけるな。ナブズの民の亡骸に群がる卑劣な青い血の蛆(うじ)め……」男は咳きこみ、血が顔をつたっていった。
ねじ釘は鉄枠にしっかりと固定されていた。「道具を持ってくる」マリシュは言った。「このまま待って――」
その時、背後ですさまじい金切り声が聞こえた。
ふり返ると、彼の後を追ってきた影の姿が見えた。それはつややかな純白の毛に包まれ、緑色の目を暗闇にらんらんと光らせた白猫だった。全身の毛を逆立たせ、尻尾をぴんと張りつめて彼を見つめている。仲間を呼んでいるのだ――理性が彼に告げた。
マリシュが走り出すと、猫は甲高い鳴き声を上げながら後を追ってきた。ナブズの町は巨大な影にあふれていた。ひと気のない門をくぐると、何かがきしむ音と馬のいななきが聞こえた。彼は薄暗い月明かりの草原に駆けこみ、悪魔の轍に伸びるカダス=ナーンの影の方に急いだ。背後からは蹄(ひづめ)の音がぐんぐん迫ってくる。
カダス=ナーンはちょうど背の高い大麦の畑にさしかかったところで、蹄の音と悪魔のような猫の金切り声を耳にしてふり返った。「畑に入れ!」マリシュは叫んだ。「畑に身を隠すんだ!」彼はカダス=ナーンを追い越して大麦の畑に飛びこんだ。猫がその後を追った。
そこでいきなり、マリシュはきびすを返して身をかがめ、白い猫につかみかかった。片手で猫をとらえ、もう一方の手でナイフを操ってその息の根を止めようという魂胆だった。だが抵抗する猫の勢いはすさまじく、両手で取り押さえるのも精いっぱいだった。ふとふり返ると、悪魔の轍にじっとたたずみ、大槍を握って敵を待ち構えているカダス=ナーンの姿が見えた。そこに白ずくめの甲冑を身につけた騎士が三人、巨大な軍馬にまたがって突進していく。
「この犬野郎!」マリシュは叫んだ。「死にたいのは勝手だが、とにかく畑のなかに隠れろ!」
カダス=ナーンはぴくりとも動かなかった。先頭の騎士が襲いかかり、ふりかざされた剣の刃が月明かりを受けて光った。刃先が首からわずかのところに迫った瞬間、カダス=ナーンはさっと身をかわすと、二番目にやって来た騎馬の前に躍り出た。
一番目の騎士が彼を通り越して疾走していくと、カダス=ナーンはすばやくかがみこみ、大槍の根もとを地面にしっかりと突き立てた。二番目の騎士は必死で手綱をひいたが、大きな馬の勢いはやまず、槍の穂先めがけて突っこんだ。大槍は馬の首を貫き、鞍上の騎士の甲冑の胸を貫いた。軍馬は騎士を乗せたまま前足を高く上げ、両者は一体となって、まるで瀕死のケンタウロスのようにもがき、やがて地面にくずれ落ちた。
一番目の騎士が馬の向きを変えた。三番目の騎士がカダス=ナーンに突進していった。もはや彼の手に大槍はなく、肩と胸からは力が抜けていた。ジャッカルの頭をかしげ、まるで物思いに耽っているようだった――ついにその時が来たのか? 私は今まさに解き放たれるのか?
だがその瞬間、マリシュがとうとう猫の尻尾をつかみ、その獰猛な白い生きもの――鉤爪をむき出し、耳ざわりな威嚇の声を上げて逆上する猫を、三番目の騎士の馬の顔めがけて投げつけた。
馬は後足立ちになり、騎士を宙に放り出した。騎士は地面に叩きつけられた瞬間、剣を手放した。カダス=ナーンは蜂鳥(はちどり)のようにすばやく飛び上がると空中で剣をつかみ、残る一人の騎士を待ち受けた。
マリシュはナイフを抜き、大麦の穂をぬって走った。落馬した騎士が立ち上がろうとした矢先、マリシュは体当たりして彼を押し倒した。
頑丈な甲冑の衝撃にマリシュはひるんだ。相手は彼の倍ほども力のある男だった。胴に伸びてきた屈強な腕が、まるで鉄の輪のようにぎりぎりと彼を締めつけた。だが両手の自由は奪われていない。彼は騎士の冑をつかんでひねり、わずかに首の皮膚があらわれると、そこにナイフを突き立てた。男の首から熱い血が噴き出した。
騎士はもがき苦しんだ。最後のあがきでマリシュの体を引き寄せ、返り血を浴びせながら、むせび泣くような呻き声をあげた。マリシュは彼の体を抱きかかえた。このような最期を遂げることになった騎士が憐れだという、心のなかの声につき動かされていたのだ。マリシュはそのことに気づいて動揺した。この男は白い魔女の残忍な奴隷じゃないか。だが彼は男の震える体から手を離さなかった。やがて男は、彼の腕のなかで動かなくなった。
マリシュは生温かい血でぐっしょり濡れた体を起こし、よろよろと立ち上がった。もう一人の騎士のことを思い出してはっとしたが、もちろんカダス=ナーンがすでにとどめを刺していた。三人の騎士の死体が破壊の轍の上に横たわっていた。生き残った二頭の馬が鼻息を荒くし、まるでぎこちなく哀悼の意を捧げるように、足で砂を掻いた。カダス=ナーンは馬と騎士の死体から大槍を力いっぱい引き抜いた。悪魔の猫は白い毛と赤い血にまみれ、もはや形もなくふやけていた。くずれ落ちた馬の体に押し潰されたのだ。
マリシュはそばにいた馬の手綱をつかんだ。たくましくて毛艶のよい馬だ。彼はその耳の裏を撫でた。やっと息が整うと、マリシュは口を開いた。「馬を手に入れたぞ。乗るかい?」
カダス=ナーンはうなずいた。
「じゃあ出発しよう。また追っ手が来るかもしれない」
カダス=ナーンの眉間に深い皺が寄った。彼は死体を指さした。
「何だよ?」マリシュが言った。
「たしかに、ここには死体処置人も埋葬人もいない。だが私は緊急事態下や遠征先での葬儀のとりおこない方をたたきこまれている。必要な道具もそろっているし、ほんの一日もあればささやかな墓碑も造れる。少なくとも彼らは意識あるまま苦痛のうちに死んだ。儀式の粗末さは埋め合わせられるだろう」
「本気で言ってるんじゃないだろうな」マリシュは言った。「白い魔女はどうなるんだ?」
「白い魔女とは?」カダス=ナーンは言った。
「悪魔だよ。〈白い魔女〉と呼ばれているんだ。そいつがナブズの町をよけたのは、民がそいつの奴隷となることを誓い、彼らの赤ん坊を差し出したからなんだ」
「埋葬が済んだら追いかけよう」カダス=ナーンは言った。
「こうしているうちにもそいつはどんどん突き進んでいくんだぞ! 馬に乗って今すぐ出発すれば、まだ追いつくチャンスはあるかもしれない。そいつがこのまま進んでいけば、きっと死体がもっとたくさん出る。埋葬されなかったり、まちがったやり方で埋葬される死体がな」
カダス=ナーンは槍にもたれかかった。「イルマク・デールのマリシュよ」彼は言った。「ここで別れなければならないようだ。私はきみの述べた論理に従うほど非情にはなれない。魔女をとらえ打ち負かしたあかつきに遭遇する他の死体のために、目の前にある三つの死体の埋葬を放り出すことなどできない。私の務めはそのようなものではない」彼はマリシュの目をのぞきこんだ。「きみの村にはこのような言葉は通じないのだろうが、埋葬されず打ち捨てられた死体はやがて〈タンザディ〉となる。わずかばかりにせよ、私ができるだけの敬意をもって埋葬されれば、〈タズラシュ〉となる。この世の生は一瞬だが、〈タンザディ〉や〈タズラシュ〉として生きるのは永遠だ」
「もし白い魔女の手下がこいつらを殺した仇を討ちにきたらどうする?」
だが、どんなに懸命に説得しても、マリシュは彼を思いとどまらせることができなかった。彼はついに馬にまたがり、ひとりで出発した。はるか向こうに見える白い月を目指し、不気味な囁き声をたてる町を後にした。
もう花も草原も見えなかった。地平線のほの暗い光に浮かびあがるのは、無数の蝿が飛びまわる沼地に鬱蒼と茂る羊歯類や、歪んだ低木だった。荒涼とした道はだんだんと広くなり、いまや馬がゆうに三十頭は並んで走れるほどの幅があった。だが、ぬかるんだ地面は足場が悪い。マリシュの乗った馬は、そろそろと一歩踏み出すたびに蹴爪(けづめ)まで沈みこんだ。
鶴の群れが沼地から月の消えた空に飛び立った。マリシュはこんなにたくさんの群れを見るのは初めてだった。真っ白なか細い鶴が、音もなく空を昇っていった。まるで天の冷たい子宮に帰り着こうとする雪のようだった。あるいは魂の流れる川を目指しているのだろうか。一羽として彼の方をふり向きはしなかった。心のなかで疑いの声が言った――アスザとテムールの身に何が起こったかを、おまえは決して知りえないだろう。
林檎はとっくになくなっていた。空腹のあまり眩暈(めまい)がした。マリシュは手綱を引いて馬を止め、鞍を降りた。道を離れて狩りをしなくてはならない。彼は藪のなかに入り、家ほどの高さのある大きな黒い羊歯の木に馬をつないだ。根もとのやや乾いた場所に、兎の足跡が見えた。手を触れてみると、どうやらまだ新しいもののようだった。彼は兎の足跡を追って沼地に踏みこんだ。
テムールと彼女の愛撫を思い出した。彼女が彼に背中をむける夜があった。その背筋は槍のように頑なにまっすぐで、ふたりのあいだの藺草の床は凍った砂漠のように冷たかった。彼は寝つけぬまま毛皮と織物の掛け布の下でうずくまり、寒さに身を固くしながら、黙って心のなかで彼女と言い争った。彼女が彼にふり向く夜があった。彼に触れる柔らかい肌は熱く瑞々しく、執拗なほどに彼を求めた。まるで彼に思い知らせるように――どう? これはあなたのものよ。これがわたしというものなのよ。
やがて、焼け焦げ、血にまみれ、粉々になった石と漆喰のくずに覆われた藺草の床が脳裏によみがえってきた。彼は必死でその光景をふり払った。息を吐き出し、すべての考えを西風にゆだね、頭のなかを春のせせらぎのように澄みわたらせた。そして沼地に足を踏み入れた。
気がつくと、彼は青と紫のタイルの敷かれた通りに立っていた。そこはこの世のものとは思えないような美しい都だった。
彼は唖然として立ちつくしていたが、やがておそるおそる後ろに一歩下がった。
すると暗い沼地のなかに戻っている。蟇蛙(ひきがえる)の陰気な鳴き声が響き、相変わらず食べるものは何もない。
疑いの声が言った――腹が減りすぎて頭がどうかなってしまったんじゃないか? 次に希望の声が言った――あそこにいけば、白い魔女を見つけ出して仕留めることができる。頭のなかでありとあらゆる思いをめぐらせながら、もういちど前に踏み出してみたが、そこは沼地のままだった。
マリシュはしばし考え、後ろに一歩下がった。そして頭のなかを空っぽにして、もういちど前に踏み出してみた。
通りではじつに様々なタイルがモザイクをなしていた――光り輝く宝石のついたものもあれば、華麗な手書きの文字が書かれているもの、小さな部屋に通じる小さな窓のついたものもあった。家々にもおびただしい種類のタイルが貼られている。ある家は円柱のようにそびえ立ち、ある家は茸(きのこ)のように丸くふくらみ、ある家は蜜蝋のように溶け出している。なかには踊っている家もある。お喋りや足音、そして川の流れる音が、柔らかなざわめきとなって彼の耳に届いた。
通りには青い肌の人間たちが、羽根や金箔でできた衣装を身につけ、あるいは渦巻く影をまとって行きかっていた。上等な絹の衣装に身を包んだそのなかの一人が、マリシュのすぐそばを通りかかった。
「すみませんが」マリシュは言った。「ここはどこです?」
男はゆっくりと顔を上げ、マリシュを見た。男の額の中央には赤い宝石がついていて、言葉を発するたびにちかちか光った。「おまえがどこから入ってきたかによる」男は言った。「そしておまえが何者かによる。だが狭鼻猿類よ、おまえにとってはジムザルカンティトルジェニア=フェンストックということになろう。それが発音しやすかろうからな。この都の客人とあれば、これで一つめの無償のものを与えたことになる」
「ただのものがいくつもらえるんです?」マリシュが言った。
「三つだ。これで二つくれてやったぞ」
マリシュはしばらく考えこみ、やがて口を開いた。「食べるものが欲しい」
男は意表をつかれたようだった。彼はマリシュをとある建物にいざなった。回転する三角形が作る、ぼやけた円錐のような建物に入り、蝋燭の灯った薄暗い部屋を抜けると、所せましと食べものが並べられた食卓にたどり着いた。雄鶏の丸焼きにカスタードソース、剃刀の刃のように薄く切ったハムに大葉子(オオバコ)のジャム、砂糖漬けの杏に山羊の乳のヨーグルト、熟成したチーズにヤムイモ、蕪(かぶ)、オリーブ、めずらしい香辛料を使った塩漬けの魚――マリシュにわかったものだけでもそれだけあった。
「妖精の食べものに手をつけるべきじゃないんだろうな」そう言ったものの、口のなかには唾液があふれ出し、話そうとすると舌がもつれた。
「たしかに。だが、精霊の食べものを恐れることはない。さあ、これで三つ与えてやったぞ」精霊は言い、お辞儀をして立ち去るようなそぶりを見せた。
「待ってくれ」マリシュは言った(ちょうど砂糖漬けの杏を飲みくだしながら、塩漬けの魚をひとつかみ頬張ったところだった)。「ここまではただでくれたんだな。じゃあ、何かと引き換えに売ってくれと言ったらどうする?」
精霊は何も言わなかった。
「おれは白い魔女を殺さなきゃならん」マリシュはオリーブを齧りながら言った。頭のなかで疑いの声が言った――なぜ本当のこと言うんだ? この都の民も魔女に服従を誓っていたらどうする? だが彼は声をふり払った。「何か役に立ちそうなものはないか?」
精霊はやはり黙っていたが、片方の眉がぴくりと動いた。
「おれは馬を持っている。本物の軍用馬だ」マリシュは言い、チーズに取りかかった。
「馬の名前は?」精霊が言った。「名も知らぬものを精霊に売りつけることはできぬぞ」
とっさに嘘の名前をでっちあげようと思ったが、何も出てこなかった。マリシュは口のなかのものをごくんと飲み下した。「名前は知らない」彼は白状した。
「ではだめだ」精霊は言った。
「その馬に乗ってた何かを殺したんだ」マリシュは説明しようとした。
「誰か」精霊が言った。
「誰かって?」マリシュが言った。
「馬に乗っていた誰か」精霊が言った。
「そいつの名前も知らない」マリシュは言い、ヤムイモをつまみ上げた。
「いや、そうじゃない」精霊は声を荒げた。「『馬に乗った“何か”を殺した』ではなく、『“誰か”を殺した』が正しい言い方だと言っているのだ」
マリシュはヤムイモを食卓に戻した。
「もうたくさんだ」彼は言った。「ご馳走と三つの贈りものには感謝するさ。だが話し方を教えてくれなんて頼んでないぜ。おれの話し方はイルマク・デールの民の話し方だ。村があった頃、おれたちはこんな風に話してたんだ。白い魔女に木っ端みじんにされたからって、おれはどこかの魔法の都の民のように話したりはしないぞ」
「おまえからそれを買い取ろう」精霊は言った。
「何だって?」マリシュは言った。その意味を考えあぐねるあまり、次に食べるものを選ぶのも忘れてしまった。
「イルマク・デールの民の話し方をだ」精霊は言った。
「いいだろう」マリシュは言った。「じゃあそれと引き換えに、白い魔女をやっつけるのに役立ちそうなものを教えてもらおうか」
「私は風よりも速く飛ぶ絨毯を持っているが」精霊は言った。「たぶんそれが魔女に追いつく唯一の手段だろう。追いつかないことには殺せはしない」
「そりゃいいや」マリシュはよろこびの声を上げた。「イルマク・デールの民の話し方と引き換えに、その絨毯をくれるっていうんだな?」
「そうではない」精霊は言った。「私は何がおまえの役に立ちそうかを教えた。それと引き換えにイルマク・デールの民の話し方を受け取った。大図書館(グレート・ライブラリ)に所蔵するつもりだ」
マリシュは眉間に皺を寄せた。「そうかい。じゃあ絨毯と引き換えに何が欲しい?」
精霊は答えなかった。
「白い魔女をくれてやろう」マリシュは言った。
「自分のものでなければ売ることはできない」精霊は言った。
「なあに、じきつかまえておれのものにしてみせるさ」マリシュは言った。「約束する」彼は茹で卵をつかんでいた手をぎゅっと握りしめ、殻を粉々に割った。
精霊はマリシュの顔をしげしげと眺め、やがて口を開いた。「三日間、絨毯を使わせてやろう。その代償に、もし白い魔女を打ち倒すことができたら、それをいただこう」
「決まりだ」マリシュは言った。
(訳:鈴木潤)