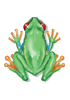鶴の群れ(後篇)
ベンジャミン・ローゼンバウム
馬には目隠しをしなければならなかった。さもなければ絨毯が宙に浮いた瞬間、足を蹴り上げて暴れ出しかねなかった。馬と人間と精霊が一枚の織物に乗りあわせ、疾風のごとき速さでナブズに向かって飛んだ。マリシュは眼下を飛ぶように過ぎ去っていく固い地面を努めて見ないようにしつつ、未練がましく杏の砂糖漬けのことを思い出していた。
連れはとっくに殺されているにちがいない――疑いの声はそう言ったが、彼は心の奥底でどうかカダス=ナーンにもういちど会いたいと願った。あのジャッカル頭の男の他に、マリシュにはもう友と呼べる相手はいなかった。
大麦の茂みのなかに、人の背丈ほどある積み石が三つ見えた。黒い石の表面には白い象形文字が描かれ、それらが墓石であることを示していた。カダス=ナーンは墓石からさほど遠くないところで、伏兵の奇襲に遭っていた。エンプティ・シティの使者はどれくらいこうして独りで闘っていたのだろうか。まるで酔っぱらいか疲弊しきった者のようにふらついている。灰色の毛は血と汗でぐっしょり濡れていた。
カダス=ナーンを取り囲んでいるのは、白い甲冑を身につけた子供の一群だった。絨毯が地面に近づくと、彼らの土気色の顔と生気のない目が見えた。這い這いしている子もいれば、よちよち歩きの子もいる。六歳を過ぎるまで生を長らえた子はいないようだ。みな手に短剣を持っている。一人の子はカダス=ナーンの背中にしがみつき、刃先でせっせと血の水路をこしらえている。
黒い大槍の先には二人の赤ん坊が串刺しになっている。彼らは短剣を口にくわえ、槍の柄(え)を両手でたぐってカダス=ナーンの握り手に向かっていく。さらに何百もの子供が周囲にひかえて、じりじりと彼に迫っていた。
カダス=ナーンは大槍をふりまわして虚ろな目の生きものを追い払おうとした。頭蓋骨を打ち砕きそうなほどの勢いに、餓鬼どもはふり落とされた。だがおかしそうに笑いながらまたすぐに彼に群がり、太ももに短剣を突き刺した。ひと振りするごとに槍の勢いは落ちていった。カダス=ナーンは白目をむき、たくましい体は疲労と痛みに震えた。
絨毯は戦場の近くの低空に漂い、マリシュは腹這いになって ジャッカル頭の戦士に手を伸ばした。「飛び上がれ! カダス=ナーン、飛ぶんだ!」
カダス=ナーンは両手で槍を握ったまま絨毯を見上げ、飛び上がろうとして足を踏んばった。だが、大槍の動きが止まったその瞬間をとらえ、白い魔女の小さな従僕たちが反撃に出た。彼の体にいっせいに群がり、四方八方から短剣を突きたてた。やがて彼は地面にくずれ落ち、その体を餓鬼の群れが飲みこんでいった。
「もっと低く飛んでくれ! やつをひっぱり上げるんだ!」マリシュは叫んだ。
「たしかに絨毯を使用する権利は売ったが、破壊する権利は売っとらん」精霊が言った。
マリシュは苛立ちを爆発させて唸り声を上げ、理性が何か言い出す前に絨毯から飛び降りた。戦闘のまっただなかに着地すると、カダス=ナーンの体から小さな敵をひとりひとりひきはがし、草原に放り投げていった。敵は彼のふくらはぎに短剣を突き立てはじめた。小さな体が次々に脇腹に突進してきて、やがて倒れこんでしまった彼の上に、白い甲冑の餓鬼の群れが覆いかぶさった。絨毯は夏の空へゆったりと漂っていった。
マリシュは必死で抵抗したが、すぐに餓鬼どもに手足の自由を奪われた。彼らの短剣が脇腹に刺さり、血があふれ出した。彼は歯を食いしばって叫び声を押し殺した。子供たちは彼の髪をひっぱり、耳をひっぱり、口をこじあけてなかをのぞきこんだ。まるでじゃれついているようだった。しがみついてきた黒ずんだ顔の赤ん坊は、頭皮がめくれて白い頭蓋骨が半分むき出しになっていた。それはあるはずのない乳首を探すように、彼の首に鼻先をうずめてきた。
かわいいアスザもよくこうして鼻をすりつけてきた。目方もちょうど同じくらいだった。五つの林檎を入れた背嚢ほどの、心地よい重み。だがあの子の目はきらきら輝いていた。疑うこともなく世界を見つめ、世界に魅せられていた。あの子の目に映る彼は英雄であり、あの子を軽々と持ち上げる巨人であり、正直で優しくて勇敢な父親だった。テムールはその焦げ茶色のいたずらっぽい瞳をのぞきこむと、固く結んだ口もとをほころばせ、美しい旋律を口ずさみはじめた。
短剣が彼の額を切り裂き、顔じゅうを血だらけにした。別の短剣は肋骨のあいだに入りこみ、さらに別の短剣が太ももの皮膚を切り裂いた。腹にも一撃あったが、腸(はらわた)には届かなかった。彼は目を閉じた。のしかかる子供たちの体が、ひどく重く感じられてきた。喉をふりしぼって叫び声を上げようとしたが、もはや息を吸うこともできなかった。
アスザとテムールをこの腕に抱きたくてたまらなかった――ここのまま独りで死ぬのかと思うと悲しくてしかたなかった。だが、きっとふたりはおれから取り上げられる運命だったんだろう? 夕暮れの草原を彼のもとに駆けてくる小さな女の子。その飛びはねるような愛らしい走り方。腕をひろげてぼろ布の人形を振りまわす姿。そこには疑いの影などみじんもない。そして美しい妻。彼と目が合うと、固くこわばるその体。だが彼が林檎の匂いのするアスザを抱き上げると、思わずほころぶ口もと。おれはふたりにふさわしい男ではなかったということなんだろう?
顔は火照り、塩辛い血で濡れていた。短剣がふりおろされ、彼の体を斬りつけては深くえぐった。もはや痛みは感じなかった。彼は刃身の光が闇に描く弧をただじっと見つめていた。
彼は暗闇に祈った。最期にアスザをもういちどこの腕に抱きしめたい。夜中に目を覚まし、魔女を恐れて泣いたあの子をあやした時のように。今こうして、魔女は本当にやってきてしまった。
わずかながら息を吸いこめるようになると、くちびるをかすかに開き、むせび泣きながら歌いはじめた。それはアスザをなだめ、もういちど寝かしつけるための子守唄だった。
眠れ、眠れ、愛しい子よ――
月は高く昇り
雲は羊のように駆ける
パパはおまえをずっと見守っている
眠れ、眠れ、愛しい子よ――
激しい風はやみ
子牛は母さん牛と眠る
眠れ、愛しい子よ、夜明けまで眠れ――
彼は左腕にのしかかっていた子供たちをふり払い、血と涙で濡れた目を拭った。頭を起こすと、目の前がぐるぐるまわり、光の残像がいくつも花開いた。子供たちは動かなくなっていた。彼はその小さな体をそっと地面に下した。
絨毯が下りてくると、マリシュはカダス=ナーンの体をかついでその上にのせた。そしてよろめきながらふり返り、おぼつかない足取りで、地面ですやすや眠っている血の気のない赤ん坊の顔をひとつひとつのぞきこんでいった。アスザはいなかった。
彼はいちばん小さな赤ん坊を抱き上げると、ぼろ布で包んで革紐で縛った。指先は血ですべり、正午の太陽は石のように灰色に見えた。赤ん坊が動かないことをたしかめると、彼はそれを背嚢に詰めて背負い、絨毯に乗りこんだ。絨毯はふわりと宙に浮き、彼はまるで揺りかごであやされる子供のように眠りに落ちた。
目を覚ますと、流れる雲が真上に見えた。痛みは消えていた。彼は起き上がって腕をたしかめてみた――傷ひとつない。“痩せっぽ”デリが鎌でうっかり切りつけた古傷さえも治っていた。
「おまえは〈絶望の子〉を打ち負かす術を教えてくれた」精霊の声がした。「その見返りとして、おまえと仲間の傷を治してやったのだが、それで十分かな?」
「ひとつ質問に答えてくれ」マリシュが言った。
「それに答えたら貸し借りなしになるのか?」
「そうとも。西風の幸あれ、それで貸し借りなしだ! 」
精霊は同意するようにまばたきした。
「やつらはもとに戻るのか?」マリシュは訊いた。「もういちど生きた子供に戻れるのか?」
「もとには戻らない」精霊は言った。「彼らは死ぬことも生きることもできない。みずから望まないかぎり、そのことで苦しみもしない。彼らの心があったところには、砂が詰めこまれているのだ」
彼らは沈黙したまま空を飛んだ。マリシュは背嚢がずんと重くなったような気がした。
絨毯の真下では、大地が目にも留まらぬ速さで通り過ぎていった。マリシュは緑の草原が湿地になり、沼地になり、やがてでこぼこした牧草地に移り変わっていくのを眺めていた。白い魔女の破壊の道はどんどん生々しくなっていった。眼下の道からはまだ煙が立ちのぼっている。じかに歩いたら火傷するくらいまだ熱いだろう。絨毯は焼けつくされた村の上をいくつも通り過ぎ、マリシュはそのたびに目をそむけた。
とうとう風にのってその気配が耳に届いた。心が薄ら寒くなるような音だった。それは苦痛に満ちた慟哭でも、耳ざわりなわめき声でもなかった。痛々しい金切り声でも、骨が砕ける生々しい音でも、おぞましい呻き声でもなかった。そのすべてが混ざったような音だった。カダス=ナーンのジャッカルの耳がそばだち、灰色の毛が逆立った。
やがて彼らはまだめらめらと炎を上げている道にさしかかった。絨毯はそのずっと上空を飛んでいた。立ちのぼる煙が霧のように大地を覆っていたが、その霧の向こうに、延々と道を作っている世にも恐ろしいものの姿が見えた。絨毯が近づくにつれ、マリシュの頭のなかが真っ白になっていった。見ているだけで、喉を焼くような苦いものがこみ上げてきた。
それは巨大な馬車だった。人の背丈の八倍ほどの高さと、道幅と同じだけの横幅があり、生きた人間の体の一部を猥雑に絡みあわせて形づくられている。千本もの手足が地面をひっかき、さらに千本の手足が大地に鞭をふるい、鎌をふりまわし、あるいはひたすら宙をかいている。幾重にも撚(よ)りあわされた心臓と肝臓と胃袋が中央でどくどくと脈打ち、その真ん中で無数に寄せ集められた肺が呼吸をしている。馬車の底には、車輪のように地面を転がされている頭が見える。飾り物のように馬車の表面のあちこちからぶら下げられ、虚ろな目で奇声をもらしている頭もある。背骨と胴体で組まれた骨格に髪の毛と皮膚の織物が張られ、車体を形づくっている。きっとそのなかに白い魔女が隠れているにちがいない。車体から突き出した尖塔には、無数のうごめく舌で織られた旗がはためいている。馬車を先導しているのは、白い鎧と面頬付きの冑を身につけた十人の騎士だ。
そして馬車の頂上には頭のない醜い生きものが座っていた。体は熊よりも大きく、蜥蜴(とかげ)のような外皮に覆われている。大きな黄色の眼球が両肩におさまり、口は腹を横切っている。マリシュたちの目の前で、それは炎の塊を吐き出し、馬車の背後の道を火の海にかえた。やがてマリシュたちに気づくと、彼らに向かって巨大な火柱を放ってきた。精霊はすかさず絨毯に命令を下して向きを変えさせた。間一髪だったが、それでも天火(オーヴン)の熱風を浴びたように肌がひりひりした。馬は興奮して後足立ちになった。マリシュは手綱をひき、なだめるように馬の耳に囁きかけた。
「なんと忌まわしい!」カダス=ナーンが言った。「精霊よ、エンプティ・シティに通報してはくれまいか? 報酬は約束する」
精霊はうなずいた。
「こちらはカダス=ナーン、〈果てしなき調査隊〉の二等斥候。〈沈黙の大隊〉のバルス=カルダレス司令官にすみやかな来援の要請を伝えたし。現下に条理を越えた凶事あり。蛮族の無知より出(い)ずる過ちの非にあらず。〈混沌〉が〈闇〉への帰還を全面的に阻むもの。世界の破滅があやぶまれたし」
精霊の額の宝石がいちど点滅した。「送ったぞ」彼は言った。
カダス=ナーンはマリシュにふり向いて言った。「エンプティ・シティからここまでゴムルの大隊がやってくるのに四日はかかる。どこかで待機して彼らに合流しよう」
マリシュはぎゅっと目をつぶった。だが、忌まわしい姿は目の裏にもありありと蘇ってきた――無数の手や舌や胃袋や皮膚が絡みあい、巨大な塊となって驀進する姿。耳にはまだ、何かが潰れるような、砕けるような、裂けるような音が、そして無数の肺がたてる海鳴りのような轟音が響いていた。おれは何を想像していたんだ? アスザとテムールはどこかで囚われの身となっていると? なんとおめでたいやつだ。「わかった」
だが目を開けた瞬間に飛びこんできた光景に、彼は思わず答を翻した。「いや、待て」
白い魔女の恐ろしい馬車から馬で十分ほどの距離に、小さな村が見えた。白い漆喰塗りの家々が、午後のうららかな陽射しのなかにたたずみ、村の前には二十人ほどの男女が隊をなして並んでいる。まともな剣や槍を持っているものはほとんどいない。弓を持った女が一人いるだけで、他の者の手には鋤や鎌や竿が握られている。女が一人馬にまたがっているものの、あとは自分の足で歩いている。そして絨毯の上のマリシュの目に、遠くの人影が映った――家族連れや、背中のまがった老婆たち、赤ん坊を腕に抱いた母親たちが、甲虫(かぶとむし)のようにのろのろと丘をよじ登っていた。
「降りろ」マリシュは絨毯に命じ、彼らは武器を構えている村人の防衛隊の前に降りたった。
「逃げた方がいい」彼は言った。「丘までいけばどうにかなる。あいつの姿を見たことがないだろう――戦って勝てるような相手じゃない」
浅黒い肌の男が地面に唾を吐いて言った。「それはグラヴェンジで試してみたさ」
「あいつは分裂するんだ」黒い髭を生やした男が言った。「小さな従者を送りこんでくる。そいつらが村人を引き裂いて、あいつの一部にしちまうのさ。そしてご存知の通り、仲間の手足があいつの一部となって追ってくるんだ。やつらはすばしこい。とてもおれたちにゃ逃げおおせない」
「おれたちはここで時間稼ぎをするんだ」別の男が言った。「村人が安全なところまで逃げられるように」だが、男の目は怯えていた。心のなかには疑いの声が響いているにちがいない。
「あいつをここで食い止めるのよ」馬に乗った女が口を開いた。
マリシュは絨毯から馬を下ろして目隠しを取り、その背にまたがった。「手伝おう」彼は言った。
「歓迎するわ」女の野暮ったい顔に神経質そうな微笑が浮んだ。すると彼女はほとんど美しくも見えた。
カダス=ナーンが絨毯から降りてくると、村人たちは武器を構えて後ずさりした。
「こちらはカダス=ナーン。きっと彼を味方につけたことを心から感謝することになるだろう」マリシュは言った。
「あんたたち、礼儀を忘れてしまったの?」馬に乗った女は村人たちにぴしゃりと言った。「わたしはアスザよ」彼女は言った。
まさか――マリシュは女をまじまじと見つめた。ちがう、おれのアスザじゃない。ただの偶然だ。彼は彼女から顔をそむけた。やがて村人たちは彼らに向けていた武器をひっこめた。
絨毯は静かに上空に消えていった。すぐに地平線に煙が立ちのぼり、騎士たちが突進してきた。その背後に巨大な馬車の姿が見えた。
「さあみんな」岩だらけの土地のアスザは言った。「しっかりやるのよ」
矢が勢いよく放たれ、一人の白い騎士の馬が倒れた。マリシュは馬に号令を出し、全力で疾走させた。村人たちも武器を構えて走り出したが、カダス=ナーンは彼らに先がけて二人の騎士のあいだに飛びこんでいった。彼は槍の柄で一頭の馬の二本の前足を打ち砕き、槍の先端で別の騎士の脇腹を貫いた。村人たちは鎌をふり上げて落馬した騎士に襲いかかった。
マリシュは見事な軍馬を駆っていることに興奮を覚えた。父親はレッド・レッグスという馬を自慢にしてかわいがっていたが、これとは比べものにもならない。彼はたくましい馬の胴体の温もりと、その歩調に合わせて鞍から腰を浮かせるリズムに心高ぶらせ、猛然と騎士の列に突進していった――おれはイルマク・デールのマリシュだ。悲しみのあまり、頭のおかしくなった憐れな男だ。
アスザは一人の騎士の突撃をかわしながら、相手の馬の目に鞭をふるった。騎士はすぐさま馬の首をめぐらして彼女を追いかけ、その後をマリシュが追った。だが彼の背後には、また別の騎士の馬のひづめの音が猛烈な勢いで迫っていた。
最初の騎士がアスザに追いつこうとしていた。マリシュはナイフを片手に握りしめ、身をかがめて馬の耳に言葉のない囁きを吹きこんだ――いい子だ。どうかおまえのすべての力をおれに貸してくれ。すると馬はアスザを追っていた騎士の真横まで追いついた。
マリシュは鞍を降り、鞍の取っ手からぶらさがった。顔のすぐ下を地面が滑るようにかすめていった。彼は騎士の馬の腹に手を伸ばし、鞍をくくりつけている腹帯の下にナイフの刃先を滑りこませた。騎士が体をねじって剣をふり下ろそうとした瞬間――腹帯がちぎれ、騎士は鞍から投げ飛ばされた。
マリシュがふたたび鞍によじのぼった時、二人目の騎士が追いついてきた。甲冑が太陽に照らされてぎらぎら光った。マリシュは今度は敵の利き手の側を走っている。しかも馬のスピードは落ちている。剣がふり上げられ、マリシュの首めがけて弧を描き、その頭を向日葵の花のように切り落とそうとした――やはり農民の命はここまでか。
彼が覚悟した瞬間、アスザの鞭が騎士の剣の持ち手に絡みついた。騎士はもう一方の手で鞭をつかんだ。そのすきにマリシュは鞍から躍り出た。鎖帷子に覆われた胴体に体当たりし、騎士もろとも地面に落ちた。
固い地面が金床で、甲冑の騎士がハンマーだとすれば、マリシュは蹄鉄と取り違えられたぼろ布の人形だった。頭の弱い憐れな娘が作ったちっぽけな人形だ。世界がぐるぐるまわりながらかすんでいった。騎士は鎖帷子の篭手で彼の首につかみかかり、怒りの奇声を発しながら身を起こし、腰から短剣を引き抜いた。マリシュは必死で両手を上げようとした。
その時、騎士の背後からアスザの手が伸び、その首に革紐を巻きつけた。騎士の面頬付きの冑が後ろをふり向くと、すかさずアスザは大声で馬に発進のかけ声をかけた。甲冑の膝がマリシュの頭にぶち当たったかと思うと、騎士は彼の目の前から姿を消した。疾走するアスザの雌馬の後ろで、岩だらけの地面を引きずられていった。
この地のアスザはマリシュに手を伸ばして立ち上がらせた。彼女は豪快な笑みを浮かべ、彼を胸に抱きしめた。彼は痛みにたじろぎ、彼女の体の柔らかさにたじろいだ。やがて彼女は腕を離し、にっこり微笑みながら、彼の肩ごしに村の方を見た。しかし微笑みは一瞬で消えた。
マリシュは後ろをふり返った。黒い髭の男が、何本もの貪欲な手足にひきちぎられているところだった。たくさんの目に覆われた二本の曲がった腕が、男の内臓が馬車に編みこまれていくのを注意深く見届けている。村は炎に包まれていた。白い甲冑の騎士が鞍から身を乗り出し、逃げまどう女に斬りつけて、まるで小麦を刈り入れるようになぎ倒した。
「やめて!」アスザは叫び、村に向かって走り出した。
マリシュも後に続こうとしたが、足をひきずってまともに走れなかった。息が切れ、脇腹に激痛が走った。アスザは地面に落ちていた槍をつかみ取り、馬に飛び乗った。彼女の金色の髪が風になびいた。テムールと同じ髪だ。おれのアスザ、おれのテムール――おれは彼女を守らなければならない。
マリシュは転んだ。倒れこんで、大地をまるで恋人のように両腕で抱きしめた。そうしないと空中に放り投げられてしまうとでもいうように、しっかりと。愚か者め――理性が言った――あれはおまえのアスザじゃない。テムールでもない。そもそも彼女はおまえのものではない。
彼は起き上がり、ふらふらと歩き出した。岩だらけの地のアスザが馬車に追いついた時、その頂上から火柱が立ちのぼった。馬は驚いて前足を上げた。炎は女と馬を包みこみ、やがて焼きつくした。黒焦げになった死体が地面に吐き出され、煙を上げた。
マリシュは立ち止まった。
馬車の上から、炎を吐き出す頭のない生きものが転げ落ちてきた――カダス=ナーンが恐ろしい馬車のてっぺんに立っている。彼の大槍が馬車の一部となったように、その肉塊に深く突き刺さっている。だが、炎の獣はよろめきながらふり返った。その口から吐き出された火柱が、ジャッカル頭の男を飲みこんだ。大槍と甲冑の鉄が溶け、彼の体をみるみる覆い、やがてカダス=ナーンは無数の貪欲な腕のなかに落ちていった。
マリシュは草地に腹這いになった。
ここならやつらに見つかるまい――希望の声が言った。だが、それはまるで森を吹き抜ける風の戯れの言葉のように感じられた。マリシュは地面に横たわりながら、痛みに耐えていた。痛みはまるで彼に歌いかけているようだった。何もかも失われ、手の届かないところにいってしまった。アスザもいない。テムールもいない。マグドもいない――冒険もない。英雄もいない。トリックスターもいない。狩人もいない。父親もいない。夫もいない。山を下ってきた風がマリシュの鼻先の草をそよがせた。地面を這う甲虫たちの姿が見えた。
背の低い草がかさこそ鳴った。針鼠が姿を現し、マリシュに鼻をつきあわせて向きあった。
「言葉を話せるなら話せ」マリシュは小声で言った。「そして願いを叶えてくれ」
針鼠はふんと鼻を鳴らした。「おまえの願いなんか聞くもんか! テオドールにあんな仕打ちをして!」
マリシュは息を飲んだ。「向日葵畑にいた針鼠のことか?」
「当たり前だ。この人でなしめ」
「すまなかった! 彼が特別な力を持っているとは知らなかったんだ! ただの針鼠だと思ったんだよ!」
「ただの針鼠だって! ただの針鼠だって!」それは目をつり上げ、全身の棘を逆立たせた。「ものの呼び方に気をつけろよ、イルマク・デールのマリシュよ。ものの名前を呼ぶということは、それがこの世界の何なのかを説明することだ。名前はおまえが考えているよりもたくさんのことを意味しているんだ」
マリシュは何も言わなかった。
「テオドールは脅されるのが嫌いだっただけだ……あの頑固おやじめ」
「テオドールのことは本当にすまなかったよ」マリシュは言った。
「そうかい、じゃあ」針鼠は言った。「力を貸してやろう。でも高くつくぜ」
「何が欲しい?」
「魂はどうだ?」針鼠は言った。
「くれてやりたいのはやまやまさ」マリシュは答えた。「おれには必要なさそうだからな。でもあいにく持ってないんだよ」
針鼠はふたたび目をつり上げた。村から甲高い叫び声と、炎が何かを燃やす音がかすかに聞こえてきた。やがて秋の匂いと、屠殺した豚の匂いが漂ってきた。
「本当だ」マリシュは言った。「イルマク・デールの牧師が村人全員の魂を小さな石に封じこめて隠したんだ。おれたちがこんな風に魂を取り引きに使わないように」
「なかなか賢い男のようだな」針鼠は言った。「だけど、何かもらわなくちゃ。魂の他に何か持ってないのかい?」
「それはその、たとえば知恵なんかのことを言ってるのか? でもそれは手放すわけにはいかない」
「だろうな」針鼠は言った。
「希望? もうほとんど残っていない」
「どっちみち好みじゃないさ」針鼠は言った。「希望は愚者の道具、疑いは賢者の道具」
「疑いは?」マリシュは言った。
「いいだろう」針鼠は言った。「だけど、ひとつ残らずもらうよ」
「ひとつ残らず……いいだろう」マリシュは言った。「そうしたら、白い魔女と戦うのに力を貸してくれるんだな?」
「もうしたさ」針鼠は言った。
「もうした? じゃあ、おれは魔法か何か使えるようになっているのか?」マリシュはそう言って体を起こした。叫び声はやみ、聞こえるのは炎がぱちぱちいう音と、馬車のたてる不気味な破壊の音だけだった。
「まさか」針鼠は言った。「見えたり聞こえたりしなかったものをやったりはしないさ。でも、どうやらちゃんと耳を傾けていなかったようだな」そう言って針鼠は緑の茂みのなかによちよち戻っていった。
マリシュは立ち上がり、その後ろ姿を見送った。親指の爪を噛みながら考えてみたが、どうしても針鼠の言葉の意味はわからなかった。しかし、もう疑いが生じることもなかった。彼は村に向かって歩き出した。
道の途中で、背嚢のなかの赤ん坊の死体がもがきはじめた。彼はそれを取り出して腕に抱きかかえ、ふたたび歩き出した。
火に包まれた村に入ると、ちょうど炎を吐く頭のない蜥蜴皮の怪物の背後に出た。怪物がくるりとふり向き、彼を焼き殺そうと炎を吐き出した瞬間、彼はとっさに赤ん坊の死体をその喉の奥に投げ入れた。息を詰まらせるような音が響き、巨大な生きものは体をひきつらせてもがいた。マリシュはのたうちまわる怪物を尻目に突き進んでいった。
大きな馬車が彼に気づき、急旋回して突き進んできた。巨大な肉がうごめき、ざわめき、悪臭を放ちながらぐんぐん迫った。何本もの腕が彼に伸びてきた。やがてたくさんの手が上着や髪やズボンをつかみ、彼を空中に持ち上げた。
彼はすぐ近くで襟もとをつかんでいる手に目を留めた。すべらかな女の手だ。指にはいつか彼がハルデの市で買った銅の指輪がはまっている。
「テムール!」彼ははっとして叫んだ。
腕はぴくっと痙攣して彼を離し、蒼白になった。指先を広げてふたたび近づいてくると、彼の頬を優しく撫で、やがて馬車から地面に落ちた。
彼は自分を空中につかみ上げている手にも見覚えがあった。「パン屋のレズールじゃないか!」彼が呼びかけると、パン生地のこびりついた手が馬車からはがれ落ちた。「シルボンとフェルボン!」彼は叫び続けた。「“盲目の”テール! “青い眼の”セラ!」マリシュはくちびるを震わせて次々に名前を呼んだ。いくつもの手が力を失くしては地面に落ちていった。腕だけでなく、馬車のあちこちに組みこまれたいろいろな部分が落ちていった。彼は真上から青い瞳の目玉が落ちてくるのを見た。
「ペルダン! マルディド! ピルグと年老いたおふくろさん! ファッツ――ああファッツ、もう冗談言って笑わせてくれないのか! チバーと異邦人のきれいな嫁さん!」彼の顔は涙に濡れていた。名前を呼ぶたびに何かが胸のなかでぱちんと弾けた。胸の奥からこみ上げてくる奇妙な感情に喉が締めつけられた。「ピズダール牧師! “太っちょ”デリ――鍛冶場からずいぶん遠くにきちまったな! “痩せっぽ”デリ!」イルマク・デールの村人の腕と手がすべて馬車から離れると、彼は体の自由を取り戻した。見知らぬ者の手が迫ってくると、彼はすかさず叫んだ。「おまえは陶器職人だな」爪のあいだに粘土が入りこんでいる手に呼びかけると、それは馬車から落ちた。「おまえは肉屋だ」血まみれの手に呼びかけると、それも落ちた。「太った農夫、若く美しい娘、ばあさん、娼婦、乱暴者」彼は呼び続けた。手や足や頭や内臓がどんどん取れ落ちていった。馬車の中央はへこみ、残された手足がやみくもにもつれあうだけになった。「エクデールの民よ」マリシュは言った。「ハルデの民、グラヴェンジの民、平原の、湿地の、岩だらけの地の民よ」
そして馬車は完全にばらばらになった。マリシュに名前を呼ばれたものが地面に落ちて動かなくなると、残ったものも手がかりを失って落ち、地面の上で虚しくのたうちまわった。
ついに頂上の大きな車体を覆っていた皮膚がはがれ落ちると、白い魔女が空中に飛び上がった。背丈は人間の女の三倍もあり、肌は骨のように白い。片目は血のように真っ赤で、もう片方の目は緑柱石(エメラルド)のような緑色だ。口いっぱいに黒い牙が並び、頭からは蛇や蜥蜴が伸び、手から稲妻がほとばしっている。彼女は牙をむいてマリシュの方に飛んできた。
ふと彼は、その首に巻かれた革紐にくくりつけられているぼろ布の人形に気づいた。子供の手のひらくらいの小さな人形だ。
「イルマク・デールのマグド!」マリシュは叫んだ。魔女はぼさぼさ頭で薄ら笑いを浮かべる若い女の姿を取りはじめ、やがてマッド・ガールとなって彼の目の前に降りたった。
「よくやったわ、マリシュ」マグドはぼさぼさの髪をひっぱりながら笑い声をあげ、地面を見下ろした。「ほんとによくやってくれた! あんたが来てくれてうれしいわ!」
「どうしてこんなことを?」マリシュは言った。「いったいどうしてなんだ?」
彼女は顔を上げ、くちびるを震わせてあごをひいた。「よりによってあんたがそれを聞くの、マリシュ?」
彼女はそろそろと腕を伸ばし、彼の手をつかんだ。彼はひき寄せられるがまま、彼女の方に一歩踏み出した。彼女は彼の手の甲を頬に押し当てた。
「あんたは狩りに出かけてた」彼女は言った。「その時、あんたのテムールが」――その名を口にすると、まるで苦虫でも噛み潰したように顔をしかめた――「レズールのパン屋の裏口であたしをじろじろ見たの。あたしはうつむかなかった。まっすぐ見返してやったら、あの女はあたしに『薄汚いない魔女め』って言ったのよ。そしてみんながあたしのまわりに群がってきて――」彼女は肩をすくめた。「ああいうのって大嫌い。押しあいへしあい騒ぎたててさ」彼女は彼の手を離し、しゃがみこんで土の塊をつかみ上げ、手のひらで握り潰した。「だから、やつらを編み上げてひとつにしてやった。お望みどおりにね。あいつらはそれが気に入ったみたいで、そりゃあ幸せそうだった。あたしはやつらを許してやったの。テムールでさえもね」
腕や脚は地面にじっと横たわっていた。内臓は降り積もった雪のように、なだらかに折り重なったまま動かなかった。
「もう遊ぶのをやめたみたいね」マグドは言い、溜息をついた。
「どうやって?」マリシュは言った。「どうやってこんなことを? マグド、おまえはいったい何者なんだ?」
「ばかね! あたしはマグドのままよ。ただね、魂を見つけただけ。ピズダールの庭から掘り起こしたの。そして〈すべてをばらばらにする精霊〉に売り渡した」彼女は手のひらの土をはらいながら言った。
「それで……子供たちは? 赤ん坊たちはどうしたんだ、マグド?」
彼女はふたたび彼の手を取ったが、目は伏せたままだった。彼の肩に頬をすり寄せ、じっと地面を見つめながら言った。「赤ん坊は大きくならない方がいい」彼女は言った。「わざわざ大きくなって嫌なやつになることないわ」彼女はぼそぼそと言った。「あたしはあの子たちを完璧な姿にしてやった。ただそれだけ」
マリシュの胸が締めつけられた。「それで、これからどうするつもりだ?」
彼女は顔を上げた。その顔にゆっくりと笑みが広がった。「どうするかは」彼女は言った。「あんた次第よ、マリシュ。戦い続けるって言うんなら、あたしにはまだまだ打つ手はあるのよ」彼女は彼ににじり寄り、胸に頬をもたせかけた。彼女の髪からなつかしい村の匂いが漂ってきた。藺草と焚き火の煙の匂い。冬の朝の空気と羊の乳の匂い。「それとも、仲良くしたっていいのよ。もう誰も責める人はいないんだから」彼女は彼の腰に腕を巻きつけた。「何もかもやり直すのよ、マリシュ。きっとそう悪くないわ」
ふたりを影が覆った。マリシュが顔を上げると、精霊が絨毯の上からこちらをのぞきこんでいた。マリシュは咳払いをして言った。「そうだな……どうやら残されたのはおれたちだけのようだし」
「そのとおり」マグドはそっと息をもらした。
彼は彼女の手を取り、後ろに一歩下がって彼女の顔をのぞきこんだ。「おれのものになってくれるかい、マグド?」
「ええ、もちろんよ」マグドの顔に生まれてはじめて満面の笑みが浮かんだ。
「よし」マリシュは空を見上げて言った。「彼女をもっていくがいい」
精霊は手にしていた小壜の蓋を開けた。するとマグドという名の白い魔女は、瞬く間に壜のなかに吸いこまれ、精霊はすかさず蓋を閉めた。彼はマリシュにお辞儀をし、絨毯は空高く飛び立っていった。
マリシュの背後で、炎を吐く怪物が破裂し、鈍い爆音をたてた。
マリシュは村を出て歩いた。しばらくすると地面に座りこみ、やがてそのまま眠りついた。目を覚まして起き上がり、やがてまたしばらく眠った。ひょっとしたら何か食べたかもしれない。はっきり覚えていない。彼はただ自分の両手を眺めていた。ごつごつした手だ。あちこちにたこができていて、爪のあいだには土が入りこんでいる。風が草地に描く波は、横たわる岩と死体に打ち寄せていた。
ある朝、彼が目を覚ますと、破壊された村にジャッカル頭の兵士たちがあふれていた。円盤状の鉄板でできた鎧をつけた兵士が、耳の尖った大きな赤い山猫を乗りまわしていた。黒い長衣をまとったジャッカル頭の男たちが墓碑の寸法を測り、腰巻ひとつの男たちが地面を掘り起こしていた。
マリシュは腰巻姿の一団に近づいて言った。「埋葬を手伝うよ」ジャッカルの頭をした男たちは、彼にシャベルを手渡した。
(完)
(訳:鈴木潤)
作品について
ベンジャミン・ローゼンバウムについては、以前「モリーと赤い帽子」を掲載したときに詳しく紹介しています。この作品もおなじく短篇集The Ant King: And Other Stories(Small Beer Press, 2008)に収められた一篇ですが、初出はTwenty Epics(lulu.com, 2006)というアンソロジーで、これはSF/Fの作家がエピック・ファンタシイを短篇でやってみようという、なんとも斬新なテーマで編んだものです。作者は、ファンタシイ専門のウェブジンにとある作品の掲載を断られたことが、この短篇を書いたそもそものきっかけだったと語っています。「〈剣と魔法〉の物語じゃなきゃファンタシイじゃないって? じゃあ書いてやろう」というノリだったようです。その勢いは作品の筆づかいにそのまま表れています。白い魔女の破壊の轍を急ぐ主人公の疾走感、愛する妻と娘を失ってしまうんじゃないか、もう失ってしまったんじゃないか、いやひょっとすると、とっくの昔に失っていたんじゃないか、という焦燥感が、エピックというテーマならではの遠近法で描かれた世界に、印象的な線をひいていきます。原題は”A Siege of Cranes”で、「鶴の群れ」は直訳ですが、”siege”には「包囲」という意味もあり、語感からエピックを想起させようというねらいもあるようです。そこをうまく日本語で表現できないのがもどかしいところですが、〈作品について〉まで読んでいただいた皆さまには、ここで作者の気概と感性を共有していただけたらと思います。禍々しい大地を見つめ続けてきたところでふいに挿入される、真っ白な鶴の群れが空に飛び立つ美しい場面は、幻想世界のなかの幻想といえるかもしれません。このローゼンバウムの短篇エピックが、読者の皆さまにとってふいに見上げた鶴の群れになりますように。(鈴木潤)