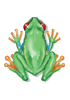デュー・ドロップ・コーヒー・ラウンジ
キャット・ランボー
女がなかに足を踏み入れたとたん、サーシャはそれを感じ取った。ぴょこんと顔を上げるしぐさは、いかにもサーシャらしく、そよ風のにおいを嗅ぐ盲目の熊を思わせる。郊外のお金持ちといったいでたちの女は、店内に目を走らせながら、このコーヒーショップに入ってきた。赤いヘアカラーでつやめく髪は、片目に影を落とすヴェロニカ・レイクふうにカットされている。ぼくが座っているところからはそこまでしか見えなかった。
ノートをバッグのなかに滑り落として、サーシャが前に身を乗り出し、入店者を見据えると、相手も見返した。はじめはちらりと、それからまじまじと。視線に手繰られるように、雑然と置かれたテーブルのあいだを縫って、サーシャのほうに近づいていく。
女のぼそぼそした声は聞き取りづらかったが、何かを尋ねるような口調だということはわかった。サーシャはうなずき、手振りで向かいの席を示した。
まずはコーヒーの注文があり、次に形式的な、あなたも何かいかがですか、いえけっこうです、のやりとりが交わされるあいだに、サーシャは古いマグカップと数枚のナプキンをふたりのテーブルから片づけた。
そして、赤毛の女が椅子を引いた瞬間、サーシャの声が大きくはっきりと響いた。「わざわざ会うことにしたのは、もうこんなことはできないと言うためよ。夫はイラクに派遣され、バサラに駐留しているの」
相手の女は凍りつき、みぞおちを殴られたかのように、胸が張り裂けんばかりの悲しみと、押し殺した怒りのなかばする顔つきをのぞかせた。サーシャはテーブルに視線を落として、青い星の柄を指でなぞっている。まるで日用品の買い忘れを心配しているような雰囲気で、恋の終わりを告げたばかりには見えなかった。
女のうつろな顔のなかで、両目は、色褪せた青い雨戸を下ろすように表情を閉ざした。宇宙がこのいたたまれないひと時の移ろいをながめている。厳然たる不変のまなざしが、ぼくではなく、サーシャとどこの誰だか知らない人にそそがれていることがありがたかった。
赤毛の女が振り返ることもなくおもての通りに消え、ドアが大きく揺れて閉まったあと、サーシャは手つかずのカフェオレとクロワッサンを引きよせた。
「意地汚いな」ぼくは座ったまま言った。
「気取ったビートニクの集会にでも出れば?」
「ちょうどいま、きみの詩を書いているところなんだ。題名は『デュー・ドロップ・コーヒー・ラウンジの麗しき女神』にするよ」
この店の最初の名前はデュー・ドロップ・インで、当時はバーだった。その後、店は次々と人手に渡り、もとの名の洒落もわからない店主たちによって、デュー・ドロップ・レストラン、デュー・ドロップ・ドーナツ・ショップ、デュー・ドロップ・テイク・アンド・ベイク・ピザに変わっていった。最新版がデュー・ドロップ・コーヒー・ラウンジというわけだ。
いまの代で、店主のマイクは、新神秘主義に則って内装をしつらえた。壁のポスターは解剖学的に正しい人体の透視図を載せたものだ。体の部位ごとに、ツボの位置が一連の宝石さながらのしるしで示され、その背景をチベットの曼荼羅が飾っている。日の光は両開きのガラスのドアから差しこんで、釣り糸でぶらさげられた水晶に当たり、カウンター脇のガラスのケースに虹を投げかけて、スコーンや乾きかけたドーナツを七色にちらつかせる。フリスビーサイズのテーブルは星や月の絵で覆われている。
はじめのころ、ぼくはマイクがしつこくかけるスペース・ミュージックの調べにうんざりしていたが、何時間、何日間、何週間、ついには何ヵ月間と聞き続けるうちに、シンセサイザーとクジラの歌声が織り成す音の絵画が頭にこびりついて、いまではごくふつうのBGMのほうに違和感を覚えるようになってしまった。
サーシャは読み物に戻った。ぼくは立ち上がり、ドアを開けて、春の陽気の恩恵に与った。穏かな風が、サーシャのカフェラテの表面を飾るハート型の泡にしわをよせ、新聞の耳を折る。赤い野球帽をかぶった細身の男が入ってきて、店内を見まわしたとき、サーシャはその男と目を合わせ、手招きして、次の門前払いに取りかかった。
「すべては錬金術のようなものだ」先週、マイクはぼくにそう言った。ぼくたちは沸騰させた酢とお湯でコーヒーマシンを洗っていた。蒸気が幽霊みたいに立ちのぼり、マイクの体にまといついて、話に耳を傾ける。
夜間にふたりで働くときは、マイクが独演会を開き、世界の仕組みの秘密を明かすのが常だ。ほとんどは眉唾物で、磁場やら未確認飛行物体やら闇の郵便組織についての話だったが、その世界はぼくの世界よりもずっと刺激的だった。なんにしても、ずっとおもしろそうだった。
とにかく、ここの仕事は捨てたものではなく、ただでさえ役に立たない英語学の学位がさらに価値を下げる一方の不景気にしては、給料も悪くない。だから、ぼくはこのコーヒーショップを片づけ、一ガロンの水のボトルを十本も運び入れ、掃き掃除をして、客がインクの染みた落ち葉みたいに散らかしていった新聞をたたむ。ときには深夜の清掃作業を引き受けなければならないが、マイクはいいやつで、このつまらない仕事を手伝ってくれる。
「うん」ぼくは適当に相づちを打った。マイクと付き合ううえで一番大事なのは、その時々の長広舌をさえぎらないことだとわかっていた。
「つまり、こういうことだ。タロットカードを知っているか?」
「占い師が使うやつ?」
「ああ、そんなようなものだ。タロットカードは金貨、剣、杯、棒の四種類に分かれていて、それぞれがダイヤ、スペード、ハート、クラブにあたる。ここまではわかるか?」
「まあね」
「そのほかに、二十二枚のカードがある。これが大アルカナと呼ばれている」
「じゃあ、小アルカナもあるってこと?」
「そう、そっちが金貨やら何やらのほうだ。ともあれ、大アルカナのカードはそれぞれが人生という旅のステップを示している」
「それを使って占いをするんだよね?」ぼくは言った。
「いや、うん、まあそうだな。だが、人生で誰もが通るステップ、いわば人生の段階のことなんだ」
「なるほどね」ぼくは言った。タンクのなかに水差しを傾け、湯を入れて沸き立たせ、すすぐ。蒸気のにおいを嗅いだ。かすかにつんとするのは、酢の残り香?
「そのことを書くといい」マイクは言った。「錬金術を題材にした文学には名作が多い」
「うん、いい考えだね」ぼくは言った。「そっちは終わった?」
マイクは給湯口に向かって鼻をひくつかせた。「もう一度すすいだほうがいいかもな。そのあと、熱い湯があるうちに床にモップをかけよう。それで今夜は終わりだ」
「つまり、こういうことだ」マイクは考えこむようにしばらく押し黙り、なんの話だったかぼくが忘れてしまったあとで言葉を継いだ。「この世をうろつく化身(アバター)というものがいる。彼らは宇宙の視線の焦点であり、タロットカードの世界と同じように、何度も繰り返される運命の瞬間だ。たとえば、サーシャはそのひとり」
「サーシャ?」
「十時ごろに現れ、読書をしながらコーヒーを飲んで二時間もねばり、ときには午後遅くまで居座るあのやせっぽちのブロンド」
「彼女がなんだって?」
「化身。この店のせいだな。ここが拠点だ」
「焦点って言ったと思うけど」
「違う、人間が焦点だ。この店は拠点で、焦点が集まる場所。ストーンヘンジと同じように、レイラインが交差する場なんだ」
「デュー・ドロップがストーンヘンジと同じ?」
マイクは笑った。「おかしいよな? おれにも理由はわからない」コーヒー豆でぱんぱんの袋でできた丸いピラミッドのうしろから、ウィスキーのボトルを取り出す。「ともかく、こいつを飲んで、お開きにしよう」
翌日、ぼくはサーシャを観察した。
十時少し前で、客が二、三人しかいない暇な時間だった。ひと息つけてほっとした。ゆうべの酒がたたって、胃がむかむかしていたからだ。
十四、五歳の男の子が入ってきた。長い茶色の髪を赤いバンダナでひとつに結び、ベルボトムのジーンズを穿いて、十代らしいひょろ長い体をしている。入り口でぐずぐずしていたが、やがてサーシャが手招きをして、何かを言った。
男の子の下あごが落ちた。
いままで、ただの言葉のあやだと思っていたが、その子はサーシャの言ったことに驚き、文字どおりあごを落としたのだ。ぼくは何か言うか、何かしかけたが、そのとき、それを感じた。宇宙の視線の重みを、ほんの一瞬だけ。ぼくに向けられたものではないが、ごく間近にいたから、サーシャが座って男の子を見上げている地点の空間と時間が、崩れ落ちてしまったかと思った。
男の子はぼくを押しのけてドアに向かった。ジャケットの背中にはチンパンジーの絵と〝ゴット・モンキー?〟の文字が躍っていた。
ぼくは目でサーシャに問いかけたが、彼女は肩をすくめ、手にしていたペーパーバック、『大いなる秘密』に戻った。十五分後、また客がひとり店に入ってきた。年配の女性で、手に黄色い花を持っている。
サーシャの手招きにぎょっとして、それから、人慣れしていない野良犬に餌をやろうとするように、こわごわとサーシャのテーブルに近づいていった。サーシャは立ち上がって椅子を勧めたが、女性は首を横に振り、ラッパズイセンを置いた。
「彼は来ません」サーシャは言った。「幸せな家庭があるんです。あなたにそう打ち明けてほしいと彼から頼まれました。コーヒーとペストリーか何かをご馳走するように、多少のお金を預かっています」おずおずと財布を取り出した。
「いいえ」女性は言った。ラベンダー色のパンツスーツを着て、入念に化粧を施し、色つやのない髪を丁寧にくしけずってある。「いいえ、けっこうです」
痛ましいほど毅然として、出ていった。
「ひどいじゃないか!」ぼくはマイクにレジを任せ、サーシャの向かいに座った。怒りが声帯を引きつらせていた。「いまのはなんだよ?」
「わたしの人生の務めよ、ぼくちゃん」
「他人に成りすましている! 人の人生に干渉している!」
「それほどたちの悪いことじゃないのよ、クレイ」入り口を指差す。「この場所のせい。宇宙のゴミ捨て場なのかもね。ここでコーヒーを飲みながら読書をするようになって、すぐに気づいた。ブラインドデートの相手にすっぽかされる人がしょっちゅういるの。実際に相手と会えた人には一度もお目にかかったことがないけど、ドアのところでためらって、店内を見まわし、先客と目を合わせて、お相手かどうか確かめようとする人たちなら大勢見てきたわ」
サーシャは身を乗り出した。「だから、手を貸してあげることにしたの。わたしのおかげで、逃げ出す理由と、この先数年はディナーパーティで披露できる話のネタができるってわけ。題して、地獄のブラインドデート。メールではとても感じがよかったのに、蓋を開けてみれば……」手をねじる。「……ちょっとまともじゃなかった」
「ちょっとどころか、めちゃくちゃだよ」ぼくは言った。「こういうふざけたことをするやつを罰する法律がなきゃおかしい。いままでどれだけのデートを邪魔してきたんだ?」
「話を聞いていないわね。ここに来る人たちの相手は現れないと決まっているのよ」
「まさか」
「見て」キャットが指差すと、小柄で赤い髪をした男が店に入ってくるところだった。「一マイル先からでも嗅ぎ分けられる。歩道をこちらに向かってくるときの足音の調子でわかるし、ドアを開けたときの顔つきからも読み取れる。でも、今回は手を出さないでおくから、その目で確かめればいいわ。この人は待ちぼうけをくわされるわよ」
ぼくは立ち上がり、注文を取った。エスプレッソのダブル。男はべっ甲のふちの眼鏡をかけ、緑がかった青色のカシミヤのセーターを着ている。店内を見まわし、ぼくがコーヒーを淹れるあいだ、ちらちらとサーシャに目を向けていた。サーシャは顔を上げず、読書を続けた。
男はどうもと言ってコーヒーを受け取り、入り口の近くに座って、腕時計を見た。誰かが入ってくるたび、そちらに首をめぐらせる。四十分で十二人の顔を見たあと、男はコーヒーを飲み干し、肩を怒らせて出ていった。
ぼくはサーシャのところに戻ったが、どう考えていいかわからなかった。
「ほらね?」とサーシャ。
「なぜどんな相手でもさばけるのさ?」
「オンラインでならどんな人間にでもなれるから」
「じゃあ、男のふりもしている?」
「そうよ」サーシャは指についたパンくずを舐めた。
「これまで話していたのと同一人物だって、どうやって思わせる?」
「あの人たちはね、思いこみにとらわれてここにくるの。この宇宙でたったひとり気心の知れた人間と、腰を落ち着けて話をするつもりでね」
「きみは人の夢を壊している」
「この世の理を教えてあげているのよ。辛い思いを乗り越えれば、人は強くなれる。笑い話にできるなら、たいしたことじゃない」
「ゆうべマイクがしゃべっていたわけのわからない話と関係あるのか? きみが化身?」
「わたしがなんですって?」
「化身。マイクが、化身とタロットカードと焦点について何か言っていたんだ」
「マイクはしょっちゅうそういうくだらない話をしていて、そのうち筋が通るのはたった十パーセント。あなただって、まともに受け取るほど馬鹿じゃないでしょ」
「そっちは少しでも筋が通るのか? サーシャ、とにかくおかしいし、きみがこんなことをしていたなんてがっかりだよ」
「感傷的なぼうやは黙ってなさい」
ぼく自身、ブラインドデートで失敗したことがなかったら、たぶんこれほど気に障らなかったと思う。ぼくはマッチ・ドットコムやヤフー・ドットコム、オーケーキューピッドやフレンドファインダー、そのほかあらゆるサイトに登録していた。
返事をよこすのは、会いに行きたいから旅費を送れという女たちや、アラスカに住んでいる熱烈なロックファンで、会うのはいやだが〝遠距離のお付き合い〟ならかまわないと言ってのける女、あるいはシカゴ在住で、以前シアトルを訪ねたときに詩の朗読会でぼくを見かけたなどと言う女だった。この女は写真を載せようとしないので、本当は十四歳の少年なのではないかと思ったものだ。
それでも、ぼくは毎晩のようにかすかな希望を追っていた。パソコンを立ち上げて、メッセージを確認し、口説き文句やお世辞やとにかく甘いにおいのする言葉を送る。そこに、このサーシャだ。やせっぽちで、ちっともかわいくないサーシャにその楽しみを汚された。むなしいものにされてしまった。
「きみはサディストだ」ぼくは言った。「最低のサディストだ」
「わたしが好きでやっていると思うの?」サーシャが言った。
「ああ、思うね。きみはこういうことが大好きで、人の夢を壊す力を楽しんでいるんだ」ぼくは吐き出すように言った。
「じゃあ、ここに座ってその夢が崩れ落ちるのをただながめていろって言うのね。ちょっとしたけじめをつけさせてあげることもできるのに」
「まじめな話、正気の沙汰じゃない」ぼくは言った。立ち上がり、フィルターを洗いに行った。
少しして、そこにマイクが来た。
「おい、サーシャとけんかでもしたのか?」心配そうに尋ねる。
「心の歪んだ異常者だって言ってやったんだよ」ぼくは言った。「あなたが彼女の友だちなのはわかっているけど、あのブラインドデートがどうとかいうのは……とにかく、間違っている!」
マイクは片手を上げて、その先の言葉を制した。「ああ、そうだな。長い話なんだ」高い鼻とスパニエル犬みたいな目をした顔に、悲しげな表情を浮かべる。「なあ、なぜ彼女がここに来るようになったと思う?」
ぼくは当てずっぽうに答えた。「前にここで働いていたとか?」
「いいや。あのな、数年前に、おれは〈ストレンジャー〉紙の個人広告欄を見て、そのうちのひとつに応じたことがある」
「何を言おうとしているのかわからないな」
「彼女に待ちぼうけをくわせたんだ」マイクは言った。「木曜の朝十時半にここで会おうと約束した。そりゃあ楽しみにしていたんだが、彼女が現れたとたんに怖気づき、黙ってコーヒーを出して、おれを待つのを見ていた。彼女は三十分ほど待って、温めたバタークロワッサンを食べ、ホットチョコレートを飲んで、出ていった。翌日、同じ時間に、今度は本を持ってやって来た。カミュの何かだ。それからというもの、週に三回か四回、ときにはそれ以上ここに通っている」
「なんで何も言わないのさ?」
「彼女は化身だ」マイクは言った。その声は畏怖に満ちていた。「おまえも感じなかったか? 現実を超越しているんだ。だから、どうにも近よりがたく、それでいて人を惹きつけてやまないところがある」ふいに言葉を切り、何かを思いついたというようにぼくを見た。「おまえもサーシャに惹かれているんだな? だからそんなに腹を立てているんだろう?」
「ぼくが腹を立てているのは、サーシャが悪意に満ちた心理劇を演じて、そのなかで人の人生を弄んだり、荒らしまわったりしているからだよ」ぼくは言った。「あなたが待ち合わせの相手だったって、サーシャは知っているの?」
「わからないのか?」マイクが言った。「ここで起こっているのはまさに超自然的な出来事なんだぞ。おれが彼女をここに導き、彼女は化身になった。原理はさっぱりだが」
頭がずきずきしてきた。「家に帰る」ぼくは言った。「吐きそうだ」
「帰れ、帰れ」マイクはしっしと手を振った。「だが、気分がよくなったら戻ってこいよ。それから、サーシャとはもうけんかするな」
ぼくは四日間仕事に出なかった。大学時代の友人たちと、連夜、元床屋だったという流行りのバーに繰り出した。骨董もののヘアドライヤーが、鋲を打った宇宙人のヘルメットみたいにずらりと壁に並び、ブリーチされた髪の毛付きの袋が天井から下がっていた。バンドが次々に登場して、夜ごと似たようなわけのわからない歌詞を、煙草でかすれた声で歌った。仕事に戻ったとき、ぼくはまだ千鳥足だった。マイクは何も言わず、ただぼくに目をそそぎ、特大のマグカップで本日のコーヒーのタンザニアンローストを淹れてくれた。そのあと、ぼくは床を掃き、洗濯バサミを使って、北側の壁に張ってある棚代わりのロープ・ネットに新聞を留めた。
サーシャは昼前に来て、ぼくの姿を見ると、はっとして足を止めた。本を ―― チャールズ・ウィリアムズの何かだった ―― を目の前のテーブルに置き、もう片方の手でポケットを探って紙幣を取り出した。
「クレイ」サーシャは言って、くしゃくしゃの紙幣を丁寧に伸ばした。「クレイ、話があったのよ。あのブラインドデートのことだけど、絶対にうまくいかないと言いたかったわけじゃないの。もちろんうまくいくこともあるし、うまくいっている人たちもいる」
サーシャの口からぽろぽろとこぼれる言葉は、まるで玉石、まるでダイヤモンド、まるで何かのおとぎ話の、心優しいお姫さまがしゃべると出てくるもののようだった。
「ここで終わった人たちは、もともとうまくいかない運命だった。わたしの言いたいこと、わかってもらえる? わたしは人の恋愛を壊しているわけじゃない。あなたはいい人だし、このことはもう何も言わないつもりよ」
窓から差しこむ光が、サーシャの藁みたいな髪に落ちて、ラッパズイセンのように黄色く輝かせている。ぼくは仲直りに応じ、次のコーヒーをおごらせてほしいと申し出て、そのやりとりのどこかで、マイクの言っていたことがひとつは本当だったと気づいた。ぼくはサーシャに惹かれていた。あるはずのない入り口を開いたような、クローゼットの奥にコートではなくナルニアの国を見つけたような、神秘的で、思いがけないものに惹かれる気持ちだ。
だからといって、何ができる? ぼくは沈黙を守った。それ以来、サーシャが来るたびに、マイクとぼくは目を見交わし、ふたりともその磁力を改めて思い知るのだった。すさまじい力で、体の奥深くから引きよせられ、ぼくたちはほかの誰かを求めるなど想像もできない状態に陥っていた。
そして、ぼくは化身たちに思いを馳せた。本人の言葉どおり、サーシャは本当に宇宙の裂け目のようなものを感じているのか? 化身はほかにもいるのか? ぼくの知り合いのなかにいたり、通りですれ違ったり、あるいはダブルのホットチョコレート、クリーム抜きをぼくの手から受け取ったりしているのだろうか?
彼が現れたとき、そして、ぼくたちを引きつけてやまない磁力の源がびくっとして、電気が走ったような反応を見せたとき、マイクもぼくもすぐさま悟った。サーシャが息を呑むさまや、ぴくりと肩を動かすようすや、カップを置いて顔を上げるしぐさから感じ取れた。
彼は若きガラハッドのように端整な顔立ちをしていて、その鼻筋にも、古代ギリシャ・ローマふうに頭を覆う巻き毛にも、凛としてなおたおやかな雰囲気があった。
視線はサーシャに向けられたが、このときのサーシャはほほ笑むことも、手招きすることもしなかった。じっと座って、目を大きく見開き、言葉もなく彼を見つめている。彼はしなやかな足取りでサーシャのテーブルに向かい、三歩でその前に立ち、身をかがめて何かを言った。
「ええ」サーシャは答え、手を差し出した。「わたしです」彼は手を取って唇によせ、甲にキスをした。シャツを脱いだにも等しいほどなれなれしいふるまいだ。
この男も化身? 私心のない女性たちを慰めるのが務め? コーヒーショップで人に声をかけるのが? 片思いに悩む男を怒らせるのが? この男はいったいどんな役割を演じている?
マイクとぼくは並んで突っ立ったまま、モカのおかわりを頼もうとする女性客を無視して、ただじっと見つめていた。サーシャが荷物をまとめ、男がその腕のなかにサーシャを包みこむようにして、ジャケットを着るのに手を貸すところをながめていた。
一瞬、サーシャが振り返り、ぼくは何かを言うならいまだと思ったが、マイクの靴のかかとがぼくの足にくいこんだ。ぼくは叫び声を上げ、サーシャはふっと笑い、マイクに手を振って出ていった。
「あのかわいそうな子にささやかな幸せを与えてやれ」マイクが言った。「息抜きだ」
「明日、戻ってくるかな?」
マイクは肩をすくめ、ようやくカウンターに目を向けて、からのカップが置いてあるのを見た。「さあな。わからんね。もしかしたら彼女はもう化身じゃなくなるのかもしれない」
マイクがモカのおかわりをついだあと、女性客は飲み物を手に取り、店内を見まわしてから、ぼくに目を合わせた。一歩前に出る。
彼女の肩越しから誰かに見られているような感覚に襲われた ―― ぼくは焦点に収まったのだ。彼女が口を開いたとき、その言葉のひとつひとつは、存在しない巨大な歯車が噛み合う音となって響いた。
「すみません」彼女が言った。「二時十五分にここで人と会うことになっているんですが……」
ドアの上のベルが鳴って、べつの客が入ってきた。格子縞のジャケット、クルーカットの髪、やや年配で、視線は店内をさまよっている。
ぼくはぐっと胸を張った。
「まずはじめに」前に乗り出して、彼女の袖にふれた。「メールであなたに言ったことはすべて嘘です」
(訳:松井里弥)
注1: 1919‐1973、アメリカの女優。40年代に『拳銃貸します』などのフィルムノワールに主演して人気を博した。当時の作品が60年代にテレビで再放送されたことから人気が再燃。『L.A.コンフィデンシャル』でキム・ベイシンガーが演じた娼婦はヴェロニカ・レイクを模している。
注2: ドゥ・ドロップ・イン(お立ちよりください)をもじったもの
注3: 古代の遺跡や史跡のなかには直線的に並ぶように作られたものがあるという仮説において、その直線のことを指す。それが特別なエネルギーの道筋だという主張もある。ストーンヘンジはいくつかのレイラインが交わる地点だとされている。
注4: MLBでロサンジェルスに本拠地を置くエンジェルスでは、ホームの試合で六回以降にチー�ムが負けているか同点のとき、チームマスコットのラリー・モンキー(逆転猿)がオーロラビジョンに現われて応援をあおる。その時、大騒ぎになるスタンドのようすを指している。
注5: アーサー王伝説、とくに聖杯伝説に登場する円卓の騎士のひとり。穢れのない純潔な騎士として描かれる。
作品について
まずは、一度聞いたら忘れられない名前である。これがほぼ本名(CatはCatherineの愛称、Ramboは結婚後の姓)というのだから驚きだ。こんな作家がいるよ、と本作「デュー・ドロップ・コーヒー・ラウンジ」を紹介されたとき、名前の妙に惹かれて飛びついた感は否めない。しかし、キャット・ランボーが名前に引けを取らないストーリーテラーだったことは、本作品、あるいは先に本サイトで公開された「死んだ女の子の結婚行進曲」でおわかりいただけることと思う。
キャット・ランボーが作家の道を歩み始めた経緯は、「死んだ女の子の結婚行進曲」の末尾に付された〝作品について〟をご覧いただきたい。そのなかで小川氏が書いているとおり、短編集のおおよそ半分はタバトという架空都市を舞台にしているが、本作品はそうではないほうの半分に入る。作者がドーナッツショップで見知らぬ女性からブラインドデートの相手と間違われたことをきっかけに生まれた物語だ。初出は2008年のオムニバス短編集、Clockwork Phoenix。その後、今年はじめて発表したソロ短編集、Eyes Like Sky and Coal and Moonlightに再収録された。現在はYAを執筆中で、もうすぐ完成とのこと。非常に楽しみだ。
短編集、Eyes Like Sky And Coal And Moonlightについて、詳しいことは近日中にレビューのコーナーへアップする予定です。(松井)
Eyes Like Sky And Coal And Moonlight
-
Her Eyes Like Sky, and Coal, and Moonlight
-
The Accordion
-
I'll Gnaw Your Bones, the Manticore Said
-
Heart in a Box
-
In the Lesser Southern Isles
-
Up the Chimney
-
The Silent Familiar
-
Events at Fort Plentitude
-
Dew Drop Coffee Lounge (本作品)
-
Narrative of a Beast's Life
-
Eagle-haunted Lake Sammammish
-
Sugar
-
A Key Decides Its Destiny
-
The Towering Monarch of His Mighty Race
-
In Order to Conserve
-
Rare Pears and Greengages
-
A Twine of Flame
-
The Dead Girl's Wedding March (「死んだ女の子の結婚行進曲」)
-
Worm Within
-
Magnificent Pigs