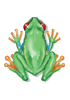ウナティ、毛玉の怪物と闘う
ローレン・ビューカス
そいつが東京を襲ったとき、ウナティはカラオケで歌っていた。というか、まさに歌おうとしていたところだった。さらに言えば、ビッグエコー渋谷店に新着配信されたばかりの曲を一番乗りで歌いあげてやろうとしていたところだった。ブリトニーがカムバックで歌ったスパイス・ガールズの名曲“Tell Me What You Want(What You Really Really Want)”のヒップホップ・リミックスを熱唱しようとしていたのだ。
ショータイムをおっぱじめるには、まだ外は明るすぎたかもしれない。でもウナティは休暇中だったし、じつのところ彼女をはじめ〈サイコー戦隊〉の隊員たちは早起きしたわけではなく、きのうの夜からぶっとおしで、ここから横浜まで川ができそうなくらいの日本酒をあおり、べろんべろんで盛り上がっていたのだ。
ウナティは個室のテーブルに乗っかり、同僚の殿方(マドーダ)の目の前に、ミニ丈のプリーツスカートの下から白いパンティをちらつかせていた。もちろん彼女だって、空軍曹長の任務中にはびしっと臙脂と灰色の飛行服や軍支給のトラックスーツを着る。
でも私生活では思いっきりはじける。なんてったって地元ヨハネスブルグにいた頃、地球上でもっとも優れたこのメカ戦隊の一員に選ばれるまえは、 〈44スタンリー〉とか〈ニュータウン〉のあたりに入りびたっていた、超 amakipkipガールだったのだ。地元っ子におなじみの極彩色のポップコーンにちなんで名付けられたそのブランドの“ネオ・パンツーラ”風、つまりパンクでワルぶったセンスにかぶれて、ぴったりした紫のジーンズにどぎついオレンジやらグリーンやらを合わせ、豹柄のヒールを履いていた。そんでもって頭はモヒカンできめて、小柄な身長に10センチほど上乗せしていたわけだ。
新しい故郷となったこの国では、“パンク・ロリータ”に夢中になった。 グウェン・ステファニー的な原宿系きどりのロリパンクとはわけがちがう。非番のときに穿くのは女子高の制服風スカート。でも生地はアンティークの着物で、しかも古着商の見立てによると、ヒロシマの原爆に耐えて残ったものだという。髪は伸ばして軽くカールさせている。モヒカンよりは戦闘向きの髪型だ。だがなんといっても最大のポイントは、白いエナメルの膝丈コンバット・ブーツ。みずからの手で殺したクジラのペニスの皮で作ったものだ。
テーブルの上に立ったウナティのうしろで、ミラーボールの光線が後光のようにきらきら輝いた。マイクがそのピアスをつけた形のいいくちびるに近づくにつれ、時間がおごそかなスローモーションに切り替わっていった。
あるいは、リュウ・ナカムラ中尉の目にそう映っただけかもしれない。休日は ストリート・ファイトに明け暮れるこの男、ウナティ・マサバネ空軍曹長に恋をしており、それはもう、植物が光合成を欲するがごとく彼女にぞっこんだった。
リュウの目には、ウナティをとりかこんで時間が猛暑でへばったウナギのごとく、ぐんなりしたまま動かなくなったように見えた。情けないことに、そのたとえはそっくりそのままリュウ自身の舌にも当てはまった。彼女のそばにいると、指令に応答する必要にでも迫られないかぎり、だらしなく舌を垂らしてしまうのだ。彼は今日こそ熱い想いを打ち明けるつもりだった。そのためにカラオケ・マシンにロマンティックなデュエット曲の予約を入れてあった。
だがそれは、何やらペニスみたいな形の物体がガラスやコンクリートの破片をまき散らし、通行人をふっ飛ばしながらビッグエコーの壁をぶち破ってくるまでの話だった。
見るもおぞましい怪物だった。黒光りするもじゃもじゃの毛のような触手は、日本製の軽自動車ほどの太さがある。内臓がはみ出してるみたいにあちこちにから突起が伸び、球根のような形の頭には目がなく、ただ真っ黒い牙がびっしり生えた口が開いている。
そいつの第一撃でテーブルがひっくり返り、乗っていたウナティは宙に投げ出された。頭からまっさかさまに落ち、まるで地殻変動でも起こったような音をたてて床に激突した。さらにすかさずテーブルが胸の真上にのしかかってきて、肺の空気を残らず押し出した。軽い脳震盪状態の視界のなかで、黒い泡がはじけ飛んだ。背後にはズゥンズゥンと卑猥なビートにのせてスパイス・ガールズの名曲をラップするブリトニーの声が響いている。
立ち上がろうともがくウナティを尻目に、触手の怪物は寿司職人よろしく〈サイコー戦隊〉を手際よく料理していった。サトウ技師長の背骨がいきおいよくへし折られ、脊椎が胃袋から飛び出した。ウナティの目と鼻の先の床のうえで、技師長は体をぴくぴく痙攣させた。やつは触手の1本でタナカ少尉の内臓をえぐり出し、もう1本でスズキ伍長を真っ二つに引き裂いた。そして尖った歯でリュウの頭をもぎ取り、ポキンといい音を響かせた。
カラオケ・マシンがデュエット曲を奏ではじめた。“Looking in your eyes, there's reflected paradise”(きみの瞳をのぞきこめば、そこに楽園が見える)リュウにまだ目があったら、というか頭があったら、マジで楽園が見えたかもしれない。彼はもじもじしてる酔っ払いみたいに、しばらくおぼつかない足で立っていた。やがて真っ赤な生血が首の切断面からいきおいよく噴き出し、〈ぶっかけ吸血鬼〉とかそんなタイトルのAVみたいに、ウナティの顔面に盛大に血しぶきを浴びせた。彼女はむせ返りながら叫び声をあげた。リュウの恋心にはうすうす感づいていた。だってほら、指令を申し渡すたび、にかっと歯を見せて、照れくさそうに頭のうしろをぼりぼり掻いてたし。それにこの80年代のクサいデュエット曲。決定的だ。そのリュウが死んでしまった。〈サイコー戦隊〉の全員が死んでしまった。さらにむかつくことに、お気に入りのクジラのペニス皮の白いエナメルのブーツが、血と日本酒でぐちゃぐちゃになってしまった。
「このつけは何がなんでも払ってもらうわよ!」ウナティは喉をげぼげぼいわせながらわめき、胸にのしかかっていたテーブルを押しのけると、いきおいよく立ち上がってサーベルを抜いた。だが触手の怪物はすでに、大虐殺の現場をずるずる這うようにして撤退していくところだった。ウナティはひっくり返ったテーブルを(そしてまだぴくぴくしているサトウ主任技師を)飛び越え、ぽっかりと穴の開いた壁を飛び越えた。ハイヒールのブーツで着地して腰を低く落とすと、すかさず空を見上げた。敵の姿がぼんやりと、流行の発信地〈渋谷109〉の真上に見える。サンドトン・シティのモールなんか駅前銀座の蚤の市に見えてしまうほどのきらびやかなファッション・ビルだ。
まるで血糊でべとべとになったゴジラ大の毛玉だった。黒いもじゃもじゃの毛のなかに大きな口が見え、サメの歯みたいに幾重にも並ぶ鋭い牙をぎしぎしいわせながら開いたり閉じたりしている。体から触手のように伸びている黒い毛を、まるでひきつけを起こしたマンガのタコの足みたいにぶんぶん振りまわし、高層ビルに亀裂を入れ、由緒ある仏塔だろうがおかまいなしに破壊していく。
ウナティは立ち上がって走り出した。敵にむかってではない。メカを隠してある8ブロック先の竹下通りにむかってだ。そこしか駐車スペースが見つからなかったのだ。
巨大ロボット〈ゴーストVF-3〉にはゼブラ・ストライプの塗装がほどこしてある。まあ、ちょっとした故郷へのオマージュだ。それは駐車したときのまま休止状態で待機していたが、鍵爪を模した左脚の甲の合金に違反切符が貼り付けてあった。ウナティはそれをひっぺがし、 ユニコーンの形に折って舗道に投げ捨てた。駐禁パトロールの婦人警官へのごあいさつ。どうせそいつも東京じゅうの公務員の例にもれず、アンドロイドにちがいない。人間になる夢ばっか見ている連中。
ウナティはメカの胸部に据えられたごつい複式回転砲を足場にしてフロントをよじ登った。だが肩部の装甲にきたところで5分ほど手間どってしまった。キーを捜してばかでかいヴィトンのバッグの中身をさんざんひっかきまわしたのだ。
よりによっていちばん底で見つかった。 ハロー・キティのヴァイブレーターと、きのうの手つかずのお弁当のあいだに挟まっていた。ロック解除装置をビーッと鳴らすと、水圧式ブレーキがシューッと空気を漏らし、作動装置がブーンとうなりをあげた。メカの無表情な顔面部が両肩に折りこまれ、コックピットが現れた。ウナティは操縦席に飛びこみ、次々にスイッチをはじいた。
〈ゴーストVF-3〉が低いエンジン音をあげはじめた。サムライの鎧を模した背中の棘飾りが倒れ、扇状に広がって連動式の戦闘機主翼に形を変えた。いまやエンジンの轟音は竹下通り全体を揺るがし、周囲の高層ビルの窓ガラスを震わせていた。ウナティは気持ちよさそうに 〈トップガン〉のテーマ曲をハミングしながらディスプレイ上の 数独パズルに取りかかった。全問正解で〈ゴーストVF-3〉の武装ロック解除だ。
「戦闘準備が完了しました」最後の数を入力すると、落ち着き払った女の声が告げた。4だ。4人の〈サイコー戦隊〉の男たち。ビッグエコーの床で、みずからの血と髄液の海のなかで息絶えた仲間たち。彼女は眉間に皺をよせ、ロケットエンジンを発射させた。〈ゴーストVF-3〉はいきおいよく離陸し、駐車場にどでかいクレーターを残した。舗道でユニコーンの折り紙が火に包まれた。
戦闘には目が追いついていかなかった。文字どおりの意味でだ。たぶんまだ酔いが残っていたせいだろう。
〈ゴーストVF-3〉が邪悪な毛玉にむかって突進すると、色彩が流れ、メカの軌道が線を描いていくように見えた。1本の触手がぎこちないコマ送りのスローモーションでメカに激突する。〈ゴーストVF-3〉の機体はその衝撃に二つ折りになり、後方に吹き飛ばされて〈渋谷109〉に突き刺さる。ぼろ布と化したブランドものの服が空を舞い、真下の通りで着飾った十代の女の子たちが首をすくめて瓦礫と火の粉をよけながら、苦悶の悲鳴をあげる。
コックピットのなかでは、ウナティが操作パネルを叩きながら母語で最大級の悪態をつきまくっていた。「冗談じゃないわよ! ふざけんな! こんちくしょう(マスーヌ・カ・ニョーコ)!」やがて〈ゴーストVF-3〉は身をよじってビルの壁面から抜け出し、崩れかけた壁にはくっきりメカ型の跡が残った。片方の翼は衝撃でもげ落ちていた。「よくも“カワイイ”を台無しにしてくれたね!」ウナティは悪態をついて、システム診断を呼び出した。やっぱいまどきの機械はなってない。だから最高司令部の上官たちに韓国製を買うべきだって言ったのに。
片翼を失くしてまっすぐ飛ぼうにも飛べなかったけど、それ以外に深刻なダメージはないようだ。機体側面の放熱装置に若干のへこみ。むかつくことに右後方のカメラが破損。でもすくなくとも、リーヴァー砲は無傷。ウナティが操縦桿を前に倒すと、〈ゴーストVF-3〉は毛玉の怪物を追って通りを駆け出した。装甲板金の足裏が地面に着地するたび、コンクリートに亀裂が走った(そして、すくなくとも1人のイケてる女子中高生が踏みつけられてぺちゃんこになった)。
意識を取り戻すと、まるで口のなかに二日酔いの鬼でも居座ってるみたいな気分だった。起き上がってみても視界はかすんだままで、すぐに喉に血の味がこみあげてきた。ウナティは口もとを拭い、あたりを見渡した。世界はなかなか焦点を結ばなかった。ぼんやりとした人影が近づいてきて、やがて温厚そうな中年の男の姿が見えた。手が伸びてきて、ハンカチを差し出した。「どうぞ」彼は言い、ウナティはそれで口のまわりについた血の染みを押さえた。カーペット敷きの床から、片方の耳だけ白い黒猫がものめずらしそうに見上げている。背後にはかすかにジャズが流れている。マイルス・デイヴィスね、と彼女は思った。まあ、じつはジャズといったらマイルス・デイヴィスしか知らないんだけど。
「ここはどこ? 何がどうなっちゃったの?」彼女は言い、血がべっとりついたハンカチを返した。男はそれを折りたたんでポケットにしまった。
「それはぼくが聞きたいところだけどな」彼は頭をかしげ、こじんまりしたキッチンだったとおぼしき場所を示した。〈ゴーストVF-3〉が煙をあげ、瓦礫まみれになって大の字に倒れている。いや、それはメカの一部にすぎない。頭部と片方の肩だ。胸腔部分のフレームはもげ落ちてところどころ溶け、そこに粉々になったリーヴァー砲の破片がくっついている。その光景にウナティは喉をつまらせた。最初はブーツ。お次は〈VF-3〉。おそるべき蛮行はいったいいつまで続くのだろう?
彼女は目を閉じた。記憶がポラロイド・カメラの連続写真のようによみがってきた。
〈ゴーストVF-3〉が渋谷駅に激突。
毛玉が列車を半分まで飲みこむ。車両がまるでトンネルに入るように、ぎりぎりと歯ぎしりしている口の奥に消えていく。
〈ゴーストVF-3〉がたまたまいちばん手近にあったパンティの自販機をつかみ、毛玉の怪物に投げつける。
焼け焦げたパンティが空を舞う。
〈ゴーストVF-3〉が飛び上がり、空中で闘う2羽のタカのように、毛玉と激しく組み合う。翼が壊れているせいで、両者はぐるぐる旋回しながら飛行。
やがて――ここがどうにも奇妙な場面だ――2本の触手が〈ゴーストVF-3〉の両脚と胸部をとらえてねじりあげ、ぞっとするような生々しい音をたてながら金属の装甲を突き破る。その寸前、ウナティは相手の体のど真ん中にメカの手をつっこんで、毛束をカーテンみたいにひっぱり、すると…… 七色のスマイル・フェイスの花が現われる。
「スパゲティはどうだい?」男が話しかけてきた。彼は首をすくめて、もげ落ちた〈VF-3〉腕の下をくぐった。垂れ下がった配線が火花をパチパチいわせている。その奥に奇跡的に無傷のままのコンロがあり、深鍋にお湯がぐらぐら沸いている。
「いいのよ、オジサン。あたしもう行くから。あの怪物をやっつけなきゃ!」ウナティは威勢よく言ったが、足もとはどうにもおぼつかなかった。
「腹が減っては戦はできぬだよ」男は穏やかな声で言い、自分の皿にスパゲティを盛り、新鮮なバジルをふりかけた。
ウナティは警戒するような目つきで男を見た。「あのさ、突然空から炎に包まれたメカが墜落してきてキッチンをぶっ壊されたにしては、ずいぶんと冷静じゃん。あんたいったい何者?」
「ぼくは作家だ。まえは広告会社に勤めていたんだけど、辞めたんだ。これという理由があったわけじゃない。ただその仕事が好きじゃなくなったんだ」
「じゃあ、何が好きなわけ?」ウナティはまだ疑るような声で訊いた。
「音楽かな。それと料理。ジョギングのことを考えること。きみは?」
「あたしが何者かってこと? それとも何が好きかってこと?」
「じゃあ最初の質問から」
その質問にウナティは深く考えこまされた。「メカ戦隊の隊長。怪物相手に闘ってることをおいとけば、ソウェト出身のふつうの女の子なんじゃないかな」
「すてきじゃないか」作家は言った。
そのとき電話が鳴った。どことなくいらだたしげな鳴り方だった。「おや、ちょっと失礼するよ」作家はふたたびメカの腕の下をくぐり抜け、玄関に入って電話を取った。
きゃしゃな造りの灰色の電話機は、なんだか懐かしい感じがした。「もしもし?」彼は受話器にむかって言った。「またきみなのかい? こんなふざけたお遊びに付き合ってる暇はないって、ちゃんと言ったはずだけどな」彼はしばらく耳を傾けていたが、やがて受話器をウナティの方に差し出した。「きみにだ」
ウナティは脇腹を押さえ、足をひきずりながら電話の方にむかった。まちがいなく肋骨が折れてる。しかもたぶん1本じゃ済まない。彼女は受話器を受け取って耳に当てた。
「もしもし」落ち着いた女の声が聞こえた。ちょうどメカの音声システムみたいだ。
「どうも」ウナティはたじろいだ。
「ハルキのスパゲティは食べた?」
「いいえ」ウナティは言った。
「食べてごらんなさい。彼の料理の腕前はすばらしいわよ。きっと気に入るわ」
「ちょっと、あなたあたしのこと知ってるの?」ウナティはむかつきはじめていた。
「ええ、何度も顔を合わせてるもの。わたしはいま何も身につけていないって、もう言ったかしら? シャワーから出てきたばかりなの」
やれやれ。テレフォン・セックスってやつね。よりによってこんなときに。「あたしはいま毛玉の怪物を追いかけてて、そいつがこの街まるごとぶっ潰しちゃうまえにどうしてもやっつけなきゃいけないんだって、もう言ったっけ?」
「まあ。いいえ、聞いてないわ。じゃあもう行かなきゃね」
「この電話ってなんか意味あるわけ?」いっそガチャンと切ってやろうか。でも女の声にはどうもひっかかるものがある。妙にどこかで経験したことがあるようなシチュエーションだ。デジャ・ヴュってわけじゃないけど、映画で観たとか、それとも小説で読んだとか。
「ないわ。ただご挨拶しようと思っただけ」
「それはどうも。じゃあね」
「ねえ、自殺の森にぜひ行ってみて。この時期は見頃だわ」
「え?」
「青木ヶ原よ。富士山の麓(ふもと)の」
「それは知ってるけど」
「きっと手がかりが得られると思うから。それだけよ」女は朗らかに言った。「じゃあね」
ウナティはしばらくツーツーという音を聞いていたが、やがて受話器を置いた。「いったいなんなのこれ?」彼女はハルキに訊いた。
「さあ。彼女はときどき電話をかけてくるんだ。あまり気にしないことにしてる」
「あたしに青木ヶ原に行けって」
「どうして彼女がそんなことを?」
「知らない、こっちが教えてほしいわ。彼女はあなたのミステリアスなお相手なんでしょ」
「うーん、行ってみるべきかな」
「そうね、もしかして毛玉の手がかりが得られるんじゃないかしら」
「“骨折り損の羊をめぐる冒険(ワイルド・シープ・チェイス)”になるかもしれない」ハルキは言った。
「それを言うなら“骨折り損のくたびれもうけ(ワイルド・グース・チェイス)”でしょ」
ウナティは慣用句の誤用というやつをそのままにしておけない質(たち)だ。
「そうそう、それだ。なぜかごっちゃになっちゃって」ハルキは詫びた。「ともかく、ぼくは近道を知ってる。この路地を通っていくんだ」
彼はウナティを勝手口にうながし、ふたりは小さな裏庭に出た。白と緑のデッキチェアと、そのわきに本が置いてあった。彼はウナティに手を貸してブロック塀のうえにひっぱりあげ、民家の裏手に沿って伸びている小道を進んでいった。白と黒の斑猫が塀に飛び乗って、ふたりの姿をしげしげと眺めた。
「ぼくはここを路地って呼んでる。でもほんとうは路地なんかじゃない」ハルキは言った。「通路でもない。専門的に言えば、通路というのは入口があって出口があるものだ。でもそんなものないからね。かといって袋小路ともちがう。袋小路にはすくなくとも入口があるものだ。それよりはむしろ“行き止まり(デッド・エンド)”というべきなんじゃないかな」
「無駄口叩いてないで早いとこ青木ヶ原に連れてかないと、あんたがデッド・エンドになるわよ」
「ああ、わかったわかった」作家は言った。「すまなかった」そしてしばらく何も言わずに彼女のまえを歩いた。小道の両わきには有刺鉄線が張られている。たしかに彼の言うとおりだ。ここは通路でも袋小路でもない。頭上に茂る木のなかから鳥の鳴き声が聞こえてくる。おもちゃのねじまきを巻くような、あるいはバネが伸びるような声。猫が塀から飛び降り、ふたりについて歩き出した。
しばらくすると井戸にたどり着き、ウナティは作家に手を貸して蓋を開けた。木製の蓋のうっすらと湿った縁には苔が生えていて、金属製の取っ手が埋めこまれていた。井戸のなかは真っ暗で、闇にむかって金属製のはしごが降りている。まだ新しいし、手入れも行き届いているようだ。強烈な臭いがむうっとたちのぼってきた。サリンガスでも充満してるような、死体でも隠されているような、あるいはそのどちらもが混ざったような臭いだ。
「レディーファーストでどうぞ」ハルキが言った。猫が彼の肩に飛び乗った。とりあえずいっしょにいってみるか、みたいな顔で。
ウナティは溜息をついてブーツを見下ろした。こんな調子じゃ、またクジラを捕りにいかなきゃいけなくなりそう。
439段、梯子を降りたところで、とうとう足が粘土質の底に着いた。
「古い人工のトンネルなんだ」ハルキは梯子から降り、手のひらの土を払いながら言った。「たぶん雨水排水用の。それか、地下鉄に通じてるのかも。廃線になった青木ヶ原行きの線路なのかもしれない」
「それか、地獄への直通道路かもね」ウナティはぶっきらぼうに言った。
「それはないと思うな」ハルキが言った。猫が肩から飛び降り、ふたりのまえを歩きだした。しばらくするとふり返って、「ねえ、来ないの?」とでも言ってるみたいにミャーオと鳴いた。
ふたりは猫のあとについて歩きはじめた。30分ほどすると、目の前にセメント造りの待避壕が現れた。錆びた鉄製の扉がしっかりと楔(くさび)打ちしてある。つい最近、誰かが通ったような形跡がみえる。そのわきの壁に、積み重ねられた絵の山が寄りかかっている。いちばん上にあるのは、カラフルなテーマパークのおばけみたいなものが描かれた絵だ。トンネルの隅にはアニメキャラの等身大のフィギュアが置いてある。髪の毛をツンツン逆立てたその男の子は、勃起した自分のペニスをむんずとつかんで、頭上に精液をふりまいている。
「これ知ってる」ウナティは言った。カウボーイの投げ輪よろしく精液をふりまわしている素っ裸のアニメキャラなんて、いちど見たら忘れるはずもない。「あのアーティスト集団の作品よ。ほら、ハングリーな若い芸術家を集めて作品を量産してる、超有名なあの男が主宰者のさ、なんていったっけ?」エイリアンの襲撃前、まだ軍に入隊していなかった頃、彼女はゲイシャ文化習得講座というふざけたセミナーを受けたことがあった。そのおかげでファイン・アートから政治、ジャスミン茶のありとあらゆる淹れ方などなど、その場にあわせた話題のひきだしというものが驚くほど増えたのだ。
「ああ、ぼくと同姓で」作家は言った。「名前はタカシだ」
「そうそう。まあなんだっていいけど」いらいらしながら絵をめくっていくと、いやになるほど見慣れた図柄が目にとまった。ウナティはその絵をひき抜いてじっくり眺めた。虹色の花びらに囲まれて、イッちゃってるみたいに満面の笑みを浮かべてる花の顔。あの毛玉の怪物の真ん中でぎらついていた顔とそっくりだ。
「それにこれもめちゃよく知ってるよ」彼女は言った。「だけど、なんでここに?」
「そんなことより」作家は錆びついた扉をぐいぐいひっぱりながら言った。「扉が開かないんだ」
「まあ見てなさいって」ウナティはにっと不敵な笑みを浮かべ、狙いすました空手キック一発で扉を蝶番ごと蹴破った(これもまたべつの文化習得講座の成果である)。
扉の外には森が広がっていた。茂った葉のあいだから、幾筋にも淡い金色の木漏れ日が射している。生い茂る葉のむこうに、富士山がぼんやりと見える。頂上の下に、雲がフラフープみたいにぐるっと輪を描いてたなびいている。猫が立ち止まって体を舐めた。木の葉を抜けて吹く風が、幽霊の笑い声みたいな音をたてた。
「超きれい」ウナティは息を飲んだ。次の瞬間、周囲の木々に、まるでクリスマスの飾りみたいに、いくつもの死体がぶら下がっているのに気づいた。顔は黒ずみ、眼球が飛び出している。首を絞められた場合に特有の現象だ。
死体はベルトやケーブル、それからネットみたいなもので吊り下がっていた。車のルーフにマットレスを縛りつけるときになんかに使うやつ。ほんの何週間か前、スズキ伍長の新しいカプセル・アパートメントへの引っ越しを手伝ったとき、ちょうどこんなのを使ったっけ。
「自殺の森――」猫がつぶやいた。「ゴールデン・ゲート・ブリッジに次ぐ人気の自殺スポットだ。『黒い樹海』の悲劇的なラストがブームのきっかけになったという説もある」
「あんた言葉を喋れるのね」ウナティは言った。
「喋れないよ」猫は無愛想に言って体を舐め、長い眉の毛の下から不機嫌そうに彼女を見上げた。
「なぜみんな坊主頭なんだろう」作家がぼそっと言った。
ウナティははっとした。そのとおりだ。まだ顔がちゃんと残っているものから鳥やリスに目玉やくちびるを齧られているものまで、死体の腐敗の具合はまちまちだ。格好だって、不祥事を起こしたサラリーマンらしきものもあれば、『黒い樹海』を地でいく絶望した主婦とか、許されぬ恋路の果ての若者たちとおぼしきものまでいろいろだ。だけど、どの死体にもひとつだけ共通点がある。髪の毛がきれいさっぱり刈り取られているのだ。
「なんかおかしなことが起こってるみたいね」ウナティは無意識下で操縦桿に手を伸ばし、リーヴァー機関砲の1クォート瓶サイズの対装甲車用(タンク・キラー)劣化ウラン20mm弾を見せつけて事態に備えようとした。
「ばか言うなよ、シャーロック」猫はつっこみを入れたが、すぐに何も言わなかったようなふりをして、たっぷりと唾液を含ませた前脚で片方ずつの耳を丁寧に撫でつけた。
「しっ! この音はなんだ?」ハルキが言った。ウナティは耳をそばだてた。イカれた芝刈り機がたてるみたいな、それかハロー・キティのヴァイブレーターを〈強〉にしたときみたいな、ブウゥゥゥンという低い音が聞こえる。
「こっちよ」彼女は木々のあいだを駆け出した。図書館の忍者みたいに、音もたてず。
低い機械音の主は、蛍光グリーンのつなぎの作業着姿の若者が握っている電動バリカンだった。若者は頭上の登山用アプザイレンから垂らしたロープを体にくくりつけて宙吊りになり、憐れな死体を両足でしっかり挟むようにして髪の毛を刈っていた。肩に赤ちゃんのげっぷ用クロスが掛かっているところを見ると、どうやら若い母親の死体のようだ。児童公園を牛耳るママ友のいじめの標的になり、世間体をずたずたに切り裂かれた末路にちがいない。長い黒髪は死体の頭皮から完全に切り離されたとたん、にわかに息づきはじめた。くねくねと勝手に動きまわるものだから、蛍光グリーンの作業着の若者はそいつが空中に逃げていってしまわないように、しっかりと手首に巻きつけた。
「ねえちょっと、そこの死体荒し(スカベンガ)! 何やってんのよ?」ウナティは叫んだ。おそらく賢明な行動とは言いがたかった。若者はびっくり仰天した拍子に命綱から手を離した。ロープは甲高い摩擦音をあげてD字型の金具をまたたく間に通り抜けた。若者は必死でロープをつかんだが、手のひらが焼けただけだった。ついに若者は空中にふり落とされた。ぞっとするようなボキッという音をたてて首から地面に激突し、一方ロープは木の根のあいだの苔むした空洞にずるずると入っていった。
「彼は?」作家が訊いた。
「死んだみたい」ウナティは死体を足でつついて確認した。バリカンはその手のなかでまだ機械音をあげていた。「で、どうする?」
「延長コードをたぐればいいんだよ」猫が言った。
「延長コードをたぐればいいんだわ」ウナティは猫を無視して言った。そして、ブンブンいっている電動バリカンの電源コードをつかんで巻き取りはじめた。
コードはうねうねと森のなかに伸びていた。いくつかの谷を越え、ろくに漏電対策もしないで、さらさら流れる小川のなかを突っきっていた。
「どうして電池を使わなかったんだろうな」ハルキが小川を飛び越えながら言った。猫はまた彼の肩に乗っかっていた。
「ちょうど切らしていたのさ」鬱蒼と茂る木々の影にある、前方の空き地から声が聞こえた。ウナティと作家が木に囲まれた空き地に足を踏み入れると、眼鏡をかけて皺くちゃのスーツを着た小柄な男の姿が目に入った。ミッキーマウスみたいな耳と尖った牙、あべこべに回転しているアニメタッチの巨大な目のついた丘状の生きものの頂上に座っている。丘の両わきからは色鮮やかな絵の具が染み出し、真下の草地をカラフルな迷彩柄に染めあげている。丘状の生きものはウナティたちを見るとにやっと笑い、目玉をぐるんとまわしてみせた。
そのわきで、ばかでかい発電機が楽しげにブンブンうなっていた。延長コードがメドゥーサのドレッドヘアよろしく四方八方に伸び、森のあちこちで使われているとおぼしき電動バリカンに電気を送っている。そうして自殺者の頭から魔法の毛束が刈り取られていくわけだ。
丘のまわりには若い男女が集っていた。作業着の蛍光色の色合いもさまざまなら、作業の種類もさまざまだが、とにかくみんな組み立てラインみたいなものにむかっている。さらにちょっと離れたところには、灰色の作業着に身を包んだヒップな見習いアーティストが、ボーリングの球が入った何十という箱の山のわきの作業台に控えていた。球の塗装を剥がし、表面にやすりをかけては次々に隣の作業台に渡していく。真っピンクの髪にごついゴーグルをした女の子がそれを受け取り、おなじみのスマイル・フェイスの花をエアブラシで描きつけている。
女の子のわきに積み上げられたスマイル・フェイスの球は、期待に目をぱちくりさせて次の工程に送られるのを待っている。次なる作業場というのは、相撲の土俵によく似た場所だ。数人の肥満体の男女が、のたうちまわる自殺者の髪の毛をねじ伏せて、ボーリングの球に巻きつけている。髪の毛は逃げ出そうとじたばたしている。ウナティたちの目の前で、一筋の毛束がある男の手を逃れて宙に伸びた。「危ない!」男が声をあげた。毛束はそいつに張り手を食らわして投げ飛ばした。男は土俵の外にすっ飛び、ドサッと肉々しい音をたてて、ウナティとハルキの足もとに転げ落ちてきた。「うぐぐぐ」巨体からうめき声が漏れた。
土俵にいた赤い作業着のアーティストが毛束の根もとをひっつかみ、鞭をふるうようにいきおいよくひっぱった。すると髪はだらりと地面に垂れ、動かなくなった。さらに2人のアーティストがその上にのしかかり、髪が息を吹き返す前にスマイル・フェイスの球に巻きつけた。
最後の工程は船渠のような木製のプラットフォームだった。学校の制服に身を包んだキュートなアーティストの男女が、完成品を空に放していた。「バイバーイ! サヨナラ! 強く大きくなるのよー! 元気でねー!」風船みたいに空中にぷかぷか浮いていく毛玉を、ハンカチをふって見送っている。スマイル・フェイスにはすでにぎしぎし軋る歯と、とげとげした触手が生えはじめている。
身の毛がよだつような光景だった。
胸が躍るような光景だった。
丘状の生きもののうえの男は、メカ戦士と作家(と猫)がすべてを理解するのを待った。男は両腕を大きく広げて言った。「ようこそ! ぼくはタカシ。そしてこれはぼくのお山。ぼくはこのお山とすべての芸術的事業の大将(キング)さ!」
「つまりあんたが本人ってわけね?」ウナティがいきりたった。
「決まってるだろ」猫があきれたように目をぐるっとまわした。
眼鏡をかけた小柄な男がにやっと笑った。立ち上がって丘状の生きものから滑り降ると、表面に緑と青のグラデーションの筋ができた。丘はうなり声をあげ、男の方に目をまわした。「もしかして――」男が言った。「きみの言う『本人』ってのは、もっとも斬新でかつ示唆に富んだ21世紀を代表するアーティストのことかい? 選りすぐりのオタク文化と日本独自のポップな美的感覚を組み合わせて スーパーフラットというスタイルを確立させた革命児のことかい? アンディ・ウォーホルの時代遅れのけちくさいファクトリーとやらをはるかに凌ぐアート集団を築いた若き指導者のことかい? 今日の世界に衝撃と刺激を与えかつ劇変をもたらしたあの男のことかい?」
「あたしが言ってるのは、あんたがあたしのブーツをめちゃくちゃにした張本人かってことよ」
「きみのブーツだって?」タカシはウナティのバストのうえを泳いでいた目線を、エナメルのブーツに移した。もはや白いとは形容しがたい。一面に血や泥や脊椎液が飛び散り、例の不気味な髪が何本かひっ絡まっている。「それってクジラのペニス皮かい?」タカシはほれぼれと眺めた。
「自分で殺(や)ったのよ」ウナティがぱっと顔を輝かせた。
「すばらしい」
ウナティはふたたび顔をしかめた。「それをあんたの毛玉の怪物がめちゃくちゃにしてくれたのよ。東京の街半分もろとも。それに〈サイコー部隊〉もろとも。まあ正確に言えば、隊員はいつでも交換可能だけどさ。士官学校新卒生の入隊志望ナンバー1部隊なわけだから」
「そんなこと言われてもね」アーティストは肩をすくめた。「真の芸術には犠牲がつきものだから」
「ふざけんな! これでもくらうがいい、このろくでなし!」ウナティはブーツのわきのホルスターからレディス・サイズの357マグナムを引き抜き、彼のこめかみに押しつけた。
「やめろ!」猫と作家が同時に声をあげた。
「他になんかいい手立てでもあるわけ?」ウナティの指は引き金のうえでじりじりしていた。
「きみはアート界というものがわかってるのかい?」ハルキが言った。「彼の顔を見てみろ」
ウナティはタカシを見た。まるで自作のスマイル・フェイスの花さながら、イッちゃってるみたいに顔を輝かせている。
「彼は死にたがってるんだ」
そのひと言でピンときた。「くそっ! そうすればこいつのアートが永遠に生き続けるってわけね」ウナティは引き金から指を離した。
「やがてより強大に、より悪名高く、そして全世界を席巻するのだ!」タカシは狂喜の声をあげた。
「お黙り」ウナティはこめかみから銃をおろし、銃口を相手の股間につっこんだ。「さもないと毛むくじゃらのタマに穴あけてじわじわと失血死させるよ」
「そいつはさらにセンセーショナルだ! 受けて立とう!」タカシは満面の笑みを浮かべた。
ウナティは無視して言った。「ハルキ、あんた物書きって言ったけど……」
「なんだい?」
「アート批評とか書いたことあるわけ?」
「いいや……でも、きみが言おうとしていることはわかった」
「ん?」タカシがパニクりはじめた。「おいおいおいおい。ここは剣を振るうところだろ。ペンじゃないだろ」
「自殺者の髪の毛を使った作品なんてとっても斬新だと思ったんだけど。でもねえ、あたしに言わせればこんなの……」ウナティは効果的に間を置き、目をぐるっとまわしてみせた――「まっっったくの猿真似もいいとこ」
「やめろ!」タカシが声を張りあげた。
「たんに奇をてらっただけ」ウナティは続けた。「使い古された手口。言うなればまさしく……」
「言うな。それを言うんじゃない」
「 ダミアン・ハーストの二番煎じ」ウナティはついに言った。
「わあああああああ!」タカシは髪の毛をかきむしった。「あんな二流アーティストと一緒にするな。こんなのあんまりだ!」
「手遅れだよ」ハルキが携帯のキーを叩きながら言った。「忌憚なき批評をすべてのアートサイトにアップロードしているところだ」
「どうかお情けを」タカシが哀れっぽい声で言った。
「残念だけど」ハルキは画面から顔を上げずに肩をすくめてみせた。「メールは大量生産のいかさまポップアートより強しってことだ」
タカシはウナティの手につかみかかり、銃をねじりあげて自分のこめかみに押しつけた。そして彼女が奪い返す間もなく、引き金をひいた。こめかみから真っ赤な血が吹き出し、スローモーションで空中に弧を描いた。アーティストのくちびるはひきつり、弱々しい笑みを浮かべるように歪んだ。やがて彼は膝をついて横むきに倒れ、ぐちゃぐちゃに潰れた血まみれの後頭部をあらわにした。彼の血は草地に波紋型に広がっているさまざまな色と混じりあい、明るい色彩をみるみる濁らせていった。
ウナティは死体を見下ろした。「うっそ」彼女は言った。「これで一件落着ってこと?」
「さがれ」猫が言った。ウナティとハルキはとっさに後ずさり、すんでのところで蛍光色の作業着の一団の下敷きになるのを逃れた。彼らはもみくちゃになって争い、色彩を垂れ流しているお山の頂上にわれ先に登りつめようとしていた。
世にも醜い争いだった。大勢の貪欲な若いアーティストがたがいを踏みにじり、ひきずり下ろし、顔面や喉もとにパンチを食らわせあっている。しまいにはナイフまで飛び出した。揉みあいは激しくなっていく一方で、誰がほんとに血を流しているのか、誰がただ絵の具まみれになっているのか、もう見分けがつかなかった。
「退散した方がよさそうだな」猫が言った。「醜い後継者争いがますますひどくなるだけだ」
「でもこんなのってないよ! タカシは死んじゃうし」ウナティはそう言って爪先で死体を蹴ってみせた。アーティストの血が、血糊まみれのブーツをさらに汚した。「こいつの名声が高まるだけで、毛玉の怪物はもっと大きくなってくんじゃ……」
「まさか」作家が言った。「辛辣な批評を受けたあとに不名誉な自殺を遂げたことで? こんなの時代を超えて語り継がれるスキャンダラスな最期でもなんでもないさ。ただの芝居がかった売名行為だ。それに、黙ってたって彼の教え子やファクトリーの仲間がまっさきに彼を中傷しはじめると思うね。それで一巻の終わりになるさ。毛玉はそのうちしぼんで影も形もなくなるか、あるいは広告会社の重役に買い取られて、ロビーに飾られるのがオチだよ」彼は付け加えた。「あくまでも、皮肉としてね」
「うわ、イタい」ウナティはぶるっと身震いした。
「うん。さあ帰ろうか。どうかな、ぼくは無性にスパゲティが食べたい気分なんだけど」
「早めのランチってやつ?」ウナティは時計に目をやった。まだ12時だ。でもほら、東京は忙しい街だから。
彼らは森のなかに戻り、セメントの待避壕を目指して歩きはじめた。猫はハルキの肩に乗っていた。背後ではアーティストたちがまだ我を忘れて取っ組みあっている。そのうちの一人が乱闘から抜け出し、地獄絵図を撮影しはじめた。さぞかしいい映像(え)が撮れることだろう。
「それで、きみはどうしてヨハネスブルグを離れたんだい?」ハルキが待避壕の扉を押しながらたずねた。
「あの街? ふん(ヘイボー)。だってあそこ、超クレイジーな街なんだもん」彼女は首を横にふって答え、頭上にぶらさがる自殺者の足の下をくぐった。「ねえ、クジラ捕りの季節っていつ頃からかな?」
(訳:鈴木潤)
作品について
作者のローレン・ビューカス(早川書房表記は“ローレン・ビュークス”)は1976年、南アフリカ生まれで、ケープタウンに在住しながら英語で執筆しているSF作家です。これまでに多数の短篇をSF各誌に発表してきたほか、Moxyland(2008, Angry Robot)、Zoo City(2010, Angry Robot)の2冊の長篇を発表。Zoo Cityで同年のアーサー・C・クラーク賞を受賞、映画化のオファーも受けるなど、一躍脚光を浴びました。同書は日本での翻訳も予定されているそうです。さらに2013年にはThe Shining Girlsを刊行予定。またマンガ原作やノンフィクションを手がけるなど、さまざまな分野で旺盛に活動しています。
この短篇は南アフリカの作家の作品を集めたアンソロジーHome Away: 24 Hours, 24 Cities, 24 Writers(2010, Zebra Press)に初出、翌年ウェブジンSFXに転載されたもの。南アフリカ出身のガール・メカ戦士が東京で不気味な毛玉の怪物と闘うという、超クレイジーでポップな物語です。〈世界の2大ムラカミ〉を彷彿とさせるキャラクターの登場をはじめ、映画、音楽、アニメ、ゲームからの引用などがちりばめられ、作者の遊び心が存分に発揮されていて、筆者は翻訳しながらにやにやげらげら笑いっぱなしでした。日本語訳の発表にあたり、作者本人からコメントをいただいたので紹介します。
この作品はいわば日本と南アフリカのポップカルチャーのマッシュアップを脱線させてみたもの。おかしくてばかばかしくて大げさだけど、わたしが心から尊敬するアーティストと作家にカメオ出演してもらっています。日本で発表されるなんて、変な話だけどなんだかすごくワクワクします。日本はずっと興味をもっていた国なんです。ちょうどいま、VertigoのFablesというコミック誌の全6シリーズのスピンオフFairestで原作を手がけているんですが、これはグリム童話の「ラプンツェル」と、日本の怪談「番町皿屋敷」のお菊や黒澤映画をもとにした話で、2002年の東京が舞台なんですよ。まったくの偶然だけど、この話も髪の毛のおばけが出てくるんです。

Lauren Beukes by Christof van der Walt
作者がマンガやアニメをきっかけに日本のポップカルチャーに興味をもったということは、本特集アンケートの回答でも言及されています。ジャパニメーションや日本製ゲームの影響力、それに「原宿系」や「カワイイ」が海外でも認知されていることはもちろん知っていますが、作者の観察眼というか鑑賞力というか、“つっこみ”の冴えには感服しました。世界じゅうにさまざまな視点が、感性が、想像��力があるのだということを、あらためて感じさせてくれます。まさに〈ワールドSF〉というフィールドが広がりつつあるいまだからこそ、わたしたちに届いた物語ではないでしょうか。なにはともあれ、ちゃきちゃきのヨハネスブルグっ子の目から見たトーキョーを、まずは手放しでお楽しみいただければと思います。(鈴木潤)
【訳注】本作品は創作およびその翻訳であり、登場する固有名詞は実在の個人・団体・事実関係を指すものではありません。以下に挙げた動画や記事は、あくまでも訳者が作品から連想したものです。
【1】「あなたが欲しいものを教えて(ほんとにほんとに欲しいものを)」スパイス・ガールズの代表曲“wannabe”の有名なサビ部分。
【2】どちらもヨハネスブルグの最先端のファッション・エリア。
【3】ヨハネスブルグ発祥のカジュアルファッション・ブランド。ファンキー&ヒップホップなTシャツが人気。名前の由来は、南アフリカで地元っ子に親しまれているカラフルなポップコーン。
【4】ズールー族の民族舞踏から派生した、南アフリカのストリート・ダンス。
【5】“原宿ガール”に多大なる愛と敬意を寄せるアメリカのポップ歌手。
【6】日本製格闘ゲームの名作ストリートファイターには「真の格闘家・リュウ」が主要キャラクターとし�て登場する。

【7】ジェファーソン・スターシップの87年のヒット曲"Nothing's Gonna Stop Us Now"を彷彿とさせる。
【8】映画『ブレードランナー』(原作:フィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』)には、主人公の謎めいた同僚ガフが暗示的にユニコーンの折り紙を落とすシーンがある。
【9】なんと実際にそういうものがあるようだ。

【10】空軍士官学生の青春をトム・クルーズ主演で描き大ヒットした、86年の映画『トップガン』のテーマ曲。
【11】日本発祥で国際的に大ヒットしたパズル・ゲーム。世界的にSUDOKUの名で知られている。

【12】たとえばこんなものだろうか……
【13】〈ロンサム・カウボーイ〉を彷彿とさせる。
【14】松本清張氏の代表作。氏は『波の塔』でも富士の樹海を自殺の舞台として取り上げている。
【15】〈Gero Tan〉を彷彿とさせる。
【16】2000年代初頭、現代美術家・村上隆氏が日本のマンガ・アニメ文化と大衆消費文化を伝統的平面絵画の手法で表現し、確立させたスタイル。ルイ・ヴィトンのコレクションのテーマに採用され、カラフルなモノグラム製品が大ヒットしたことは記憶に新しい。

【17】90年代を代表するイギリスのコンテンポラリー・アーティスト。動物の死体を巨大なガラスケースに入れて展示した作品で物議を醸し、またキャンバスに多数のカラフルなドットを配した〈スポット・ペインティング〉スタイルを確立した。