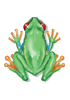星の鎖 第一章
ジェイ・レイク
第一章
夢
ザライは〈壁〉の頂上を何年もさすらってきた。大半の期間はマニックスがとなりを歩いてくれた。頂上を旅するようになったのは、二人が最後に乗っていた〈レイピア〉号を離れてからだった。〈レイピア〉は狂乱と冒険とスリルそのものだったが、自分が海賊船の副船長になるなんて、それも男と一緒だなんて、ザライは考えたこともなかった。長年バケツ船を駆って〈鎖〉を登り降りしていたあいだは。
ザライはふっと笑いをもらした。人生は思いがけない方向に進むものだ。とりわけ愛はそう。そもそも、ザライは内省など得意ではなかった。いちばん幸せだったころ、ニックスにはいつもそのことでからかわれた。
思い出はザライを現実に引き戻した。たったひとり、凍てつくような霧に覆われた高地の竹林をかきわけ進んでいる。これより上はない最高高度。視界は霧と氷に閉ざされ、平水域世界の諸女王国は見えなかったが、右に数十歩も進めば、長く甘美な落下を経て北半球の大地と最期の再会を果たすことになるとわかっていた。
たったひとり。
近ごろは、その最後の数歩が望ましく思えることすらあった。
ニックスは壮大な計画を企てる男だった。計画というよりは夢に近かった。そのほとんどは、エンキドゥ族の行商人の包みから出てくる古い鏡のように、ひび割れ、薄汚れていた。ザライが若いころ、男について言い聞かされ、教えられ、考えたことは、ニックスにみごとに当てはまるようだった。
幼稚。
軽率。
衝動的。
愚か、といってもいいかもしれない。銀貨や貴重な工具を持たせたり、記憶や思考を要する大事な仕事を任せたりするわけにはいかなかった。
でも、ニックスはそうした短所を合わせてもなお補ってあまりある存在だった。
〈鎖〉で何年も共に過ごすうちに、ザライの目から愛による目隠しが外れ、ニックスの数々の欠点が見えるようになった。彼女の恋人は過ちの塊、矛盾と一貫性のなさと疑心暗鬼の寄せ集めだった。あのころ〈レイピア〉号で、ほかの男たちや数少ない無法者の女たちに囲まれてザライが学んだことは、それでもニックスを愛しているということだった。
ザライはニックスの気転、稲妻のような思考の飛躍、彼女によろこびをもたらしてくれる力強い手を愛した。ひと目を忍んで手すりにもたれかかって、あるいは当直の長い夜を通じてゆっくりと休みなく、彼女が疲れきるまでよろこびを与えてくれた手。ザライはニックスの誠意と心のひろさ、猛々しさと意外な繊細さを愛した。気づかれていないと思って彼女を見つめるときの視線が好きだった。そして何よりも、彼女の愛への応えかたが好きだった。無条件で、みじんの批判もほんのわずかの疑いも混じらない愛を返してくれた。
彼はありのままのザライを、彼女のやることなすこと、彼女にまつわるすべてを愛した。それがニックスの愛だった。
いなくなるまでは。
ザライはふたたび、きらきら光る霧のカーテンの向こうにかすむ暗い縁(ふち)へと目をやった。はるか彼方に沈みゆく太陽が、散り散りの虹を霧のなかへと矢のように放っている。眼下遠く、メソアメリカ国の大地から〈壁〉を登ってくる羽毛の生えた蛇のようだ。あの縁は彼女の命を奪い、聖域に導いてくれる。つかのまの痛みを経て、長く孤独な瞬間へと心を解放してくれる。
終わりの見えない、毎日の痛みとはちがう。
天のためだけに、彼女は前に進んだ。
神のため、"彼女"の天のためではない。ザライは生まれてこのかた、古き女神とその御業には縁がなかった。女はこの世にあるべくしてあり、この世はそこに生を受けた者のためにあった。どこから、なぜやってきたかは関係ないではないか?
ニックスがいなくなってからは、星々だけがザライを駆り立てた。
だから彼女は高みの道を歩んだ。左手で、〈壁〉の上にそびえる真鍮の大歯車に触れながら。ザライは真夜中に軌道環が通過する大音響に耐えた。彼女は僧侶や山賊や、物陰で爪を光らせるすばしこい山猫と争った。
ザライは歩きながら、手を伸ばして星々に触れられる場所がないかと探した。
翡翠の院主(いんじゅ)は親切だった。ザライには分不相応だったかもしれない。出会ったとき、ザライは彼の果樹園から桃を盗もうとしていた。二年前のあの夜、果実は霜にきらめき、月明かりを浴びてだいだいとも灰色ともつかない不思議な色を放っていた。ザライは桃を二つもぎ、三つめに手を伸ばした。今晩の夕食と明日の朝食はこれでしのげるだろう。
「平水域の諸女王国は、かつて果樹の森で覆われていたのだよ。シンドからアンダルシアまで」彼はザライの真後ろで言った。
ザライはすばやくふり向き、片手でバネ銃をつかんだ。マニックスがいなくなってまだ数週間だった。彼女はまだ、彼が今にも帰ってくるのではないかと期待していた。憤り、悲嘆し、たぶん、傷ついていた。いなくなったなんてとても信じられなかった。でも、覚悟を決めておくに越したことはない。
小柄な男性に遭遇しようとは思ってもみなかった。彼は霜をかぶった桃よりもいくらか濃いだいだい色の法衣をまとっていた。肌は浅黒く、まぶたの形のせいで目はほとんど閉じているように見えた。髪はまったくない。唇には、いざなうような笑みが浮かんでいた。
「果物はこの世が与えてくれる恵みよ」ザライは言った。
「こう言ってはなんだが、これらの木を植えて、世話をした人がいることも確かなのだよ」男はおじぎをし、体を起こすと、ふたたび笑みを見せた。「木のもととなる種はこの世の恵みだが、木そのものは長年の労働のたまものだ」
これには思わず笑みが浮かんだ。「労働もまた、この世の恵みだわ」
彼は眉を寄せた。「品よく話す有能な女性が、なぜひとの果樹園でこそこそしているのかな」
「お腹が空いているの」
「それならば、わたしのところに食べにいらっしゃい」
現行犯で捕まった夜の盗人は、当主の後から赤い柱が連なる寺院のあたたかい光のなかへと入っていった。
彼らは広壮な部屋で食事をとった。高い天井は青と金に彩られ、赤塗りの巨大な柱に支えられていた。食事は豚肉とキャベツの餡が入った蒸し餃子と、炒めたサヤインゲンにとろみのあるブラウンソースをかけたものだった。料理はなじみのない香辛料と油の味がした。箸を使うのが初めてだったので、ザライは苦労した。老人は、自分のもてなしに問題があろうとは思い至らないようだった。
「きみは何を探しているのかな」ずいぶん経ってから、彼はたずねた。
ザライは一瞬考えこんだ。「見つけられないものよ」
「となると、探求は困難になるのでは」
「ええ、まあ」彼女は料理の入ったお椀に目を落とした。「そういうことになるわ」
しばしの沈黙がおとずれた。気詰まりというよりは心地よい沈黙だった。老人はやがて口を開いた。「わたしも探している。真実と、意志と、夢見る心を」
「それも見つけるのは難しそうね」ザライは顔いっぱいに笑みが広がるのを感じた。ニックスが発ってから、初めてのことだ。
老人は優しさのこもった声で言った。「本質的に見つけられないものほどは、難しくないよ」
「わたしは星に触れたいの」ザライはうっかり口走った。自分で自分に驚いた。愚かな夢、ばかばかしい夢。男の夢。マニックスですら最後には投げだした夢。
ふたたび沈黙がおりた。今回は、ふさわしいことばを選ぶための静けさだった。「星は小さくて熱くて、とても遠くにあるのだよ」
「天は頭の上にあるわ」
「天はひとの心のなかにある物語。頭の上にあるのは空だ」
彼女はうなずいた。「宇宙のぜんまい仕掛けによって支えられている」
老人は箸をおろした。「軌道環をつかんで、地上との繋がりを抜け出すつもりかね」
「かもしれない。なにか方法があるはずだわ。わたしは〈壁〉を歩いているの。悟りが得られないかと思って、てっぺんからの眺めを見にきたの」
「わたしは〈壁〉の上に座って、悟りが訪れるのを待っている」彼はまた頬笑んだ。「そのような精神の恵みにあずかる道は、もしかしたらわたしたちの中間にあるのかもしれないね」
「わたしはザライ。鎖海賊船〈レイピア〉号の元副船長です」
老人はおじぎをした。「わたしは翡翠の院主だ」
彼女はすでに望みを明かしてしまった。ならば、この思いつきをとことん追求してもいいだろう。「空に通じる道をご存じ?」
「上向きだよ」翡翠の院主は言った。その声はかすかに愁いを帯びていた。「上に向かうだけだ。きみが探しているものがそこにあるとは思わないが、それでもやはり、きみの道なのかもしれない」
ザライは思い切ってマニックスを頭から追いはらった。彼とは関係ないことだ。もうこれからは。
老人はザライを果物泥棒、盗人として追い出したりしなかった。彼女は寺院で一週間を過ごした。勤行をみまもり、お寺の人々が大歯車の歯に近づくためにつくった足場を眺めた。
ザライはずっと後になって、院主は彼女の探求について何を言おうとしていたのだろうと考えた。ニックスを失ったことと結びつけるのは簡単だったが、彼はザライの本質をもっと深く見通していたのかもしれない。ザライ自身に見えるよりも深く。そう考えると、怖いようなほっとするような気がした。
彼女はやがて、泥の球体が連なる都市を見つけた。球体は大歯車に貼りついていた。〈壁〉の頂上から八百メートルほど上方に伸びる真鍮の絶壁には、付着物はめったになかった。純粋に工学的に考えても、溶接あるいはリベット締めなしに物質を接着するのは困難だ。宇宙のぜんまい仕掛けは、神の産物にふさわしく、そもそも不浸透性の金属から完成されていた。それでも、何者かがこのような偉業をなしとげたのだ。
ザライは街に近づく前に、離れた場所から二日間様子をうかがった。うっかり襲撃に遭いたくなかったし、ひとの生活空間にずかずかと踏みこむような真似もしたくなかった。〈壁〉のほとんどは、見捨てられた場所だった。家々は遠い昔に家主を失い、今では風が通りすぎるだけだった。ザライが〈壁〉で見てきたのは、無人の宮殿や静まりかえった村、ひと気のない通りばかりで、にぎやかな市場や防護壁に囲まれた街はまれだった。
でも、ここは何かがちがった。この街をつくった人々は空を飛べたにちがいない。彼らは階段も梯子も、ほかのいかなる手段も必要とせず、虚空に面した開口部から出入りしたらしい。都市のデザインは風変わりで、月明かりの下でも太陽の下でも景観は静けさに満ちていた。ザライは日の移ろいを通じて街を観察した。住人は陽光が斜めに射す時間帯にしか外出しないのかもしれなかった。彼らが翼蛮族だったら最悪だ。この混乱した天使たちは〈壁〉の上部をうろつき、出会う者すべてを敵とみなすのだった。
ザライが気になったのは、街に住んでいた者の正体ではなかった。どうやって真鍮に物質を固定しているのか、それが知りたかった。
星に近づくためには、なんとかして大歯車を登る必要があった。そして大量の装備を運び上げなければならない。
こういうことはマニックスが得意だった。
ザライは無意識に浮かんだ考えをふり払った。三日目の明け方、彼女は街に入った。
マニックスは変わった男だった。ザライよりいくらか背が低く、ずんぐりした体格はそもそも彼女の好みから外れていた。目の色は淡く、髪の毛は亜麻色と栗色が混ざっていた。手足は体全体の大きさに比べて異様に小さかった。
それでも、ザライはマニックスに抗いがたい魅力を感じた。しばらくして、最初に惹かれたのは彼の匂いだったと気づいた。あの男はセックスのような、愛のような、ほっとする匂いがした。そばにいて彼を胸いっぱいに吸いこむと、ザライの心は思いがけない安らぎを見出した。
二人は小さな焚き火を前に、腰と肩を寄せて座っていた。鼻をつく煙と、彼らをとりかこむ夜の森が放つ濃厚な香りを越えて、彼の男の匂いがザライを誘った。彼女は横を向き、マニックスの丸い、屈託のない顔を見つめた。
「なぜ、星なの?」それは彼女が長年抱いていた問いだった。答えを知るのが怖かった。あるいは、質問すること自体が怖かったのかもしれない。
ニックスは棒きれを手に取り、赤く燃える熾火をつついた。樹液が噴き出して灰が舞い、甘く焦げたはかない匂いがした。彼はしばらく火を掻き立ててから、ザライをじっと、腰がむずむずしてくるような眼差しで見つめた。
「うーん……」
ザライは沈黙に戸惑った。マニックスがことばに詰まるのはめずらしい。不安が頭をよぎった。踏みこみすぎてしまったのだろうか。
マニックスはふたたび火をつついた。火の粉が上がり、小さな星々が冷気のなかでてんでに舞った。「そうだな。ザライ、考えてごらんよ」彼は空中に図を描くかのように、棒きれの先を動かした。「おれたち二人は〈壁〉の上に住んでいる。そして平水域の諸女王国を見おろす。そこに暮らすのは、世界を大局的に眺めることのできない陸上生活者たちだ。星にかこまれて暮らす人々は、〈壁〉の頂上にいるおれたちを見おろして何と思うのだろうか。おれたちもまた、地上の人々と同じように自分の人生に弄ばれているのだろうか。おれは一番高いところまで登って、遠く離れた場所から自分という存在がどう見えるのか、知りたいんだ」
ザライは彼のことばを反芻した。「星のところまで登って、世界を見おろすのね」
「天に通じる梯子があればいいんだが」マニックスはにっと笑い、片手をザライの腿に伸ばした。「少しなら、今夜二人で登れるんじゃないか」
ザライは彼に導かれるままに考え事を手放した。二人は親密な影に溶けこみ、互いの情熱を重ね合わせた。たしかに変わり者だが、ニックスは彼女の恋人だった。二人は火が夜を愛するように愛し合っていた。
それから数日後、二人は黄色い巨石が転がる一帯を苦労して進んでいた。岩は黄鉄鉱に騙されるものを誘うようにきらめいた。ザライは、あの晩から胸にあった問いをマニックスに投げかけた。「そんなに高くまで届く梯子をどうやってつくるの?」
彼は笑った。ザライにとっては鈴のような声だ。粗雑なつくりの、情感に欠ける調子はずれな鈴だが、彼女の心を沸きたたせる調べを奏でてくれる。「梯子はつくらないよ、愛しい人。ほかならぬきみのことだ、わかるだろう」
「バケツ船かなにかを使うということ?」ザライは〈鎖〉で働いていた時分、バケツ船〈怠惰の極み〉号で船長を務めていた。鎖海賊のジャントンを殺してしまうまでは。その後は償いとしてそれまでの生活を捨てて、禁断の男の世界に飛びこんだ。バケツ船は捕捉装置で〈鎖〉をつかんで移動した。〈壁〉を下るのはたやすいが、上るには大変な機械力を要した。ザライには想像できた――真夜中に通過する軌道環に同じように船を固定すれば、地球が転がり遠ざかるのに従って空に飛び立つことができる。
考えただけで興奮すると同時に恐怖がわいてくる。
「そうさ」ニックスが答えた。「天に飛びこんで、星々に向かって航行するのさ」彼はまた笑った。「あるいは最低でも月だ。だいぶ近そうだものな」
ザライはひび割れ、きらめく岩肌をすべり降り、とげだらけの茂みを避けて足場を確保した。〈壁〉の頂上は、意欲ある歩き手ならおおむね通行に苦労しなかったが、この一帯は大幅に改善の余地があった。
「わたしたち、どうやったらそこまで航行できるかしら?」
「"わたしたち"は航行しないよ」彼は答えた。
ニックスの声に含まれる何かに、ザライの心はほんの一瞬凍りついた。
「航行しない?」
「そうだとも、ザライ。危険すぎる。一緒に行ったら、上手くいかなかった時に二人とも死ぬことになる」
少年が思ったことを軽率に口にするみたいに、考えるよりも先にことばがすべり出た。「あなたが一人で行って上手く行かなかったら、わたしはどうなるの?」
「生き続けるさ」彼は言った。そっけない声だった。「きみなら生きていて、元気で、また自由に恋をできる」
「人はみな孤独なのね」ザライは惨めたらしく言った。「一人で生まれ、一人で死んでいく。あなたなしでずっと生きていくくらいなら、人生最期の瞬間を二人だけで過ごしたいわ」
彼は立ち止まりザライに向き合うと、黄色い巨石にもたれかかるようにして彼女を引き寄せた。「わからないかな。きみを愛しているから、危険な目には遭わせたくないんだ」
「ちがうわ」ザライは彼の肩に顔を埋めてつぶやいた。「愛しているなら、置いていかないはず」
聞こえなかったのか、マニックスはただ彼女の髪を撫でてぎゅっと抱きしめ、あやすようにささやきかけた。まるでザライが子供でしかないみたいに。あるいは、男でしかないみたいに。
二人は何週間ものあいだ、空の上の世界での生存方法について語り合った。そもそも空気はどこでも均質なのではなかった。これは、〈壁〉から遠く飛びすぎた者の体験談から明らかだった。ザライとマニックスは、空気が少なくなり、どんどん薄くなって真空に近づくだけなのか、それともエーテルや自在に浮遊する燃素のような別の物質が存在するのか議論した。呼吸はどうなるのか。その物質は帆やオール、あるいは何かもっと別の道具を使って漕いだり押したりできるのか。
同様に、食糧に水、生活必需品も問題だった。空気の有無とは関係なく、天にきれいな水の湧き出る泉や井戸が存在しないのは明白だった。旅人の食糧となる果実も、獲物となる動物もいない。航行の手段がどうであれ、これらの品々を携帯する必要があった。〈壁〉上方の荒涼とした岩砂漠を横断する場合と同じように。
これにより、空の旅を実現するための船のデザインも大まかに決まった。貨物積載能力、貯蔵庫、船内の動線。
もっとも明白かつ困難な問題は、船を空に送りこむ方法だった。軌道環に船を固定することが基本原理となるのは確実だったが、それをどうやって実現するかはまったく別の話だ。
それでも彼らは飽きずに語り合った。木で小さな模型をつくり、ぬかるみの土手や砂地にスケッチを描き、〈壁〉が何らかの答えを与えてくることを期待して歩きつづけた。ほかの多くのことと同様に、じゅうぶん遠くまで歩き、じゅうぶんに目を見開いていれば、〈壁〉はもたらしてくれるはずだった。
あいにく、〈壁〉が最初にもたらしたのは、ザライとニックスを何年ものあいだ結びつけてきたものの終焉だった。
ザライは球体の泥壁を手探りで這い上がった。きつい道だが、楽な道はなかった。
近くで見ると、泥の球体はそれほど形が整っているわけでもなかった。表面はむらがあり、いい加減といえるほどだ。ザライは構造健全性を把握するのに苦労した。それでも、球体によじ登って入り口を調査し、壁面を観察することは可能だった。
ザライはそうした。
最近の彼女には、他にすることもなかった。マニックスはいない。空に向かう船もない。そのような船をつくる見通しも立たない。二人のうちでは彼が職人で、鋳造工だった。金属の加工はザライにはなじみのない技術だった。機械の操作には通じていたが、つくり方は見当もつかなかった。
それでも、人は学べるものだ。そして〈壁〉はもたらした。
球体の内側は、巨大な崖ツバメの巣のようにがらんどうなのではなく、不定形の部屋がごたごたと配置されていた。ザライには、すべてがとても原始的に感じられた。だれが何のためにつくったのだろうか。それは知的な生物ではなく動物の手によるもののように思えた。ザライが知る限り、人間、エンキドゥ族、あるいはほかの何者だろうと、思考する生物は例外なく、それぞれの習わしに準じたパターンを作りたがった。ところがここにあるのは、滝の下に散らばる小石にも等しい、優雅なまでのパターンの欠如だった。
ザライが最も興味を覚えたのは、球体のうしろ側の〈壁〉と接している部分だった。その部分の内壁は、外壁の湾曲面とはやや様子が異なった。見たところ重量感があり、まだら模様が目立ち、植物が混ぜこんであった。
三つ目の球体で、ザライはナイフを取り出して壁面を削り、細長い葉をほじり出そうとした。葉は妙にべたつき、無数の小さな手でつかみかかるみたいにナイフにまとわりついた。ザライが葉のサンプルを取り出すには、時間と体力と、てこの原理を利用した工夫が必要だった。
「これが秘訣ね」ザライはがらんとした空間に向かって言った。彼女自身の声が何十回もささやき返した。ザライは外に這い出して、この葉をつけていた植物をどこで見つけられるだろうかと考えた。この植物の注目すべき特質は、何と混合すれば活性化するのだろうか。
ザライとニックスはめったに喧嘩しなかった。意見がくい違うことは少なかったし、まれに問題が持ちあがったとしても、口論で解決しようとはしなかった。それでも、ニックスが強い酒を飲み過ぎたときや、ふとしたことばがザライの心に妙な具合に突き刺さってしまったときは、愛という光に浴している二人であっても予期せぬ喧嘩になることはあった。
別の晩、ふたたび火を囲んでいた時もそうだった。二匹の野ウサギ――あるいは、野ウサギよりも毛並みが粗いが、よく似た動物――を硬い木の棒に串刺にして、マニックスが数分ごとに向きを変えながら焼いていた。ザライはパチパチとはぜる脂の香ばしい匂いに生唾を飲みながら、野営場所近くの小さな湿地でリーキを集めていた。
水がより低い方へと流れようとするのは明白なので、〈壁〉の頂上でこのような景観に出会うたびにザライは驚いた。本来なら、頂上は砂漠のはずだった。平水域世界の海からこんなにも離れているのだ。しかし、神は彼女の創造物をよりよく配置なさったのだろう。
火明かりのそばに戻っていくと、ニックスが妙な顔をしていた。眉間にしわを寄せて目を細め、もともと赤味の強い肌は炎に照らされて悪魔のようにぎらついていた。
「大切なひと、どうしたの」ザライは優しく声をかけて、集めたリーキを平らな石に置いた。傍らには、彼らがいつも持ち歩いている小鍋があった。ザライは身をかがめて、マニックスの流れるような髪に触れた。
「天に向かうおれの船のことを考えているんだ」
「天に向かうわたしたちの船」ザライは苛立たしげに言った。この問題は依然として決着していなかった。
マニックスはザライを見上げた。顔は光に照らされて妙に平らに見えた。「おれの船だ。この向こう見ずな冒険できみを失うつもりはない」
「この向こう見ずな冒険で、わたしがあなたを失うのは構わないというの?」ザライは笑いとばそうとした。「愚かなひと。わたしの愛があなたの愛より小さいとでも思っているの?」
「おれの愛し方はきみの愛し方とはちがう」マニックスは意固地になった。彼は頭を垂れ、話を終わらせようとした。「もうよそう」
「そんな風に愛情を比較されたくないわ」
マニックスは顔を上げた。目が涙にうるんでいた。「比較したのはきみの方じゃないか」
「ごめんなさい。そんなつもりじゃなかった」
ニックスはウサギの向きを変えたが、ザライとは目を合わせようとしなかった。「おれの愛の中心には許しがある。きみには欠けているが」
「愛とはすなわち許しだわ。あるいは一切腹を立てないこと」
「忘れてくれ」恋人は言った。「しゃべりすぎた」
「お願い、話して」
「だめだ!」マニックスはまだ目を合わせなかった。
「じゃあ、なぜわたしの目を見られないのか説明してよ!」
長い沈黙が落ちた。ことばにならない怒りが張りつめていた。ウサギがパリパリと音を立てはじめると、マニックスは思い出したように串を回した。
やっとのことで、彼はザライの目を見た。彼女は彼のまなざしに沸き立つものを見た。喪失感、憤り、むきだしの怒り。「出会った時のことを覚えているか?」
「ええ……」ザライの顔から笑顔が消えた。マニックスの表情は変わらなかった。
「おれは、奇襲を受けたときのへまをきっかけに鎖海賊に転身したというバケツ船の船長を探していた。本当にひどい、ふざけた話だった。どこかのばか女が言われたことを鵜呑みにして、ことばの下の真実に耳を傾けようとしなかったせいだ」
ザライは赤くなり、怖じ気づいた。マニックスは彼女のことを話しているのかもしれない。女性的なことをはねつける、不機嫌なときのいつもの調子で。だが彼女は黙っていた。
「ジャントン……」彼は言った。
ジャントン。
マニックスは彼女のことを話していた。
ザライの心は破裂した浮き袋のようにつぶれた。ジャントンは彼女が誤って殺してしまった男だ。彼女は、求愛と保険金詐欺が複雑に絡みあった背後に、鎖海賊の真の目的が隠れていることを理解していなかった。彼がなぜ〈怠惰の極み〉号を奇襲したのか。彼がなぜ不思議なほど無防備に彼女に近づいてきたのか。ザライに倒された時、彼がなぜあれほど驚いた顔をしたのか。彼女は理解していなかった。
ザライが自分の船から飛び出した時、あの粋な海賊はまだ息をしていた。でも彼女は、ジャントンがバケツ船の次の港までもたなかったことを知っていた。
その日、神はザライから顔を背けた。そしてマニックスが現れるまで、その慈悲の眼差しを彼女に向けることはなかった。そして今、ザライは恋人のことばに打ちのめされていた。
「ジャントンがどうしたというの?」彼女はこらえきれずにたずねた。
「彼を殺すほどの愚か者はどこのどいつか、知りたかった」ニックスはいまや、追憶の彼方をさまよっていた。「その女に、どういうつもりであれほど優しい、愛情深い男の命を奪ったのか聞きたかった。それから、彼女がじつに軽率に手渡した死を、つき返してやるつもりだった」
ザライの胸は凍りつき、拳のように硬くなった。体全体が締めつけられた。自分の声が、とてつもなく長いトンネルの遠い出口から出てくるように感じた。「わたしを殺してジャントンの敵を討とうとしていたの?」
「恋人の仇を討つために、彼を殺した犯人を倒すつもりだった」ニックスは視線をザライに戻した。目は険しく充血し、涙とわずかな狂気を宿していた。「きみの正体を知るずっと前に、親密になってしまったんだ」
「なぜ、今ごろ?」彼女は叫んだ。またしても、ことばが彼女から引きはがされた。
「〈レイピア〉号を離れるまで、きみだったとは知らなかった。知ったとしても、受け入れなかっただろう。ジェレミーが船長になっておれたちを船から追い出した時、やつは無視しようのない事実を教えてくれた。それからというもの……」
「わたしがジャントンを殺したから、空の向こうには連れて行きたくないのね」
マニックスの声は悲痛そのものだった。「歩くことで、忘れようとしてきた。星に向かって歩みつづけるうちに、胸につかえたものを手放せると思っていた。でも心は、そう簡単に手放してくれない。本当を言うと、いつかきみを殺してしまいそうだから、空の向こうに連れて行きたくないんだ」
「そんな……」ザライは叫んだ。涙がこみ上げたが、体を裏返しにするような思いでこらえた。
マニックスは立ちあがり、ナイフを手にして暗闇に向かって歩いて行った。ザライが最後に見た彼の姿は、暗がりに消えてゆく背中だった。野ウサギは本格的に焦げはじめた。
マニックスは戻らなかった。
(続く)
(訳:志村未帆)