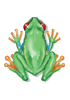星の鎖 第四章
ジェイ・レイク

Illustration by Norio Kozima
第四章
星
議論は一カ月続いた。
残骸を探す探検隊が送り出された。発見物の回収にあたり、赤い肌をした狩猟民族の一団と小競り合いがあった。翡翠の院主(いんじゅ)の指揮で、ロソダの葬儀が執り行われた。眠れぬ夜が続き、キーには見張りがつけられた。彼は薬品の樽や蒸留器のはざまで火のついた朽ち木とともに横たわっているのが見つかったのだ。顔と胸には弔いの泥が塗られていた。
しかし、何よりも議論が続いた。
「われわれはもう二度と飛ばない」キーはにべもなかった。彼は髪を切り落とし、一番大切にしていた工具と一緒に燃やして死魂を手放した後に言った。
鍛冶屋兄弟は多少は楽観的だったが、気を落としていることには変わりなかった。「〈ダレト〉がより安全とは保証できない」崔(チョイ)が言った。「〈マニックス〉も同じだ」
エーアはただ、悲しげに肩をすくめた。
だれもが意見を持っていた。だれもがザライが答えをもたらすことを期待した。翡翠の院主だけは静かな笑みを浮かべて彼女を見守り、何も言わずにひたすら待ちつづけた。
二週間後、十二回目の話し合いで、ザライは立ちあがり杖をテーブルに置いた。一同は第一造船所の外に張り出した天幕の下に集っていた。なかでは多少の作業が続けられたが、集会にはキャンプの人間がほぼ全員集まった。外で行われる作業はほとんどなかった。
まるで、三百の肺を持つ怪物が息をとめて、ザライが口を開くのを待っているかのようだった。
「わたしはあそこにいた」ザライは言った。ここにいるみなには周知の事実とはいえ、言わずにいられなかった。「わたしはあそこにいた。あの寒くて暗い、星々の明かりだけが頼りの空間に。エーテルで肺が傷つき、しばらくは目が見えなくなった。わたしはあそこにいた。戻れなかったとしても……」ザライは「無傷で戻れなかったとしても」と言うつもりだったが、不正確な気がした。「ロソダのように、降り注ぐ光と炎のなかで死んだとしても、わたしの最後の望みは変わらなかったはず」一同の注意を自分の声と視線に引きつけようとして、ザライは体を前に乗り出した。「みんながもう一度試みてくれることを望んだはずよ」
ザライは杖を手に取り、くるりと後ろを向いて歩きはじめた。天幕の端に差しかかると、立ち止まってふり向き、テーブルを囲んだ一同をもう一度見まわした。「わたしたちはもう一度試みるわ。そしてわたしがもう一度飛ぶ」
愚か者の歓声を背に、ザライは霧雨のなかへと歩み出た。雨が彼女の涙を隠した。
光。光のなかで死ぬこと。もっとつまらない運命もある。例えば、闇夜に消えて二度と戻らないこと。
ああ、ニックス。
次に話し合われたのは──もう言い争いはなかった──〈ダレト〉を飛ばすべきか、一歩進んで〈マニックス〉を打ち上げるべきかどうかだ。
真鍮と銅で被覆されたエーテル船のそばに、中心メンバーが集まった。ザライはその日、杖を使わずに過ごそうとしていた。
「船体は完成しています」崔が言った。「空気も水も搭載済みで、内部設備も機能している。〈ギメル〉での教訓を活かしました」彼はザライにゆっくりと視線を送り、「初飛行の」と言い添えた。
「ロソダの記述は非常に明確だったわ」ザライはみなに言った。彼女はナビゲーターの残したメモを、翡翠の院主に助言を求めながら読み返していた。二人とも、エーテルの流れに沿って船を航行させる方法など何も知らなかった。しかしそれを言うなら、だれも知らなかった。
おそらく、ロソダ以外は。
「つまるところ、降下方法が問題よ」アーマインが、その場にいないキーに代わって言った。「推進力は火か、空気か。着陸に使うのは火か、翼か、パラシュートか。〈ダレト〉を飛ばすことで、この点をはっきりさせられるわ」
「その場合、〈ダレト〉にはだれが乗るの?」ザライは声を平坦に、穏やかに保ち、湧き上がるパニックを抑えようとした。軌道環に持ち上げられ、やがて上下の区別のない暗闇に放り出されることを考えるたびに、パニックに脅かされた。飛ぶのはザライだ。自分より先に、だれかを死なせるわけにはいかない。彼女は骨身に染みて理解していた。次に命が失われたら、計画はおしまいになる。
アーマインは肩をすくめた。「当然、人間でしょう」彼女はちらりとエーアをにらんだ。「エンキドゥ族の身体じゃ〈ダレト〉に収まりきらないわ」
ザライは崔を見た。彼は肩幅が広く、腕も肉付きがいい。「男の人もほとんどは収まらないでしょう」鍛冶屋はわずかに視線を強めた。崔には、彼の兄が持ち合わせているような軽妙なユーモアが欠けているのをザライは知っていた。「議論をこれ以上続ける必要はないと思うわ」彼女は言った。「〈マニックス〉を打ち上げます。〈ギメル〉の初飛行で試みたように、圧縮ガスを推進力として、パラシュートで帰還する。これ以外の方法をとるのは、命と時間と労力のリスクが大きすぎるわ」
「確かですか?」エーアのエンキドゥ独特のアクセントがいつにもまして強く感じられた。まるで、記憶の奥底からわざわざ探し出してきた言葉のようだ。
「いいえ! 何一つ確かではないわ。ロソダが死んで、わたしが死ななかったこと以外は」
「キーは傷つくわよ」アーマインが忠告した。
そう言われて、ザライはしばし戸惑った。「キーが傷つくことはないわ。リスクは全員で共有している。ロソダが死んだのはキーのせいでも、あなたのせいでもない。わたしのせいでも、ロソダ本人のせいでもない」
「逆を言えば、ロソダの死はキーのせいでもあるってことよ」木こりは悲しげな、静かな声で言った。
「当たり前よ! これは遊びじゃないのよ。湖畔の別荘で、釣り用の筏をつくるような気晴らしとはわけがちがうわ」
一同は神妙な面持ちでうなずいた。
「これはわたしのやり方で進めるわ」ザライは宣言した。「あなたたちはみな、わたしの役割は夢を抱くことだと言ったじゃない。今さら反論しないで」
ニックス、わたしはまちがってる。わかってる。でもほかにどんな方法があるというの?
その晩ザライは翡翠の院主と、切り出しが進んでいる林に降りていった。木こりたちは安全を考えて夜は働かなかったが、見張りを立てていた。林のなかで、ガラス猫や野生化したクリスタル・オートマトンに出くわす心配はなかった。
院主は今日も桃をたずさえていた。ザライが知る限り、何日かかろうが、キャンプから徒歩でいけるような範囲には桃の木などなかった。院主がキャンプに加わって一カ月近くが過ぎたが、彼はまだ新鮮な果物を持っていた。
「あなたはもう一度飛ぶのだね」彼は言った。
質問なのか、事実を述べているのか、ザライにはわからなかった。「だれかが飛ぶわ」彼女は言葉を濁した。
「あなたの言葉を聞いたよ。だれかが飛ぶのなら、それはあなたになる。自分の代わりに別の人を送るなんて、できないのだろうね」
「船長の職業病よ」ザライは小道をふさぐ倒木をまたぎ越えた。「女王は人を送って自分の代わりに死なせるわ。船長は先頭を切って嵐に踏みこむの」
「愛の一つの形だ」翡翠の院主の声があまりに小さかったので、ザライは立ち止まって耳を澄ませた。そして彼の言葉に固まった。「あなたは心から大切にしている人の命を犠牲にしはしない」
ザライは震えながら深呼吸した。伐採林に立ちこめる夜の香気が彼女を満たした──青臭く湿っぽい、しみ出る樹液と砕け散った樹皮の匂いだ。吸って、吐いて。ザライは自分に言い聞かせた。
「マニックスがいなくなって久しいわ。もう死んでしまったかもしれない。知る由もないけれど」
院主は再び、小さすぎる声で言った。「あなたが愛しているのはマニックスだけではないよ」
ザライはふり向き、怒りを吐き出した。「ほかにはだれもいないわ!」
「女と男という形では、確かにいない」院主の顔にかすかな笑みが浮かんだ。「あるいはそれなのかもしれない。わからない。わたしはもう数世紀も禁欲の誓いを守っている。老人に何がわかるだろう? でもわたしは、あなたがエーアと黙々と作業する姿を見てきた。鍛冶屋の兄弟となごやかに言い争うのを見た。ロソダを娘か妹のように見守っているのを見た。キー、アーマイン。キャンプにいる者はみな、あなたの夢の申し子だ。だからあなたは彼らを愛している」
「まるでわたしが天使かなにかのようね」ザライは憮然として言った。
静かな闇のなかで、院主が頬笑む音が聞こえるようだった。
「わたしはもう一度、天へと飛ぶわ」ザライは続けた。自分でもなぜかわからないが、妙に意固地になっていた。「だからといって、わたしは天使じゃない。ただ、意志の強い女なだけよ」
「天に飛びこむことは、天使になる条件として十分だと思うよ。少なくとも、大多数の人にとっては」
「院主は翼を信頼しすぎだわ」ザライは言った。
「あなたは信頼しなさすぎだ。翼をつくっている本人だというのに」
ザライと翡翠の院主は歩きつづけた。それぞれの思いは沈黙が代弁した。やがて二人は、伐採林のなかでもっとも開けた場所に出た。夜空が、空き地の端の木々からなる短い地平線の向こうに広がった。
ザライは空を見上げ、ニックスがしばしば口にしていた問いを思い出した。「星が何でできているか、考えてみたことはありますか?」
「天地創造の考え方は」翡翠の院主が応えた。意識がどこか遠くをさまよっているような、ぼんやりした声だった。「それぞれが新たな可能性を抱いている。そして無限に増えつづける」
ザライは彼が、愛と同じように、と言い添えるかと思いかけたが、院主はまたもや沈黙した。
「今度はもっと大きな輪を描いて飛ぶわ」ザライは言った。「そうすれば戻ってきて着陸できる。その次の旅はさらに大規模になる。月に向かうか、遠くの星々のあいだを航行するわ」
「月がどのくらい離れているか、知っているのかい?」
「関係あるかしら?」ザライは自分が頬笑んでいることに気づいた。最近では珍しいことだ。「軌道環をつかんで、月の環が近づいてくるのを待てばいいだけじゃない。船を切り離して、今度は月の環をつかむ。月が環をまわって戻るのを待って、真夜中の銀色の世界に突入する。同じようにして帰還できるわ。天地創造による環を次々とたどりながら」
「なるほど」翡翠の院主はすっかり感心した様子だった。
「ロソダと二人で、何度も話し合ったもの」
「彼女が飛ぶ前に」
ザライはまばたきをして涙をおさえた。「彼女が飛ぶ前に。ええ、そうよ」
翌日、ザライは〈ダレト〉が作業小屋から消えていることに気づいた。
「薄(ボー)!」ザライは叫び、二人の鍛冶屋のうちより頼りになる方を呼んだ。
薄がやってきた。彼の長い革の前かけは鋳造所での作業で煤けていたものの、ザライに呼ばれて来ただけにしては妙に早かった。
呼ばれることを予期していたかのようだ。
「船はどこ?」
薄は少なくとも、ザライが〈マニックス〉のことを言っていると勘違いするふりはしなかった。「崔とキーが頂上に運びました」
「いつ?」
薄は彼女の目を見た。「昨日の晩です」
「打ち上げたの?」
「今夜です」
「そんなことをして、わたしに見つからないと思っていたの?」
薄は視線を落とした。「わたしの計画じゃない」
でも、彼はザライに伝えなかった。「上に行くわ」
「ザライ」薄は彼女の腕に触れた。「彼らはあなたの安全を守ろうとしている」
「逆らうことで?」
彼の指が離れた。「いつからあなたは女王になったんです?」
このひと言にザライは凍りついた。ザライは薄を見つめ、薄も視線を返した。ザライはかっとなって翡翠の院主との前夜の会話を思い出した。彼女はやっとのことで口を開いた。「わたしはずっと、船長以外の何者でもないわ。女王なんてとんでもない」
「〈マニックス〉に乗ったら、あなたが船長です。あなたの言うことが絶対です。ここでは、あなたは夢をつなぐ」薄の指がぴくっと動いた。ザライを引き寄せようと思ったかのように。あるいは、殴ろうとしたのかもしれない。「夢は、あなたのものではない」
そう、夢はニックスのものだった。ザライにはわかっていた。彼女はせいぜい予言者の弟子でしかない。遠くの星々の美しさに魅せられた彼の言葉を伝えているにすぎない。ニックスは天を語った。ザライが持ち合わせていたのは、大地に縛られた言葉と、夜に向かって登るという信念だけだった。理屈を越えた信念だった。
ザライは薄にうなずきかけると、自分がねぐらにしている球体に通じる梯子にとぼとぼと向かった。
だれも来なかった。翡翠の院主すら来なかった。外では陽が移ろい、球体の入り口から差す光の角度が時間の経過を知らせた。キャンプの物音が聞こえてきた。危険を知らせる叫び声がして、何かがガシャンと落ちた。鍛冶場からは槌の音が響いた。重い荷を運ぶグループの息のあった掛け声がして、その荷物、あるいは別の何かを空の近くへと吊り上げるデリックのロープがきしんだ。
風も同じような情景を運んできた。鋳造所の炉の鼻につく匂い、切り立ての木材、熱した油でトウガラシを炒める匂いがした。
ザライには作業が見えない。塔の頂上にいる仲間たちも見えない。でも、彼らがそこにいることはわかっていた。
やがて、夜のとばりが降りた。ザライは闇に支配されるに任せた。ろうそくも、ランプもランタンもいらなかった。音も匂いも変化した。暗くなってから一、二時間後、大勢の集団が発射櫓に登っていった。
ザライのもとにはだれも来なかった。声をかける者もいなかった。自分は女王でも船長でもないとザライは気づいた。彼女はひとりだった。
ニックスだったら、こんなことは許さなかっただろう。考えるまでもなかった。彼なら、ロソダが死んで〈ギメル〉が失われた後も、笑顔で陽気に冗談をとばし、素手で空まで登ってみなに模範を示そうとしたはずだ。
沈黙の共謀も、打ち上げ中止になった船を用意するようなこともなかっただろう。
彼は自分の名を冠した船を数日のうちに、悲しみが新鮮なうちに発射架台に乗せたはずだ。そして華々しく空を切りひらいたにちがいない。
そこに思いあたって、ザライは立ち上がった。厚手のコートを手に取り、球体から降りて発射櫓の第一梯子へと向かった。
みなはザライを待っていた。キャンプのほとんど全員が、第二と第三プラットフォームに集結していた。彼らはザライに向かって次々に手を伸ばし、彼女の肩に触れ、短く刈られた髪をなで、腕に指を走らせた。まるで、ザライ本人が再び飛び発つために、見知らぬ人々のあいだを縫って歩いているようだった。彼女は笑わなかったし、ほとんど口を利かなかった。ただ挨拶代わりにうなずき、人だかりをすりぬけて一番上のプラットフォームまで登りつづけた。
船長でも女王でもない。ザライは思った。わたしは夢の言葉を守る一人の女、それだけだ。
最上段で、エーアが彼女を迎えた。エンキドゥ族の顔は静かな、穏やかな悲しみを湛えていた。
「どうしたの?」ザライはたずねた。エーアは黙って首を振った。
翡翠の院主が〈ダレト〉のそばに立ち、開いたハッチのなかを覗きこんでいた。アーマイン、キー、崔。全員そろっている。ザライは女王ではないと決心したものの、改めて裏切りの痛みを感じた。「だれが飛ぶのよ?」彼女は答えを求めた。「なぜなの?」
薄が歩み寄った。冷たい強風がうなりをあげた。塔に人が残っているには遅すぎるとザライは知っていた。もう、プラットフォームを空けなければならない時間だ。このままでは一同は聴力を失うかもしれない。しかしだれも気にしていないようだった。
「わたしたちはロソダを埋葬した」ザライはほとんどやぶれかぶれだった。「辛うじて、見つけられた部分を」
〈ダレト〉のハッチのなかからくぐもった声が響いた。ザライが近づくと、なかにいる人物は外に顔を向けようとして無理やり体をねじった。
ニックス。
マニックスのずんぐりした、不細工な、愛すべき顔が彼女を見返した。「久しぶりだな」マニックスは歯が抜けた笑顔をみせた。いつの間に無くしたのだろう? 「飛ぶ機械をつくってくれたんだな」
ザライは彼に抱きつくべきか、叫ぶべきか、飛び降り自殺すべきかわからなかった。
「マニックスに黙っているよう頼まれたんです」薄が肩の後ろで言った。
ザライが翡翠の院主を見ると、彼はかすかにうなずいた。知っていたのだ。前日の晩、二人で林のなかを歩いていた時も知っていたのだ。ザライはマニックスに視線を戻した。目に涙が溜まり、ランタンの明かりと遠くの星々の輝きがにじんで視界が曇った。
ザライはやっとのことで、喉に詰まっていた言葉を吐き出した。彼女を危うく窒息させそうだった言葉を。「戻ってきたのに、教えてくれなかったのね。あれだけのことをしたわたしの元に、戻ってきてくれた。でも教えてくれなかった」
「おれは飛びたかった」ニックスは答えた。「そして空からきみのところに戻りたかった」
ザライはふり向いた。「みんなは彼のいいなりになったわけ?」
「わたしがそうさせた」翡翠の院主は言った。
「あなたが船長で、ここの王様というわけね」
「彼は院主だ」エーアがつぶやいた。
ザライはふたたび、裏切りの鋭いショックを感じた。
「おれは飛ぶ。そして光に照らされて戻ってくる」ニックスはザライの後ろから言った。「二人の愛を、夜明けの炎につつんで持って帰るよ」
「その夜明けの炎が、ロソダを殺したのよ!」キーが顔をしかめたが、ザライはかまわず続けた。「もう一度あなたを失うなんて、ごめんだわ」彼女は体をぐるりと回し、さらにもう一回りした。「男も女もひとり残らず今すぐプラットフォームを降りること! 特にあなた、行方不明者のマニックス。さあ、どいた、どいた。朝になったら〈ダレト〉を降ろして〈マニックス〉を上げるわ」彼女はハッチに身を乗りだした。「でもまず、船の名をロソダに変えます。このキャンプで命を失う英雄は一人でたくさんよ」ザライは起き直り、周囲を見まわして自分を見つめる全ての目と視線を合わせた。「明晩、わたしたちはエーテル船を打ち上げます。船長はわたし、マニックスが立会人として同乗する。そしてエーアを乗組員として連れていくわ」
「あれに乗れるのは──」だれかが言いかけたが、すぐに口をつぐんだ。おそらく肘で小突かれたのだろう。
「さあ真夜中がくる前にさっさと降りてちょうだい。でないとみんなであの世行きよ」
その晩、夜もだいぶ深まってから、ザライはじつにひさしぶりに二人で眠った。“眠った”とは言えないかもしれない。ザライは暗闇のなかで頬笑んだ。ニックスは彼女の腕のなかにおさまり、自由に動かせる方の手でザライの右の胸の丸みを戯れになぞっていた。彼女の腰は真新しい記憶と高まる期待に震えた。
「どこに行っていたの?」ザライはついにたずねた。
「遠くに」マニックスはつぶやいた。「きみを殺してしまわないように」
ザライは臨終の息を吐くかのように、その名を発した。「ジャントン」この海賊の死をきっかけに、彼女の人生は一変した。殺しが原因で〈怠惰の極み〉号を失い、女ばかりの世界から、なじみのない男の世界へと飛びこんだ。やがてマニックスと出会い、その後彼まで失った。
彼女に殺された男は、三度目の復讐をしようとしているのだろうか。
次の質問はもっと難しかった。「なぜ戻ってきたの?」
マニックスは口をザライの肌に当てていたので、くぐもった声になった。まるで、空中に言葉を発して彼女の耳に届けることを嫌がり、ザライの体に直接注ぎこもうとしているかのようだった。それでも、ザライには彼の言おうとしていることが十分にわかった。「死んだ男を愛するよりは、生きている女を愛するほうがいい」彼は唇をザライの胸から離し、頭をそらせて彼女の目を見ようとした。「おれはその逆をやろうとしてきた。あまり良いものではなかった」
「ごめんなさい」ザライは言った。彼女は長い年月の重みと、決して意図したわけではなかった大昔の殺人の全責任を感じた。
「ここに着いたとき、まずは院主のところに連れていかれた。おれがだれだか気づいた人たちに」マニックスはザライの体に両腕をまわし、さらに抱き寄せた。「きみがここで何をしてきたか知ってからは、飛ぶことしか考えられなくなった。天から戻ってきて、きみの許しを請おうと」
ザライはたじろいだ。「わたしの許しですって?」
「きみを置いていったことを」
「あなたの恋人を殺したんだもの」ザライは言った。
「おれたちの人生はどちらも打ち砕かれ、再生した。そしてきみは星界への橋をつくった」ニックスは姿勢を変えて、キスができるように体を引き上げた。息と息のあいまに、彼はつけ加えた。「一緒に行こう」
ザライは船長としても女王としても容赦なくせきたてたが、〈ロソダ〉の準備には五日かかった。まず、発射架台のカウンターウェイト装置とバランスを大幅に調整する必要があった。推進力は圧縮ガスのまま、帰還方法は複数用意された。船体の気密性が点検され、航路の地図が何度も描き直された。ザライ、エーア、そして特にマニックスは、操縦桿の操作や不測の事態への対応、地上でのテスト結果、ザライ自身の短く身のすくむような飛行について説明を受けた。
今回の飛行も短く、ザライが以前〈ギメル〉で飛んだ時よりわずかに長く設定された。それでも彼女はエーテル船にたっぷりの食糧と水、工具や物資を積みこむよう指示した。
「その重さとバランスで、船がどんな風に飛ぶのか確認したいわ。上下の区別がない場所で、なにが浮遊するのか」このことを考えるとザライは昼食を戻しそうだった。彼女は不快な連想と吐き気を追い払った。
その日、後になって薄がザライをわきに連れだした。彼女がニックスと一緒にいない、まれな瞬間だった。「準備ができましたね」彼は言った。
「不安はなくなったわ」
「無茶な飛行をするつもりですか?」
「どういうこと?」
鍛冶屋は頬笑んだが、ザライには彼の目に宿る不安が見えた。「戻りますよね?」
「まあ、薄……」ザライは手を伸ばして彼の顎をなでた。「わたしはいつでも戻ってくるわ」
「彼が隣にいれば、その必要もないのかもしれない」
ザライは肩越しにふり返った。ニックスは小屋のすぐ外で、女性熟練工が不安そうな表情で手にしている銅の被覆に見入っている。
「薄、わたしに必要なのは」ザライは言いかけてから、考えがまとまらないことに気づいた。翡翠の院主は正しかった。彼女は愛し、ふたたび愛した。人の愛はひとつのはずだった。だれだって知っている。ニックスがジャントンを愛するがために、彼女を置き去りにしたように。そしてザライを愛するがために、ジャントンの思い出を裏切ったように。ザライ自身、薄が自分に叶わぬ思いを寄せていると何ヶ月も前から知りながら、その結果を恐れて見て見ぬふりをしてきたように。
ニックスが帰ってくるかもしれなかった。
そして彼は帰ってきた。
「わたしに必要なのは」ザライはもう一度言った。彼女は二人の気持ちのために、できるだけ優しい嘘をついた。「空に手を伸ばすことよ。わたしが戻ろうと戻るまいと、新しく、より良い船をつくって後に続いてほしい。夢を追いつづけるのよ。わたしたちが知らないどんなことを星々が知っているのか、わかるまで」
「わたしに必要なのは、あなたが行くことです」薄もお返しに優しい嘘をついた。
エーアは最初の一人だった。そしてこのエンキドゥ族が最後の一人になる。打ち上げの晩、ザライは言葉少ない建設者と散歩に出た。二人はキャンプを離れて広々とした着陸場所に向かった。〈ロソダ〉をホームに導くためのかがり火が、すでに焚かれていた。
「あなたを指名したけれど、頼みはしなかったわね」ザライは言った。
エンキドゥ族は低くうなっただけで、あとは何も言わなかった。
ザライはねばった。「一緒に来てくれる?」
「もちろん」
「自分から志願する気はあった?」
ふたたび沈黙が落ちた。
「そうだと思ったわ」ザライは深く息を吸ってから、言葉を継いだ。「だからあなたを指名したのよ。あなたはだれよりも先にきた」
「翡翠の院主に送られてきた」エーアはまるで罪を認めるかのように言った。
「あなたはいちばん最初にそう言っていたわね。だんだんわかってきたけど、この計画を影で支えているのは院主なのね」
「あなたがすべてを支えている」エーアのしわがれた声のなかに、確固とした、不屈の忠誠心が響いた。
「わたしは手段にすぎないわ。マニックスの夢と、罪悪感の手段よ。翡翠の院主の目標を、なんであれ達成するための手段。そして、みんなが共有しているビジョンを実現する手段よ」
エーアはほとんどむせび泣くように言った。「空に向かう船を、いったいだれが一人きりで作れるのか?」
「一緒よ」ザライは言った。「一緒につくった。そしてわたしもみんなのために働いた。わたしと航海に出てくれる?」
大きな、毛むくじゃらの手がザライの手を包みこんだ。彼女自身の手が、イチジクの実を包むときのように。「イエス」
二人はキャンプに戻り、発射櫓に向かう途中で翡翠の院主を見つけた。「なぜなの?」ザライはたずねた。
「天にも天使がいるべきだから」彼は答えながら、またしても新鮮な桃をザライに手渡した。
急に歓声がして、彼らは騒々しい一団に囲まれた。ニックスが先導し、薄、崔、十人ばかりの木こりと熟練工たちがどんちゃん騒ぎを繰りひろげていた。一行が〈ロソダ〉に乗りこみ、真夜中の空に踏み出す時がきた。
ザライは、院主の本当の理由がなんであれ、今はもう知ることができないこと、おそらくこの先も知ることはできないことを理解した。
エーテル船は当然ながら、試作機に比べてかなり大きかった。あまりに大きいので、打ち上げ責任者以外はプラットフォームに立てなかった。キーがエーアの役目を引きついだ。三人の飛行士は梯子の最上段から直接船に乗りこんだ。薄が後ろに待機し、ハッチをきっちり閉じた。
今夜は風のうなりが強く、指示を叫ぶ声やはなむけの言葉はことごとくさらわれていった。三人は船内に身をおちつけ、ザライは不安に耐えた。ニックスは子供のようにはしゃぎ、エーアは顎の大きな顔に満面の笑みを浮かべた。
ザライは今回はチェックリストを忘れなかった。彼女は詰め物をしたヘルメットの紐をしめ、しかるべき手順を踏み、目の前の窓の上にある時計の針の動きに気を配った。〈ロソダ〉は西向きに、発射架台に斜めに据えられていたので、窓から見えるのは地球の大歯車の頂上ばかりだ。
振動が始まり、騒音がやってきた。キーは最後にもう一度窓を叩いた。ザライはうなずき、船体がつかみ上げられ、夜の世界へと連れ去られる瞬間を待った。
ニックスがここにいる。二人は一緒に天に行くのだ。どちらが生き残り、もう一方を弔うのかなどとくだらない喧嘩をする必要もない。
船体が持ち上がったとき、ザライは恐れを忘れていた。騒音がまともな程度に戻ったとき、ザライは恐れを忘れていた。船体を軌道環から切り離し、上下の区別が失われたとき、彼女は恐れを忘れていた。
ザライはニックスの方を向いた。「星のあいだを飛んでいるわ」
彼は前面の舷窓から外を見つめていた。近くには軌道環がそびえ、かなたには月の輪が見えた。地球はどんどん後ろに遠ざかった。
「では、進路をホームに向けましょうか?」ザライは茶目っ気をみせてたずねた。
「このまま星のあいだにいようじゃないか」ニックスは息を吸った。
「ドラゴン砲がある」エーアが言った。
ザライは過去と未来の間でためらった。帰路があらかじめ設定された点火ボタンに手をかけて、どうすべきか考えた。外からは天界が誘いかけた。
ザライは笑い、道を選んだ。
(完)
(訳:志村未帆)
作品について
ここでの紹介ははじめてになりますが、ジェイ・レイクは1964年生まれ、2003年にL・ロン・ハバードの基金ではじめられたSF作家の登竜門、〈未来の作家〉コンテストで首席に選ばれ、翌年にはキャンベル新人賞を受賞しています。以後、3つのシリーズを含む9冊の長篇、6冊の短篇集、2冊のノヴェラ単行本、共著を含む12冊のアンソロジーを発表し、ジャンル外の長篇も一冊書いていて、もはや押しも押されもしない新世代の中心作家です。作風もファンタシイからハードSF、スペースオペラ、スリップストリームと幅広く、オールドファンにもわかりやすい、ファン気質もたっぷり残したオーソドックスなSF作家だといえるでしょう。愛嬌のある顔に豊満な体躯、さらにはアロハシャツが大好きという親しみやすい容貌で、2007年のワールドコンの際には来日して、元気な姿を日本のファンにも披露しました。けれど、残念なことに翌年結腸ガンを患い、以後闘病の記録を残そうと、ドキュメンタリー映画を撮影しています。2012年になって再発と転移が確認され、化学療法の再開と手術が予定されているそうで、いまは少し落ちこんでいるようです。その闘病生活はブログにも詳しいので、励ましのコメントを寄せていただければありがたいと思います。世代を問わず大勢の作家仲間に愛されている、とてもいい人なのです。代表作は2007年刊のMainspringにはじまるクロックパンク三部作で、地球をはじめ星々の自転、公転といった運行すべてが巨大な歯車でつながったぜんまい仕掛けでおこなわれている世界を描いた、壮大なスケールの法螺話です。赤道には巨大な壁がそびえて、北半球と南半球は完全に分断され、アメリカは独立せず、大英帝国と中国が二大勢力となっていて、宗教が大きな力をまだ保持しているのですが、作家本人はたしか無神論だったような気がします。このノヴェラもシリーズの番外篇として、「愚者の連鎖」(SFマガジン2010年6月号)の続編の形で書かれ、〈サブタレイニアン〉誌2009年秋季号に掲載されています。
ここでうれしいお知らせがあります。この作品がSFマガジンの2012年11月号に転載されることになりました。前作も掲載しているので、当然のことなのですが、長さが長さなのでここで紹介するしかないと思っていたのに、わざわざ誌面を割いていただくことになりました。早川書房さまありがとうございます。なお、ジェイクのほかの作品はSFマガジン2009年6月号「ローズ・エッグ」、ミステリ・マガジン2010年8月号「100パーセントビーフのパティをダブルで」を読むことができるので、併せてお楽しみいただければ幸いです。(小川隆)
〈ジェイ・レイク著作リスト〉
■The City Imperishable シリーズ(ファンタシイ)
1. Trial of Flowers (October 2006) Night Shade Books
2. Madness of Flowers (October 2009) Night Shade Books
■Mainspring シリーズ(クロックパンク)
1. Mainspring (June 2007) Tor Books
2. Escapement (June 2008) Tor Books
3. Pinion (March 2010) Tor Books
■Green シリーズ(SF)
1. Green (June 2009) Tor Books
2. Endurance (November 2011) Tor Books
3. Kalimpura (January 2013)
■その他長篇
Rocket Science (August 2005) Fairwood Press
Death of a Starship (December 2009) MonkeyBrain Books
The Baby Killers (novella) (August 2010) PS Publishing
The Specific Gravity of Grief (novella) (2010) Fairwood Press
■その他短篇集
Greetings from Lake Wu, Wheatland Press (November 2003)
Green Grow the Rushes-Oh, Fairwood Press (2003)
American Sorrows, Wheatland Press (August 2004)
Dogs In The Moonlight, Prime Books (August 2004)
The River Knows Its Own, Wheatland Press
The Sky That Wraps, Subterranean Press (September 2010)
■アンソロジー
Polyphonyシリーズ(スリップストリーム)
Polyphony 1 (with Deborah Layne), Wheatland Press (July 2002)
Polyphony 2 (with Deborah Layne), Wheatland Press (April 2003)
Polyphony 3 (with Deborah Layne), Wheatland Press (October 2003)
Polyphony 4 (with Deborah Layne), Wheatland Press (October 2004)
Polyphony 5 (with Deborah Layne), Wheatland Press (October 2005)
Polyphony 6 (with Deborah Layne), Wheatland Press (December 2006)
All Star Zeppelin Adventure Stories(with David Moles), Wheatland Press/All-Star Stories (October 2004)
TEL: Stories, Wheatland Press (August 2005)
Spicy Slipstream Stories (with Nick Mamatas), Lethe Press (September 2008)
The Exquisite Corpuscle (with Frank Wu), Fairwood Press
Other Earths (with Nick Gevers), DAW Books (April 2009)
Footprints (with Eric T. Reynolds), Hadley Rille Books (July 2009)