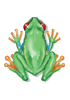星の鎖 第二章
ジェイ・レイク

Illustration by Norio Kozima
第二章
探求
ザライはねばり草――と彼女が呼ぶようになった草――の収穫中、誰かに見られていることに気づいた。球体の都市はあれ以来無人のままで、凍りついたかのようだった。彼女はもう何ヶ月も静かで歪(いびつ)な住処(すみか)に一人で暮らしていた。実験、また実験の日々だった。空を越えて旅する船のつくり方は見当もつかなかったが、真鍮の大歯車の垂直面に沿って装備を持ち上げる方法は見つけつつあった。
一度に一つずつだ。
そして今、一人のエンキドゥ族が彼女を見つめていた。毛むくじゃらの男で、鼻孔は大きく膨らみ、額は傾斜している。翡翠の院主(いんじゅ)と同じようなオレンジ色の法衣をまとっていて、片手には杖を、もう一方には包みを抱えていた。
ザライは作業を中断して体を起こし、手を振った。相手に気づいていないふりをするのは無意味だし、またとない会話のチャンスを逃すつもりはなかった。
エンキドゥ族は、ザライが作業をしていたスゲの茂みに降りてきた。そばまで来ると、彼はお辞儀をした。
「師匠がよろしくと言っている」彼の声は太く、くぐもっていた。
人生のある段階では、ザライはエンキドゥ族に対して、男の子や大人の男に対するのと同じような軽蔑を抱いていた。彼女が船長を務めた最初で最後の船、〈怠惰の極み〉号では、短い間だったが、アアという名のエンキドゥ族の鎖舵手と一緒に働いた。あのエンキドゥの女は、若かったザライの盲目的な信念をいくらか揺るがした。その後の数年間に〈レイピア〉号で出会ったエンキドゥ族たちは、彼女の思い込みを粉々にしてくれた。
「ようこそ」ザライは言った。「何もないけど、できるかぎりのおもてなしをするわ。あなたは翡翠の院主に仕えているの?」
「院主は……」エンキドゥ族は言い淀んだ。
ザライは言うべきことはないかと探した。彼の重い口を開かせる口上や挨拶はないだろうか。基本に戻ってみよう。
「あなたの名前は?」
「エーア」
「わたしはザライ」
エーアは見事なぼさぼさ頭を揺らしてうなずいた。
ザライはやり方を変えてみた。「翡翠の院主はどうしてあなたに〈壁〉の上を歩かせたの?」
「あなたを探す」
ザライはこの会話は無意味だと気づいた。さらに別の方向を試すしかない。「エーア、ここでねばり草を刈り取るのを手伝ってもらえるかしら。ナイフは持ってきた? ちょっとコツがいるから、教えるわね」
エンキドゥ族は働き者だった。当初は戸惑いを覚えた彼の沈黙にも、ザライはすぐに慣れた。彼女はしばしば、翡翠の院主はなぜエーアを寄こしたのだろうかと自問したが、考えて答が見つかることではなさそうだった。
こうして、ザライはねばり草を刈ってエキスを抽出することに精を出し、エーアにも同じ作業を与えた。ザライは毎晩、実用に耐える起重機をつくるのに必要な資材の量を計算した。エーテル船を、大歯車の真鍮の表面に沿って八百メートル持ち上げるのだ。精製したねばり草で、プラットフォームは堅固に固定できるだろう。しかし、設計の原理は応力と負荷と安定性を付き合わせて考える必要があった。
今さらながら、マニックスが恋しくてたまらなかった。彼女は頭をひねり、見直しをかさね、模型をつくり、やっとのことで作業を進めていたが、彼だったら素材を曲げたり叩いたり組み合わせたりするうちに完成させただろう。
ザライではそうはいかない。
二週間ほど経ったある晩のこと、エーアはザライがつくった木製の模型を眺めて、何本かの支柱を指さした。「ここを筋交いにすると、強度が増す」
このエンキドゥ族が到着して以来、ザライが耳にした最も長い発言だった。
彼女は驚いてたずねた。「あなた、機械工学の知識があるの?」
エーアはうなずいた。
ザライはリフト・タワーと中間デッキの模型の前を離れた。実物が完成すれば、大歯車の基底部から全長八百メートルのうち、最初の約二百メートルを構成するはずだった。模型の細い小枝は巨大な丸太の代わりだったが、ザライには丸太を手に入れるあても加工する道具もなかった。「来て。自分で納得がいくようにいじってみて」
エンキドゥ族は二メートル半ほどの模型の前にしゃがみ、直接触れることなく木材に沿って指を動かした。想像のなかで完成させている、とザライは理解した。エーアは明らかに、ザライの作品を以前から観察していたようだ。彼は悩むさまも見せず慣れた様子で検討していた。
模型はエーアに任せて、ザライは土器の壺でねばり草を煮出す作業に戻った。なめらかな壺の内側には、同じ植物の樹液を固めたものが塗りこめてあった。
一週間後、サフラン色の法衣をまとった笑顔の男が二人現れた。二人は翡翠の院主と同じ人種だった。肌は浅黒く、目は生まれつき細かった。崔(チョイ)と薄(ボー)は兄弟で、会話が不得手なエーアを補ってあまりあるほどおしゃべりだった。彼らは工具をたずさえ、小さな加熱炉を手車にのせて牽(ひ)いてきた。
「こいつがなかなか厄介だった」薄がにやりと笑って言った。「イバラだらけの渓谷は、崔に運ばせたんだ」
「それに蛇だらけだった」崔が言い添えた。「ぼくが毒蛇の巣を踏むように、わざわざ導いてくれたものな」
二人は仲のいい兄弟らしくお互いを叩きあった。そして再び、小鳥がさえずるようなおしゃべりに戻った。彼らは持参した加熱炉を据えつけると、鉱石やくず鉄を探しはじめた。より大きな加熱炉をつくるためだろう。少なくとも、ザライはそう推測した。
ザライはねばり草の作業に戻り、エーアは第一リフト・デッキの見直しと、その先の構造の検討に集中した。エーアはザライに対しては無口だったが、崔と薄を相手に尺度や容量や切断方法について話し合うことは苦にならないらしかった。
こうしてこの年は過ぎていった。ねばり草の接着剤はずいぶん溜まった。加熱炉は次から次へと大きくなり、工具づくりが始まった。人も増えた。火明かりと会話に引き寄せられてきた放浪者もいれば、商用で通りかかり、仕事を終えた後に戻ってくる者もいた。翡翠の院主は一人ずつ順繰りに女性を二人寄こした。彼女たちは〈壁〉を旅してくる道すがら、星空を歩こうとしている船乗りの物語を広めてきた。
新年を祝うころには、ザライはちょっとした集落を率いるようになっていた。二十名を越える人員には、木工職人、鍛冶屋、製帆の経験のある仕立屋がいた。木こりの二人組は〈壁〉を三キロほど下ったところに手ごろな林を発見し、ロープやケーブルづくりを得意とする職人たちと協力して、立派な円材を工事現場まで運びこもうとしていた。
ニックスがここにいて、自分の夢がどんな形になっているか見ることができたら、とザライは思った。
集落のメンバーは屋外に集まり、敷きたての石畳の上に粗末な椅子を並べて焚き火台を囲んでいた。ワインにイノシシのロースト、サギの蒸し煮や各種野草の祝宴だった。ザライはワインのでどころを訝(いぶか)しんだが、ともかく祝杯をあげる必要があると感じていた。
「わたしたちに乾杯」彼女はまじめくさって言った。一同はおしゃべりを中断し、一斉に彼女のほうを向いた。「最初に来てくれたエーアのために。わたし以上にわたしの道を見通してくれた翡翠の院主のために。そして、今もこれから先もこの地を踏むことはないマニックスのために。天への梯子を登れることを、あなたが教えてくれた」彼女はグラスを傾け、ワインを足元の岩に注いだ。「どこにいるのであろうと、この流れが彼を見つけますように」
涙がこみ上げたが、ザライは抑えようとしなかった。
みなはへべれけになるまで飲んだ。奇跡的にも、崖から落ちた者はいなかった。
薄と崔は腰を下ろして、ザライと船のことを話し合った。そこは兄弟が建てた作業場だった。鍛冶場と工場を組み合わせた施設では、すでに金属柱や締め具の製作が始まっていた。塔はこれらの部材を支えに球体都市の周囲と上方へと発展し、ねばり草で固定されていた。
「通り抜ける方法、知っていますか?」薄がたずねた。
ザライは質問に戸惑った。「どういうこと?」
崔が笑顔をみせた。「空気みたい、水みたい、それともエーテル? 船は何のなかを通ります? 潜水艦、飛行船。なにで?」
「バケツ船よ」ザライは〈鎖〉で船長として働いていたころを思い出しながら言った。「でも、上まで運ぶ方法すらまだわからないわ」
「いずれわかります」薄はうなずいた。「エーアが見つけてくれる。彼はとても賢い。塔を建てれば、彼が運んでくれる」
「それは頼もしいわ」ザライには彼らが何の話をしているのか見当もつかなかった。ここにいるたった二十数名の力で、ニックスの夢はすでに彼女の手の届かないところまで発展していた。自分一人で成しとげようだなんて、よくも考えられたものだ。
いいえ。ザライは思った。なにも考えていなかったわ。
考えていたのなら、マニックスは去らなかったかもしれない。
「あなたの言う通りだわ」ザライは自信のあるふりをして言った。「でも、媒質が何かはっきりしないの。マニ――古い友人とわたしは、とても薄い空気かエーテルだろうと推測したんだけど」
「エーテルはどんなものでしょう?」崔が言った。
「気体のようなものだと思う。空の向こうの広がりを満たしている媒質よ。話を信じれば、漕いだり、押したりできるそうだわ」
薄は再びうなずいた。「もし薄い空気なら、あまり押せない」
「ロケットだ!」崔が威勢よく言った。「何でも押せる。真空でさえも」
「ロケット?」ザライは混乱した。「花火のような?」
「なんだってロケットになります」彼は物知り顔で言った。「水や空気をつめた瓶でも、なんでも」
憶測。すべてはばかばかしい夢から出発した根拠のない憶測にすぎなかった。「空の上になにがあるのかわからないのよ」
兄弟は視線を交わした。「いずれわかります」しばらくして薄が言った。「エーアが塔を頂上まで完成させる。上に行って試作機を飛ばし、様子をみましょう」
「初飛行、無駄にさせません」崔は付け加えた。「単なる当てずっぽうで」
ザライは憶測と言ったが、誰の目にも明らかなことだった。「あなたたち、何か考えがあるのね」
「もちろん」薄は言った。彼はふり返ると、いつのまに増えたガラクタの山の一つから、布の覆いを外した。
ガラクタじゃない。ザライは気づいた。試作機だ。真鍮と銅の船だ。豚の膀胱のような形をしていて、中央にクリスタルの窓が嵌められている。脇にはパイプや管がボルトで留められている。
「これが」崔が指さして言った。「ロケット……」
それから数ヶ月で塔はかなり伸びた。エーアと木こりたちは、〈壁〉の表面を下った先の渓谷から、隠れた木立をそっくり切り出そうとしていた。崔と薄の兄弟は、山形鋼や締め具、ソケットや滑車や車軸を鍛造した。二人は難破船の集積場から運んできたくず鉄と、〈壁〉の表面を探しまわって集めた鉱石を土窯で精錬し、作業場を埋めつくすほどの部材をつくりあげた。
うわさが広まるにつれて、さらに人が集まった。翡翠の院主のおかげにちがいなかったが、ほかの者たちもそれぞれに話を広めはじめていた。
ザライが驚いたことに、集落に集まった人はみな、あらかじめニックスの夢を心に抱いていた。だれもが星空を見上げた。少なくとも、ここに来た人はみなそうだった。
ザライが特に強い印象を受けたのは、ロソダという少女だった。彼女はえび茶と灰色に染めた革の衣をまとっていた。肌は崔と薄の鍛冶場で精錬された鉄と同じくらい黒く、その目は嵐に荒れる地平線の色だった。彼女は誰に対しても、何についても多くは語らなかった。しかし、伸ばした革に描かれた天の地図を持っていた。地図には惑星や月の軌道環の位置関係が示され、特に明るい星々と星座についての注釈もあった。
ロソダとザライとの共通言語は、平水域世界の英語が少しだけだった。それでも、星空を眺めるには事足りた。そして彼女は、とても遠くから来たらしかった。
「あなたが作ったの?」ザライは二人が意思疎通をはかれる唯一の言葉でたずねた。彼女自身、英語にそれほど自信があるわけではなかったが、〈鎖〉を離れると、〈壁〉の全域にわたって使用されている言語は英語だけだった。少なくとも、北半球に面した側では。
「わたし、つくる」ロソダは勢いよくうなずき、ペンを握る真似をした。
ザライはなめらかな革に手をすべらせ、星々の印や、軌道環に記された細かな襞模様を入念に眺めた。それは地球をはじめ、惑星を天空につなぎとめる大歯車の歯を示していた。「なぜ?」
少女は驚いたようだった。「なぜ、空は?」
ザライはロソダの言葉を聞きまちがえたと思い、質問を意味の通る文章に読みかえようとした。「空は世界の一部よ。わたしたちを囲んでいるものよ」
「ちがう」ロソダは顔をしかめた。彼女は、自分の英語力では言い表せない何かを言おうとして苦心していた。「なぜ、世界は上? 落ちる?」
「落ちる……?」
ロソダは、革の衣の切れこみのようなポケットから小さな工具を取り出して、腕を伸ばすと手放した。レンチはザライの屋外作業場の押し固まった地面に落ちて一回跳ね、テーブルの脚にぶつかって音を立てた。
「重力よ」ザライは言った。
「重力!」ロソダはうなずいた。「なぜ、空は上? 重力ない?」
「それは……」鋭い質問だった。ザライはいつも、世界をそのまま受け入れてきた。太陽も惑星も光り輝く星々も、神が配置した通りに並んでいて、神がそのように配置したというよりほかに理由などなかった。雨はなぜ降るのかと問うてもしかたがない。ただ、そうなのだ。
「上に行く、何が落ちるか調べる」少女の顔が満足げに輝いた。彼女は革の天体図を指さして言った。「道、みつける」
道をみつける。ザライは考えた。それが鍵だろう。塔はいままさに建設が進んでいる。船の試作機も完成済みだし、設計士たちは彼女の想像をはるかに超えて賢かった。どこに行き、どうやって戻ってくるかはもはや二次的な問題ではなかった。少女が答えたように。
そうすると、ここでの自分の役割は何なのだろうとザライは思った。
「あなた、夢をみる」ロソダは言葉にされなかった問いに答えた。ザライの顔にはっきりと書いてあったにちがいない。
「いいえ、夢をみたのはマニックスよ。わたしは共有しただけ」
「あなた、共有する」ロソダは手を伸ばして、ザライの手を軽くたたいた。「あなた、共有する」
ザライはしばらくのあいだ、重力の問題を考えつづけた。なぜ天は地球に落ちてこないのか? あるいはその逆でもいい。軌道環の質量は地球をはるかに凌ぐ大きさだった。ザライは丸一日かけてつぎつぎと小石を渓谷に落とし、それが転がっていく様子を観察した。夜になるとキャンプ内の焚き火のまわりをめぐり――焚き火は今ではいくつもあった――人々に隕鉄や雷石や隕石の話を聞かせてもらおうとした。
ザライが得た答で二番目に多かったのは、「神は世界をこのように造られた」の何らかのバリエーションだった。一番多かったのは、憐れみと当惑が混ざったまなざしだった。
ここにいる人はだれもが空に飛び立ちたがっているのに、根本的な問いを口にする者はいなかった。そんなはずはないとザライは思った。みな自問したことがあるにちがいない。そうでなければ、ここにいるはずがなかった。
ザライはエーアを探した。エンキドゥの男は暗がりに立ち、星明かりを頼りに粗挽きされた製材の山を見つめていた。
「どこまで登れるのかしら?」ザライはたずねた。
「足場はもう頂上まで」エーアはガラガラ声で言った。「まだ安全じゃない」
「一緒に来てくれる?」
エーアの歯が星明かりに光った。彼は顔をほころばせていた。
二人は一緒に、不規則なジグザグ階段を登っていった。赤道の大歯車に歯が刻まれているところまで、たっぷり八百メートルはあるとザライは知っていた。なかなかの距離だ。
最初の数百メートルは無人都市の泥の球体を足がかりにしていた。ザライは、最初のプラットフォームまでは登ったことがあった。これが構造全体の基盤部分で、球体群を越えた高さ三百メートルほどのところに設(しつら)えられていた。プラットフォームは支柱やトレッスルを支えにいくつもの球体を足場とした上で、そびえ立つ真鍮の壁にも、無秩序に入り乱れる片持ち梁や井桁により固定されていた。もちろん、大量のねばり草が使われていた。構造は当然ながら自立しているが、堅固に固定する必要があった。
プラットフォームに達すると、エーアは立ち止まって四隅に設置されたデリック・クレーンを指さした。クレーンから垂れるワイヤーは闇のなかへと消えていた。ザライはあたりを見まわした。デッキ上には丸太や金属部品が山積みになり、より高い構台を支える柱が立ち並んでいた。階段は立派な木の梁のあいだを縫って上へと伸びていた。
二人は一歩一歩進んだ。冷たい夜気が肺にしみた。登る動きに筋肉が痛んだ。すぐそばの真鍮の壁面は、音も熱も、光さえも吸いこむかのようだった。金属というよりむしろ意志の固まりだった。神が手ずから創られた創造物なのだ。その気になれば指先で触れて確かめることができるほど、それは明らかだった。
もしかしたら、神は重力からなるのかもしれない。
やがて二人は第二デッキに到着した。そこにも小さなデリックが設置されていた。床板にはペンキで四百という数字が書いてあった。
「これで半分ね?」ザライは確認した。
「そう」エーアはいつもの無口な彼に戻っていた。
次のセクションは明らかに建設途中だった。梁や支柱が足場に囲まれてそそり立っていた。より小さい、間に合わせのクレーンやデリックが上方に見えた。ものによっては、横木に滑車を付けただけの簡素なものだ。階段の枠組は据えつけられていたが、蹴り上げ板はなかった。
エーアは足場の一角に固定された梯子を指さして言った。「少し危険」
二人はさらに登った。
最後のほうでは、ザライは端をねばり草の塊で固定したロープにしがみついて登った。柱に短い杭を水平に打ちつけたものが最終的な梯子だった。大歯車の頂上はザライのすぐ頭上にあった。彼女はV字型の歯の谷の部分にいた。手を伸ばせば、地球の歯車と天の軌道が接する場所に触れられそうだった。
でも二人はまもなく降りなければならない。真夜中の轟音は地上にいてもすさまじかった。軌道環の通過をこれほど近くで経験するなど、聴力を捨てるにも等しい。
それでもザライはふり返って下を向き、北半球をぐるりと見渡した。
真下にある〈壁〉の頂上は、目まいがするほど近く見えた。〈壁〉の壁面は花崗岩の滝のようになだれ落ち、はるか下の海へと伸びている。平水域の大地は、はっきりと湾曲した水平線の彼方に横たわっている。大西洋は、平水域世界の諸女王国のなかでも特に強力な国をとり囲んでいると聞いていた。頭上に冴えわたる星々は手が届きそうなほど近い。二人が登ってくるあいだに月も昇っていた。ザライは、夜の気まぐれな羊飼いの銀色の光と滑空する白鳥にこれほど近づいたことはなかった。
エーテル船から見える天は、きっとこんな感じなのだろう。
「ニックス」ザライは薄く冷たい大気にささやきかけた。「どこにいるの?」
闇は何の答も与えてくれなかった。数十メートル下で、一番高く一番小さな仮設プラットフォームに立って彼女を待つエーアの息遣いが聞こえるだけだ。
ねばり草がなければ、このすべてが実現不可能だった。まだまだ先は長いが、それでも……。ザライは泥の球体都市をつくり、姿を消した鳥人たちに心のなかで感謝した。
「降りましょう」ザライはエーアに声をかけた。「軌道環がやってくる前に」
もちろん、騒音対策も重要な課題になるだろう。あとで薄と崔と話し合わなければ。ザライは心に留めた。
二人は階段を降り、作業場に戻っていった。
失敗
ザライはハッチをくぐりぬけて船内に入った。最終完成形ではなく、実物大の木製模型だった。金属製の本物は、無人都市の泥の球体に設えられた船台で組み立てられていた。薄と崔は、乗組員席の大きさや位置、展望窓の設置場所、制御装置の最適な配置などの細部を決めるためにこの模型をつくった。
いまのところ、推進力として最も有力視されているのは圧縮空気だった。加熱炉のまわりやコールドプレス作業場では議論が続いていた。熱心に火薬を支持する者もいたし、〈壁〉のはるか西方からやってきたおしゃべりなエンキドゥ族の一団は、見知らぬ化学薬品の数々を推した。彼らは船乗りの街をまるごと酔いつぶせるほどたくさんの蒸留器を作り、しばしば眉を燃やしながら金属フラスコで燃焼実験を行っていた。
彼らを止めようとしても無駄だとザライは思った。彼女に何がわかるだろう。計画はとうの昔にザライの手に負えなくなっていた。それぞれの集団は思い思いの作業をしていたが、薄と崔は、何をつくるにせよ――スリング、発射架台、操縦システム、制御盤――模型船をひな形とするように指示し、ある程度の整合性を保たせていた。
それ以外はもはや制御された混沌とでも呼ぶしかなく、〈鎖〉でバケツ船をつくるどんな造船工でも、この状況に身を置けば気が散るどころでは済まないにちがいなかった。ザライはまさにその状態にあった。
妙なことだが、この目的をもった狂気のなかでザライにとって一番話しやすかったのは、ほとんど言葉が通じないにもかかわらずロソダだった。ロソダは毎晩、天を見上げて過ごしていた。建設中の発射櫓(やぐら)の上で夜を明かすことも珍しくなく、毛織物と綿布で頭を何重にも覆い、通過する軌道環の轟音から耳を守った。軌道環通過に関するより詳しい図解と注釈、そして月やほかの惑星、天候や空気そのものの性質についての丁寧な観察結果が続々と回覧された。
ロソダはまた、エーアや薄と崔の兄弟とともに船の打ち上げ装置の設計を進めていた。
ザライは自分の無能さをつくづく思い知らされた。彼女の仕事といえば、ロソダの後をついてまわって通訳し、エーテル船の実物大模型を見にいくことしかないようだった。いつかだれかがその本物に乗って〈壁〉から飛び立ち、星空に達するのだろう。
自分はそのだれかになれるだろうか。
ザライは気が滅入りそうな問いを頭からふり払い、薄の話に集中しようとした。彼は先ほどから熱心に、やけに丁寧な説明を続けていた。
「……ここに座ると、エーテルのなかを飛ぶ龍(ドラゴン)が見えます」
「龍ですって?」ザライはたずねた。
薄はハッチの隙間から外にいる崔にちらっと目をやり、ふたたび視線を戻した。「龍……」彼はゆっくりと言った。「ほら、あの」
「天使と同じ」崔は言った。「世界中の建築に使われている」
「天使が世界の建築に使われているの?」
薄は厳かにうなずいた。「今にわかります」
だれかは知ることになるだろう。ザライは不快な考えを追い払った。「船の制御方法は決まったのかしら」
鍛冶屋は親指と親指をくっつけて、両手を蝶のようにはためかせた。「飛ばします」彼は笑顔で言った。「樽につめた花火みたいに」
「さぞ快適でしょうね」
ザライは小さなシートに腰かけていた。正面にはのぞき窓が二つあった――模型では単なる穴だが、本当の船ではガラスかクリスタルが嵌められるはずだった。操縦者は六枚のパドルを操作して船を動かすことになっていたが、満足に操作するには腕が少なくとも三本は必要に思えた。ニックスだったら、この問題をどうやって解決しただろう。足元にはレバーが並んでいるが、今のところどことも繋がっていなかった。制御盤はまだ設計すら決まってなかった。
ザライは体をひねってふり返り、船の後方を見た。三人掛けの長椅子が、船体後部のカーブに沿って置かれていた。その真上と向かい側に窓が、最船尾にハッチがあった。道具用のキャビネットは枝編み細工の箱で大きさと位置を示してあった。機能や用途やアクセス方法は不明だった。
模型は子供のおもちゃに毛が生えた程度の代物だったが、ザライにはその先にある未来の形が目に見えるようだった。真鍮と機械油の臭いが漂う気さえした。操縦士の汗、金属容器に圧縮して詰めこまれていた空気の妙な臭い。騒音、振動、寒さまで感じた――まちがいなく寒いはずだ。太陽に近づきすぎない限りは。
ザライは自分を諫めた。わたしたちはエーテルのなかに漕ぎ進む。それだけだ。
帰還方法については、だれも議論していなかった。
ニックスってば、とザライは思った。ばか、ばかな人。帰ってくるつもりなんてなかったのね? マニックスは自分の夢に沿って生きた。心にぽっかりと空いた穴を埋めようとしてザライの元を去り、二度と戻らなかった。まだ夜空に飛び立ってすらいなかったのに、姿を消した。
ザライはこらえきれずに泣きはじめた。薄は彼女の肩にそっと触れ、深い優しさをたたえた表情を見せてその場を去った。とりとめのない、熱い思いが涙となってザライの頬をつたった。
「わたしたち、戻ってこないのね?」彼女はたずねた。
「アルシドルが帰りの空錨装置を開発している」ロソダが言った。英語もだいぶ流暢になった。アルシドルとは一体どこのだれなのだろう。ザライは頭をひねった。
ザライが計画の中枢メンバーと見なす面々が、崔と薄のかなり拡張された加熱炉の前で大テーブルを囲んでいた。当の兄弟と、もちろんエーア、ナビゲーターのロソダ、木こりのアーマイン、電力技師のキー、そしてザライ本人だった。彼女は夢の番人であり、何千もの細々とした質問の解答者だった。だれかが決断を下さなければならないからで、彼女に知識があるからでも、技術があるからでも、批判的思考に長けているからでも、決定力があるからでもなかった。
渦の中心にいる女にすぎない。
「車軸は動かずに、車輪が動く」ロソダが静かに言った。
「そういうの、やめてちょうだい」ザライは答えた。「心を読んだみたいに言わないで」
「顔を読んだだけ」
崔が咳払いした。「さきほどの質問ですが、ほかの可能性も検討してきました。例えば、船に命綱をつけるとか」
「何を使って?」
「もちろん、それが問題となるでしょう。案はほかにも出ています。翼で飛んで戻る。強力なロケット群で地球に追いつく。月まで到達できるエンジンもいい――そしたらそこで休憩し、燃料を補給して戻ってくる。十分な食糧と空気を積みこんで、軌道環をつかんだまま次に地球と接する時を待つとか」
ザライは呆れて言った。「どれもこれも問題だらけに思えるけど。だから戻ってこれないんでしょう?」
「龍が」薄は言った。エーアとキーが訳知り顔でうなずいた。アーマインは不愉快らしく、面長な顔をいつも以上に歪めた。ロソダは星々に思いを馳せているのか、上の空だった。
「龍って、あなたの言っていた天界の天使のこと?」
「天使はあなたの」崔は答えた。「中国では龍です」
ザライは意味を読み解こうとした。「空に飛びこんだら、その先はお祈りまかせってことね」
「ほかにも選択肢はある」薄は言った。ザライは薄が真剣なまなざしで彼女を見ていることに気づいた。「でも上手くいかないでしょう」
ザライは天への片道の旅に踏み出せるのだろうか? できるのだろうか?
自分でもいささか驚いたが、ザライはすでに答を知っていた。答は最初から決まっていた。ニックスはそもそも、地上への帰還については語らなかったのだから。
「もちろん」ロソダがつぶやいた。
ザライはナビゲーターに鋭い視線を投げた。「自分が乗るみたいな言い方ね」彼女は言った。
ロソダは笑顔をみせた。「四人が飛ぶ。あなたとわたしとあと二人が」
「そんな向こう見ずはいるかしら」
「このキャンプにいるすべての男と女とエンキドゥ族と南半球人がそうだ」エーアが言った。これまた、彼にしては驚くべき長さの発言だった。
南半球人。ザライは考えた。ここに南半球人がいたなんて驚きだ。ここに来るために、〈壁〉を越えてきた人がいるのだ。そのことを心に留めて、ザライはロソダに視線を戻した。
少女はうなずいた。闇夜のように黒い顔に、控えめな笑みが広がった。
「つまり、わたしたちは飛び立ち、あとは龍頼みというわけね」ザライはテーブルに両手をついて身を乗り出した。「推進力はどうするの?」
「先週、爆発音が聞こえたと思いますが」アーマインが語りはじめた。
かなり大きい、ところどころ雨漏りのする倉庫のなかで、金属とガラスとクリスタルからなるエーテル船が形になりつつあった。船には奇妙な美しさがあった。ザライが大人としての最初の年月を過ごしたバケツ船と比べれば、はるかに見目麗しい。船体は中央が太く、やや縦長だった。横断面はほぼ円形で、船首に向かってすぼまった先に一連の丸窓が嵌められている。後部のハッチは後ろ向きの四本のチューブのあいだに設えられていた。船体の表面にはジンバル式の吹き出し口が約一メートル間隔で並び、各々を繋ぐパイプが船体の金属被覆に合わせて褐色に塗られているので、ちょうど、逞しい体つきの人間の筋肉に走る血管網のように見えた。
だれかが溶接線に沿って渦巻き模様を描き加えたらしく、エーテル船は今にも燃え上がりそうな雰囲気を放っていた。正面の窓の上には太く短いチューブが一本あり、そこから四又に別れたミサイルが突き出ていた。
「これで龍を撃つの?」ザライはたずねた。
薄は肩をすくめた。「あるいは、天使をつかまえる」
ザライは顔をしかめた。「たとえ龍に遭遇したとしても、撃つなんて考えられないわ」
「引き牽(つな)です」崔が種明かしした。
「龍に、地球に連れ戻してもらう」ロソダが言い添えた。
わたしをからかっているのね。ザライは思った。易々と餌に食いついて、彼らを喜ばせるつもりはなかった。「打ち上げ用フックはどこ?」
「打ち上げ装置をテストしてから、つけます」薄が言った。「設置箇所を調整しなくては」
彼の弟は勢いよくうなずいた。「それに、パラシュートを納める空間も必要です」
「いったい何種類の……帰還手段を想定しているの?」ザライはたずねた。「まさか全部なの?」
薄と崔はまたしても顔を見合わせた。薄は答えた。「念には念を」彼は自分の手をしばし眺めた。「でも、試作機があります」
「ええ、わかってるわ。あなたの作業場にある木の船のなかで何時間も過ごしてきたもの」
「飛ぶ試作機です。エーテル船の小型版で、帰還手段をテストします」
ザライは薄の口調に釈然としないものを感じた。「なんだか歯切れが悪いわね」
「誰かがそれぞれの試作機を試すなら、より縁起が良いでしょう」
ザライははっと気づいた。「帰還手段に問題があればその人の命が失われるかもしれないのね?」
「あるいは溶接が外れて、彼はエーテルを吸ってしまうかもしれない」崔が沈黙をやぶって言った。
「彼、ですって?」新たな目的意識がわいてきた。「女にしかできない仕事もあるのよ」
「これは危険――」崔は言いかけたが、口をつぐんだ。
「崔」ザライは優しく言った。「わたしはかつて鎖海賊だった。ワイヤーに逆さまにぶら下がったまま、絶壁を八キロ移動したこともある。手榴弾やナイフや、ビレーピンや銃弾だってかわしてきた。エーテルを少々吸うことなんて、これまでの人生と比べたらわけもないわ」
「リーダーはあなたです」より頑固な薄が言った。でも公正を期すなら、二人とも頑固だとザライは思った。薄はかたくなな声と表情で言葉を継いだ。「あなたがみんなの夢を抱いている」
「薄、わたしはリーダーじゃないわ。今ではもう、みんなが何をしているかも把握していない。この計画に対するわたしの貢献といえば、ねばり草の煮だし方を考え出したことくらいよ。接着剤を発明――いいえ、再発明しただけ。エーアは塔やウィンチを建設している。アーマインと仲間たちは木を切り出している。ロソダは星界の地図をつくっている。キーは火薬やオイルや圧力容器を使って何やら企んでいる。彼はしょっちゅう〈壁〉の一部を吹き飛ばしているから、下の人たちは驚いているでしょうね」ザライは言葉を切り、兄弟二人をじっと見つめた。これは〈鎖〉で働いていたころにニックスから教わった技だった。「ここでのわたしの役目がみんなの夢を抱くことなら、その夢を空まで持っていかせてほしいの。しっかりつかんで、地球に戻ってくるまで離さないから」
マニックスも一緒に飛んでくれる。彼は心の奥深くにいる。ザライは、自分は結局、マニックスを本気で諦めたことなどなかったのだと気づいた。愛する人が戻ることはないとわかっていたが、それでも彼とともに上空に向かうのだ。
「それに」ザライはささやいた。「テストが失敗したら、エーテル船は永遠に飛ばないかもしれないわ。そうなるのなら、後悔を抱いて地上で生きるよりも、空中で死んだほうがいい」
ずいぶん口論があった。キーはキャンプから出て行き、三日間戻らなかった。ロソダはしばらくのあいだザライと目を合わせなかった。薄は怒っていた。崔は悲しげだった。アーマインは苛立ちを隠さなかった。様子が変わらないのはエーアだけだった。
「だれかが空に登るしかない」エンキドゥの男は、大きい、ゆったりした声で言った。ザライと二人で発射櫓の第二プラットフォームに立ち、デリック・クレーンを点検している時だった。
「ええ、そうよ」ザライは答えた。「わたしたちはこの夢を分かち合っている。でもほかのみんなにはそれ以上の目的がある。わたしが戻らなくても、夢は消えないわ」
「あなたは戻る」エーアはザライの体よりも太い丸太の垂木を叩いて言った。「無駄に登らない」
「わたしたちがしていることは、何ひとつ無駄にならないわ」ザライは言った。
二人は次の階段を上がり、第三プラットフォームの発射架台の点検に向かった。長い登りだった。ザライとエーアが到着すると、熟練工が二人、巨大な木樽に何やら手を加えていた。すぼまった端には小さな窓ガラスが三つ嵌めこまれていた。一方、膨らんだ部分にはごちゃごちゃとパイプが巻きつけられていた。
「〈ギメル〉ね」ザライは見てとった。彼女が試作機を最初に見たのは、薄と崔の作業場でだった。〈アレフ〉はいわば、試作機の試作だった。組み立てられ、採寸とテストを終えたのち、分解されて再び材料となった。〈ベト〉は第一プラットフォームからの落下実験で破損した。これにより設計の見直しが行われ、〈ギメル〉がつくられた。〈ギメル〉は試作機として初めて軌道環に打ち上げられ、〈壁〉の頂上に戻る予定だった。
フライトはとても単純なものになるだろう。何よりも重要なのは、打ち上げ装置の検討だった。軌道環が〈ギメル〉をとらえ、〈壁〉の頂上から連れ去る。操縦者はロソダの計算通りに時間を計り、推進ノズルを始動する。そして円を描くように〈ギメル〉を操縦して出発点に戻り、パラシュートと真剣な祈りの力を借りて着地する。フライトは全行程で十分にも満たないだろう。数々のプロセスを調べる必要があった。例えば、操縦者の肺活量だ。エーテルが鍛冶屋たちが計算している以上の速さで船内に入りこんできた場合、彼女はある程度の時間息を止めなければならない。
「〈ギメル〉だ」エーアが言った。エンキドゥ族は船体をゴツンと叩いた。
銅板を打ちつけていた女性熟練工が顔を上げた。「気をつけてくださいよ」
ザライは彼女の名前すら知らなかった。彼らはここで、最終準備の一環として試作機を金属で被覆していた。エーテル船に関わる作業は、ザライが〈鎖〉時代に見てきた造船過程とは何もかも勝手がちがった。
エーアはぼそぼそと謝罪をつぶやいた。ザライは体を屈めて窓ガラスのなかを覗いた。〈ギメル〉の内部は狭かった。まだ名前のない本物の船をおもちゃにしたようだった。それなりの背たけの女性なら、膝を曲げてうずくまるのがやっとだろう。そして船首の両側に据えられた操縦桿に両手をかけて、空に向かって落ちる瞬間を待つのだ。
エンキドゥ族がザライの肩に触れた。ザライは体を起こし、エーアの目を見つめた。二人は友人ではなかった。少なくとも、彼女とロソダのように強い絆を育んできたわけでも、彼女と鍛冶屋兄弟とのようにお互いに好感を持っているわけでもなかった。それでも、エーアはザライにならって、〈壁〉の頂上の無人都市、泥の球体が設えられたこの場所にやってきた最初の一人だった。
マニックスの夢を共有した、最初の一人だ。
ザライはその夢を、消えた恋人の身代りとして抱いていたにすぎなかったが。
ああ、ニックス。
「エーア」ザライは言った。
エンキドゥ族の顔は、ザライにはうかがい知れない感情でしわくちゃになった。「あなたは飛ぶ。どの女性よりも高く」
「わたしは戻ってくるわ」ザライはささやいた。ニックスとはちがう。「必ず戻ってくる」
それから数日間は、最初の打ち上げ実験の準備で慌ただしく過ぎた。下の作業場では〈ダレト〉の組み立てが進んでいたが、薄と崔は〈ギメル〉をある程度の状態で回収して再利用しようと考えていた。キャンプの構成員はだれもが第三プラットフォームに登り、〈ギメル〉の金属被覆や窓の密閉具合や、小さなハッチを点検した。推進ボトルの圧を測り、操縦桿の動きを確認した。
ザライが一番心配していたのは、狭い船体に体が納まるかどうかだった。「あの入り口から入るのは子供だって無理よ」彼女は言った。
薄は肩をすくめた。彼は自分の肩や胸の幅広さを見せつけるようにして言った。「あなたは細い女性だ。腰回りが通るだけの余裕はあります」
「次の試作機は、もっとハッチを大きくしないと」
「それか、もっと小柄な船長を探さないと」薄は言った。彼の声に笑いが混じっているのをザライは見逃さなかった。
彼らは操縦桿の配置を再検討した。ザライは、〈鎖〉を航行するバケツ船の装置なら、ブームから引っ掛け鉤まで何でも熟知していた。同様に、海賊が積荷を横取りする時に使う長い捕獲アームや、垂直に伸びる〈壁〉の静かな一隅に密かに設けられた、彼らの石造りの港のことなら知り抜いていた。ザライはそこの甲板で二十年働いてきたのだ。
ここでは、空が彼女の海だった。そして彼女の甲板は、天水桶ほどの大きさしかなかった。〈ギメル〉を目の前にして、それがどこに向かおうとしているのか、そしてエーテル空間で自分の身に何が起こるのだろうかと考えると、背筋が凍り心臓を冷たい手でつかまれる思いがした。
気にしない。ザライは自分に言い聞かせた。単なる不安だ。何の意味もない。
「空気はあります」薄が言った。ザライが黙りこんだのを誤解したようだった。「船体から漏れたとしても、予備の耐圧瓶があります。飛行はあっという間です」
「わかってるわ」ザライは言った。まさにそのために、ゴム製マスクの装着を何日もかけて調整してきた。しかし、どうしてもわからないことがいくつかあった。エーテルは肌に触れるだけでも危険なのか。熱すぎたり冷たすぎたりしないのか。気圧が高すぎたら? あるいは低すぎたら?
この飛行が成功するのなら――この飛行が成功したあかつきには――崔と薄は次に打ち上げる船に鳥籠を固定して、小鳥やコオロギやネズミをエーテルに直接さらしてみようと考えていた。じっさいにどの程度危険なのか調べるのだ。
今回の飛行では、エーテルに接するのはザライただ一人だ。ドラゴン砲だかなんだか知らないが、組立途中のエーテル船の背から飛び出していたあの物体すらない。ときどき、鍛冶屋兄弟の仕事はユーモアと区別がつかなくなった。
「だれかほかの人に飛んでもらいます?」薄の問いに、ザライは考え事を中断した。「志願者には事欠かないでしょう」
「いいえ」ザライは深呼吸した。「わたしが飛ぶわ」
「今日の午後、これをウィンチで上にあげます。エーアが監督します。明日、打ち上げ位置ですべてを再確認します。明日の晩、〈ギメル〉はエーテルに送りこまれる」
ザライはため息をついた。「あっけないわね。それでわたしたちは地球を後にして、星々のあいだを歩むのね」
鍛冶屋はにやりと笑ってザライを肘でつついた。「少なくとも、頭を突きだしてあたりを見まわすぐらいはできるでしょう」
ザライは後ろを向き、地球の曲線を見渡した。平水域の諸女王国は北に延び、丸い地平線に消えていた。太陽が出ているこの時間ですら、ちらほらと星が見えた。ザライの理解では、〈壁〉の頂上より上にはほとんど空気がなかった。〈壁〉の底部や、その先に広がる平水域の諸女王国を覆う厚い空気の層とはまるで別ものだ。一方で、下方からは日光というブランケットに遮られて天界が見えなかった。
あたりを見まわす。二年前、ニックスは天空に頭を突きだしてあたりを見まわすためなら人殺しだって厭わなかっただろう。そしてザライは喜んで手助けしただろう。一年前には、ザライはそれが自分自身の夢の頂点だと思っていた。
でも、いまは……。
ザライは、自分を圧倒している感情がどうにもならない畏れだと気づいた。
バン、とくぐもった音がしてハッチが閉められた。ザライは接着剤やおがくずやハンダの匂いに包まれて座った。腰がひりひり痛んだ。狭すぎるハッチをパニック寸前になりながら通り抜けたせいだ。崔は船体に何やら打ちつけていた。薄は小窓から船内を覗いている。エーアはその脇に明かりを持って立っていた。
恒星時の真夜中まで一時間を切った。軌道環が頭上を通過する瞬間に船は打ち上げられる。これから五十分、〈ギメル〉のなかで待機する時間がこの旅で一番長い部分だ。打ち上げられてしまえば、すべてはあっという間で怖がる暇もないだろう。生きて帰って来るか、エーテル空間のどこかで死ぬか、二つに一つだ。
ザライは朝からなにも食べられずにいた。水を飲み下すのもやっとだった。彼女のお腹は、洗濯女が絞ったズボン下のようにきつく締めつけられていた。口はからからに乾き、最終確認事項をつぶやいているうちに唇が割れた。
外から何を言われても、ザライはただ「イエス」と答えた。この日のために操縦を練習し、復習し、訓練し、耳を傾け、学び、テストしてきたのだ。
だからもう、すべてを忘れてかまわない。
薄がガラス窓を叩いた。指が四本、次に五本。あと四十五分だ。
軌道環の通過に伴う轟音があまりにすさまじいので、エーア以外はみな第二プラットフォームに避難することになっていた。そこでさえ耳栓をつける必要があった。エーアはパッドをたくさん詰めた特殊な革のヘルメットを被っていた。ザライも同じものを被っていたが、緊張のあまり騒音を気にする余裕などないだろう。
ザライは首をひねり、頭のすぐ上の板張りの丸天井を見上げた。打ち上げ装置がここに、内側から切り離し可能なトグルによって船体に仕込まれていた。先端に大量のねばり草をつけた、より複雑なつかみ機がその上方に控えている。エーアが通過する軌道環に向けてこれをスイングさせ、同時に〈ギメル〉を発射架台から解き放つことになっていた。
ザライはイメージした。軌道環が彼女を捕らえ、地球が遠ざかる。空はより暗くなり星にあふれ、空気は薄く冷たくなる……。もしももっと水が飲めていたら、尿意をもよおしていただろう。
平水域世界の女王国から手に入れた時計が、打ち上げまでの残りわずかな時間を刻んでいた。船が引き上げられる時刻と、トグルを外す時刻に印がつけてあった。
ザライが〈壁〉から引き離され、エーテル空間へと放りこまれる時が刻一刻と迫っていた。
「マニックス」ザライはささやいた。「わたしになんてことをしてくれたの」
ザライは目を閉じて、彼の匂いを思い出そうとした。彼の感触、ずんぐりとした四角い顔。まぶしそうに彼女を見る様子。ザライを見つけるとしわくちゃな笑顔になったこと。体に置かれた彼の手の感触。耳に流れこむ彼の言葉。遠い星や、空の上からの眺めを夢見る言葉。
ザライはもの思いに耽り記憶の彼方をさまよっていたが、やがて時計のカチカチという音が騒音にかき消された。騒音はやがて轟音となって響きわたった。ザライは慌てふためき、打ち上げ前に確認すべき項目があったのを思い出した。ドンドンと叩く音がした。エーアだ。持ち場を離れて、正面の三つ窓の一つから手を振っていた。
彼は毛むくじゃらの太い親指を立てると、打ち上げ装置の制御席に駆け戻った。
ザライはヘルメットのぶ厚い耳覆いを下ろした。接近する軌道環のとどろきはあまりにすさまじく、音を越えて体感の域に達していた。
関節が思いきり圧迫され、ザライの息と体重は一気にさらわれた。もはや何を畏れているのかもわからなかった。
意識の片隅で、ザライは時計の動きに注意しつづけていた。トグルを外すまで、たった一分だ。ねばり草がエーテルにどう反応するかは予想もつかなかった。凍って固くなるのか、沸騰するのか、はがれ落ちるのか。いずれにせよ、〈ギメル〉が打ち上げ位置から離れれば離れるほどザライの帰還は困難になる。正直、この小さな船を破損させずに着陸させることは、この試み全体で最も尻込みしたくなる部分だった。危険が明らかで理解可能だからだ。
逆に、エーテルの危険性のほうはぴんとこない……。
ザライの体はシートにめりこみ、引っぱられ、ベルトに押しつけられた。ヒュルヒュルとうなる音がした。未確認の裂け目からエーテルが流れこんできたのだろうか。時間が、時間こそがザライの敵だった。
目玉が顔から飛び出してしまいそうだった。気温は下がっているのか。ほかには何が起こっているのか。体は妙な感覚がした。伸ばされ、火照り、歪められていた。
これは本当の自分ではないのだとザライは思った。これは夢の体だ。ニックスと一緒に見ている悪夢だ。さんざん苦しんだあげく、叫び声をあげて目覚めるとニックスが温かい腕で抱きしめてくれるのだ。ザライはそれが本当であることを祈った。
万が一まちがいだった時のために、ザライは時計を見つめ、決められた時刻になると解除ハンドルに手をかけた。
ハンドルを引いた。
何も起こらなかった。トグルが引っかかっていた! ザライは死ぬまで軌道環に引っぱられ続け、死体は永遠にエーテル空間を漂うのだ。ニックスが彼女を起こしてくれるのでなければ。
あるいは、もう一度ハンドルを引いてみようか。
自分自身の汗の刺すような匂いにむせながら、ザライは渾身の力でトグルを引っぱった。ハンドルがもぎ取れるんじゃないかとはらはらしたが、〈ギメル〉は静かになった。振動が収まった。ただ、何となく落ちていくような、いやな感覚があった。
何となくではなかった。ザライは落ちていた。空気は妙な味がして、風のうなりは大きくなった。こうなるとザライは軌道環にくっついたままのほうが良かったと思いはじめた。堅固なものにしっかり固定されていれば、彼女の墓は少なくともどこかになる。どこかに向かって、ではなく。
後ろでゴロゴロと音がした。ジャイロスコープだ。ロソダは圧縮ガスをいつ発射すべきかザライに指示していた。〈ギメル〉の向きが変わり、前方の窓ガラスに印された線に発射櫓が重なって見えるまで待つ予定だった。真正面からではないが、船はガス発射により曲線を描いて帰還するはずだ。
ところが〈ギメル〉はスピンした。スピンなどするはずだったか? バケツ船の甲板とはだいぶ勝手がちがった。大嵐に翻弄される縄の吊り橋よりもひどかった。何もかもがひっくり返り、外では世界がぐるぐる回転していた。ザライは吐き気がした。胃袋はひん曲がり、胃液に浮かぶわずかな物を押し出そうとしていた。
それでも彼女はガラス窓の線から目を離さなかった。船が回転しながらも、たいまつを灯した発射櫓の細長い線とそろうのを待った。彼女が発射櫓だと思い、願い、祈ったものと。
「ニックス」ザライはささやいた。「こんなつもりじゃなかった。わたしを目覚めさせて、お願い」
「ガスのレバーを引くんだ」ニックスがザライの後方で言った。
「そしたら目が覚めるのね?」ザライは汗みどろだった。肌が嘔吐しているかのようだ。口のなかは塩辛く、金属の味がした。
「そしたら、目が覚めるよ」
ニックスは彼女を愛していた。いまでも愛していた。ジャントンのことがあっても。
ザライはレバーを引いた。突然、なだらかに、確実に、彼女の世界は「落ち」ついた。体の謀反は徐々に収まった。すさまじいパニックは静まりはじめた。頭上には世界が圧倒的な存在感でのしかかっていたが、ザライは落ちついた。
〈ギメル〉は帰還の途についた。
操縦、操縦しなければ。でもどうやって?
マニックスは目覚めさせてはくれないとザライは悟った。空気は薄く冷たくなっていた。風のうなる音は消えた。ザライは小さな操縦桿を握り、船の方向をできるだけ保とうとした。太鼓の上で豆粒を弾ませるようなことだが、できないことはない(これもまた、キャンプにいる鬼のような連中から教わった実際的な知恵だった)。
塔を目指すが、塔そのものは避ける。木こりたちはキャンプの西側の大きめの草地を整え、岩をどかしてくぼみや穴を埋めていた。〈ギメル〉が接近できれば、そこに着陸する。できなければ、降下した場所に着陸するしかない。
「落ち」つきは圧縮ガスの瓶が空になるにつれて失われていった。それでも舵を取ることはできた。予備のガスが小さいノズルにある――ザライは思い出した。それが無くなったら、地球に受けとめられるがままだ。大地はその時点でザライを迎える場所で受けとめてくれるだろう。
空気は? ザライは片手を操縦桿から離してゴムマスクを取ろうとした。空気が足りない。ザライはもつれる指でマスクを顔へと引き寄せようとした。それでも、たとえ甘く快い空気のためであっても着陸場所から目を離すことはできなかった。地面は猛烈な勢いで近づいていた。
〈ギメル〉を最後に減速する方法はなんだったか? パラシュートはなかったっけ?
ニックスはせっぱ詰まった口調になっていた。彼はザライの後ろに、この狭く窮屈なキャビンのどこかにいるらしかった。しかしザライにはもはや聞き取れなかった。まるで、キャンプに到着したばかりのころのロソダとの会話のようだった。
そのとき、彼のごつごつした小さな手が後ろから伸びてきて、一番奥のレバーを引いた。あるいは、ザライの手だったかもしれない。何もかもがあやふやになっていた。彼女の意識は砂漠の湧き水のように、湧き出たとたんに蒸発した。
「落ち」の質が変わった。地球の引力が船をとらえ、〈壁〉が目前に迫った。ザライは叫ぼうとしたが、もはやそれさえできなかった。彼女は意識を失った。
(続く)
(訳:志村未帆)