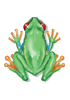星の鎖 第三章
ジェイ・レイク
第三章
回復
次にザライが耳にしたのは、薄(ボー)の静かな笑い声だった。崔(チョイ)と二人で、流麗な母国語で話している時にだけ聞こえる鈴のような含み笑いだ。そんな時の二人は、何やら面白いことをたくさん語っているようだったが、ふだんはキャンプのほとんどの人と同じように英語で話した。
ザライは目を開けようとした。まぶたがはりついて離れない。恐怖が体を駆けぬけた。思わず声をあげたのだろう、薄の柔らかい笑い声が止んで足音が近づいてきた。
「あなたは生きています」鍛冶屋の声が鈴の音の向こうから聞こえた。音はずっと彼女の耳の中で鳴っていたらしい。ザライは薄に手を握られるのを感じた。
「え……」声がまともに出なかった。
「シーッ」薄の指が彼女の指を包み、ぎゅっと握った。ニックスならそうしてくれたように。「空気が足りなかった。エーテルが多すぎた。休んでください。治ります」
ザライは薄が治ると言った根拠を問いただしたかった。どうしてわかるというのだ。でもたずねなかった。かわりに大人しく横になった。耳のなかでは脈がこだまし、スリッパをはいた老女の足取りのように小刻みで覚束ないリズムを刻んだ。目は痛み、まぶたはかさぶたか湿布でふさがれていた。鼻のなかはのっぺりしていた。嗅覚が焼け落ちて、代わりに栓をはめられたようだった。
指を握られたまま、横たわっているしかなかった。やがて彼女は目を覚ました。いつのまにか眠りに落ちていたのだ。
「スープを」誰かが言った。ロソダだ。訛りでわかった。ザライの聴力はまだおかしかったが、耳鳴りは収まりつつあった。高圧や落下を感じる朦朧とした夢も減ってきた。ザライはいまさらながら、体中が痛むことに気づいた。
「口を開けて」ロソダはスプーンで、塩の効いたさっぱりしたスープをザライの唇に運んだ。
天にも昇るような味わいだったが、胃が一気に締めつけられた。
ザライはこのようにして数日を過ごした。遠くから聞こえる作業の音や、ときおりのドカンという爆発音から、外では計画が続けられていることが伝わってきた。
ザライは時間の経過をきちんと把握していなかった。できなかった、と言うべきだろう。彼女は眠り、痒がり、ロソダやアーマインの助けを借りて用を足すという恥ずかしさに耐えた。四日目あたりだろうか、ロソダと薄がベッドの脇にやってきた。ザライは今では、息づかいや固い泥の床を踏みつける足音から、友人たちを判別することができた。
「院主(いんじゅ)から、目の覆いを外すように指示されたの」ロソダが前置きなしに言った。
これは予想外だった。「院主ですって?」
薄が衣擦れの音をたてた。ザライには彼が控えめに肩をすくめるのが見えるようだった。緊張したときの癖だ。「翡翠の院主は飛行実験の翌朝に来ました」
薄はなぜ緊張しているのだろう。「院主がきたなんて、知らなかったわ」ザライは静かに言った。少なくとも、声は出るようになった。起きあがって、院主に挨拶したかった。
「彼はあなたを治療した。でも、しばらくは聞き慣れた声だけに囲まれているほうが良いだろうと判断した」
「起きあがってご挨拶したいだろうけど」薄はつけ足した。「それはしないほうがいい」
「じゃあ、なぜ……?」ザライはたずねた。彼らはなにかを求めている。「なにかあったの?」
「なにも」
ザライには、言葉にならない「でも」が聞こえるようだった。
ロソダの手がザライの頬をかすめた。「目の湿布を外しに来たの」
「な、なにが出てくるのかしら」
「光が」薄が言った。「暗く光る、あなたの目の輝きが」
ロソダはザライに触れた。泥と葉の湿布の下に指がすべりこんだ。湿布はどんな匂いで、どんな薬草が使われているのだろう。
「目を閉じて」ロソダがささやいた。「しばらくそのままにして」
彼女の英語はほんとうに流暢になった。
薄は再びザライの手を握った。またしても、ニックスならそうしてくれたように。ザライは彼の手を見たのではなかったか。〈ギメル〉のなかで、船が難破しそうになったときに。
湿布とともに顔が妙な具合に引っぱられた。肌は勢いよく解放され、ひりひりした感覚が残った。ザライは、肌の一部が泥と葉とともに剥がれたにちがいないと思った。
しかし、目の向こうの闇は赤みを帯びた。
「光が」ザライは言った。「光が」
「しばらく待って」ロソダがやや声を落として言った。二人の息は荒くなっていた。
「ひどいの?」ザライはたずねた。
「あなたの顔のままです」薄は彼女の手を握る手に力をこめた。指が折れるんじゃないかと不安になるほどに。
頭になにか被せられた――布だ。ロソダが布をかけている。まぶたの裏の赤い影は黒に戻った。
「まばたきできる?」ロソダが言った。
自分は視力を失ったのだとザライは思った。彼らはそれを恐れている。ザライがまばたきすると、闇は濃い灰色に変わった。影のなかで影が動いた。
ザライはもう一度まばたきした。ロソダの笑顔が輝いた。彼女の目も。
「あなたが見える」ザライはささやいた。
「よかった」ナビゲーターは体を屈めて、ザライに軽くキスをした。「おかえりなさい」
薄はザライの手を握ったままだった。どちらかが溺れかけているように。ザライはもう一度目を閉じ、マニックスはどこにいるのだろうと考えた。
翌日――もう、時間の経過はまちがえようがなかった――翡翠の院主がザライに会いに来た。寺院を離れた彼は不思議と小さく見えた。院主は熟れた桃をたずさえていて、よくできた彫像のように頬笑んだ。
「あなたは天に触れて、生きて帰ってきた」彼はザライのベッドの隣に、彼女には見覚えのない椅子に腰かけた。
「そのようです」ザライは礼儀正しく答えた。彼女はまだ一人では立ち上がれなかったし、だれもわざわざ手伝おうとはしなかった。「あなたが来ていたなんて、知りませんでした」
「自分がどこにいるか、本当にわかっている人なんていないよ」院主は笑い、皮膚の硬くなった親指を桃のてっぺんに差しこんだ。ザライは魅せられたように、院主が桃を割るのを見つめた。節くれだった手に果汁がしたたり、法衣の袖を汚した。果肉は朝日のように明るく輝き、内側では暗紫色の種が目配せするようにきらめいた。
ザライはようやく、飛行実験いらい彼女の鼻と喉を支配していた金属臭以外の匂いを感じとった。
「果物はいかがかな?」翡翠の院主は丁寧に申し出た。
「ええ、ぜひ」ザライは息を深く吸った。
ザライは初めて自分の手で食べた。院主はつぶれかけた桃を一切れ一切れ手渡し、ザライの回復ぶりが嬉しくてたまらないという様子で頬笑んだ。食べはじめると、打ち上げの前日から失われていた食欲がよみがえってきた。
ザライは目覚めた。生きていた。帰ってきた。
しばらくすると桃はなくなった。ザライの顔と手はべとついた。子供に戻ったような気分だった。単純で、汚くて、満たされていた。
「ありがとう」一息ついて、彼女は言った。
「こちらこそ」院主は答えた。「もし天があなたをまるごと飲みこまされ、〈壁〉の頂上に吐き出せなかったとしたら、消化不良で苦労しただろうね」
「わたしが死にかけたのは天のせいではないの。空気よ。エーテルは肺と相性が悪いみたい」
「あなたの小さな船には隙間があったそうだね」院主は桃の種を手の平で転がしていたが、種はやがてどこかに消えた。「こんどは、あのとても強力な接着剤とゴム布で船体を内張りしているそうだよ」
「ほかのだれかが死なないように?」そうたずねて、ザライはまともな人間なら二度と彼女を飛ばさせないだろうと気づいた。
「あなたが死なないように、でしょう」院主は身を乗りだし、年老いた手をザライの手に重ねた。二人の手は乾きかけた桃の果汁でくっついた。「ザライ、あなたはまだ星界のなかを歩んでいない」
でもニックスはいない。〈ギメル〉のなかで彼に遭って以来、ずっと我慢してきた涙が堰を切ったようにあふれ出た。院主は彼女の手を握ったまま、なにも言わずに見守ってくれた。ザライの目から、悲嘆と恐れと痛みがとめどなく流れた。
ようやく涙が止まると、院主はふたたび笑顔になった。「あしたは、〈壁〉の上を歩きましょう」
予想通り、二度目のテスト飛行ではザライは〈ギメル〉に乗らなかった。その名誉に浴したのはロソダだった。ザライは納得していた。少なくとも沈黙を守る頭では。彼女はまだ杖を使って歩いていたし、耳鳴りも残っていた。ザライの体は落下着陸で負ったダメージと、悪い空気を吸った影響から十分に回復していなかった。
「エーテル障害だ」院主は名づけた。
「苦しかったはず」薄は言った。
「すぐによくなるわ」ロソダは言った。
いずれにしても、〈壁〉の反対側からやってきた小柄で色黒な女性は、ザライよりも容易に狭いハッチを通りぬけるだろうし、閉塞感にもそれほど苦しまないだろう。
ザライは、ロソダが飛び発つ日に頂上のプラットフォームから打ち上げを見守りたいと言い張った。階段を登ることは難しかったので、エーアがザライを乗せるスリングを用意し、プラットフォームからプラットフォームへと彼女を吊り上げた。打ち上げに必要な荷物を運ぶかのように。
彼らは今、泥の球体都市から八百メートル上方の狭くて揺れるプラットフォームにいた。大歯車の先端を成す真鍮の壁が左右に伸びている。度肝を抜かれる大きさだが、人間に理解できる範囲の小ささだ。エーテル空間の果てしない広漠とは別物だった。
ザライは冷たい空気を吸いこんだ。だれかの冷や汗が匂ったけれど、自分のものとは思えなかった。〈ギメル〉が放つゴムと接着剤の匂いがした。下の世界から漂う塩気と植物の匂いや、天の虚ろな痛み、毛むくじゃらのエーアの心休まる体臭や、翡翠の院主の落ち着いた雰囲気も感じられた。院主はザライと一緒にスリングで登ってきたのだ。
ロソダ、エーア、薄、崔、ザライと院主が集まると、頂上のプラットフォームは満員になった。〈ギメル〉と発射架台がかなりの場所をふさいでいた。
〈ギメル〉は本当に小さかった。銅の被覆は貼り直されていたが、ザライには前回の飛行でついた汚れや傷が、そして大失敗に終わった彼女の帰還の後に施された補修の跡が見てとれた。
「あのなかに入っていたなんて、信じられないわ」ザライは言った。
「固い決意のたまものよ」ロソダは言った。
「あなた、帰ってくるわよね」質問は単純だった。口にすると妙な感じがしたが、同時に重い問いであることを実感した。翡翠の院主が、ザライの腕を支える手にやや力をこめた。
彼女を地面につなぎ止めようとしている。忘れないように。
「もちろん、帰ってくる」ロソダは笑った。「あなたを連れていく先がどこなのか、だれかが解き明かさないと。マニ……エーテル船を飛ばすときに」
「マニ……?」
薄が、妙に優しい目でザライを見つめた。翡翠の院主以外はみな、照れくさそうに目を逸らした。「エーテル船はマニックスと名づけたんです。あなたが怪我で休んでいた時に決めました」
ザライは怒りが〈壁〉を転がり落ちる岩のように押し寄せるのを感じた。「よくもそんな……」そう言いかけたところで、翡翠の院主が腕をきつく握った。かなり痛かった。
ほんとうに、よくもそんなことを。でも彼女はノーと言える立場だろうか。彼女の船ではないのだ。星界自体も、彼女のものではない。
それにふり返ってみれば、これはそもそもニックスの夢だった。夢は彼らを〈壁〉の頂上に、そしてその先まで連れてきてくれた。こんなに近く、こんなに高い場所まで。死なずに、あるいは飛ばずにこれ以上天に近づくことはできない場所まで。
「いい旅を」ザライはロソダに言った。
それから、空気圧や機密性や補助推進装置、操縦桿の連携や、上下の概念の問題が話し合われた。ザライには説明した覚えがなかったが、彼らはどういうわけか理解していた。彼女は耳を傾け、うなずき、タイミングよく相づちを打ち、議論についていこうとした。しかし、心のなかでは〈ギメル〉のことを、マニックスのことを考えていた。
船ではなくて、人間の彼のことを想った。でも実のところ、彼はたしかに一緒に飛んでくれるような気がした。
「エーアとここに残って、打ち上げを見守りたいわ」ザライは静かに言った。
「だめだ!」薄が叫んだ。崔は首をふり、ロソダは驚いた顔をした。翡翠の院主とエーアだけが賛成しているようだった。
「パッド入りのヘルメットと毛布をだれかに持ってきてもらうわ。夜は冷えるから」ザライは譲らなかった。「自分の身に起こったことを確認したいの。当然でしょう」
「彼女は夢を持ちつづけている」エーアがしゃがれ声で言った。「わたしが見守る」
薄は歯を食いしばり、身を震わせた。彼の弟は兄の肩に触れた。なだめようとしているのか、力を貸そうとしているのか、ザライには区別がつかなかった。「やめさせたいところです」鍛冶屋はやっとのことで言葉を吐き出した。「でもザライ、あなたを押し止められる人はだれもいない」
翡翠の院主が体を近づけた。「忘れないように」彼はザライの耳にささやいた。「この世は星々の恵みだ。前に進み、摘みとれるものを摘みとりなさい」
議論はなかなか収まらなかったが、結局ザライが勝利した。彼女には自分がリーダーだとは、夢の担い手だとは思えなかった。むしろ、意地でも自分の要求を通そうとする駄々っ子だった。それでも一同は譲歩した上で、彼女にヘルメットと毛布とコーヒーと、焼きたてのお菓子を運んでくれた。木こりのアーマインと仲間たちがドングリの粉と野鳥の卵とアミガサタケから作ったお菓子だ。アミガサタケは、〈壁〉のそそりたつ垂直の崖面に出ている、静かで湿った木々の根に混じって生えていた。
ザライはエーアとロソダと共に時を待った。
どうしても見たかった。
ナビゲーターは真夜中の一時間前に〈ギメル〉に乗りこんだ。ザライは寒かった。本当は凍えていたけれど、だれかにそれを明かすわけにはいかなかった。エーアにさえ。この大柄なエンキドゥ族は小さな船のハッチをきつく締め、ドアの周囲に銅とゴムの充填剤を塗りこめた。それから船のまわりを行き来して、ジェット・ノズルのパイプを一つずつ点検し、発射架台と打ち上げ装置の配置を一通りチェックした。
夜空は澄んでいた。真夜中にほど近い今、軌道環は地球本体の裏側に隠れている太陽を反射して淡い黄金色の光をたたえた。ザライはウィンチとカタパルトからなる打ち上げ装置をつぶさに観察した。カウンターウェイトを使って伸ばしたアームをすばやくスイングさせ、〈ギメル〉を軌道環に打ちつける。ねばり草のパッドが凍てつく真鍮に接着すると同時に、船を放つ。
ザライはこんな機械装置に命を委ねていたのだ。そして今、ロソダの命が委ねられている。
きみは戻った。ザライの頭のなかで、ニックスによく似た声がした。
「わたしは戻った」ザライはささやいた。「でもこのざまよ。歩くのには杖がいるし、影に怯えている」
エーアがふり向いて彼女を見た。エンキドゥ族は親身に顔をしかめ、顔が破裂しそうなほど眉を突き出した。「大丈夫?」
「大丈夫よ」ザライはしっかりした声で言った。
まもなく、エーアは船の前窓を叩いてロソダに手をふった。それからザライと一緒にプラットフォームの断崖側に陣取った。「ここに立つ」彼はガラガラ声で言った。「柱を握って。とても揺れる」
ザライは西に目をやった。軌道環が見る見るうちに低空に迫ってくる。真鍮の巨大な帯が地球を刺そうとしているかのようだ。
子供のころから見慣れた光景だ。今さら怖がるなんておかしかった。早くも、プラットフォームが微かに揺れている気がした。
揺れはすぐに錯覚ではなく本物になった。まるで巨人が、彼らを地球側の空の涯下で八百メートル持ち上げている柱を揺さぶっているようだ。ザライには、ロソダが狭い〈ギメル〉の船内で経験していることが手に取るようにわかった。でも彼女が何を考えているのかは見当もつかない。
エーアはふだんから口数が少ないが、完全に無言になり、迫りくる軌道環を一心に見つめた。レバーにかけられた手は、カウンターウェイトのつけられたアームを動かして船を持ち上げる瞬間を待った。ザライはエーアの仕事の正確さを知っていた。彼女も沈黙を保ち、エンキドゥ族が革のヘルメットのぶあつい耳覆いを下ろすのを見て、慌てて同じようにした。
真夜中は猛烈な轟音とともにやってきた。〈ギメル〉の内部でも十分うるさかったが、外の騒音は次元を越えたスケールだった。頭上にそびえる軌道環は巨大すぎてほとんど意味を失っていた。〈壁〉そのものを見ているかのような、人間の想像力をも打ち負かす大きさだった。空に現れたもう一つの〈壁〉、太陽のまわりにぐるりとめぐらされ、一年をかけて一周する巨大な円だ。桁外れだった。
それにしてもこの轟音は……。
音はザライの骨に入りこみ、関節をゼリー状にした。胃の中身をどろどろの混濁液にし、吐き気をもたらした。目を無感覚になるまで揺さぶり、ヘルメットの耳当てを超えて聴力を決定的に奪ったにちがいなかった。
自分の耳はもう二度と使い物にならないだろう。ザライは音の感覚を失い呆然として、軌道環が頭上を通過するのを眺めた。真鍮の軌道環は陽光を反射して輝いた。プラットフォームは死にかけた犬のようにはげしく震えた。エーアが打ち上げアームのロックを外した。〈ギメル〉が振りあげられた。アームが離れた。船はぐらつき、あっと言う間に遠ざかった。真夜中の通過とともに、流れ星のような速さで東に運ばれていった。
ザライは船を目で追おうとしてふり向き、プラットフォームから転げ落ちそうになった。エンキドゥ族が彼女の腕をつかんだ。遠くで閃光があがり、銅で覆われた船は遠ざかる真鍮の塊から切り離され、火の粉のように舞った。
ザライが忘れもしない、あの瞬間だ。
もう一度閃光があがった。そしてもう二回。ジャイロスコープが船を回転させ、ホームに向かわせようとした。ロソダが操縦桿を操り、あっちに一押し、こっちに一押ししているのだろう。今回の飛行では、圧縮ガスの代わりにキーの化学薬品が使われていた。主要推進ノズルが火を吹くと、ザライはその明るさに驚いた。光は花火のようにとぎれとぎれに見えた。
エーアはザライの腕をつかんでいた手に力をこめた。エーアも驚いているのだとザライは悟った。
炎があがり、またちかちかと光った。そして地面に向かって揺れながら落下してきた。キャンプと着陸場所に向かってではない。燃える灰の塊のように、ただ落ちていた。
その瞬間、ザライはロソダを失ったことを知った。〈ギメル〉は墜落し、ザライのナビゲーターをあの世に連れ去った。ニックスはその力強い手で船をホームに導いてはくれなかった。そして彼はここにもいない。
一歩下がって細い手すりの向こうにすべり落ちれば、二人がいる場所に行ける。八百メートル下の地面はザライに誘いかけた。頭が割れるような無音を越えて、彼女に聞こえた唯一の声だった。ザライには自分の心臓の鼓動すら感じられなかった。下へと誘う声だけが聞こえた。
ロソダが落ちている、まさに今。
「彼女を殺してしまった」ザライはそう言おうとした。唇を動かしたものの、言葉は出てこなかった。軌道環の通過は、ザライのナビゲーターと共に彼女の声を奪った。
ザライはエーアの力強い腕に抱き上げられた。彼女は驚いて逆らおうとしたが、エンキドゥ族は長い階段をゆっくりと下りはじめた。ザライにできることは、ロソダの命の最後の炎が夜世界の闇へと舞い落ちていくのをエーアの肩ごしに見つめるだけだった。
(続く)
(訳:志村未帆)